労働時間における休憩の定義|休憩時間の計算や労働基準法上の考え方とは
更新日: 2024.4.12
公開日: 2021.9.15
MEGURO

労働時間中の休憩は、「最低限これくらいの時間は取るべき」といった原則が労働基準法の中で定められています。従業員側の無知や立場の弱さにつけ込んで休憩をおろそかに扱うと、従業員の労働生産性が下がったり、休憩時間分の給与を請求されたりするので、注意が必要です。
毎日、休憩なしで最高のパフォーマンスを発揮し続けられる人間は存在しません。ここでは、従業員のやる気や気力・体力を維持しつつ、労働争議を予防できるように、労働時間における休憩の考え方を解説していきます。
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の計算時間や付与ルールについて、本記事の内容をわかりやすくまとめた無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」 「必要な休憩時間数をいつでも確認できるようにしたい」 という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 休憩時間の定義

仕事中における休憩時間とは、「従業員が仕事から完全に離れることを保障された時間」のことを表しています。
「電話番」など、休憩時間中になんらかの労働を任せている場合、厳密には休憩時間になりません。このように休憩時間は労働時間とは切り離された状態です。そのため、労働時間に休憩時間を含むわけではありません。労働時間と休憩時間は分かれています。
1-1. 電話番や来客対応中は休憩にならない
労働時間にあたるか休憩時間にあたるかどうかを判断するには、仕事から解放されているかという点が重要です。例えば、顧客からの電話、来客の対応をしている場合は労働時間とみなされます。また、休憩時間であっても電話番をしながら食事している場合も同様です。休憩時間ではなく、業務の待ち時間とみなされます。
このように休憩時間中に労働を強いると、企業は給与を支払わなければなりません。給与を支払わずにいて、後に従業員から休憩時間における労働分の支払いを求められた場合、高額の請求が発生しかねません。そのため、休憩時間の運用方法については早めに見直して、体制を整えるようにしましょう。
なお、上司や管理者が直接的に休憩中の労働を命じていなくても、暗黙の了解として任せている場合も休憩時間とはみなされません。
関連記事:労働時間6時間の場合の休憩の有無について詳しく解説
2. 休憩時間は労働時間に応じて与える時間数が労働基準法で決められている
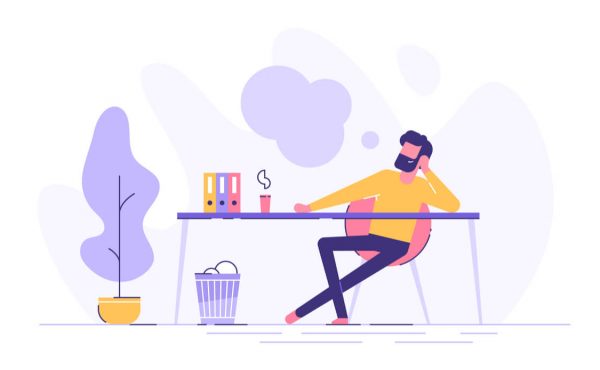
労働基準法では、休憩時間について以下のルールがあります。
- 6時間以下の労働は休憩を取らせる必要なし
- 6時間を超えて8時間以内の労働は最低45分以上の休憩を取らせること
- 8時間を超える労働には最低1時間以上の休憩を取らせること
このような決まりを守れない企業は、労働基準法違反です。SNSやネットが高度に発展した現代社会では、企業の悪評を隠し通すことはできません。
万が一、ネット上に「休憩時間に仕事をさせられる」「休憩時間だからと給与を払ってくれない」
といった話が流出してしまえば、企業イメージが大幅に低下するでしょう。
企業イメージが損なわれると、従業員の退職が相次いだり、新卒の就活生が集まらなくなったりする可能性も出てきます。
労働基準法を守らない企業を好意的に見てくれる一般消費者は少ないので、企業イメージや株価を守るためにも従業員に最低限度の休憩を取得させましょう。
なお、「5時間勤務の人が2時間の残業をする」「7時間勤務の人が1時間の残業をする」など、残業によって発生した休憩時間が発生した場合であっても労働時間の途中に休憩を与える必要があります。
参考:労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説 , 労働時間6時間の場合の休憩の有無について詳しく解説
3.休憩時間の与え方の3原則


休憩時間の与え方は次の3つの原則で成り立っています。
- 全従業員に一斉に与える
- 従業員の自由に使わせる
- 労働時間の途中に与える
それぞれ詳しく解説します。
3-1. 全従業員に一斉に与える
運送業や金融業、官公庁などの一部の業種を除いて、企業は従業員全員に同時に休憩を取らせる必要があります。基本的に、「Aさんには12時から1時間の休憩」「Bさんは13時から1時間の休憩」といった形で時間をずらして休憩を与えることはできません。
ただし、「労使協定」を結んでいる場合は、交代制の休憩システムを採用することもできます。労使協定とは、従業員の残業や休憩などについて定めた契約のこと。法定労働時間である1日8時間、週40時間以上の残業を頼む場合、「36協定」と呼ばれる労使協定の締結が必須です。
社内の休憩制度に手を加えたり見直したりする場合は、自社の労使協定を確認しましょう。
3-2. 従業員の自由に使わせる
必要な休憩時間が業務から離れて自由に使わせる必要があります。
休憩の必要な時間は従業員の労働時間によって異なります。その日の労働時間が「6時間を超える場合は、45分以上の休憩」「8時間を超える場合は60分以上の休憩」が必要です。
3-3. 労働時間の途中に与える
休憩は、あくまでも働いている間に体や頭を休める時間のことなので、「出社前に1時間の休憩時間を取る」という就業規則を作ったとしても、朝8時から1時間の休憩を設け、9時から17時まで休憩なしで従業員に働いてもらうといった対応を取ることはできません。
同様に、「終業時間後に休憩を持ってくる」といった対応も、原則として禁止です。仮に、朝10時から18時まで勤務し、終業時間後に1時間の残業をする場合、正規の休憩時間は「10時から18時の間」に取らせる必要があります。
勤務前後の時間帯は、そもそも労働時間ではなく従業員の自由時間なので、安易に手を出さないように注意しましょう。
4. 休憩を与えなかった場合の罰則


上記の原則を無視して、企業が従業員に適切な休憩時間を与えなかった場合の罰則は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」です。
労働基準法は刑罰が存在する法律なので、違反すると容赦なく処分されてしまいます。多くの場合、企業の経営者や会社そのもの、現場の管理職といった人が罰則の対象です。
5. 休憩時間を付与する際の注意点

休憩時間を従業員に付与する際は次の点に注意しましょう。
- 雇用形態によって休憩時間に差はない
- 労働協約で労働基準法を下回る規約は定められない
5-1. 雇用形態によって休憩時間に差はない
休憩時間の付与は3つの原則で成り立っています。3つの原則は雇用形態に関係なく適用されます。例えば、正社員とアルバイトが8時間労働した場合、どちらも同様に1時間の休憩が認められています。雇用形態によって休憩時間に差はないため、正社員だから、アルバイトだから、といって適切な休憩時間を与えないことは認められません。
5-2. 労働協約で労働基準法を下回る規約は定められない
労働協約とは労働組合がある場合に、労使間で労働条件ほかのルールを定められる仕組みです。労働協約で労働条件についての取り決めは定められますが、労働基準法を下回る休憩時間の規約は定められません。
6. 休憩時間を分割しよう!休憩が取れない時の対応策

とはいえ、仕事が忙しくて毎日きっちりと休憩を取らせることができなかったり、従業員側が自主的に休憩を取ってくれなかったりする場合もあります。そんなときにおすすめなのが、
- 休憩時間の分割
- 上司が率先して休憩を取る
- 定期的な小休止を設ける
といった対応策です。
6-1. まとまった休憩を取れない場合は休憩時間を分割する
1時間のまとまった休憩を取れない場合は、休憩時間を分割しましょう。午前に15分、昼に30分、午後に15分といった形で休憩時間を分割すれば、隙間時間を見つけて休んでもらうことができます。
労働基準法のルールで重要なのは、1日を通して最低限度の休憩時間を確保することなので、1日8時間を超えて働く場合でも、合計1時間こまめに休んでもらえば問題にはなりません。
6-2. 上司が率先して所定の休憩を取る
休憩中に仕事をする従業員が目立つ場合は、上司に周知して、管理職から率先して休憩を取ってもらうのも効果的です。有給や育休の取得と同様に、上の立場にいる人が積極的に休めば、職場の部下も自然と同じように休憩を取ることができるようになるでしょう。
6-3. 定期的に従業員共通の休憩時間を設ける
社内に喫煙者がいる場合、「タバコ休憩の有無」が問題になる場合もあります。人それぞれの事情からくる休憩時間の不公平感を減らしたい場合は、定期的な従業員共通の小休止を作るのもおすすめです。
たとえば、1時間に1回、誰でも自由に席を立てる5分から10分程度の休憩時間があれば、非喫煙者も休めるので苦情が少なくなるでしょう。
小休憩を増やすかわりに昼休憩を40分に短縮するといった対応を取れば、従業員1人あたりの労働時間が減り、仕事の能率が下がってしまう心配もありません。
7. 労働時間と休憩時間の関係を把握して生産性を高めよう

労働基準法における休憩の原則は、以下のように定義されています。
- 勤務時間中に与える
- 全員に同時に与える
- 仕事から完全に離れた自由時間を与える
休憩の考え方や取得ルールを誤解していると、労働基準法違反で摘発されたり、未払い賃金の支払いを求められたりしてしまいます。長い目で見た場合、休憩時間をごまかすほうが企業にとってリスクが大きいです。
勤怠管理を担当する人事担当者は、会社を守るため、そして従業員の生産性を高めるために、従業員へ適切な休憩を与えましょう。
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の計算時間や付与ルールについて、本記事の内容をわかりやすくまとめた無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」
「必要な休憩時間数をいつでも確認できるようにしたい」
という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。 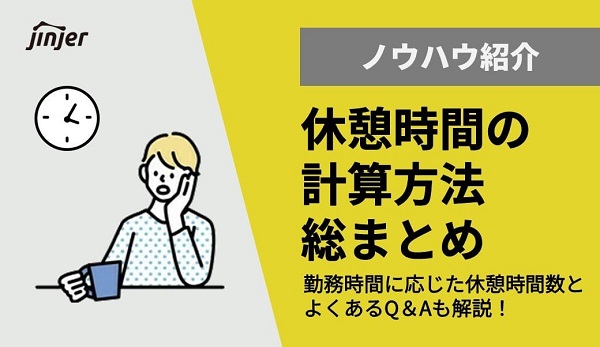
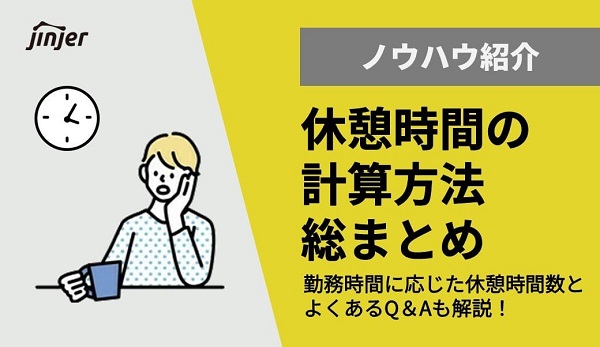
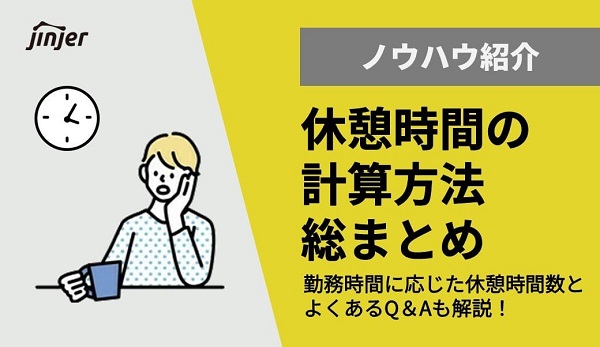
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25




















