2021年の大幅な税制改正とは?最新の情報と2025年分所得税の精算について解説
更新日: 2025.12.19 公開日: 2022.3.11 jinjer Blog 編集部

新型コロナウイルスの影響を受け、2021年は多くの税制改正がおこなわれました。すでに元の生活に戻りつつありますが、そうした税制改正は2025年の時点では継続しています。
また、リモートワークや副業をはじめとした新しい働き方や、多様化した働き方に対応するために、税率や税制の見直しも頻繁におこなわれています。
本記事ではどのような税制改正がこれまでに実施されたのか、2025年度税制改正についての情報とあわせて解説していきます。
関連記事:所得税とは?源泉所得税や定額減税など複雑な処理を詳しく解説
目次

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 2021年の所得税関連の税制改正とは
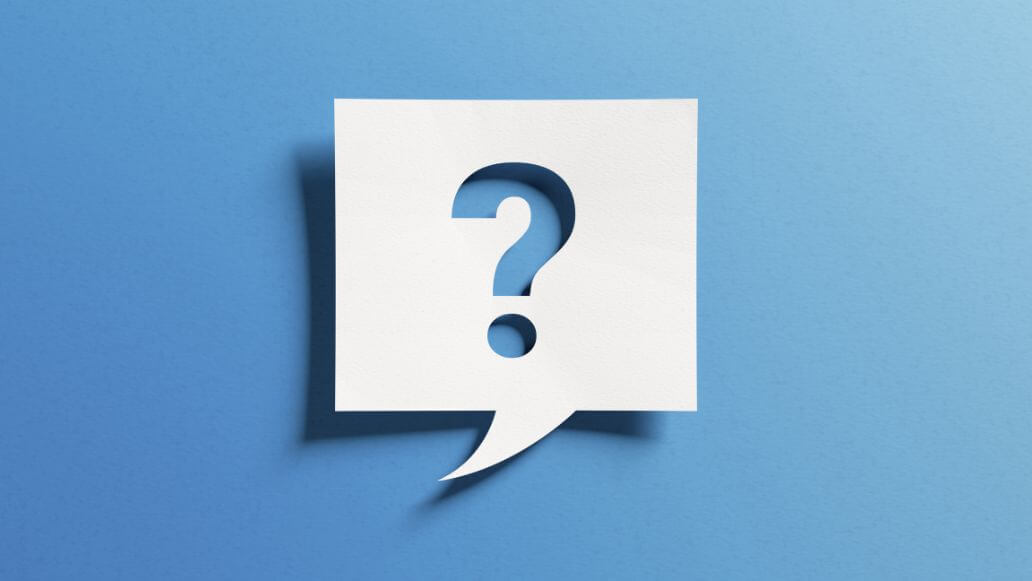
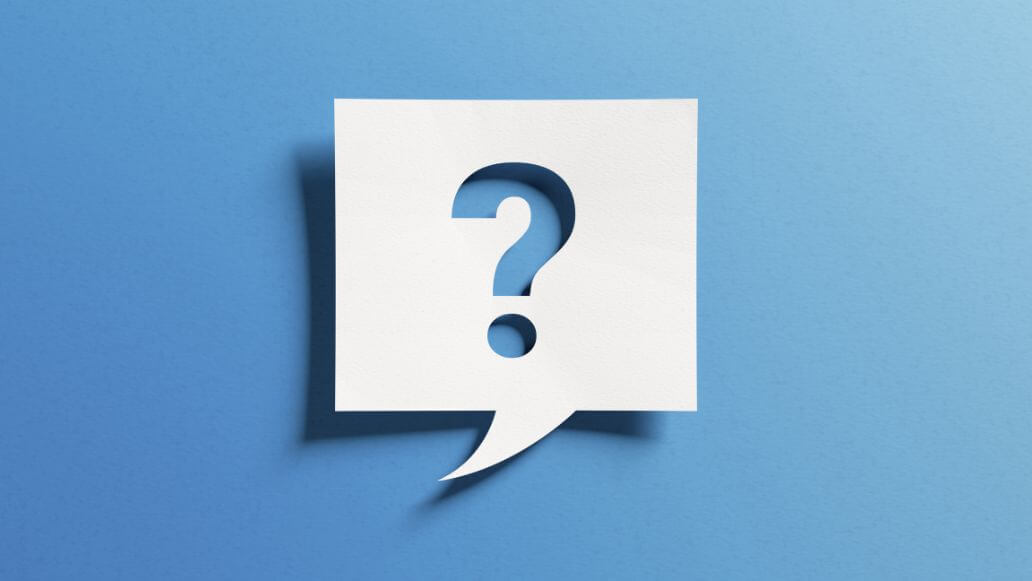
2021年の所得税関連の税制改正は、新型コロナウイルス感染症によって生じた社会経済環境の変化に対応するため、住宅ローン控除の特例延長など、納税者の負担を軽減し経済を下支えすることを目的として実施されました。
このような改正の動向からも、今後、大規模災害や感染症の再拡大、急速な物価上昇など、社会情勢の変化が生じた場合には、政府が状況に応じて所得税制度を柔軟に見直す可能性が高いと考えられます。
ここでは2021年に所得税関連で税制改正されたものについて解説していきます。
1-1. 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築をおこなった場合に、一定の要件を満たすことで、年末のローン残高に応じて減税を受けられる制度です。元々は、一定の要件に該当すれば、住宅ローンの年末残高の1%相当の所得税が10年にわたって控除されていました。
しかし、消費税率が10%に引き上げられたことを受け、一定の住宅を新築・取得して自ら居住した場合には、控除期間を3年間延長できる特例(最大13年)が設けられました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、この特例の入居期限が延長されました。
1-2. セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制とは、対象となるOTC医薬品(処方せん無しに購入できる医薬品)を購入した時に適用となる制度です。市販薬の購入費用が年間で1.2万円を超過した場合に課税対象の所得からその金額を差し引くことが可能となります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除内に特例として存在する制度です。この制度が利用できる期限は、元々は2021年12月までと定められていましたが、2021年の税制改正により、期限が5年間延長されて2026年12月まで利用できるようになりました。加えて、対象となる医薬品についても一定の見直しがおこなわれました。
1-3. エコカー減税・環境性能割の延長
エコカー減税は、国土交通省が定める環境基準を満たす自動車の購入者に対して、環境性能割と自動車重量税が減税される制度です。元々は2021年4月末で終了予定だった制度ですが、2021年の税制改正により、適用期限が2年間延長されました。そこからさらに延長がされ、2026年3月31日が2024年の時点で提示されている期限です。
現在の燃費基準を達成している車種に限っては2年間の免税が継続されます。
基準を達成していない車種も再度施行される燃費測定試験の基準をクリアすれば、2年間免税が継続します。
また、環境性能割(自動車取得税の代わりに導入された課税制度)もエコカー減税と同様に、元々は2021年3月末で終了予定の制度でしたが、2021年の税制改正に伴い2021年12月末まで期限が延長となりました。こちらも再延長され、2026年3月31日が2024年の時点で提示されている期限です。
1-4. 退職所得課税の適正化
退職所得とは、退職によって一時的に受け取る給与(退職金や退職手当)を指します。退職所得の場合、他の所得とは分けて計算する分離課税の特別措置がされています。
特別な措置理由として、退職所得は「長年の働きに感謝する」という配慮から、税負担の軽減等がされていました。
しかし、近年は短い期間で退職し、転職や起業するケースが増えてきました。
そのため、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当については、1/2課税の適用に上限額が設けられることになりました。
この制度が実際に適用されるのは、2022年以降の所得税からとなっています。
本章で解説したように、税制は細かく改正されており、給与計算をおこなう際や年末調整・確定申告の際にミスが起きやすいため、気を付けて業務に取り掛かる必要があります。
当サイトでは、税金の計算方法や計算時に気を付けるべきポイントなどを解説した資料を無料で配布しております。税金の計算において不安な点がある方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
2. 2022年以降の所得税関連の税制改正


2022年からも税制は改正され続けており、さまざまな変化がありました。制度そのものや課税方法の変更、限度額の見直しなど、大きな変化を中心に2025年までの変化を確認しておきましょう。
2-1. 2022年までの変更点
2022年までに実施された改正には、子育て支援制度の変更や退職所得の取扱い見直し、さらに住宅ローン控除に関する措置の改正などが含まれます。
子育てに関連する非課税措置
国や自治体などから子育てに関連する助成金や給付金を受けた場合は、雑所得として処理し、確定申告をする必要がありました。
しかし、この見直しがおこなわれてから所得税・住民税ともに非課税として扱われるようになっています。会社がおこなう対応はありませんが、もしも従業員から相談された場合は説明できるようにしておくとよいでしょう。
退職所得の課税方法の変化
退職所得には、退職所得控除や1/2の制度があります。これまでは勤務年数を問わず「退職所得 = (退職金支給額 - 退職所得控除額)× 1/2」という計算式で、退職所得が算出されていました。
しかし、2022年分の計算からは、勤続年数が5年以下で300万円を超えた部分の退職金には、この1/2が適用できなくなりました。
住宅ローン控除の適用期限・借入限度額等の見直し
住宅ローン控除は以前からあるものですが、2022年度に適用期限や借入限度額などの見直しがおこなわれました。
住宅ローンの適用期限(令和3年12月31日)が4年延長されたり(令和7年12月31日まで)、控除率が1%から0.7%に変化したり、住宅を購入した人にとっては大きな改正になっています。
居住用財産の買換え等に関する特例等の見直し
マイホームを売却して新しい住宅を購入した場合、一定の条件を満たすと、売却益に対する課税を将来に繰り延べられます。これは、売却益が完全に非課税になるわけではなく、新しい住宅を将来売却する際まで課税を先送りできる制度です。
もともと適用期限が設けられていたこの「買い替え特例」ですが、令和4年度税制改正によって適用期限がさらに2年間延長されました。特例の適用にはさまざまな条件がありますが、所得税に大きな影響を与える重要な改正のひとつです。
2-2. 2023年の変更点
2023年の所得税改正では、スタートアップ企業の成長を後押しするための新たな税制措置が導入されたほか、特定非常災害による損失については繰越控除期間の見直し(延長)などもおこなわれました。
スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
2023年4月1日以降、個人が保有する株式を売却した場合に、その売却益(譲渡益)について一定の条件下で課税が猶予される新たな制度が創設されました。
具体的には、売却した株式の譲渡益を「自己資金による創業」や「プレシード・シード期のスタートアップ(一定のエンジェル税制の対象企業である未上場ベンチャー企業)」に再投資する場合、再投資分については譲渡益課税が免除されます。
この制度により、個人投資家は、売却益を次世代の起業や革新的なスタートアップへの投資に回すことで、資金循環を促進しつつ、税負担を軽減できるようになります。特に、創業初期のスタートアップにとっては、成長資金の確保がしやすくなる点で大きな支援策となっていることでしょう。
特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し
2023年4月1日以後に発生した特定非常災害によって住宅や家財などに被害を受けた場合には、これまでよりも手厚い税制上の支援が受けられるようになりました。従来、災害による住宅・家財の損失について雑損控除を適用すると、その年の所得では控除しきれなかった金額は3年間に限り繰り越して控除することができました。
しかし、近年の大規模災害の増加を踏まえ、2023年4月1日以後に生じた特定非常災害に係る損失については、この繰越控除期間が3年間から5年間へ延長されています。これにより、復旧が長期化しやすい大規模災害の被災者でも、所得状況に応じてより長い期間にわたり控除を活用しやすくなりました。
さらに、住宅・家財の損失だけでなく、特定非常災害によって事業や不動産収入などに損失が生じ、純損失となった場合も同様です。一定の要件を満たすことで、この純損失についても繰越控除期間が従来の3年間から5年間へ延長されます。これにより、被災によって収入が大きく減少した事業者や、不動産収入が損なわれた納税者にとっても、より柔軟に税負担を軽減できる制度となっています。
2-3. 2024年の変更点
2024年の所得税関連の変更で注意したいのは、定額減税が実施されたという点です。今後も同じような制度が実施される可能性があるので、このタイミングで確認しておきましょう。
定額減税の実施
定額減税とは、物価上昇による家計の負担を軽減し、国内消費の活性化を図ることを目的として実施される制度です。令和6年度税制改正により、2024年6月から所得税と個人住民税を合わせて1人あたり4万円(所得税3万円・住民税1万円)が減税されました。
会社は、2024年6月以降の給与や賞与の支給時に定額減税を適用し、年末調整で過不足を精算する必要があります。今回の措置は一時的なものですが、今後も同様の制度が導入される可能性があるため、この機会に仕組みを理解しておくとよいでしょう。
子育て世帯等の住宅ローン控除の拡充
「子育て世帯等の住宅ローン控除の拡充」とは、住宅価格の上昇や子育て世帯への支援強化を目的として、住宅ローン控除のうち子育て世帯や若年夫婦世帯を対象にした優遇措置を拡大する制度です。
具体的には、「子育て特例対象個人」に該当する者が、2024年1月1日から12月31日までに一定の省エネ基準を満たす住宅を新築・取得して居住を開始した場合、住宅ローン控除の借入限度額が一般世帯よりも引き上げられる特例が適用されます。
2-4. 2025年の変更点
2025年度税制改正では、給与所得控除や所得控除の内容が大きく見直されています。基本的にすべての納税者に関係する基礎控除についても改正がおこなわれているため、多くの人に影響が及ぶといえるでしょう。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
基礎控除の引き上げ
2025年分の所得税計算から、基礎控除額が次のように引き上げられます。令和7年分・令和8年分と令和9年分以降で一部の控除額が異なるため、変更点を確認しておくことが重要です。
|
合計所得金額 |
令和7年分・令和8年分 |
令和9年分以後 |
|
132万円以下 |
95万円 |
|
|
132万円超え336万円以下 |
88万円 |
58万円 |
|
336万円超え489万円以下 |
68万円 |
|
|
489万円超え655万円以下 |
63万円 |
|
|
655万円超え2,350万円以下 |
58万円 |
|
|
2,350万円超え2,400万円以下 |
48万円 |
|
|
2,400万円超え2,450万円以下 |
32万円 |
|
|
2,450万円超え2,500万円以下 |
16万円 |
|
|
2,500万円超え |
0円 |
|
基礎控除額の引き上げにより、より多くの納税者の課税所得が減少し、結果として税負担の軽減が見込まれます。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
2025年分の給与所得の計算から、次のように給与所得控除の最低保障額も引き上げられます。
|
給与等の収入金額 |
給与所得控除の金額 |
|
|
改正後 |
改正前 |
|
|
162万5,000円以下 |
65万円(最低保障額) |
55万円(最低保障額) |
|
162万5,000円超え180万円以下 |
収入金額 × 40% – 10万円 |
|
|
180万円超え190万円以下 |
収入金額 × 30% + 8万円 |
|
このように、給与所得控除と基礎控除の引き上げにより、2025年分以降は給与収入160万円以下であれば、所得税はかからないことになります。
関連記事:年収103万円以下のアルバイトは年末調整が不要?令和7年分から160万円以下へ基準が変更!
特定親族特別控除の新設
令和7年度税制改正により、新たに「特定親族特別控除」という所得控除が創設されました。特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の一定の人がいる場合に、最大63万円の所得控除を受けられる制度です。なお、特定親族の合計所得金額に応じて、次のように控除額が段階的に減少する点が特徴です。
|
特定親族の合計所得金額 |
所得控除額 |
|
58万円超え85万円以下 |
63万円 |
|
85万円超え90万円以下 |
61万円 |
|
90万円超え95万円以下 |
51万円 |
|
95万円超え100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超え105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超え110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超え115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超え120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超え123万円以下 |
3万円 |
特定親族特別控除の新設で、もし子のアルバイトなどによる所得が一定額を超えて扶養控除の対象とならない場合でも、合計所得金額が123万円(給与収入が188万円)を超えなければ、特定親族に該当し、その子を扶養する者は特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族等の所得要件も次のように改正されています。
- 扶養親族および同⼀⽣計配偶者の所得要件:58万円以下
- ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の所得要件:58万円以下
- 勤労学⽣の所得要件:85万円以下
例えば、配偶者のその年の合計所得金額が50万円の場合、従来は所得要件が48万円以下のため配偶者控除を受けられませんでしたが、2025年分以降は控除を受けられるようになります。
2-5. 2026年以降に予想される税制改正は?
税制改正は各省庁から提出される「改正要望」をもとに検討・実施されます。したがって、令和8年度税制改正要望を確認すれば、今後導入される可能性のある制度改正をあらかじめ把握することが可能です。具体的には、次のような所得税に関連する見直しが検討対象となっています。
- 暗号資産取引に係る課税の見直し
- 金融所得課税の一体化
- 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し
- NISA対象商品の拡充を含む制度の充実
さらに、物価上昇への対応策として「給付付き税額控除」の導入が検討される可能性も指摘されています。これらの内容は現時点ではまだ決定事項ではありません。今後の税制改正の動向を注視し、制度が正式に決定した際には速やかに社内で情報を共有し、実務対応を強化することが重要です。
3. 【会社担当者向け】税制改正に対する実務対応


税制改正は毎年実施されるため、給与計算や年末調整の担当者は、改正内容を早期に把握し、正確に対応することが求められます。ここでは、実務において特に重要となる対応ポイントを解説します。
3-1. 最新の税制改正を給与計算や年末調整に反映させる
税制改正により、所得税率や控除制度などは変更されることがあります。最新の改正内容を反映させずに給与計算や年末調整をおこなってしまうと、正しい所得税額を計算・納付できず、結果的に従業員へ不利益を与えるおそれがあります。
また、源泉所得税の納付漏れ・遅れが発生した場合には、延滞税や不納付加算税といったペナルティ(罰金)が会社に課される可能性もあるのです。小さな見落としでも会社全体の信頼を損なうリスクがあります。
そのため、最新の税制改正をいち早くキャッチアップし、日頃から情報を収集する体制づくりが重要です。国税庁などの公式発表だけでなく、専門ニュースサイトや税理士事務所の解説記事など、複数の情報源を定期的にチェックする仕組みを整えておきましょう。
関連記事:2025年(令和7年)の年末調整の変更点!手続きのポイントもわかりやすく解説
3-2. 早期にシステム改修を実施する
税制改正の内容を反映するためには、給与システムや年末調整システムの改修が欠かせません。ベンダーが提供するアップデートを適用するだけでなく、自社独自の給与規程や支給項目に影響がないかも併せて確認する必要があります。
特に、改修作業が年末に集中すると業務負担が増すので、早めのテスト運用と動作確認をおこなうことがポイントです。スムーズな対応のためには、早い段階から改修計画を立て、テスト環境で実際のデータを用いた検証をおこなうことがポイントです。テスト段階で不具合を洗い出しておくことで、本番稼働時のトラブルを防止できます。
さらに、近年は電子申告(e-Tax・eLTAX)など、電子化対応が求められるケースも増えています。これらの新たな仕組みを導入する際は、社内の情報システム部門との連携を密にし、セキュリティや運用手順の確認も忘れずにおこないましょう。
関連記事:年末調整の電子化とは?やり方、企業におけるメリット・デメリットを解説
3-3. 従業員への案内と問い合わせ対応を丁寧におこなう
税制改正の影響は、従業員の手取り額や控除内容など、個々の生活にも直結するため、社内への丁寧な周知が欠かせません。特に、扶養控除・配偶者控除の見直しや生命保険料控除・地震保険料控除などの保険料控除の改正がおこなわれた場合は、従業員からの問い合わせが増える傾向があります。
そのため、会社としては改正内容や影響範囲をわかりやすく整理した案内資料を用意し、スムーズに対応できる体制を整えておくことが重要です。また、年末調整時には改正点を反映した記入例を配布すると、従業員が迷わず手続きを進められます。
4. 2025年分の所得税を精算する流れ


ここでは、2025年分の所得税がどのように計算・調整されるのか、実務担当者にも理解しやすいように順を追って解説します。
【2025年分の所得税精算に関する主な期限】
- 年末調整後の源泉所得税の納付期限:2026年1月13日(火)※納期特例の場合は2026年1月20日(火)
- 年末調整後の法定調書や給与支払報告書の提出期限:2026年2月2日(月)
- 確定申告の期間:2026年2月16日(月)から2026年3月16日(月)まで
なお、法定期限が土日または祝日にあたる場合は、その翌日が提出・納付の期限となるので留意が必要です。
4-1. 毎月の給与や賞与・ボーナスから所得税を徴収する(源泉徴収)
会社は、従業員に給与や賞与などを支払う際、あらかじめ所得税を差し引いて国に納めます。これを「源泉徴収」といいます。差し引く金額(源泉徴収税額)は、「源泉徴収税額表」に基づいて計算され、扶養親族等(配偶者や子どもなど)の人数や社会保険料の金額などが考慮されます。
ただし、源泉徴収によって毎月天引きされる所得税はあくまで概算です。そのため、実際に1年間で納めるべき所得税額とは一致しないことがあります。例えば、年の途中で結婚・離婚などにより扶養状況が変わったり、給与や社会保険料の金額が変動したりした場合などには、源泉徴収額と実際の税額に差が生じます。この差を調整するのが、年末におこなう「年末調整」です。
参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
関連記事:給与計算における所得税の計算方法とは?源泉徴収の仕組みも解説
4-2. 期限(2026年1月末)までに年末調整で源泉所得税を精算する
年末調整とは、1年間(1月〜12月)に支払われた給与や賞与などに対して源泉徴収された所得税を再計算し、実際に納めるべき税額との差額を精算する手続きです。通常は10月から12月にかけて実施され、12月分の給与支給時に過不足額を調整します。
また、精算後の源泉所得税は翌年1月10日(※納期特例を利用する場合は1月20日)までに納付する必要があります。さらに、年末調整が完了した後には、次の書類を作成する義務があります。
- 源泉徴収票:従業員へ交付
- 法定調書:税務署へ提出
- 給与支払報告書:従業員の居住地の市区町村へ提出
これらの交付・提出期限はすべて翌年1月31日までと決まっているため、年末調整の作業を12月中に確実に完了させておくことが不可欠です。
関連記事:年末調整での還付金(返金)処理はいつまでに?仕組みや方法を解説
4-3. 年末調整に間に合わない場合は従業員に確定申告を促す
年末調整時に申告漏れがあったり、年末調整後12月31日までに保険料を支払ったりした場合には、その年の所得控除額が変わる可能性があります。控除額が変わると、年末調整で算出された税額も変動するので、基本的には年末調整のやり直し(再調整)が必要です。
ただし、年末調整には源泉所得税の納付期限や法定調書の提出期限があります。そのため、期限内に再調整が間に合わない場合は、従業員本人に確定申告をしてもらい、還付を受けてもらう対応も可能です。確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。還付申告の場合は翌年1月1日から5年間申告できます。
なお、追加で所得税を納付する必要がある場合には、会社を通じて再調整をおこなう必要が生じることもあります。そのため、従業員が確定申告で内容を修正する場合は、会社へも必ず報告してもらうよう周知しておくと安心です。
参考:No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁
関連記事:年末調整の再調整は可能!方法やポイントをわかりやすく解説
4-4. 年末調整をミスしたら?どのような対応が必要?
年末調整で会社側にミスがあった場合、所得税法で定められた年末調整の実施義務を適切に果たしていないことになります。税務署からの指摘や従業員からの問い合わせを受けるなど、トラブルに発展するおそれがあります。
さらに、源泉所得税の納付漏れが発生している場合、申告・納付が遅れるほど延滞税などの罰金が増える可能性もあります。そのため、期限を過ぎていても、従業員への説明・謝罪を含め、速やかに年末調整の再実施をおこなうことが重要です。
すでに源泉徴収票を交付済みの場合は、訂正後の内容に基づいて従業員に再交付が必要です。同様に、法定調書や給与支払報告書を提出済みであれば、正しい内容に修正したうえで、税務署や市区町村に再提出することが求められます。
また、年末調整の誤りによって源泉所得税を過大に納付していた場合は、「誤納額還付請求書」を所轄の税務署に提出することで還付を受けられます。なお、「誤納額充当届出書」を提出すれば、過誤納金を今後納付する給与や賞与の源泉所得税に充当することも可能です。
参考:No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|国税庁
関連記事:年末調整のよくある間違いと訂正方法・やり直しを防ぐコツとは
5. 所得税関連の税制改正は毎年確認して最新の情報で処理しよう


2021年は新型コロナウイルスの影響を受け、住宅ローン控除の特例延長など、納税者負担軽減を目的とした税制改正が多く実施されました。2022年以降も、住宅ローン控除の見直しや、勤続年数5年以下の退職所得における課税方法の変更など、さまざまな改正が続いています。
さらに、2024年には物価高対策として定額減税が実施されました。2025年も基礎控除・給与所得控除の引き上げや特定親族特別控除の創設など、重要な改正がおこなわれています。
このように、税制改正は毎年おこなわれるため、給与計算や年末調整の担当者は、最新情報を早期にキャッチアップし、システムの改修や従業員への丁寧な案内をすることが重要です。



労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
所得税の関連記事
-


所得税の累進課税制度とは?年収別の計算事例や税負担軽減のポイントを紹介
勤怠・給与計算公開日:2022.04.18更新日:2025.12.19
-


所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.27更新日:2025.05.20
-


所得税率の種類一覧|給与や賞与の所得税の計算方法も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.24更新日:2025.12.19





















