給与支払報告書とは?書き方や提出方法・期限をわかりやすく解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2021.10.13
OHSUGI

支払った給与額等を市区町村に提出するための書類が、「給与支払報告書」です。給与支払報告書の書き方は複雑であり、源泉徴収票とは提出先や目的が異なります。
そこで本記事では、給与支払報告書の提出方法や期限、書き方を詳しく解説します。給与支払報告書を正しく提出するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
▼給与明細について詳しく知りたい方はこちら
給与明細とは?発行の必要性や記載する項目を詳しく紹介
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、給与支払者が給与受給者に対して支払った前年中の金額などを、市区町村に提出するための書類のことです。
給与支払報告書に記載する内容は、給与受給者本人に交付される源泉徴収票とほとんど同じであり、給与支払報告書を提出することで住民税額が決定します。
ただし、ほとんど同じといっても給与支払報告書と源泉徴収票書類は、提出先と目的が大きく異なります。
給与支払報告書は「住民税と国民健康保険の計算のため」に作成して市区町村へ提出しますが、源泉徴収票は「所得税を納めていることを証明するためのもの」であり、税務署に提出をおこなうという違いがあるので混同しないようにしましょう。
給与支払報告書は、総務省や自治体のホームページからフォーマットをダウンロードできるので、必要がある場合はいつでも入手できます。
1-1. 給与支払報告書は2つの書類で構成されている
給与支払報告書の基礎概要を理解できたところで、給与支払報告書の構成について解説します。
給与支払報告書は「個人別明細」と「総括表」の2つによって構成されています。
1つずつ詳しくみていきましょう。
個人別明細
個人別明細は、給与の支払いを受ける従業員の個人情報が記載されている書面です。記載する内容は、従業員の住所、氏名、給与額、社会保険料額などがあげられます。基本的には源泉徴収票とほぼ同じ内容なので、記載する内容に関しては特に間違いなどを意識しなくても大丈夫です。
総括表
総括表は、個人別明細書をまとめるための表紙的なものであり、何人分の個人別明細書を提出したか、退職した人の有無などを記載します。
そのため、従業員が住んでいる市区町村の数だけ作成しなければなりません。
1-2. 給与支払報告書の提出対象者
給与支払報告書の対象者は、前年1月1日〜12月31日までに給与を支払った人です。年の途中で退職した人や1度だけしか支払っていない人も対象であり、給与支払報告書を提出する必要があります。
また、給与支払報告書の対象に雇用形態は関係ありません。雇用形態が正社員ではなく、アルバイトやパートタイマーであっても期間内に給与の支払いが発生していれば、給与支払報告書に発行が必要です。前年中に退職している従業員、一度だけ給与を支払った短期契約の従業員へも提出しなければなりません。
ただし、前年中に退職した従業員に関しては、給与の支払額の合計が30万円以内の人に限り、個人別明細書を提出する義務が免除されます。
1-3. 給与支払報告書の提出期限
給与支払報告書の提出期限は例年1月31日であり、31日が土日祝日であれば翌平日が期日となります。
例えば、令和6年度分の給与支払報告書は、令和7年1月31日までに提出しなければなりません。
仮に提出期限を過ぎてしまうと、通常12ヵ月に分割される住民税が11分割、10分割というように配分が変わるため、できるだけ早めに提出しましょう。
なお、在職者の給与支払報告書を提出する場合は、提出する年の1月1日時点で住んでいる市区町村に提出する必要があります。例えば、令和7年1月31日までに提出する給与支払報告書は、令和7年1月1日現在住んでいる市区町村に提出するということです。
一方、退職者に関しては、退職日時点で住んでいた自治体に提出します。
2. 給与支払報告書の書き方
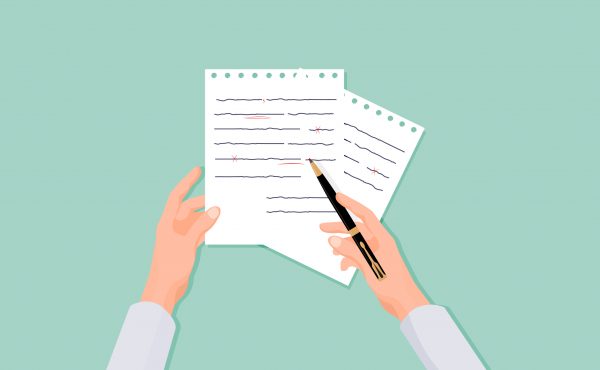
給与支払報告書の書き方については、「個人別明細書」と「総括表」に分けて解説します。
給与支払報告書を正しく提出するためにも、それぞれの書き方を理解しておきましょう。
2-1. 個人別明細書の書き方
個人別明細書の書き方は、源泉徴収票とほとんど同じです。
支払金額や源泉徴収税額、控除対象配偶者など、すべて源泉徴収票と同じように記載します。
ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいる場合と、16歳未満扶養親族がいる場合は、氏名・フリガナ・個人番号を記載する必要があります。
- 支払いを受ける者:従業員の住所や氏名などを記載する(住所は1月1日現在のもの)
- 支払金額:その年に支払った給与の総額を記載する
- 給与所得控除後の金額:源泉徴収票をもとにして給与所得控除後の金額を記載する
- 所得控除の額の合計額:社会保険料控除や生命保険料控除など、控除の合計額を記載する
- 源泉徴収税額:年末調整後に確定した源泉徴収税額や復興特別所得税を記載する
- 控除対象配偶者や扶養家族、障害者:控除対象配偶者や扶養家族などを該当箇所に記載する
- 社会保険料の金額、控除額:社会保険料や生命保険料などの控除額とその内訳を記載する
- 扶養親族:控除対象の配偶者や扶養親族、16歳未満の扶養親族の名前などを記載する
- 配偶者の合計所得:配偶者が控除対象の場合は合計所得を記載する
- 国民年金保険料等の金額、旧長期損害保険料の金額:社会保険料控除を受けた国民年金保険料などの金額を記入する
- 支払者:従業員に給与を支払った会社の情報を記載する
2-2. 総括表の書き方
総括表は基本的に市区町村から送付されるものに記入します。
そのことから、記載する内容は市区町村によって異なる場合があるため注意しましょう。
間違えないようにするには、提出先の記入例を確認しながら作成することをおすすめします。
- 給与の支払期間:前年の1月分から12月分
- 提出区分:通常は年間分であり、退職者の場合は退職者分に丸をつける
- 法人番号:事業所の法人番号を記載する
- 給与支払者:事業所の情報を記入したあと代表者印を押す
- 事業種目:事業内容を記載する
- 提出先市区町村数:提出する地区町村の数を記載する
- 受給者総人員:1月1日時点の在職者数を記載する
- 報告人員:給与支払報告書を提出する人を在職者と退職者に分ける
- 所轄税務署:所得税の源泉徴収を実施する事業所を管轄する税務署を記載する
- 給与の支払の方法およびその期日:給与の支払い方法と支払日を記載する
- 特別徴収税額の払い込みを希望する金融機関:払い込みを希望する金融機関の名称や所在地などを記入する
- 給与支払者番号:市区町村から通知された給与支払者番号を記載する(初めての場合は新規に丸をする)
本章で、住民税の金額を確定させるのに必要な給与支払報告書の記載方法を解説しましたが、そもそも住民税がどのように算出されるかは正しく理解されていますでしょうか?当サイトでは、給与支払報告書に記載が必要な所得税や住民税の計算方法を解説した資料を無料で配布しております。税率の変更や計算ミスが起きやすい給与計算業務を効率化させる方法も紹介しておりますので、給与計算業務でお悩みの方はこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
3. 給与支払報告書の提出方法

給与支払報告書の提出方法は、下記の3つになります。
- 窓口持参
- 郵送
- eLTAX
ここでは、これらの提出方法について簡単に解説していきます。
3-1. 窓口持参
窓口持参というのは、該当する自治体の窓口に直接提出する方法です。
自治体によっては給与支払報告書の枚数が異なるため、事前に確認しましょう。
3-2. 郵送
郵送は、該当する自治体へ郵便で提出する方法です。
書類の準備方法は窓口持参と同様ですが、到着までに時間を要するため、提出期限を過ぎないよう余裕を持って提出しましょう。
3-3. eLTAX
提出方法には、eLTAXによる電子申請を用いる方法もあります。
eLTAXというのは「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税の手続きをインターネットを活用して地方税の手続きを電子的におこなうシステムです。地方公共団体が共同で運営しているシステムなので、一つの窓口で各地方公共団体への手続きをすることが可能です。
利用方法は、作成したファイルをアップロードするだけなので、余計な手間を省くことが可能です。
なお、eLTAXを利用する際には利用者IDを取得する必要があるため、事前に取得しておくとよいでしょう。
4. 給与支払報告書を作成する際の注意点
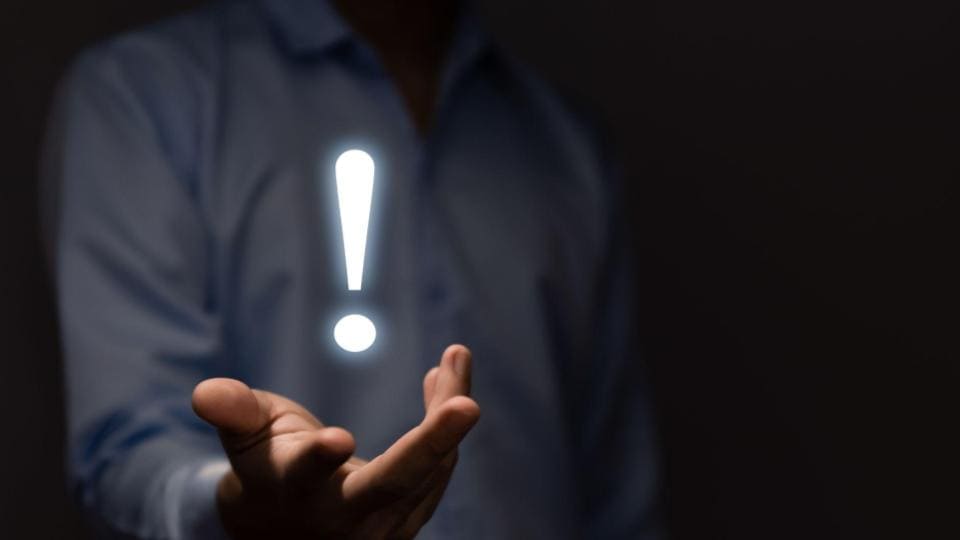
給与支払報告書には、記載する項目がたくさんあるため、従業員の人数によっては作成するだけでもかなりの労力が必要です。しかし、どんなに大変でも必ず作成しなければならない書類なので、記入漏れやミスがないようにすることが重要です。
ここでは、作成するときの注意点を解説するので、担当者の方は事前にチェックしておきましょう。
4-1. 従業員のマイナンバーを収集する
給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要です。そのため、担当者は全従業員のマイナンバーを収集しておく必要があります。
マイナンバーを収集する際には、運転免許証や通知カードといった本人確認書類も提示してもらい、間違いがないか確認しましょう。また、担当者はマイナンバーの収集だけでなく、管理も徹底しなければなりません。重要な個人情報なので、不正アクセスの防止や持ち出しの制限など適切な対策を講じましょう。
4-2. 退職者でも給与支払報告書が必要となるケースがある
退職者で、年間の給与支払額が30万円以下の場合は、給与支払報告書を提出する必要はありません。
ただし、30万円を超える場合は、例えすでに退職している従業員であっても給与支払報告書を提出する必要があります。また、市区町村によっては、30万円以下であっても提出を義務付けていることがあるので、提出先の自治体に確認をしておくことも重要です。
ちなみに、在職者は年間の給与支払額が30万円以下であっても提出しなければならないので、間違えないように注意しましょう。
4-3. 源泉徴収票の枚数によっては提出方法が限定される
2021年1月以降に提出する給与支払報告書に関しては、前々年に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAX(電子申告)もしくは光ディスクなどで提出することが義務づけられています。
税制改正前までは1,000枚以上となっていましたが、改正後の現在は100枚以上となるので、義務化の対象となっている場合は窓口や郵送での提出はできないということを理解しておきましょう。
5. 給与支払報告書を理解して正しく提出しよう

給与支払報告書は源泉徴収票とほとんど同じ内容の書類ですが、提出先と目的が大きく異なります。給与支払報告書は、市区町村が住民税額を計算するための書類なので、そこをしっかり踏まえて作成する必要があります。
また、書き方や提出方法は自治体によって違う場合もあり、あらかじめ確認しておくなどの手間もあるので、業務負担が増えるかもしれません。
負担が大きい場合は、提出方法を「eLTAX」にするなどの工夫をおこなってみてください。特に、初めて給与支払報告書を作成する方は、ミスがないよう報告書を正しく理解するという工程も増えるので、業務負担を軽くしてスムーズに提出できるように準備を整えておきましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25






















