一日の労働時間の基準と上限を労働基準法からわかりやすく解説
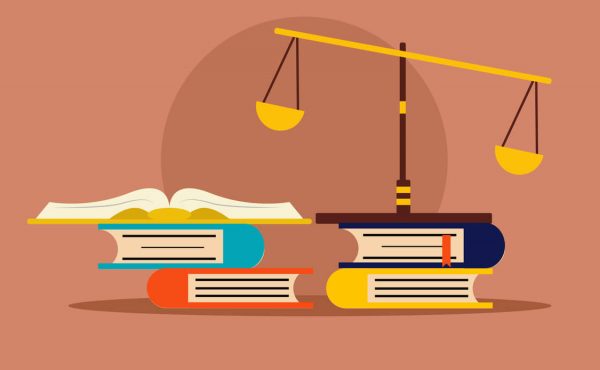
一日の労働時間は労働基準法によって「8時間まで」と定められています。労働基準法で決められた法定労働時間を越えて従業員に働いてもらう場合、会社と従業員の間で残業・休日などに関する取り決めである「36協定」の締結が必要です。
36協定を結ばずに労働時間を超過してしまうと、会社側が労働基準法違反で処罰されてしまうため、労働時間の管理には細心の注意を払いましょう。
ただ、そもそも一日の労働時間上限について正確に理解していなければ、適切な勤怠管理をすることができません。
今回は、労働時間に関して違法にならないために知っておきたい一日の労働時間制限や、労働時間上限を越えた場合の対処法、一日の労働時間をオーバーしないようにするための対策などをご紹介します。
関連記事:労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
人事担当者様からの労働時間に関するご質問回答BOOK!
勤怠管理をおこなう上では、労働時間の定義や、労働させられる時間の上限、休憩を付与するルールなどを労働基準法に基づいて正確に知っておかなければなりません。とはいえ、労働時間や休憩などに関するルールを毎回調べるのは大変ですよね。
当サイトでは、労働基準法に基づいた労働時間・残業の定義や計算方法、休憩の付与ルールについての基本をまとめた資料を無料で配布しております。【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
この一冊で労働時間の基本をおさえることができる資料となっておりますので、勤怠管理を初めて行う方におすすめの資料です。ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次
1. 一日の労働時間の上限は原則8時間

企業における労働時間の上限は、原則8時間です。
残業代が発生するかどうか、会社が法律違反で処罰されるかどうかなど、さまざまな点で「労働時間8時間」がボーダーラインになってくるため、まずは一日の労働時間の上限についておさえておきましょう。
1-1. 一日の労働時間は労働基準法で制限されている
労働基準法は、日本における「働き方」の最低限のルールを定めた法律です。労働者も企業も、両者が労働基準法の基準を守って働く必要があります。
そんな労働基準法第32条第2項で定められているのが「1日の労働時間は8時間まで」という制限です。
法律によって一日の労働時間を制限している理由は、ルールがない状態だと立場の強い企業側が労働者に無理な働き方を強制してしまう可能性があるからです。
実際のところ、お給料を払って雇用をしている側のほうが、強い立場にあることが多いです。
そのため、法律で労働者の権利を保障しておかないと、不利な労働契約が増えてしまうリスクがあります。このリスクを軽減し、労働者側の生活を守るために、法律で一日の労働時間を8時間に制限しているのです。
ただし、一日の労働時間の上限は8時間ですが、これを下回っていれば、何時間に設定しても問題ありません。
1-2. 労働時間の定義は「企業の指揮命令下にある状態」のこと
労働時間とは、「企業の指揮命令下にある状態」のことを指しています。
名目上どのような時間であったとしても、事実として会社の仕事をしていたり、会社の指示によって何らかの作業をしていたりする時間は、あくまでも労働時間です。
例えば、「昼休憩中も電話がかかってくるかもしれないため、オフィスのデスクで食事をしている」という状況は、多くの人が休憩を取っているように感じるでしょう。
しかし、厳密にいうと「顧客からの電話を待っている状態」であり、「電話がかかってきたら業務として電話対応をする必要がある状態」なので、休憩時間にはなりません。
企業が従業員に休憩を与えるときは、完全に仕事から切り離した自由な時間を与える必要があるのです。
また、仕事を家に持ち帰らないと終わらないような量・時間帯に仕事を上司が部下に頼んだ結果、自宅での作業が必要になった場合も、業務をした場合はは労働時間に含まれます。
企業は労働時間を設定することのほかに、実際に労働した労働時間を従業員ごとに集計・管理することが義務付けられています。
上司や人事側の理解が浅く、従業員側が労働時間の定義を知っている場合、「残業ではない」としていた時間分の未払い給与請求を起こされる可能性があるので、人事は労働時間の定義を理解しておきましょう。
1-3.アルバイトにも労働時間の上限がある
アルバイトでも、労働基準法によって労働時間の上限が決められています。
「一日8時間」という上限は、正社員だけに当てはまるものではなく、アルバイトやパート、非正規雇用社員など雇用形態に関わらず適用されます。
そのため、アルバイトの労働時間が一日8時間を超える場合は、残業代が発生するので注意が必要です。
また、かけもちをしているアルバイトの場合は、それぞれの企業で8時間を超えなくても、労働時間の合計は一日8時間を超えないようにしなければなりません。8時間を超えた労働は残業扱いになり、原則として後から雇用契約を交わした企業が割増賃金を支払うことになります。
もしも、自社が他の企業よりも後に雇用契約をしていて、一日の労働時間の上限を超えて働かせている場合、残業代を支払わないと罰則の対象となるため、掛け持ちをしていないか確認することをおすすめします。
2. 所定労働時間、法定労働時間、実労働時間の違い
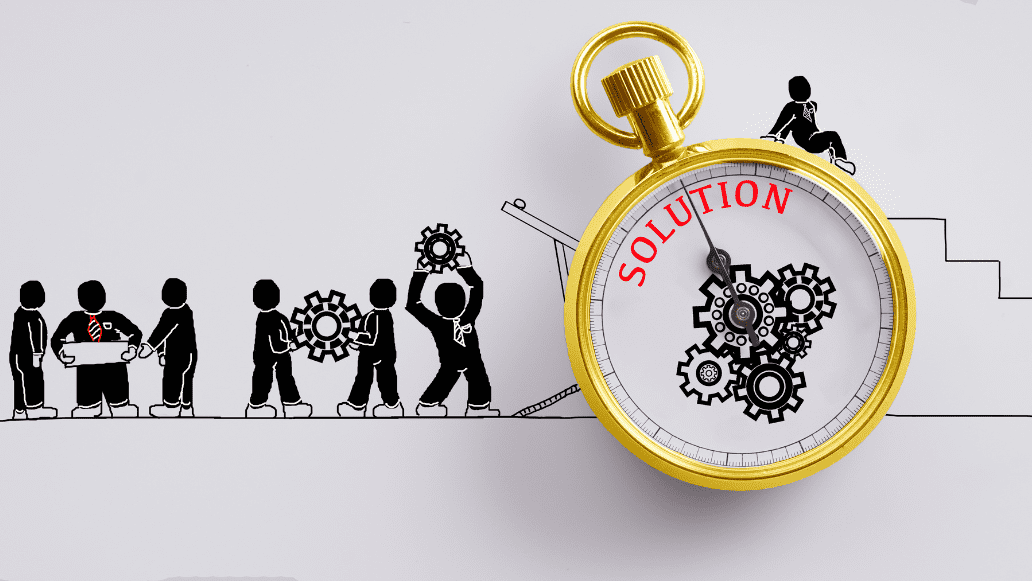
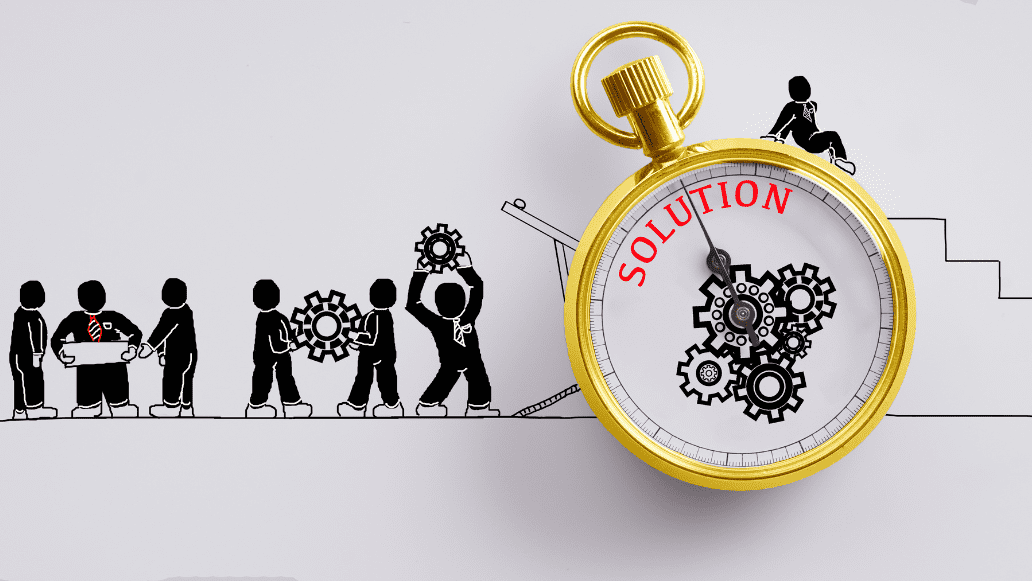
労働時間の制限について考える際に重要なポイントのひとつが、「所定労働時間」、「法定労働時間」、「実労働時間」の違いです。まずは、それぞれの定義を見ていきましょう。
2-1. 法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法の第32条で定められた「労働時間は一日8時間、週40時間まで」という基準です。
2-2. 所定労働時間
所定労働時間とは、入社時に決めた始業から終業までの時間から、休憩時間を引いた契約の際に取り決めた勤務時間のことです。所定労働時間を設定する場合は、原則法定労働時間より長くすることができません。
2-3. 実労働時間
実労働時間とは、法定労働時間や所定労働時間にかかわらず、実際に働いた時間のことです。
例えば、朝9時に出社して1時間の休憩を取得し、17時で定時を迎えるという内容で雇用契約を結んでいるとします。終業時間から始業時間を差し引いた時間の中には休憩時間が含まれるため、この場合の所定労働時間は7時間です。
実労働時間は実際に働いた時間なので、所定労働時間に時間外労働時間(残業)をプラスしなければなりません。もし3時間残業をしていて、20時に退勤した場合の実労働時間は10時間です。
労働基準法では、「法定労働時間を越える労働」に対して割増賃金の支払いを義務付けています。そのため、所定労働時間と法定労働時間を混同していると、残業代が必要な従業員に支払わなかったり、残業代の必要がない従業員に支払ったりする可能性があります。
従業員の残業代を正確に計算するために、人事担当者はそれぞれの労働時間に関する定義や基準を理解しておきましょう。
関連記事:労働時間とは?社会人が今さら聞けない基本情報を徹底解説!
3. 残業時間も含めた一日の労働時間の上限とは


法律で定められた労働時間の上限は8時間ですが、残業をしなければ業務が終わらない場合もあるでしょう。ただ、残業時間にも上限があるため、「何時間でもさせて良い」というわけではありません。
では、8時間を超えた部分の労働時間については、何時間が上限になるのでしょうか。ここでは、上限に関する3つの指標をご紹介します。
3-1. 時間外労働には36協定の締結が必要
法定労働時間を超える労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結が必要です。。36協定とは、時間外労働や休日労働をさせる場合に労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る協定のことです。
この36協定を届け出る際は、「一日」「一ヵ月」「一年間」で法定労働時間を超えて働かせられる労働時間を所定の書類に記載しなくてはなりません。
したがって、残業時間を加えた一日の労働時間の上限は、法定労働時間である8時間と、自社が届け出ている36協定に記載された一日に法定労働時間を超えて労働させられる時間を足し合わせた時間数になります。
例えば、自社の36協定に記載された一日あたりで法定労働時間を超えて労働させられる時間が2時間であるなら、8時間+2時間で、10時間が一日の労働時間の上限となります。
3-2. 法律で36協定の上限規制がある
残業時間には、法律で規制されている上限が存在します。先ほどご紹介した36協定に記載する「一ヵ月」「一年間」で法定労働時間を超えて働かせられる労働時間数は、企業が自由に定められるものではなく、法律でその上限が決まっています。
36協定による時間外労働の上限は、「月45時間、年360時間以内」です。月20営業日あったとすると、一日あたりの残業時間は2.25時間となり、法定労働時間とあわせると、10.25時間=10時間15分が一日の労働時間の上限の目安となります。
36協定で一日の残業時間の上限を定める際の上限は特に何時間までと指定されているわけではありません。しかし、36協定の月と年の残業時間の上限を考慮した時間に設定する必要があるので注意しましょう。
なお、特別な事情がある場合、あらかじめ特別条項付き36協定を締結し、労働基準監督署長に提出しておくことで、例外的にこの上限を超えることができます。ただしその際でも無限に残業させて良いわけではなく、「月100時間未満、年720時間以内」など一定の範囲内におさめなければなりません。
この上限を一日の労働時間に換算すると、100時間÷20営業日で5時間となるので、一日の最大労働時間の目安は13時間となります。
3-3. 勤務間インターバルを考慮した時間
36協定で締結されている残業時間を超えた場合は、罰則が課せられます。ただし、罰則対象となる残業時間の超過は、一日の残業時間で決まるわけではありません。法律違反とみなされるのは、法律で規制されている残業時間を、月単位や年単位で超過した場合です。
したがって、極端な例として、一ヵ月のうち一日しか残業させず、その残業時間が6時間など長時間に及んでも月の残業時間は超過しないため、問題にはなりません。
しかし、残業が長時間に及ぶと、自宅で休息や睡眠をとる時間が減り、従業員の健康に害を及ぼしかねません。
そこで国が推奨しているのが、「勤務間インターバル制度」です。
勤務間インターバル制度とは、退勤した時間と翌日出勤するまでの時間に、必ず一定数の休息時間を確保する制度です。国が推奨している休息時間は11時間以上であるため、退勤した時間から翌日出勤するまでの間に11時間が確保されない場合は、労働時間や働き方を変える必要があるかもしれません。
例えば、定時が9時~18時である場合、22時までの勤務であれば休息時間を11時間設けることができますが、22時を超えるような労働は十分な休息が取れないため、労働時間を是正する必要があると考えてよいでしょう。
関連記事:勤務間インターバル制度とは?導入方法や助成金について解説
4. 一日の労働時間に応じて休憩を与える必要がある

労働基準法では、一日の労働時間に対する休憩時間についてルールを定めています。
そのため、一日の労働時間は原則8時間となっていますが、企業は従業員に休憩を与える必要があります。
具体的に説明すると、一日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合、最低でも45分以上の休憩が必要です。
また、一日の労働時間が8時間を超える場合は、最低1時間以上の休憩を取らせる必要があります。
休憩の付与は労働基準法で決まったルールなので、休憩なしで従業員に仕事をさせると、労働基準法違反となります。
休憩に関する注意点は、「労働時間の合間に与える」ということです。例えば、労働時間の前後、出社前や退社間際にまとめて休憩時間を設定しても、「従業員に十分な休憩を与えている」とはみなされません。
ただし、最低限必要な休憩時間を小分けにして与えることは可能です。そのため、まとまった休憩を取らせることができない場合は、15分休憩や20分休憩を組み合わせて一日の休憩時間を確保しましょう。
なお、休憩時間は従業員が一切会社の仕事をしない自由な時間なので、休憩に対して給与を支払う必要はありません。
また、
労働時間8時間・休憩1時間という勤務体制を採用している場合、企業は実働時間である8時間分の給与で、実質9時間従業員を拘束することも問題ありません。
関連記事:1日の労働時間のうち休憩時間は何分必要?労働基準法の定義を解説!
5. 労働時間の超過を防ぐ対策には勤怠管理システムの導入がおすすめ!

時間外労働が増えると、割増賃金の支払いが増えてしまい人件費が圧迫されるかもしれません。また、従業員の健康に被害を及ぼす可能性もあります。万一、労働時間の上限を超過していた場合は、労働基準監督署からの臨検が入ったり、最悪の場合処罰されることにもなりかねません。
そこで重要なのが、労働時間の超過を防ぐ勤怠管理システムの導入です。
タイムカードや出勤簿による勤怠管理だと、労働時間の集計をしてみなければその月の残業時間が分かりません。しかし、勤怠管理システムであれば、残業時間をリアルタイムで把握することができるため、「集計してみたら法律違反になっていた」というリスクを無くすことができます。
また、労働時間の上限を超えそうな従業員とその上司にアラートを出すこともできるため、月の途中で残業時間が超過しそうな従業員の業務量を調整するなどの対策をすれば、上限超過を防げます。
勤怠管理システムがあれば、月次の出退勤情報も一覧で確認できるため、残業が多いが成果につながっていない従業員と面談をして事情を調べたり、配置転換や人員の手配などをしたりして、一人あたりの労働量を調整することも可能です。
その他にも、シフト収集・作成の機能や各種申請など便利な機能が搭載されているので人事や労務の業務負担を軽減できます。勤怠管理システムで何ができるかを知りたい方は、以下のリンクより勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る
6. 労働基準法に則った適切な労働時間を設定しよう

一日の労働時間が8時間を越えると、1.25倍の割増賃金を支払う必要があるため、労働時間をしっかりと管理することには企業側のメリットにもなります。
しかし、従業員一人ひとりの労働時間を確認するのは、時間も手間もかかります。その負担を減らし、労働時間を適切に管理できるのが勤怠管理システムです。
残業時間や労働時間をリアルタイムで把握できる勤怠管理システムを活用すれば、人件費のコストカットや生産性向上にもつながります。
労働時間を適切に管理できないと、健康に害を及ぼしたり生産性が下がったりすることもあるので、勤怠管理システムで労働時間を正確に把握して長時間労働を防ぎましょう。
人事担当者様からの労働時間に関するご質問回答BOOK!
私たちが普段働くときにイメージする「労働時間」と労働基準法での「労働時間」は厳密にみるとズレがあることがよくあります。勤怠管理をおこなう上では、労働時間の定義や、労働させられる時間の上限、休憩を付与するルールなどを労働基準法に基づいて正確に知っておかなければなりません。
とはいえ、労働時間や休憩などに関するルールを毎回調べるのは大変ですよね。当サイトでは、労働基準法に基づいた労働時間・残業の定義や計算方法、休憩の付与ルールについての基本をまとめた資料を無料で配布しております。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
この一冊で労働時間の基本をおさえることができる資料となっておりますので、勤怠管理を初めて行う方におすすめの資料です。ぜひダウンロードしてご覧ください。



勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25



















