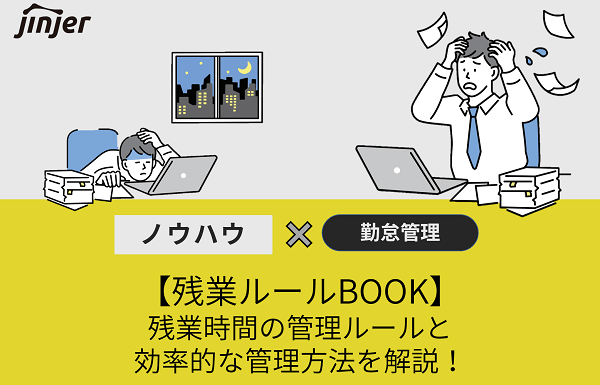中小企業が残業時間の上限規制について知っておくべき2つのポイント
更新日: 2024.5.29
公開日: 2020.7.13
OHSUGI

働き方改革関連法が2019年4月1日に施行されてから、大企業の残業規制はよる明確になり、労働に関する捉え方などに変化が見えてきました。
そして2020年4月1日、この法案は大企業だけではなく、中小企業にも適用範囲を広げました。
そのため、中小企業にも大企業と同じように残業に関する考え方や認識を、規制をもとに見直す必要があります。そこで今回は、働き方改革関連法の残業規制に関して、中小企業が知っておくべきポイントについて触れていきます。
関連記事:働き方改革で残業の上限規制はどう変わった?わかりやすく解説!
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。
法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 残業の上限について中小企業が知っておくべきこと

2020年4月から中小企業に適用される「働き方改革関連法」で何がどのように変化するのかを、中小企業の人事担当者は把握しておくことが求められます。
もともと、労働に関しては「労働基準法」がすでに施行されていました。1日8時間、週40時間を上限とした法定労働時間が定められていることは、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。
また、残業時間に関しても、あらかじめ労使間で労使協定(36協定)を締結することで、月45時間、年360時間を上限に残業をすることが可能になる仕組みがあります。さらに、特別条項付きの36協定を結ぶことで、年間6ヵ月であれば時間の上限なく残業が可能でした。
しかし、「働き方改革関連法案」によって次のように残業時間についてのルールが変更されたのです。
| 項目 | 新36協定 | 旧36協定 | |
| 有効期間 | 最大1年間 | 最大1年間 | |
| 残業時間上限 | 通常 | <通常>
月45時間、年360時間 <1年変形> 月42時間、年320時間 法的拘束力有り |
<通常>
月45時間、年360時間 <1年変形> 月42時間、年320時間 法的拘束力無し |
| 特別条項付き | ・年間6回(6ヵ月まで)
・年間720時間まで ・休日勤務含め、「複数月の平均が80時間以内、単月100時間未満」まで 法的拘束力有り |
・年間6回(6ヵ月)まで
・時間数の上限無し 法定拘束力無し |
|
| 罰則 | 36協定を結ばずに時間外労働をおこなわせた、上限を超えた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 36協定を結ばずに時間外労働をおこなわせた、上限を超えた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
このように「働き方改革関連法案」によって残業時間の上限が設けられました。
働き方改革や36協定はご存知の方が多いと思いますが、残業時間の定義になるとわからない方も少なくないでしょう。ここを理解せず残業管理をしてしまうと、気づかないうちに上限を超えてしまうようなことが起きかねません。当サイトでは、残業管理のおおもとになる各用語の定義から、本記事の本題である残業時間の上限規制についてまとめた資料を無料で配布しております。残業時間に関して不安な点が少しでもある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:残業時間に関わる「36協定」について基本をわかりやすく解説
1-1. 中小企業の残業時間上限が規制された背景
従来の残業に関するルールでは、特別条項付き36協定の場合、年6ヵ月であれば残業時間に上限が設けられていませんでした。そのため、改定前の36協定では「特別条項をつけることで無制限に残業させることができる」という認識を持つ企業が増え、長時間残業をなくすことができませんでした。この現状にメスを入れたのが、働き方改革関連法です。改正された36協定には法的拘束力が生まれ、かつ特別条項付きの残業時間にも上限時間が設けられました。この追加には、従来から問題視されていた「過労死」「超過労働による心身の崩壊」などを抑止することにつながります。
残業時間の上限は当初は大企業のみで、中小企業は猶予期間が設けられていました。しかし、2020年4月から中小企業への適用もスタートしています。
2. 残業時間の上限について中小企業がおこなうべきこと

法案の範囲拡大にともない、中小企業がまずおこなう必要があることは、「現状把握」「労働時間の管理体制の見直し」の2点です。
2-1. 自社の労働時間管理が適切におこなわれているかどうかがポイント
“現状把握”といっても労働時間に関与しない現状把握をしても意味がありません。まずは、「政府発表の指標と照らし合わせて自社の労働時間管理が適切におこなわれているかどうか」「個人の労働時間の把握」を重点的におこないましょう。
「個々の労働時間の把握」に関しては、各部門や個人単位で現状を把握することが重要です。その日の残業している人数や個々の累計残業時間、残業発生が多い部門、時期、個々の仕事量などを統合して、残業が多い原因を探ることから始めると、残業時間抑制に対する策も投じやすくなるはずです。
2-2. 労働時間管理体制の見直しは枠組みをしっかりと構築することから
いくら残業時間を抑制しようとしても、具体的にどのような枠組みで管理をすればいいのかを明確にしておかないと、管理する側にも混乱を招いてしまうでしょう。おすすめは上述した36協定の残業時間上限規制をもとに管理体制を構築することです。36協定の残業時間上限をもとに管理体制を構築することで、労働基準法を遵守した勤怠管理が可能になります。
関連記事:残業管理をわかりやすく簡潔にするルール作りのポイント
3. 従業員の労働時間の把握には勤怠管理システムがおすすめ


従業員の労働時間を把握するには、タイムカードだけではなくパソコンの使用時間や起動時間、ログアウト時間なども含めるようにし、不正や隠ぺいが無いようにするのが得策です。
勤怠管理システムであれば、不正、隠ぺいの防止だけでなく、従業員がどれだけ残業しているかを自動で集計してくれます。従業員の残業時間をリアルタイムで把握できるため、残業時間の上限超過を防ぐ管理が可能です。
他にも勤怠管理システム導入で次のようなメリットが生まれます。
- 従業員の打刻漏れを一括で確認できる
- 有給休暇の管理ができる
- スマートフォンやタブレットで打刻ができる
3-1. 従業員の打刻漏れを一括で確認できる
勤怠管理システムであれば従業員の打刻状況が一括で把握できます。打刻漏れがあった場合は従業員に向けてアラートが発せられるため、管理者が打刻漏れをアナウンスする必要はありません。その結果、打刻修正の際に発生していたコミュニケーションコストを削減できます。
3-2. 有給休暇の管理ができる
勤怠管理システムのなかでには有給休暇のを管理できるシステムがあります。このようなシステムであれば、従業員の有給休暇残数や取得数などを把握できます。
「働き方改革関連法案」によって年に10日以上の有給休暇が付与されている従業員は、5日以上の有給休暇取得が義務化されています。有給休暇を管理できるシステムであれば、対象の従業員が適切に有給休暇を消化しているかがすぐに確認可能です。
3-3. スマートフォンやタブレットで打刻ができる
勤怠管理システムであれば、スマートフォンやタブレットでの打刻も可能です。そのため、外出することが多い営業職や建設業、物流業の勤怠管理に適しています。外出先で打刻ができれば、打刻のためにわざわざオフィスに戻る必要もなくなるでしょう。
関連記事:中小企業向け勤怠管理システム|導入前の課題、導入後の効果とは
4. 残業時間の上限に関する見直しを今から始めよう!


働き方改革の適用は大企業のみという認識を持たれている方もいらっしゃったのではないのでしょうか。2020年4月からは中小企業にも適用範囲が拡大されたため、中小企業の人事担当者は今一度、自社の運用が適切におこなわれているかどうかを確認してみましょう。
また、昨今の社会情勢から、企業規模に関わらず柔軟な働き方の重要性がますます高まるでしょう。法律を遵守することはもちろん、誰もが働きやすい環境作りの一環として勤怠管理システムの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25