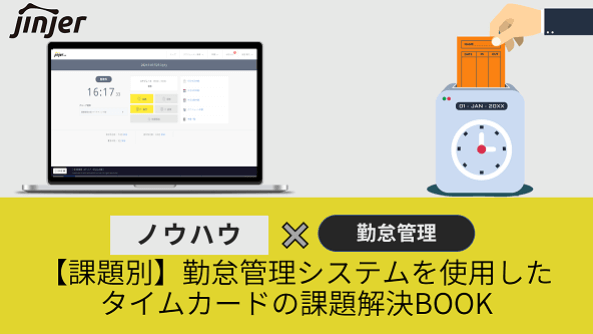タイムカードの打刻ルールは必要?ミスを減らすための具体例を解説

タイムカードを使って労働時間を管理するためには、打刻に関するルールが必要不可欠です。今回は、タイムカードの打刻ルールが必要な理由やルールを設けるうえでの具体例などについてご紹介します。
これからタイムカードを使って勤怠管理をしようと考えている方や、改めて打刻ルールを見直したい方はぜひお読みください。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 客観的な労働時間の把握のために、タイムカードの運用には明確なルールが必要


2019年4月1日からの法改正により、高度プロフェッショナル制の労働者を除くすべての従業員の労働時間を客観的に把握することが義務化されました。
これにより、始業・終業の確認及び記録の原則的な方法も定められました。
始業・終業の確認及び記録の原則的な方法の一つとして、「タイムカードでの客観的記録を基礎として確認し、記録すること」ということが設けられています。
しかし、タイムカードの押し忘れが発生すると基礎となる客観的記録が正確に把握できなくなり、実際の労働時間と乖離が生まれます。
そこで、タイムカードの打刻ルールを設けることにより、計測ミスをなくし、使用者は労働時間を客観的に把握することができます。
また、タイムカードを使って従業員の勤務時間を管理するためには、「打刻するタイミング」に対して明確なルールが必要です。
例えば、使用者は着替えの時間や掃除などの雑務の時間も労働時間として把握しなければならたいため、「打刻するタイミング」は明確化する必要があります。
2.正確にタイムカードを打刻するためのルールの具体例

前章でお伝えしたように、使用者が従業員の労働時間を客観的に把握するためには、タイムカードを打刻するルールを設ける必要があります。
本章では、タイムカードを打刻するルールの具体例についてご紹介します。
2-1. 出勤時と退勤時に必ず本人が打刻すること
打刻は出勤時と退勤時におこなうものであり、このことも就業規則に記載しましょう。
記載していない場合、打刻する時間帯が出勤時と勤務開始時間のどちらなのか分からなくなってしまいます。
また、打刻する時間帯と合わせて必ず本人がおこなうということも大切です。タイムカードは他の人でも扱えてしまうため、不正打刻がおこなわれる可能性があります。
【関連記事】タイムカードの改ざんは違法!正しい対処法や対策をご紹介
2-2.タイムカードに打刻するタイミングを明確化すること
第1章でもお伝えしたように、2019年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、新たに従業員の労働時間の「客観的な把握」が使用者の義務化されているため、使用者は労働時間の範囲を理解しておく必要があります。
具体的には、以下のような時間も労働時間に換算するため、使用者は打刻するルールを明確化する必要があります。
- 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替えなど)を事業場内においておこなった時間
- 業務に関連した後始末(清掃など)を業場内においておこなった時間
- 使用者の指示があった場合には即時に業務にあたることを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間
- 参加することが業務上義務づけられている、研修・教育訓練を受講していた時間
- 使用者の指示により、業務に必要な学習などをおこなっていた時間
例えば、タイムカードは職場に着いたタイミングではなく、始業を開始するタイミングで打刻するといったようにルールを明確にしておきましょう。
2-3. 時間外労働が発生した際の対処法
極力時間外労働は避けるべきですが、急な仕事が入ってしまい、打刻後の時間外労働が発生してしまう場合もあります。そのようなことが起きてもしっかりと対応できるようにしましょう。
例えば、打刻後の時間外労働は原則禁止にして、状況に応じては上長に相談して対応するといったルールを策定しておきましょう。打刻後であっても時間外労働が必要と判断された場合、退勤後に再度出勤したと処理するのが一般的です。なお、通常の勤務に打刻後の勤務を加えた労働時間が8時間を超える場合は、割増賃金の支払いが必要です。
2-4. 直行・直帰・在宅勤務等のルール
会社によっては直帰や在宅労働などをおこなう従業員がいることもあります。就業規則にタイムカードに関するルールを記載する場合には、自社の労働形態を考えたうえでルールを作成しましょう。例えば、タイムカードの打刻の代わりに、メール報告や社内システムへのログイン時間を出退勤時間とするルールが挙げられます。
自社のことを考えてルールを作ることにより、働き方を変えることなく、従業員一人ひとりの労働時間が管理しやすくなります。
2-5. 打刻ミスや不正打刻への対応を就業規則に明記する
打刻方法や打刻する時間帯だけではなく、打刻ミスや不正打刻に関する規定も就業規則に記載しましょう。打刻ミスや不正打刻といったトラブルに関する規定を設けることで、従業員に対して訂正な対処ができます。
例えばペナルティを与える場合、必ず就業規則に記載しておかなければなりません。ただし、就業規則に記載するだけではなく従業員にペナルティがあることや、打刻ミスをしてしまった際の対応方法をしっかりと周知して理解してもらうことも大切です。
【関連記事】タイムカードの正しい打刻方法とミスを起こさないための予防策
3.タイムカードで運用する問題点


タイムカードで運用する際はルールを策定していても、次のような問題点が発生する可能性があります。
- 集計に時間がかかる
- 従業員の勤務状況をリアルタイムで把握できない
- ヒューマンエラーが発生しかねない
3-1.集計に時間がかかる
タイムカードの運用は労働時間の集計作業に時間がかかってしまいます。従業員の労働時間は一人ひとり異なります。さらに、従業員の打刻ミスや不正があった場合は、修正作業にも時間を要しかねません。
このようなタイムカードの集計作業によって労務担当者の負担が増加してしまいます。
3-2.従業員の勤務状況をリアルタイムで把握できない
タイムカードで運用している場合、従業員の勤務状況をリアルタイムで把握できません。一般的にタイムカードの集計作業は月末~月初に実施されます。そのため、従業員がどれくらいの労働時間だったのかは集計時にしか把握できません。
しかし、会社は従業員の勤務状況を正しく把握して、時間外労働が増加していないかなどをコントロールする必要があります。このような従業員の労働時間のコントロールがタイムカードでは難しくなってしまいます。
3-3.ヒューマンエラーが発生しかねない
タイムカードで従業員の労働時間を管理していると、ヒューマンエラー発生の可能性が考えられます。具体的にはタイムカードの集計時間をまとめる集計表への記入ミスや計算ミスなどです。ヒューマンエラーに気付かずにそのまま処理してしまうと、給与額や有給休暇残数などに誤差が発生しかねません。
4.スマホやパソコンから打刻ができるの?

勤務時間を管理するうえで大切なタイムカードですが、スマートフォンやパソコンから打刻する方法もあります。ここでは、タイムカード以外で従業員に打刻もらう方法やそのメリットについて説明します。
4-1. 勤怠管理システムであれば打刻可能
勤怠管理システムを自社に導入することにより、タイムカードを使わずに打刻してもらえます。打刻できるものとしては上記で挙げたもの以外にも、タブレットや顔、指紋などがあります。システムによって打刻できるものが異なるため、導入する際に必ずチェックしてみましょう。
当サイトでは、勤怠管理業務で起きうるミスをどのように低減させられるかを解説した資料を、無料で配布しております。勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の管理画面を掲載しているため、自社の活用シーンもイメージしながらご確認いただけるでしょう。システムの導入により勤怠管理業務が効率化されそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
5. 勤怠管理システムのメリット


まずタイムカードを使わないことにより、不正打刻されてしまうことを防ぎます。そして、打刻に関する問題が起きた時でもすぐに対応できます。
勤怠管理システムによっては問題が発生した時に知らせてくれるアラート機能が搭載されているものがあるため、ミスを見逃さずに済むことでしょう。また、自動的にシステムが給与計算をおこなう機能もあり、従来のような手計算よりもミスを減らせます。
【関連記事】勤怠管理システムを導入する目的とは?メリット・デメリットも確認
5-1.リアルタイムで勤務状況を把握可能
勤怠管理システムであればタイムカードと異なり、リアルタイムで従業員の勤務状況を把握可能です。そのため、時間外労働時間が上限に達しそうな従業員がいれば、事前に時間外労働時間をコントロール可能です。また、有給休暇取得状況を把握できる勤怠管理システムもあります。このようなシステムであれば、有給休暇の取得も促せます。
5-2. 集計業務の負担が軽減
勤怠管理システムは従業員の労働時間を集計する必要がありません。システムで自動的に集計してくれます。そのため、労務担当者に発生していた従業員の労働時間の集計業務の負担を軽減可能です。
5-3. ヒューマンエラーを減少できる
タイムカードの場合、集計時のミスや従業員の打刻ミスなどのヒューマンエラーが発生するかもしれません。しかし、勤怠管理システムであればシステムで機械的に管理するため、ヒューマンエラーの発生が減少します。また、先述のように何か不備があった際にアラートを発する勤怠管理システムもあります。
6. 勤怠管理システムを活用して適切に労働時間を管理しよう

タイムカードの打刻ルールは適正な労働時間を把握するうえで欠かせないものです。今回紹介した具体例を参考にしつつ、自社の打刻ルールを改めて見直してみましょう。また、タイムカードから勤怠管理システムに切り替えて、打刻しやすい環境にしてみるのもおすすめです。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25