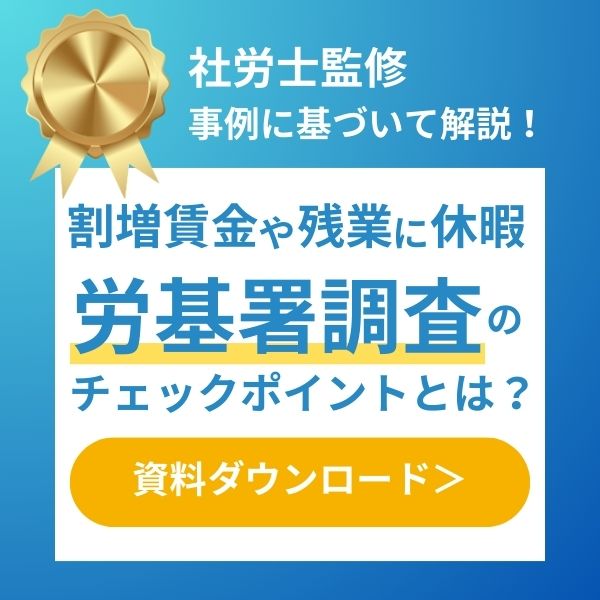在宅勤務(テレワーク)の導入で福利厚生は見直す?導入事例を紹介
更新日: 2025.5.16 公開日: 2021.11.12 (特定社会保険労務士・中小企業診断士)

近年、在宅勤務を導入する企業が増えています。
通勤ストレスの緩和などさまざまなメリットがありますが、コミュニケーション不足や運動不足になりやすいというデメリットもあります。
そこで、在宅勤務の導入に合わせて福利厚生を見直し、社員の健康をサポートするサービスを用意するのがおすすめです。
▼在宅勤務・テレワークについて詳しく知りたい方はこちら
在宅勤務の定義や導入を成功させる4つのポイントを解説
目次

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 福利厚生とは?


福利厚生とは、自社で働く従業員への非金銭的な報酬であり、給料やボーナスに加え、働く環境の向上や生活の質を高めるための制度です。主に「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。詳しく説明します。
1-1. 法定福利厚生
法定福利厚生とは、法律で定められた企業が従業員に対して提供しなければならない最低限の福利厚生制度のことです。これには、健康保険や雇用保険、労災保険、介護保険などが含まれます。これらの制度は、従業員の健康や生活の安定を保障する役割を果たし、従業員が安心して働ける環境を提供します。法定福利厚生の充実は、企業にとっても重要な社会的責任であると言えるでしょう。
1-2. 法定外福利厚生
法定外福利厚生とは、企業が従業員に対して法的に義務付けられていない、任意で提供される福利厚生のことです。これには、従業員のモチベーションを向上させたり、定着率を高めたりするための独自の制度やサービスが含まれます。具体例としては、資格取得の支援制度や、社内イベントの開催、健康促進のためのプログラムなどがあります。企業がこれらを充実させることで、従業員の満足度や働きやすさを向上させることが期待されます。
2. 在宅勤務の導入による就業規則・福利厚生を見直す必要性


「働き方改革」が施行されて以降さまざま働き方が認められるようになりました。
新型コロナウイルス感染症対策としてこれまで在宅勤務を認めていなかった企業も在宅勤務を導入する流れになっており在宅勤務を導入する企業が増えました。
また、在宅勤務にすることで通勤ストレスの解消、家族と接する時間が増えるなどのメリットがあるため在宅勤務やテレワークを導入する企業は今後も増えることが想定されます。
しかし、在宅勤務やテレワークを導入する際は従業員の働き方が大きく変わるため、企業は「就業規則」と「福利厚生」を見直す必要がでてきました。
関連記事:在宅勤務を導入する企業のメリット・デメリットを徹底解説
2-1. 就業規則の見直し
就業規則は企業が自由に決められる制度です。労働時間や賃金などの労働条件を明確にするのが就業規則で、従業員がいつでも確認できる状態にすることが求められています。在宅勤務は出勤や退勤がしやすいため勤務時間の変更があるかもしれません。また、交通費についても出社日数が減ると通勤手当の減額ができるようになります。
そのため、在宅勤務を導入する際はテレワークについて盛り込まれた就業規則を新たに作成するといいでしょう。
在宅勤務に伴い、就業規則には新たなルールやガイドラインを盛り込むことも必要です。例えば、在宅勤務中の業務報告や連絡手段、作業環境の整備に関する指針など、具体的な内容を明記することで、従業員が安心して業務に取り組むことができます。
また、在宅勤務での労働時間の管理をしっかり行うことで、適正な働き方を促進し、従業員のメンタルヘルスの保護にもつながります。
関連記事:在宅勤務の就業規則の在り方や見直しのポイントを解説
関連記事:在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
2-2. 福利厚生の見直し
福利厚生を見直すことは、企業が従業員のニーズに応えるために非常に重要です。特に在宅勤務を導入する場合、従業員が快適に仕事を続けられるようなサポートを整えることが求められます。例えば、在宅勤務手当や環境整備手当を新設することで、従業員は自宅で必要な作業設備を整えやすくなります。これにより、快適な作業環境が確保され、生産性の向上につながります。
さらに、在宅勤務の環境をサポートするために、定期的な健康診断やオンラインフィットネスへの参加を促すなど、身体的健康を維持するための福利厚生も重要です。これらの取り組みは、従業員が健康で活力のある状態で働くために必要不可欠です。
また、コミュニケーションの不足を解消するために、オンラインでの懇親会やチームビルディングイベントを企画することもおすすめです。これにより、社員同士のつながりを強め、チーム全体の士気を高める効果が期待できます。
このように、在宅勤務に特化した福利厚生を見直し、充実させることで、企業は従業員の満足度を向上させるとともに、優秀な人材を引き寄せることができるでしょう。
3. 在宅勤務の導入で検討すべき福利厚生の見直しポイント


福利厚生を見直すときは、まず在宅勤務になることによって何が変わるのか明確にするといいでしょう。
- 労働場所
- コミュニケーション
- 食事
- 育児
- 健康
以上の5つが出社勤務から在宅勤務に切り替わると変わることです。
3-1. 労働場所
在宅勤務になると自宅が仕事場になります。
オフィスで仕事するときと同じような環境を作らないと業務効率が低下してしまうおそれがあるため、同じような環境を構築する必要があります。
用意するのはパソコンやモニター、タブレットなどの仕事で利用するだけの物だけではなく、テーブルやイス、照明などの備品も必要になることがあります。
また、インターネットやスマートフォンの通信費や、光熱費なども自宅で仕事するようになると出社していたときよりも高額になってしまいます
3-2. コミュニケーション
出社しているときは、出勤時に挨拶を交わしますし昼食を同僚と食べたり、喫煙所や休憩スペースでほかの従業員と会話を交わすことがあるでしょう。
しかし、在宅勤務はほかの従業員と直接会う機会がなくなってしまうためコミュニケーションが不足してしまいます。
従業員のなかにはコミュニケーション不足が原因でストレスを抱えてしまいモチベーションが低下し、離職してしまうこともあります。このようなリスクを軽減するために、企業はオンラインツールを活用したコミュニケーションの機会を増やす工夫が必要です。
例えば、定期的にオンラインミーティングや1on1を開催し、従業員が意見やアイデアを交流できる場を設けることが重要です。
また、リモート環境でも気軽に参加できる社内イベントやバーチャル懇親会を企画することで、従業員同士のつながりを促進し、帰属意識を高めることができるでしょう。
このような施策を通じて、コミュニケーションが活発な職場環境を維持することが、在宅勤務の成功を支えるカギとなります。
3-3. 食事
弁当を持参している従業員は問題ありませんが、昼食を外食にする従業員や社食を利用する従業員は食生活が大きく変わってしまいます。
在宅勤務では昼食を自分で用意することになります。
食事のメニューを考えるのが面倒で、調理の手間がかかるからはインスタント食品ばかり食べるようになってしまうと、従業員の健康に影響が出てしまうかもしれません。
このような健康リスクを軽減するために、企業は栄養バランスを考慮した食事支援を行うことが重要です。 具体的には、食事宅配サービスの利用や、従業員向けに健康的なレシピの提供を行うことが考えられます。
また、食堂が利用できない分、オフィスで提供されていたような栄養バランスの良い食事の代替案を用意することで、従業員の健康維持をサポートすることが可能です。 さらに、時折オンラインでの「ランチミーティング」を実施することで、食事を共にしながらコミュニケーションを図ることも効果的です。
このように、在宅勤務においても食事に関する支援を充実させることが、従業員の健康促進と職場環境の向上につながります。
3-4. 育児
子育て期間中の従業員と在宅勤務は相性がいいです。
出社していたときの通勤時間にあたる時間を、保育園や小学校の送迎の時間にすることもできますし、勤務時間を調整して子育ての時間を確保することもできます。
育児と仕事の両立ができるため、子育てが終わったあとにスムーズに職場復帰できるというメリットもあります。
さらに、企業側が育児に配慮した柔軟な勤務制度を導入することで、従業員の定着率を向上させることが期待できます。 例えば、出産育児休暇後に徐々に勤務時間を増やす段階的な復職プログラムや、育児に関する相談窓口を設けることで、従業員の不安を軽減し、安心して業務に復帰できる環境を整えることが重要です。
このように、在宅勤務は育児をしながら働く従業員にとって、より良い選択肢となるでしょう。
3-5. 健康
在宅勤務中の健康管理は特に重要です。従業員が在宅で仕事をする際、運動不足だけでなく、食事の偏りやストレスも健康に影響を与える要因となります。
そのため、企業はオンラインで参加できるフィットネスプログラムや健康に関するワークショップを提供することが重要です。これにより、従業員は自宅で簡単に体を動かす機会を得られ、心身の健康を維持しやすくなります。
また、メンタルヘルスをサポートするプログラムの導入も効果的です。従業員が孤独を感じず、心理的サポートを必要とする場面で、企業がしっかりとしたサポート体制を整えていることを示すことは、従業員の安心感に繋がります。
4. 在宅勤務の導入でおすすめの福利厚生サービスの事例
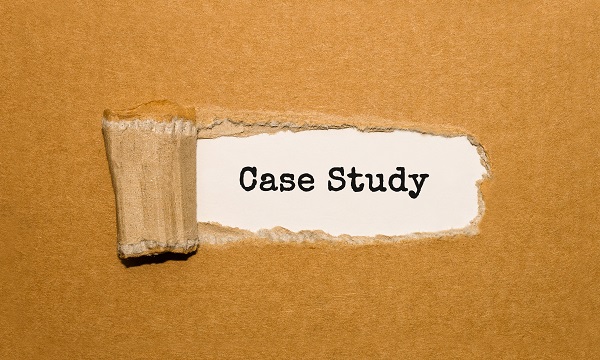
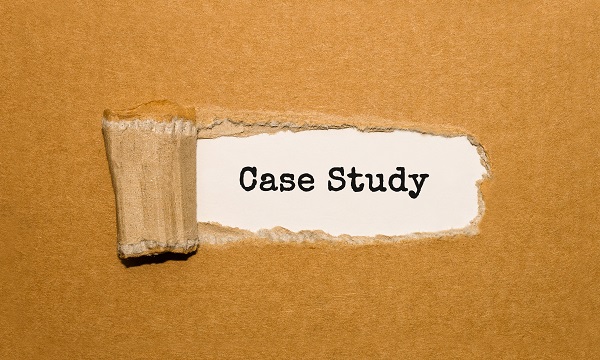
在宅勤務向けの福利厚生の例を解説します。
4-1. 在宅勤務の環境づくりサポート
自宅で快適な作業環境を整えることは、在宅勤務の生産性を高めるために非常に重要です。効率的な仕事をするためには、適切な作業スペースが必要ですが、多くの従業員にとって自宅に必要な家具や設備を揃えることは簡単ではありません。
そこで、企業が提供する在宅勤務用の環境整備サポートが役立ちます。例えば、従業員が自分に合ったデスクと椅子を選べるような補助金やレンタル制度を導入することも一つの方法です。これにより、従業員一人ひとりの作業スタイルに合わせた設備が整えられ、快適な作業環境を確保することができます。
また、作業環境を整えるためには、学習ツールやIT機器のサポートも欠かせません。例えば、必要なソフトウェアのライセンス提供や、業務用のパソコンの貸与といった支援を行うことで、従業員がスムーズに在宅勤務を開始できるようになります。
さらに、在宅勤務時には、作業環境だけでなく、周囲の音や光にも配慮が必要です。適切なカーテンや遮音パネルなどの設置支援を提供することで、より集中しやすい環境を作ることができ、業務に取り組む際のストレスを軽減する効果も期待できます。このように、多角的にサポートすることで、従業員が在宅でも効率よく働ける環境を整えることが企業にとっての重要な使命であると言えるでしょう。
4-2. 栄養バランスの摂れた食事をサポート
在宅勤務の従業員からニーズが高いのが食事補助です。
オフィスに出社していたときは、自分で食事メニューを考えることがなかった従業員が急に自分で食事を用意するとなっても対応が難しいです。
食事補助の福利厚生はさまざまあります。
お弁当を配達してくれるタイプ、新鮮な食材とレシピがセットのタイプ、ちょっとしたお惣菜を配達してくれるタイプなどさまざまあります。
食事メニューを考えるストレスから解放されるだけではなく、新鮮で栄養バランスの摂れた食事をすることで心身ともに健康となり業務効率の向上が期待できるでしょう。
また、オンラインでの料理教室や栄養指導を提供することも非常に有効です。従業員は、食生活の改善や健康意識の向上に貢献し、長期的に見ると医療費の削減にもつながります。 さらに、栄養バランスを考えた食事の宅配サービスを導入することで、従業員は手軽に健康的な食事を摂取でき、仕事のパフォーマンスも向上します。
このように、福利厚生の一環として食事支援を充実させることで、従業員の満足度を高め、企業全体の生産性に寄与することが期待できます。
4-3. コミュニケーション不足をサポート
在宅勤務になるとコミュニケーションが不足してしまいます。そこで注目されているのが「オンライン体験型イベント」の福利厚生です。オンラインミーティングツールを通して、絵画教室やメイク講座、演劇のワークショップなどさまざまなイベントを体験できます。
こうしたイベントは、普段の業務とは異なる場でコミュニケーションを図る機会を提供します。また、チーム内の心理的な距離を縮めるだけでなく、参加者同士の交流を深めることが可能です。従業員が楽しみながらスキルを磨ける場を設けることで、職場の士気やエンゲージメントの向上につながります。従業員のコミュニケーション不足を解消する施策をしているがうまくいかないという方は、オンライン体験型イベントの福利厚生がおすすめです。
このように、効果的に従業員のつながりを強化するためにも、オンラインイベントは大いに活用できる手段となります。
4-4. 運動不足解消をサポート
在宅勤務での運動不足を解消するためには、定期的な運動を取り入れることが不可欠です。企業が提供できるフィットネス支援の一環として、オンラインフィットネスクラスやヨガのセッションを導入することを検討してみてください。
また、従業員が自分のペースで参加できる動画教材やアプリを活用し、自由な時間に運動を行える環境を整えることも効果的です。このような取り組みにより、従業員は自宅で手軽に運動する機会を得られ、心身の健康を保ちながら業務に集中できるようになります。
さらに、運動不足を補うための親子参加型のトレーニングやグループチャレンジなど、家族を巻き込む企画も好評です。これにより、従業員の家族も含めた健康意識の向上を図ることができ、より充実した健康づくりに寄与します。
このように、福利厚生としての運動サポートを充実させることで、従業員の健康維持はもちろん、職場全体の雰囲気やコミュニケーションの向上にも大きく寄与するでしょう。
5. 福利厚生を導入するメリット


福利厚生を導入することで、企業は従業員に多くのメリットを提供することができます。具体的には、従業員の満足度の向上、生産性の向上、さらには採用力の強化につながります。
充実した福利厚生は、従業員の帰属意識やモチベーションを高め、結果として企業全体のパフォーマンスの向上をもたらすのです。
5-1. 従業員の満足度が向上する
福利厚生を導入することで、従業員の満足度が向上します。居心地の良いオフィス環境を整えることで、従業員は業務に集中しやすくなり、より良いアイデアを生み出す可能性が高まります。また、自由に有給休暇を取得できる環境や、特別な日にはさらに休暇を付与する制度は、従業員にとって安心感を提供します。
このような働きやすい環境が整うことで、従業員の企業に対する満足度が向上し、離職率の低下にもつながるのです。
5-2. 生産性が向上する
福利厚生の導入によって、企業の生産性が向上する理由は多岐にわたります。居心地の良いオフィス環境や自由な休暇取得は、従業員に仕事への張り合いを生み出し、モチベーションを引き上げます。加えて、スポーツクラブの利用やヨガプログラムの導入により、身体的・精神的な健康を維持することができ、従業員は心身ともにスッキリとした状態で業務を行うことができます。
こうした健康的な状態が続けば、職場の作業効率が向上し、企業全体の業績にも良い影響をもたらすことが期待されます。
5-3. 採用力が向上する
福利厚生を導入することで、採用において優秀な人材が集まりやすくなります。 企業は、給与以外にもさまざまな待遇を提供することが重要です。
社内が働きやすい環境を整えることは、企業がどれだけ従業員を大切にしているかを示す一つの指標です。 例えば、誕生日に特別な休暇を設けたり、リモートワーク制度やフレックスタイム制度を利用できる環境を整えることで、求職者に対して企業の魅力をアピールできます。 また、優秀な人材を引き寄せるには、具体的な福利厚生の内容を吟味し、ターゲットとなる人材が求める条件に合った施策を取り入れる必要があります。例えば、オフィスから徒歩10分以内に住む従業員には家賃を半分補助する制度を導入することで、「満員電車に長時間乗ることは時間の無駄であり、体力を消耗する大きな要因」と考える候補者にとって非常に魅力的でしょう。
さらに、自宅勤務を行う社員のために、自由に高さを調節できるデスクを導入することも有効です。これにより、仕事中に眠くなったら立ち上がって仕事をすることが可能になり、合理的に働くことを重視する人材に対して、企業が健康と生産性を重視していることを示すことができます。
このような工夫を通じて、目指す人材に響く魅力的な福利厚生を整えれば、優秀な人材を確保するための大きな力となるでしょう。
6. 在宅勤務にあった内容の福利厚生の見直しが大切


在宅勤務者を本格的に導入するまえに、福利厚生サービスの見直すのをおすすめします。
福利厚生サービスは会社が自由に決められるため、在宅勤務者が増えるのであれば在宅勤務者向けのサービスを導入するといいでしょう。
とくに人気なのが食事のサポートです。
昼食を社食や外食でしていた従業員は在宅になると不摂生になってしまいがちですが、福利厚生サービスを利用することで健康的な食事をすることができます。



人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
在宅勤務の関連記事
-


在宅勤務手当(テレワーク手当)とは?課税・非課税や金額相場を解説!
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.12.25
-

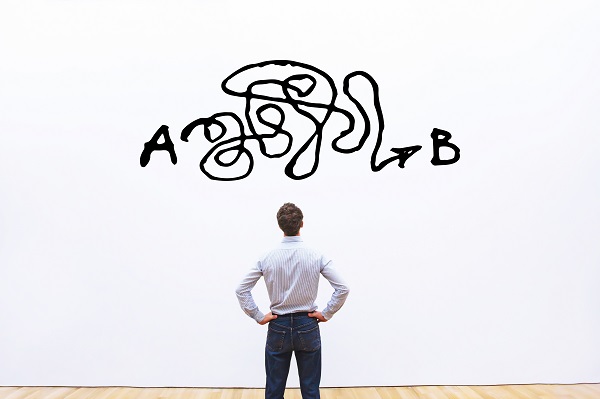
在宅勤務導入のデメリットとは?問題点から見える課題や解決策を紹介
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.02.12
-


在宅勤務とは?定義やテレワークとの違い・導入を成功させる4つのポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.09.29