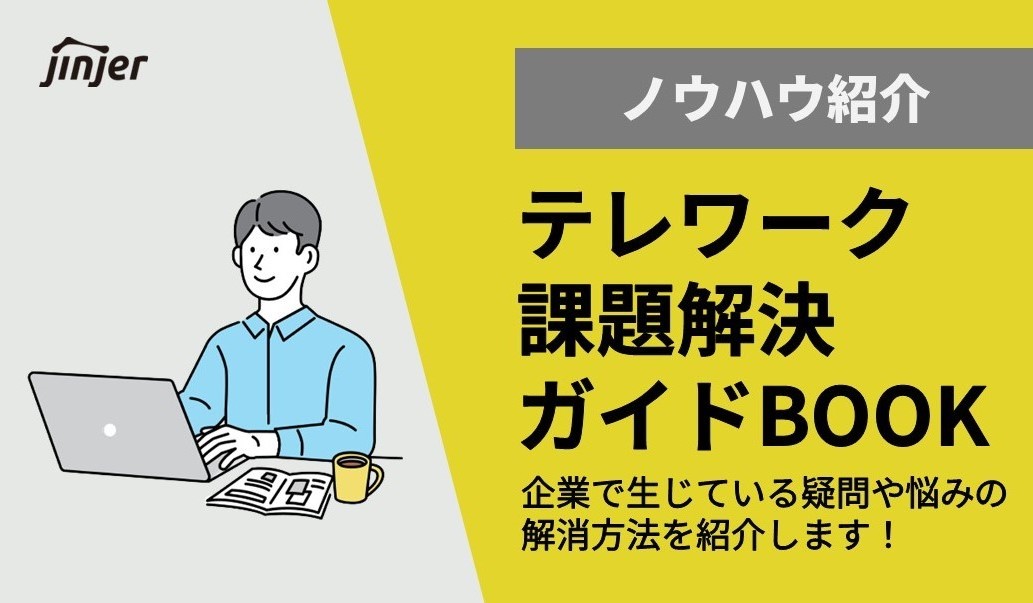在宅勤務手当とは?支給額の相場や支払い方法を詳しく紹介

在宅勤務を開始する場合、従業員の生活費負担が増えることを考慮し、在宅勤務手当を支給する企業があります。
実際、在宅勤務によって主に電気代が増えたという従業員の意見が多く、電気代の増加分として在宅勤務手当を支給すべきでしょう。しかし、実際には在宅勤務手当を支給している企業はまだ少なく、従業員の負担だけが増えている状況です。
本記事では在宅勤務手当の定義や、支払相場、支払方法など、在宅勤務手当の支給に関して詳しく解説していきます。今後在宅勤務の導入を考えている方は、ぜひ手当も含めて考慮してみてください。
▼在宅勤務・テレワークについて詳しく知りたい方はこちら
在宅勤務の定義や導入を成功させる4つのポイントを解説
目次
1. 在宅勤務手当とは?
 在宅勤務手当とは、自宅で業務をおこなう従業員のために支給される手当のこと。在宅勤務に切り替えることで、メリットばかりが増えるように見えますが、実際には従業員が負担する分が増えてしまいます。
在宅勤務手当とは、自宅で業務をおこなう従業員のために支給される手当のこと。在宅勤務に切り替えることで、メリットばかりが増えるように見えますが、実際には従業員が負担する分が増えてしまいます。
在宅勤務手当は、従業員の負担を減らすために支給されています。本章では在宅勤務手当の目的をご紹介します。
1-1. 導入時の負担を軽減するため
在宅勤務手当が支給されるひとつの目的が、在宅勤務を導入する際にかかる、環境づくりのための費用です。
これまで家で仕事をする習慣がなかった従業員にとっては、仕事用のデスク・チェアを導入する必要があり、場合によっては部屋屋スペースの確保が必須。
自宅に業務をおこなえる環境を構築するために必要な費用を負担するために、在宅勤務手当が支給されています。
1-2. 通信費・電気代を負担するため
在宅勤務手当、もうひとつの目的が業務開始時の通信費や電気代を負担するためです。こちらは在宅勤務導入後の費用負担で、在宅勤務開始後から終了時まで、常にかかる費用です。
在宅勤務をおこなうには、インターネットの環境が整っており、他の従業員と通信をおこなわなければいけません。また、在宅勤務はIT機器を活用した働き方なので、必然的にパソコンを動かすだけの電気代が必要になります。そのほか、デスク周りの照明も従業員の電気代で負担する必要があります。
また、通信環境はすでに整っている方がほとんどだと思いますが、セキュリティの観点からすると、企業から通信機器を付与し、支給されたパソコンのみを接続するという対処が必要な場合もあります。
在宅勤務手当では、この電気代や通信費の負担分を補うため、支給されています。
在宅勤務手当の目的は上記の通りですが、そもそも在宅勤務にすることで生じるメリットやデメリットに関しては、すでに考えられていますでしょうか?在宅勤務手当で会社としての支出は増えますが、離職防止効果があったり生産性が向上したりと、最終的にはプラスな効果が得られるのです。
当サイトでは、まず考えるべきである在宅勤務のメリットやデメリット、よくある悩みとその解決策をまとめた「テレワーク課題解決方法ガイドBOOK」を無料で配布しております。導入検討中だが自社に合うかわからない方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:在宅勤務時のセキュリティ対策で押さえるべきポイント
関連記事:在宅勤務を導入する企業のメリット・デメリットを徹底解説
2. 在宅勤務手当の支給額相場は?
 実際に在宅勤務手当を支給する場合、どれくらいの額を支給しているのでしょうか。ここでは人材紹介をおこなう『エンワールド・ジャパン株式会社』が2020年12月に実施した調査結果をもとに、在宅勤務手当の支給額をご紹介します。
実際に在宅勤務手当を支給する場合、どれくらいの額を支給しているのでしょうか。ここでは人材紹介をおこなう『エンワールド・ジャパン株式会社』が2020年12月に実施した調査結果をもとに、在宅勤務手当の支給額をご紹介します。
事前情報として、調査をおこなった企業269社のうち、毎月在宅勤務手当を支給している企業は約2割という結果が出ています。
在宅勤務手当の支給率(n=269)
- 毎月支給している:20%
- 一時金(単発)を支給した:7%
- 在宅勤務環境整備のために購入した備品の金額に応じて支給した:6%
- 支給していない:67%
2-1. 在宅勤務手当の支給金額(毎月)
以下の表では、日系企業、外資系企業、全体の在宅勤務手当の支給金額をまとめています。
| 支給額 | 全体 | 日系企業 | 外資系企業 |
| 3,000円未満 | 15% | 11% | 18% |
| 3,000円~5,000円未満 | 38% | 33% | 41% |
| 5,000円~10,000円未満 | 37% | 39% | 35% |
| 10,000円~30,000円未満 | 10% | 17% | 6% |
全体で3,000円以上手当を支給している企業は、半数以上占めていることがわかります。
また、日系企業と外資系企業を比べてみると、10,000円以上の支給割合では、日系企業が多い結果が出ています。
2-2. 定期代の支給はどうなる?
出勤時に支給していた、定期代は変わらず支給しているのでしょうか。
こちらも調査結果があるので、ご紹介します。
- 定期購入費用の支給を継続している:25%
- 定期購入費用の支給を停止、出勤日数に応じて支払い:65%
- 通勤手当は在宅勤務前から支給していない:1%
- その他:8%
調査結果を見ると、出勤日のみの支給に切り替えている企業が多いことがわかります。企業によって在宅勤務の頻度も異なるので、各企業ごとに合った手当を見直すことが大切です。
関連記事:在宅勤務に交通費は必要?クリアにしておきたい線引や注意点
関連記事:在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
参考:在宅勤務における企業の従業員サポート調査|エンワールド・ジャパン株式会社
3. 在宅勤務手当を導入するメリット

在宅勤務手当によって在宅勤務を実現するメリットは次のとおりです。
- 多様な働き方を実現できる
- コストを削減できる可能性がある
- 従業員のモチベーションが向上する
- 企業イメージを向上させられる
3-1. 多様な働き方を実現できる
在宅勤務を実現することで、従業員の多様な働き方を実現可能です。多様な働き方を実現することで、従業員の業務効率の向上や離職率低下につながります。日本は少子高齢化が進み、労働力不足が懸念されています。このような状況において、多様な働き方を実現して離職率を低下させることは貴重な労働力の確保につながるでしょう。
3-2. コストを削減できる可能性がある
在宅勤務を導入すれば、交通費やオフィスにかかる費用などのコストを削減できる可能性があります。例えば、従業員1人あたりに月に1万円、25人の従業員に交通費として支払った場合、毎月25万円の経費が発生します。在宅勤務であればこれらの交通費を削減可能です。削減した交通費を在宅勤務手当として支給もできます。
3-3. 従業員のモチベーションが向上する
在宅勤務手当を支給し、在宅勤務を導入することで従業員のモチベーション向上が期待できます。在宅勤務ができれば、従業員はプライベートの時間を充実させられます。プライベートの充実は業務に好印象をもたらすでしょう。従業員のモチベーション向上がもたらすのは業務の効率化だけではありません。従業員のモチベーションが向上することで、自社の定着が期待できます。
3-4. 企業イメージを向上させられる
在宅勤務手当の支給による在宅勤務は企業イメージの向上が期待できるでしょう。多様な働き方を実践している企業としてイメージが向上がすれば、求人への応募増加につながります。また、企業イメージが向上することで、顧客からの信頼も高まり、取引の活性化につながる可能性もあるでしょう。
4.在宅勤務手当を導入するデメリット

在宅勤務手当を導入するデメリットは次のとおりです。
- 給与システムの見直しが必要
- 業務のために負担した費用を計算する必要がある
4-1. 給与システムの見直しが必要
在宅勤務手当を導入するには給与システムの見直しが必要です。在宅勤務手当は課税対象であるため、支給方法によっては所得税計算にかかる手間が増えます。そのため、給与システムの設定を見直して適切に所得税計算を必要があります。一律支給の場合、各種保険の対象となるため、給与システムの設定によっては保険料にズレが生じてしまいかねません。
4-2. 業務のために負担した費用を計算する必要がある
在宅勤務手当を支給するには、業務のために従業員が負担した費用であるかを計算する必要があります。例えば電気代やインターネット費用はプライベートで使用した部分なのか、業務のために使用した部分なのかを判断しづらいでしょう。企業のなかには業務のために負担した費用を計算する手間を省くために、在宅勤務手当として固定の額を一律で支給しているケースもあります。
5. 在宅勤務手当を導入する際の注意点

在宅勤務手当を導入する際は次のような点に注意しましょう。
- ルールを明確にする
- 課税対象について従業員に説明する
5-1. ルールを明確にする
在宅勤務手当を導入するにはルールを明確にしておくことが大切です。ルールを策定したら、従業員から理解を得ることも必要です。例えば就業規則に在宅勤務手当について反映したのであれば、書面で配布する、社内に掲示するといったような対策を講じましょう。また、在宅勤務手当のルール説明役を設けて、どのような概要なのかを説明する機会を設けるのも効果的です。
5-2. 課税対象について従業員に説明する
在宅勤務手当にまつわる課税についても従業員に説明する必要があります。例えば支給方法によって課税、非課税が異なることを伝えておくことで、後々のトラブルを防げます。従業員が実際に負担した額を計算して支払う場合は非課税ですが、一律支給する場合は課税対象です。課税対象となると、従業員の手取りは減少するため、事前に理解を得ておけば不満の増加を抑えられます。
6. 在宅勤務手当の支払い方法
 最後に在宅勤務手当の支給方法をご紹介します。支給方法としては、他の手当と変わらず、「現金支給」「現物支給」の2種類です。
最後に在宅勤務手当の支給方法をご紹介します。支給方法としては、他の手当と変わらず、「現金支給」「現物支給」の2種類です。
また注意したいのが、在宅勤務手当が課税対象なのか、非課税対象なのか、税金の有無に関してです。ここでは在宅勤務手当の支給方法と併せて、課税の有無を解説していきます。
6-1. 在宅勤務手当の2種類の支給方法
在宅勤務手当は「現金支給」「現物支給」の2種類があります。
在宅勤務手当の多くは現金支給で、給与への上乗せによっておこなわれます。現金支給した場合のメリットは従業員が状況に合わせて手当を使えることが挙げられますが、企業が想定した使用用途以外に使われてしまうデメリットが挙げられます。
一方、現物支給では在宅勤務に必要な物資を直接支給する方法をいいます。個人で好きな環境を構築できないデメリットはありますが、使用用途をそれた使い方をされないメリットがあるため、場合によっては現物支給の方が向いている可能性もあります。
ただし、負担分が多い電気代に関しては現物支給が難しいため、一定の額を給与に上乗せする現金支給になってしまいます。状況に応じて支給方法を変えるのが大切です。
6-2. 在宅勤務手当は課税される
各種手当の課税・非課税は、手当の支給方法と使用用途によって異なります。在宅勤務手当の場合、「一律〇円、給料に上乗せ」としている企業がほとんどですが、この場合は使用用途が自由な資金として支給されるため課税されてしまいます。
電気代のために手当を支給しても、実際に支給した分の電気代がかからなければ、その差額が従業員の所得となってしまうからです。
しかし、「在宅勤務のためにデスクチェアを購入したため〇円を支給して欲しい」と従業員から申請があり、その都度負担額を支給した場合、こちらは使用用途が明確で実際にかかった費用も分かっているため、課税対象にはなりません。
在宅勤務手当の支給方法としておすすめなのは、現金支給ですが課税対象になる点には注意が必要です。
7. 在宅勤務に切り替えたら在宅勤務手当を検討しよう
 新しい働き方や時間や場所に縛られない働き方として、在宅勤務が推奨されていますが、切り替え時には在宅勤務手当として従業員の負担分を支援するはたらきが大切です。
新しい働き方や時間や場所に縛られない働き方として、在宅勤務が推奨されていますが、切り替え時には在宅勤務手当として従業員の負担分を支援するはたらきが大切です。
支給額や支給方法には少し迷いますが、他者の支給額を参考にしたり、従業員の意見を聞いたり、他者の意見や行動を参考にするのも大切です。在宅勤務切り替えには、企業だけでなく従業員の負担も増える可能性があることを、しっかり把握しておきましょう。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25