
企業で働く従業員は、毎日出勤・退勤時間を記録して勤怠管理をおこないます。ところが、この記録時に不正を働いたり、記録したタイムカードなどの勤怠記録を改ざんしたりするケースも少なからず発生しています。
従業員は、数分の時間調整という感覚で軽い気持ちでおこなっているかもしれませんが、勤怠不正はれっきとした違法行為なので是正するための罰則や対策が必要です。
ここでは、違法行為が発覚した場合の企業の対処法や勤怠時間の改ざんを予防するための方法を解説します。
更新日: 2025.9.29 公開日: 2021.9.27 jinjer Blog 編集部

企業で働く従業員は、毎日出勤・退勤時間を記録して勤怠管理をおこないます。ところが、この記録時に不正を働いたり、記録したタイムカードなどの勤怠記録を改ざんしたりするケースも少なからず発生しています。
従業員は、数分の時間調整という感覚で軽い気持ちでおこなっているかもしれませんが、勤怠不正はれっきとした違法行為なので是正するための罰則や対策が必要です。
ここでは、違法行為が発覚した場合の企業の対処法や勤怠時間の改ざんを予防するための方法を解説します。
勤怠の改ざんがあった際、直ちに従業員を解雇とすることは、法律的にも「不当解雇」とみなされる可能性があるため、処罰には順を追う必要があります。
当サイトでは、従業員による勤怠の改ざんが起こった際、どのように対応していけばよいか、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「従業員の不正に適切に対処したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。


従業員がタイムカードの出勤・退勤時間の改ざんをしたなど、不正が発覚した場合には、企業側が毅然とした対処をおこなわなければなりません。不正を見過ごすことは、職場秩序の崩壊や他の従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。
まずは事実確認をおこない、就業規則に基づいた懲戒処分の判断や処分手続きの実行、未払い賃金の再精査など、複数の工程を慎重に進めることが求められます。
ここでは、不正発覚時の対応について解説していきます。
不正が発覚した場合、まずは事実確認をおこないましょう。そのために必要なのは「証拠」です。例え、明らかに改ざんされたことが判明しているとしても、不正をした本人が認めなければトラブルになる可能性があります。
証拠がないまま事実確認をした場合、言い訳や言い逃れをすることもあるため、オフィスへの入退室やタイムカードの代理打刻が分かる防犯カメラ映像やパソコンのログイン記録など、客観的に「不正」が分かる証拠を確保しましょう。
また、被疑者に対しては、本人の言い分も聴取して公平性を保つことが重要です。この際、就業規則や労働契約の規定もあわせて確認し、違反の程度を明確化しておくことで、後の処分判断が円滑になります。
懲戒処分には、制裁罰が軽いものから重いものまで複数の種類があります。その中でも最も重い罰が、企業が従業員をペナルティとして解雇する「懲戒解雇」です。
勤怠の不正や改ざんがおこなわれた場合の懲戒処分は、懲戒解雇が妥当といわれています。実際に、タイムカードの打刻で不正を働いた従業員が懲戒解雇となったケースもあります。
ただし、必ず懲戒解雇にするべきというわけではないので、制裁罰に関しては従業員との信頼関係や必要性に応じて決めましょう。
勤怠の不正をおこなった従業員が、必ずしもすべて懲戒解雇される、というわけではありません。場合によっては、従業員に処分が科されないこともあります。
過去には、勤怠管理を担当する労務が従業員の不正を承認してしまったケースにおいて、管理する企業側が不正を見抜けなかったとして懲戒解雇処分が認められなかった判例があります。従業員の不正の見逃しは企業側の責任となるため、勤怠管理は正しくおこなうことが重要です。
従業員の勤怠不正が発覚したら、すぐにその従業員を懲戒解雇に処するのではなく、軽めの処分をおこなうところから始めましょう。
まずは懲戒処分のうち最も軽い「戒告」で、従業員の改善を促します。それでも不正が改善しないときは、減給、出勤停止と徐々に重い罰になるよう手順を踏みます。
単なる打刻ミスの場合は口頭での注意で済むことも多いですが、勤怠の不正は法律違反となる行為です。明らかに意図的な不正や改ざんが見られ、それによって本来ならば発生しない残業代を受け取っていたときなどは、重い処分を免れることはできません。
ただし、懲戒解雇相当の行為が発覚したとしても、情状酌量の余地がある場合あ「論旨解雇」を検討してもよいでしょう。これは一方的な解雇ではなく、従業員に退職を促すもので、一定期間内に退職をすれば依願退職扱いとなります。
残業代の水増しのような不正・改ざんをおこなった従業員に対しては、どのような処分を下したとしても余分に受け取った残業代の返還請求を忘れずにおこないましょう。
勤怠の改ざんによって不正に残業代を受け取っていた場合、企業はその返還を請求することが可能です。民法上の不当利得返還請求に該当するため、支払から3年以内であれば請求が認められやすいとされています。請求をおこなう際は、不正の事実と金額を証拠に基づき明示し、書面で通知することがトラブル防止につながります。
返還請求をおこなわないと、他の従業員に「不正や改ざんでお金を受け取れる会社」と考えられてしまうので注意してください。
法律違反、労働契約違反の不正や改ざんに対してきちんと処罰をおこなうことは、不正を予防する大事なポイントです。


勤怠の不正や改ざんは、企業内の規律を乱すだけでなく、法律を犯す行為です。
特に、虚偽の勤怠記録によって賃金を不正に受け取る行為は、刑事罰や損害賠償の対象となることもあるため、法的責任を明確に理解したうえで、社内対応をおこなうことが求められます。
では、どのような法律にふれるのかを具体的に見ていきましょう。
勤怠の不正により賃金を不正取得した場合、「詐欺罪」(刑法246条)が成立する可能性があります。これは、虚偽の申告を通じて雇用主を欺き、不当に金銭を得たとされる行為に該当します。
打刻の不正のみで逮捕されることは多くないものの、刑法において詐欺罪は、最大10年の懲役または50万円以下の罰金に処されるもので、決して軽い罪ではありません。
また、第三者と共謀して代理打刻などをおこなった場合には「共同正犯」として複数人に刑事責任が及ぶこともあります。企業側が訴えを起こさなかったとしても、社内で刑事責任を意識した適切な対応を取ることが重要です。
参考:e-GOV 法令検索
民法においては、勤怠の不正は労働時間を改ざんしているため労働法違反となります。また、本来の勤務時間とは異なる実態のデータを元にお金を多く受け取り、相手となる企業に損害を与えることは、民法703条の「不当利得返還請求」または民法第704条の「悪意の受益者返還義務等」に抵触する可能性があるので法律違反になります。
これらの法律に抵触した場合、企業側は不正による支払い金額を証拠に基づいて計算し、従業員に返還を求め、従業員は不正によって受け取った賃金を会社に返還しなければなりません。
民法703条の請求は3年の消滅時効が適用されるため、発覚後は早急な対応が求められます。
参考:e-GOV 法令検索
勤怠改ざんは、労働基準法においても重大な違反行為となります。労働基準法は、労働者を守るために企業が順守すべき法律です。
労働基準法第109条により、労働時間の記録は事業主に義務付けられており、正確な記録が保たれていない場合には監督官庁から是正指導や罰則が科されることがあります。また、不正に賃金を支払った場合には、支払義務を果たしたとみなされず、事業主側の管理責任も問われます。
従業員が出勤簿など勤怠の改ざんをおこなったとしても、従業員自身が労働基準法違反で罰せられることはありませんが、遵守させる責務を果たしていないとして企業が罰せられる可能性があるのです。ただし、従業員自身も社内の罰則規程に則って、始末書の提出や減給、降格などとなることもあるでしょう。
参考:e-GOV 法令検索


勤怠不正は、主に手作業で打刻をおこなう方法に多く見られます。勤怠管理を手作業でおこなっている企業の場合、勤怠不正や改ざんがおこなわれるリスクがあるといえるでしょう。しかし、改ざんの手口を知っておけば、不正防止に活かすことができます。
ここでは、不正や改ざんのおもな手口を紹介するので、万が一のときのための参考にしてみてください。
出勤・退勤時、タイムカードをタイムレコーダーという機械に通して打刻をするタイムカード式の勤怠管理は、比較的不正や改ざんがしやすい方法だといわれています。特に、遅刻してしまったときなど、打刻をおこなうタイムレコーダー自体の時刻を修正して時間通りに出勤したと見せかけるのは、タイムカードの不正でおこなわれやすい手口です。
また、タイムカードさえあれば本人以外でも打刻ができるため、社内にいる他の人に代理で打刻してもらうケースが少なくありません。
タイムカードの代理打刻は、不正打刻かつ違法なので注意が必要です。
タイムカードでの打刻は機械が時刻を打ってくれますが、紙やExcelなどで運用される自由記入式のタイムシートは、不正の温床になりやすい形式です。
従業員が自己申告で出退勤時間を記入する方式では、実際の労働時間と異なる記録をおこなっても、事実を確認することがむずかしいため悪用されやすいです。特に、上司による確認が形式的におこなわれている場合、不正が見過ごされやすくなります。
遅刻をした、または定時で退社した場合でも、出勤時刻を早めに、退勤時刻を遅く記載して残業時間を水増しし、残業代を不正受給することもできるので注意しましょう。
こうした状況を改善するためには、手動による記録は極力排除し、客観性を持たせることが重要です。


勤怠の不正を発見した際、関係者の立場によって対応方法は異なります。部下、上司、派遣社員など、相手の雇用形態や関係性に応じた対応をとることが、トラブルの拡大防止につながります。
適切な手順を踏まずに処分や報告をおこなった場合、逆に企業側が責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、不正打刻や虚偽申告などが発覚した場合の、立場別の対処法を解説します。
基本的に、勤怠を含む部下の不正は、上司にあたる管理職の責任となってしまいます。部下の勤怠不正を隠すため、上司がタイムカードを正しい内容に直してしまうことも改ざんにあたるので注意が必要です。
このような改ざんのほか、不正を隠す行為、見逃す行為があった場合、部下共々懲戒解雇処分になることもあり得ます。つまり、部下の不正に対する対応によって、自分自身が処罰の対象となるのです。
部下の勤怠不正が発覚した際は、前述の処分の手順と同様に、まずは口頭での注意をおこないます。それでも不正が見られる場合は労務などに報告をします。その後は、会社として懲戒処分をおこなうために調査をした上で、処分内容が決定されます。
部下の場合とは異なり、上司の勤怠不正を発見した場合は、部下から直接口頭で注意することは難しいでしょう。本来は管理する側である管理職の不正となれば、なおさらです。
上司の不正は、社内の他の上司にもなかなか相談しづらいものです。不正を告発するためにどのように動けばいいのか、社内で相談できる人がいない場合は、弁護士に相談してみるのもひとつの手段です。弁護士によっては無料相談をおこなっているので、検討してみましょう。
また、一般企業では、内部通報を受け付ける「通報窓口」を設置しているところが多くあります。
上司か部下かにかかわらず、誰もが不正をする可能性があります。勤怠時間の改ざんなどの不正があったとしても、すぐ発見できるように、企業としては社内の誰もが内部通報できる開かれた体制を整えておくことが重要です。
派遣会社に籍をおいて働く派遣社員は、派遣先の企業の労働契約ではなく、派遣会社との労働契約の元で働いているので、勤怠不正が発覚した際は派遣会社への報告が必要です。
報告に際しては、タイムカードや業務記録、業務実態などの証拠を整理し、客観的に不正を示せるよう準備しましょう。
発見したのが直属の上司であれば直接派遣会社に報告をおこない、その他の社員であれば派遣社員の直属の上司、または派遣会社との契約担当をおこなう社員に派遣社員の不正を報告してください。
しかし、派遣社員は就業先企業のルールに従って勤務する必要があるので、契約の見直しや、再発防止策の要求を検討しましょう。派遣社員であっても不正行為が組織内のモラルに影響を及ぼすため、派遣先としても状況の把握と再発防止に向けた体制の構築が求められます。
関連記事:勤怠管理は何をチェックするべき?用意すべき法定三帳簿とは?


タイムカードや手書きのタイムシートでの勤怠管理では、個人で時刻を調整しやすいため、不正がおこなわれやすいデメリットがあります。そんな勤怠管理の不正を予防するための方法として、デジタル技術を活用した勤怠管理システムの利用がおすすめです。
勤怠管理システムでは、打刻した時間を自動的に集計できるので管理がしやすく、一人ひとりの残業時間などもリアルタイムで集計も把握できるメリットがあります。そして、正確な打刻時間を管理できることも、大きなメリットです。
勤怠管理システムは、現在さまざまなシーンで使われているデジタル技術が採用されています。
各社員の私物であるICカード、タブレットやスマートフォンでの打刻ができ、さらに指紋や静脈を使用した生体認証にも対応するシステムもあります。
いずれの方法でも、本人以外は打刻が不可能です。そのため、代理打刻による不正を予防できるのはもちろん、正確な打刻時間で勤怠管理をスムーズにおこなうことができます。
このように、最新のデジタル技術により、従来のアナログなタイムレコーダーでの打刻や手書きタイムシートのような不正を勤怠管理システムでおこなうことは困難で、本人の正しい時間での打刻のみを管理できます。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ


出勤時間や退勤時間をごまかして遅刻を避けたり、残業代を多くもらったりする勤怠の不正は明らかな罪であり、就業規則違反にあたる行為です。不正や改ざんが発覚した場合は、企業による適切な対応が求められます。
しかし、自分で記入するなどの客観性に欠ける打刻方法では、不正や改ざんが簡単にできてしまうため、企業側が改善する必要があるというのも事実です。
近年では、デジタル技術を応用した勤怠管理システムで、厳密に正確なデータの管理が可能となっています。このようなシステムでは勤怠の不正や改ざんもできないので、未然に防ぐためにも導入を検討してみることをおすすめします。
勤怠の改ざんがあった際、直ちに従業員を解雇とすることは、法律的にも「不当解雇」とみなされる可能性があるため、処罰には順を追う必要があります。
当サイトでは、従業員による勤怠の改ざんが起こった際、どのように対応していけばよいか、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「従業員の不正に適切に対処したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
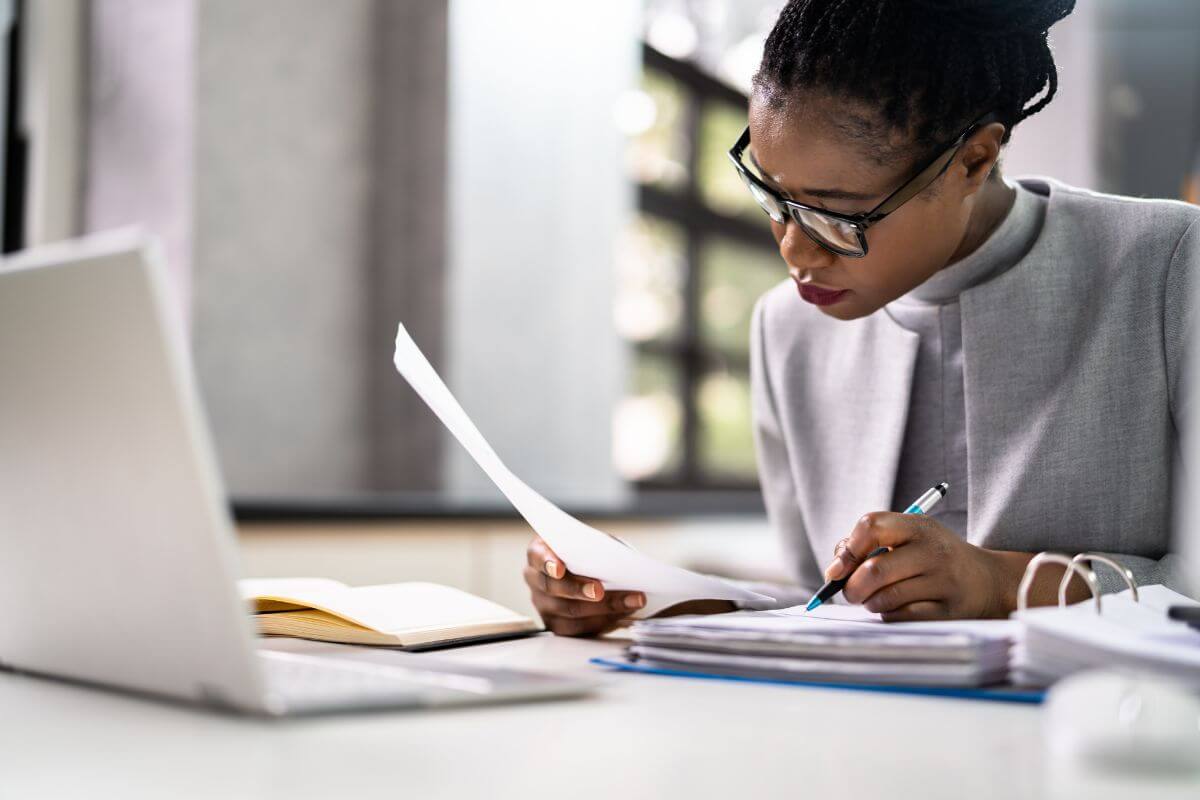
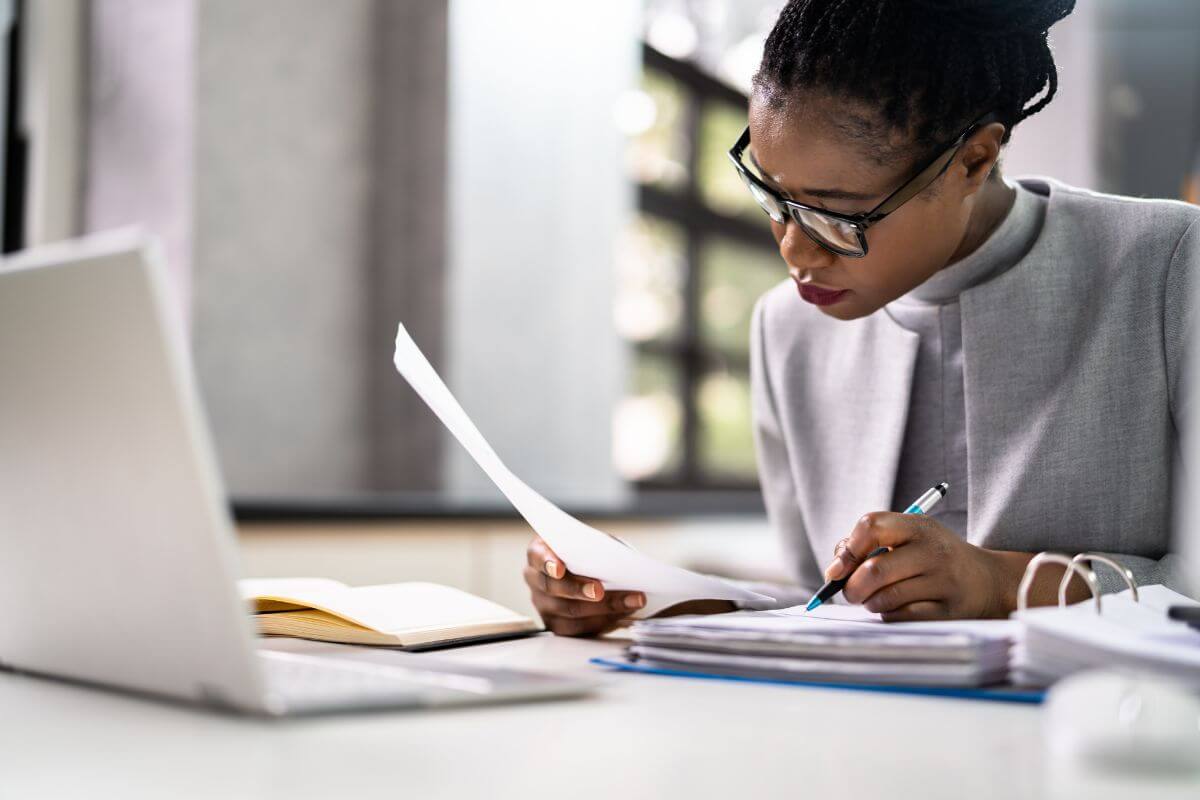
法定四帳簿とは?電子化の可否・保存期間・規則を破った場合の罰則を解説
公開日:2025.03.09更新日:2025.02.21


残業の過労死ラインとは?時間・管理職の場合・企業の対策を解説
公開日:2025.01.31更新日:2025.01.31
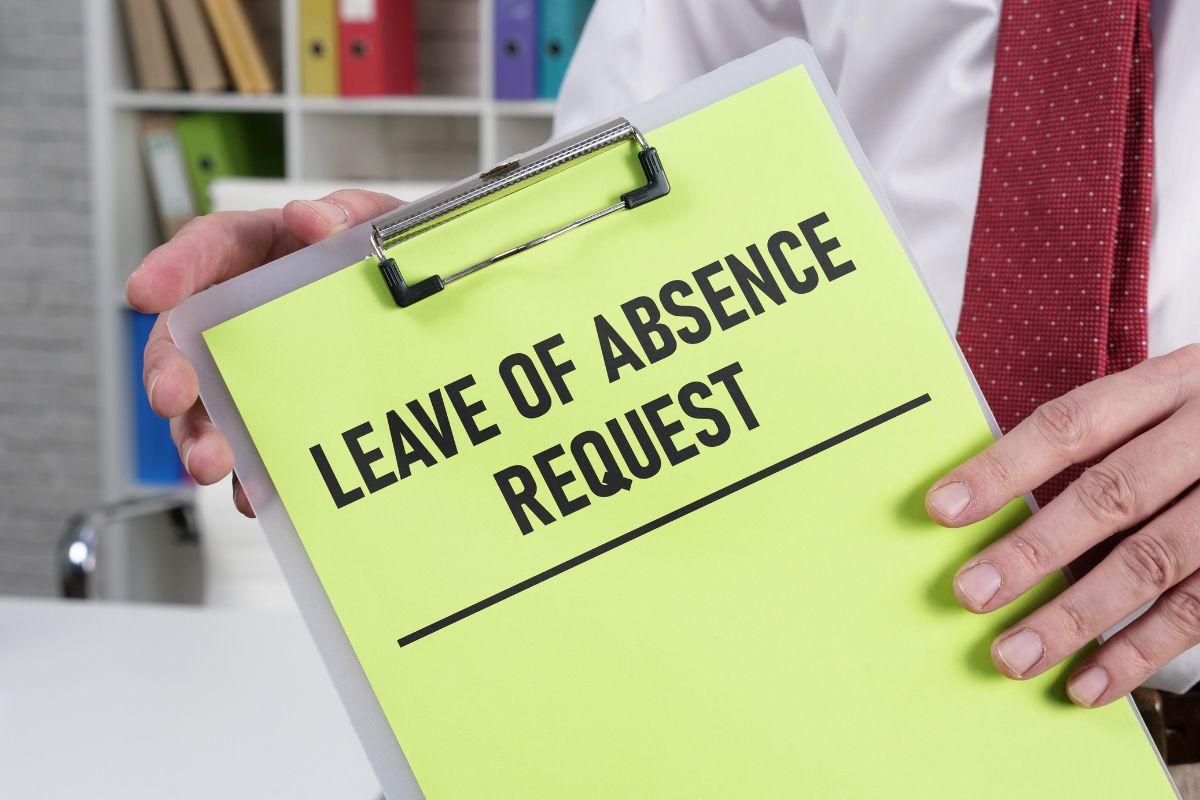
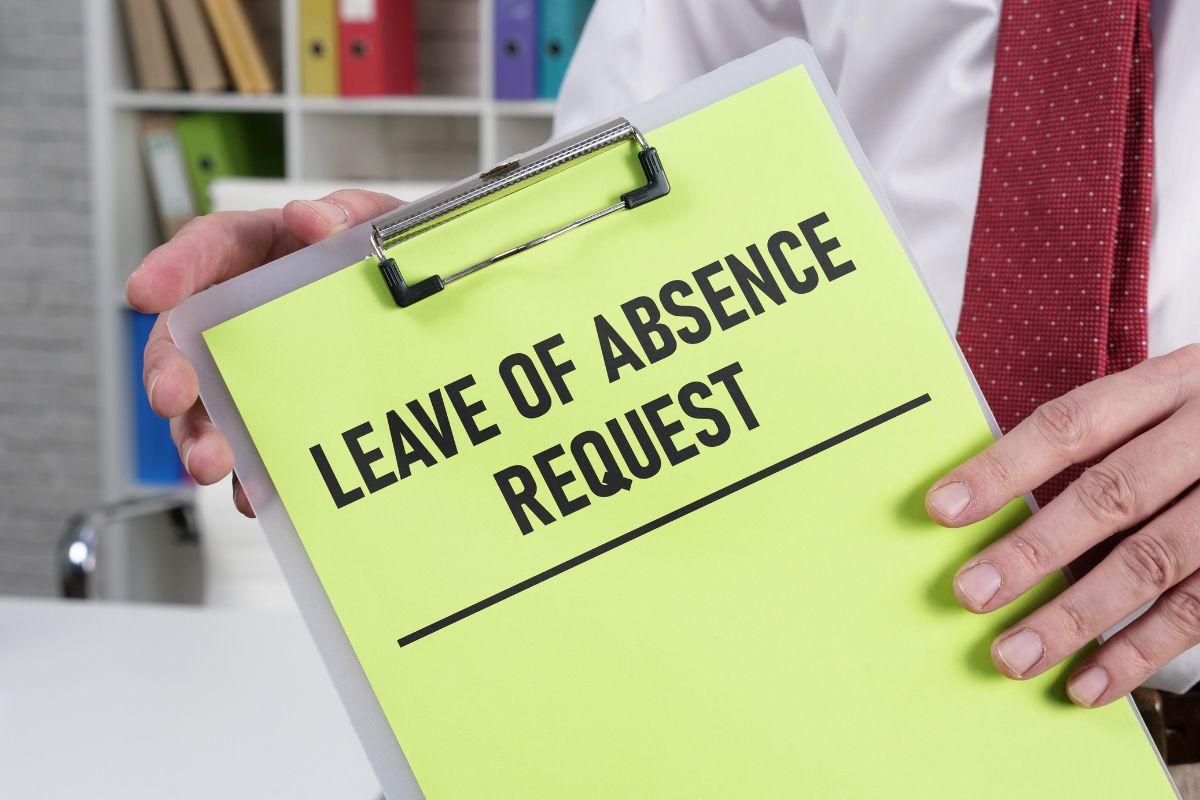
欠勤とは?休職との違いや欠勤控除の方法を解説
公開日:2024.12.21更新日:2025.05.02