コンプライアンスとは?意味・違反事例・必要な取り組みをわかりやすく解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2024.12.31 jinjer Blog 編集部

コンプライアンスとは?」
「コンプライアンスの違反事例は?」
「コンプライアンスの遵守に必要な取り組みは?」
自社のコンプライアンスに不安を感じ、上記のように悩んでいる人はいるのではないでしょうか。
コンプライアンスは、法令や規則を守るだけでなく、社会的な規範や倫理を遵守するために重要な概念です。近年、企業の不祥事や情報漏洩が相次いだことで、コンプライアンス違反がもたらすリスクはますます高まっています。
本記事は、コンプライアンスの基本的な意味から、具体的な違反事例、企業が取り組むべき対策まで詳しく解説します。法令遵守の重要性を再確認し、健全な企業経営を実現するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次

従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. コンプライアンスの本来の意味とは


近年はさまざまな場面で耳にすることが多いコンプライアンスという言葉ですが、本来はどのような意味を持っているのでしょうか。改めて確認していきましょう。
1-1. 直訳すると「法令遵守」になる
コンプライアンスとは、英語の「comply(従う)」に由来し、直訳では「法令遵守」を意味します。
法令とは国民が守るべきものとして国が制定している法律や政令、省令などです。コンプライアンスでは、これらに加えて国や地方自治体によって定められた条例やルールも含んで守るものだと考えられています。
しかし、単純に法令だけを守ってればよいというわけでもありません。
1-2. 近年は「社内規範」「社会規範」の意味も含む
近年はコンプライアンスの意味に「法令遵守」に加えて「社内規範」や「社会規範」などの要素も含まれます。
社内規範とは、企業が独自に定めた就業規則や行動指針などのことです。組織内の秩序維持において重要な役割を果たします。
一方で社会規範とは、時代ごとの社会的な期待や倫理観にもとづいた行動のことです。情報漏洩、ハラスメント、ジェンダー平等などが特に近年は注目を集めています。
社会規範は時代によって変化していくものであるため、社会的批判を受けないためにもその時代に適した内容にすることが重要です。
2. 内部統制やコーポレートガバナンスとの違い


コンプライアンスと似た意味をもつ言葉には「内部統制」や「コーポレートガバナンス」があります。
いずれも企業を健全に運営するためのルールや仕組みを指しますが、少し内容が異なります。どのような違いがあるのか見ていきましょう。
2-1. 内部統制との違い
内部統制とは、企業を健全に運営するために企業内で決める規則やルールを指します。
- 業務の有効性や効率性を高める
- 財務報告の信頼性を確保する
- 法令を遵守する
- 資産を保全する
内部統制では以上の4つを主な目的としており、コンプライアンスは内部統制の目的のひとつである「法令を遵守する」という部分に含まれています。コンプライアンスを徹底するには内部統制の整備も不可欠であるわけです。
また、内部統制は上場企業や大企業では整備が義務とされています。
2-2. コーポレートガバナンスとの違い
コーポレートガバナンスは内部統制と非常に似ており、企業を健全に運営する体制のことを指します。
異なる点はコーポレートガバナンスによって監視される対象です。内部統制は主に経営者が従業員を監視したり、管理したりする仕組みですが、コーポレートガバナンスは株主や取締役会が会社の経営者を監視します。
従業員を監視する経営者を監視するのがコーポレートガバナンスという層になった仕組みです。そのため、コンプライアンスを確保するにはコーポレートガバナンスも重要であり、コンプライアンス・内部統制・コーポレートガバナンスの3つは非常に深い関係にあります。
3. コンプライアンスが重視される背景


コンプライアンスが重視される理由には、近年の社会における以下のような変化や考え方が大きく関係しています。
- 企業の不祥事が増加している
- 企業への法規制が厳罰化している
- 企業への社会的意識が変化している
- インターネット・SNSが普及している
- グローバル化・多様性への対応が求められている
なかでも、法規制の厳格化は重要な背景です。労働基準法の改正やデータプライバシー保護に関する法律の整備など、企業が遵守すべき法令は年々増加しています。
法令違反による罰則や社会的信用の失墜を避けるために、コンプライアンス体制を強化せざるを得ないのが現状です。
また、デジタル技術の進化も無視できない要因といえるでしょう。インターネットやSNSの普及により、不祥事や違反行為は瞬時に拡散されるリスクがあります。
そうした時代の変化の中で自社を守るために、コンプライアンスを重視し強化する流れが強くなっています。
4. コンプライアンス違反が企業に与える影響
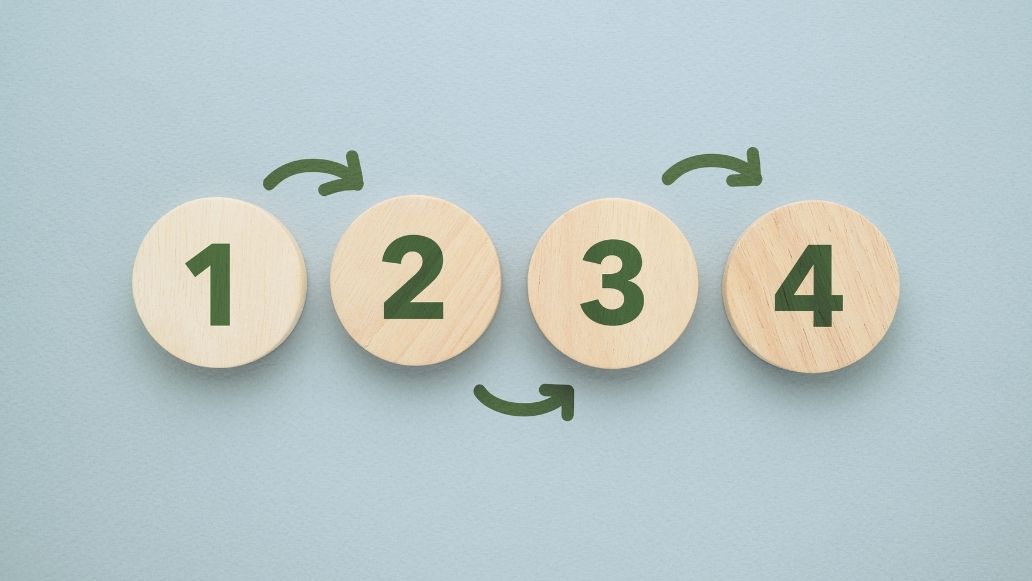
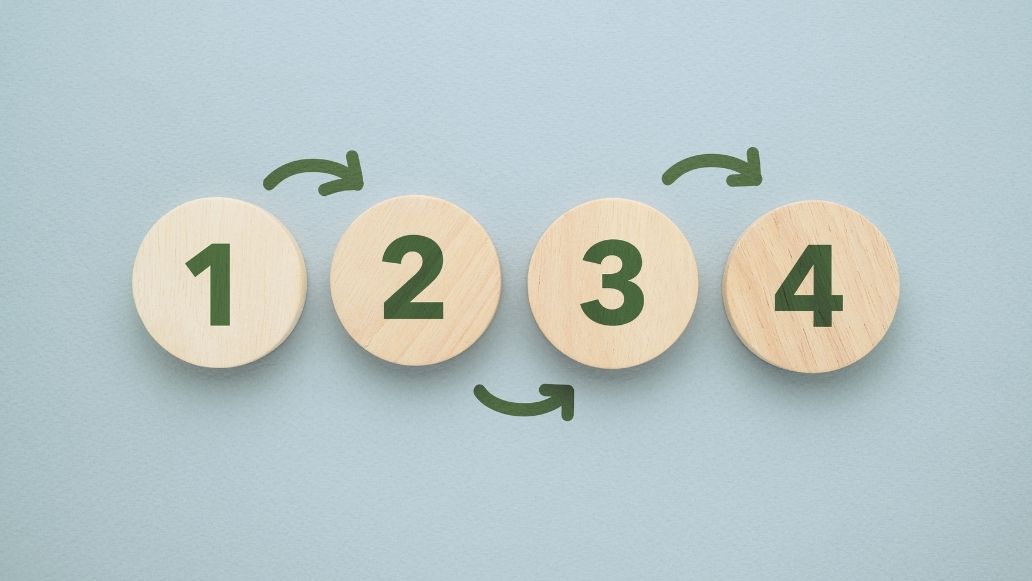
コンプライアンス違反が企業に与える影響として考えられるのは、主に以下の4つです。
- 経済的損失・法的リスク
- 信用の失墜・顧客離れ
- 従業員の離職
- 株主離れ
パワーハラスメントや個人情報漏洩が発覚した場合、損害賠償請求がおこなわれることが一般的です。多額の賠償金が発生し、企業の財務状況に深刻な打撃を与えるでしょう。
また、コンプライアンス違反が明らかになると、企業の信用は急速に失墜します。消費者や取引先からの信頼を失えば、不買運動や取引停止が相次いで売上の大幅減につながりかねません。
一度失った信用を回復するためには、多大な時間と労力が必要です。競争力の喪失や株価が下落、資金調達の困難さも重なることで、倒産に追い込まれる企業も少なくありません。
5. コンプライアンス違反が発生する主な原因


コンプライアンス違反が発生する原因は、従業員側にのみあるとは限りません。企業の体制や環境が原因でコンプライアンスの軽視や違反が発生しやすくなります。
5-1. コンプライアンスに対する知識が不足している
コンプライアンス違反の主な原因の一つとして、従業員や経営層の知識不足が挙げられます。
企業が法令や社内規則を遵守し、社会的な倫理観に沿った行動を取るためには、コンプライアンスへの正確な知識が必要です。しかし、日々変化する法令や規則に対して最新の情報を把握できていなければ、意図せず違反するリスクが高まります。
とくに、法律や規則の変更が頻繁におこなわれる分野では、知識不足による違反が発生しやすいため注意が必要です。定期的に研修や教育などを実施したり、法改正に迅速に対応できる体制を整えたりしておきましょう。
5-2. 企業全体の風土や管理体制が不十分
企業におけるコンプライアンス違反の大きな原因の一つとして、企業全体の風土や管理体制の不備も挙げられます。
とくに、法令遵守よりも業績達成が優先されるような風土だと、不正行為や違法行為を助長する温床となる可能性が高いです。過度な売上目標の設定は避け、不正会計やハラスメントなどの問題が発生しにくい環境を作りましょう。
また、内部監査や内部通報制度など不正を未然に防ぐ管理体制が整っていない場合、不正行為が発覚しにくい傾向があります。問題の深刻化を防ぐためにも、責任の所在や監視・指導する役割を明確にしておきましょう。
5-3. 従業員に対するプレッシャーが強い
コンプライアンスを軽視していなかったり、違反になるとわかっていたりしても、コンプライアンス違反をせざるを得ない状況に従業員が置かれている可能性も忘れてはなりません。
- ノルマを達成するために手段を選べなくなる
- 上司からの圧力で追い詰められてしまう
- 競争に勝つために不当な手段で成果を得ようとしてしまう
このような状況になると、コンプライアンスよりも目的を重視して違反してしまうケースがあります。目標やノルマに無理はないか、マネジメント層の教育は十分か、評価制度は適正かなど、従業員に必要以上のプレッシャーがかかっていないか確認することも重要です。
「コンプライアンスのを守りたくても守れない」そんな状況になっていないか、十分に確認しましょう。
6. コンプライアンス違反のよくある事例


コンプライアンス違反でよくある事例は、以下の4つです。
- 労働関係のコンプライアンス違反
- 法令関係のコンプライアンス違反
- 情報管理関係のコンプライアンス違反
- 経理関係のコンプライアンス違反
それぞれ、の特徴や具体的な事例を紹介します。
6-1. 労働関係のコンプライアンス違反
労働関係におけるコンプライアンス違反は、企業が法令や労働者の権利を無視して不適切な労働環境を強いることで発生します。
労働関係のコンプライアンス違反として代表的なものは、以下の4つです。
- 長時間労働
- 賃金未払い
- ハラスメント
- 不合理な待遇格差
長時間労働の代表的な事例として、大手広告代理店で発生した過労死事件が挙げられます。新入社員が1ヶ月に130時間以上の残業を強いられた結果、精神疾患を発症しました。
また、ある企業では、上司が部下に対して侮辱的な発言を繰り返したことで精神疾患を発症しています。社内で起こるハラスメントは隠蔽しやすく、表面化しにくいことが問題視されました。
6-2. 法令関係のコンプライアンス違反
法令関係のコンプライアンス違反は、企業や組織が法律や規制を守らずに行動することで発生します。
法令関係のコンプライアンス違反として代表的なものは、以下の4つです。
- 独占禁止法違反
- 景品表示法違反
- 個人情報保護法違反
- 食品衛生法違反
景品表示法違反の事例として、通信事業会社が「業界最速」などの誇大広告をおこなったケースがあります。消費者庁から課徴金を命じられ、最終的には経営が悪化し、事業売却に追い込まれました。
また、独占禁止法違反の例として、大手アパレルメーカーが下請け業者に不当な経費を負担させたケースが挙げられます。結果的に、公正取引委員会から再発防止を求める勧告を受けました。
6-3. 情報管理関係のコンプライアンス違反
情報管理におけるコンプライアンス違反は、企業や組織が取り扱う機密情報や個人情報の取り扱いが不適切な場合に発生します。
情報管理関係のコンプライアンス違反として代表的なものは、以下の5つです。
- USBメモリの紛失
- 顧客情報の私的利用
- サイバー攻撃によるデータ流出
- 社外秘データの持ち出し
- メール誤送信
社外秘データの持ち出し事例として、大手通信会社の子会社に勤務する元派遣社員のケースが挙げられます。約900万件の顧客情報を不正に持ち出して売却した事件で、社会的信頼を大きく失墜することになりました。
また、外部からのサイバー攻撃として、大手SNSサービスの個人情報流出事件が挙げられます。システムの脆弱性を突かれたことで、利用者や取引先、従業員の個人情報が合わせて44万件が流出しました。
6-4. 経理関係のコンプライアンス違反
経理におけるコンプライアンス違反は、企業の財務状況を不正に操作したり、企業の資金を私的に流用したりなどで発生します。
経理関係のコンプライアンス違反として代表的なものは、以下の3つです。
- 粉飾決算
- 業務上横領
- 脱税
粉飾決算の事例として代表的なものは、とある金属商社の事件が挙げられます。在庫商品の価値を過大評価して計上して仕入れの計上を翌期に遅らせることで、表面的には黒字に見せかけていました。事件後に信用を回復できず、最終的には破産に至っています。
また、とある大手電機メーカーは、決算前に部品を高値で売却して利益を確保し、決算後に買い戻すことで利益を操作していました。証券取引等監視委員会による調査で発覚し、多額の課徴金が課されています。
7. コンプライアンス違反の防止に必要な取り組み


コンプライアンス違反の防止に必要な取り組みは、以下の通りです。
- コンプライアンス研修を実施する
- 社内マニュアル・ルールを定めて周知する
- 内部監査などで監視体制を強化する
- コンプライアンスの相談窓口・部門を設置する
それぞれ、詳細に解説します。
7-1. コンプライアンス研修を実施する
コンプライアンス研修は、企業が法令や社会的規範を遵守し、倫理的な行動を促進するために不可欠です。
研修を実施することで、従業員が法的要件や企業のルールを理解し、適切な行動を取れるようになります。基本的な法令に加え、業界特有の規制や社内ルールも含めて教育することで、研修の効果をより高められるでしょう。
なお、コンプライアンス研修は単発で終わらせるべきではなく、定期的かつ継続的に実施することが重要です。定期的に実施することで、最新の法令や社会規範にもとづいた行動を取れるようになります。
7-2. 社内マニュアル・ルールを定めて周知する
コンプライアンス違反を防止するためには、社内マニュアルやルールを作成し、徹底的に周知することも大切です。
従業員がマニュアルやルールを理解できていれば、業務を進める際に迷うことなく、法令遵守の観点から適切な判断をくだせます。法令や規制を知らずに違反行為をおこなう可能性も減らせるでしょう。
社内マニュアル・ルールは、全員がアクセスできる形で作成することが大切です。デジタルツールを活用して社内ポータルサイトやクラウド上で管理すれば、いつでも閲覧できるでしょう。
7-3. 内部監査などで監視体制を強化する
コンプライアンス違反を防止するためには、内部監査を通じて監視体制を強化することも重要です。
企業の業務が法令や規定に従って適切におこなわれているかを確認しておけば、潜在的なリスクや不正行為を早期に発見できます。大きな問題が発生する前に予防措置を講じられ、企業の信頼性や社会的信用の維持に貢献できるでしょう。
また、内部監査を実施することで企業全体のコンプライアンス意識の向上にもつながります。従業員は法令遵守を意識して業務をするようになるため、不正行為やミスが発生しづらい環境が作れるでしょう。
7-4. コンプライアンスの相談窓口・部門を設置する
コンプライアンス違反を未然に防止し、企業内の透明性を高めるためには、相談窓口や専用部門の設置も欠かせません。
従業員が不正行為やハラスメントなどの問題を安全に報告できる場があれば、問題が深刻化する前に発見・解決ができます。
相談窓口を運営する際は、運用ルールと方針を策定して従業員に周知することが重要です。受付方法や対応時間を明確にし、従業員が気軽に利用できる体制を整えましょう。
8. コンプライアンスへの理解を深めて企業の信頼性を維持しよう


今回は、コンプライアンスの基本概念や具体的な違反事例、企業が取り組むべき対策などを詳しく解説しました。
現代の企業経営では、法令だけでなく倫理や社会規範を守ることも求められています。違反が発覚すれば、経済的損失や信用の失墜など深刻な影響をもたらしかねません。
コンプライアンス体制の強化や従業員教育を通じて、健全な企業運営を実現するための取り組みを進めましょう。



従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















