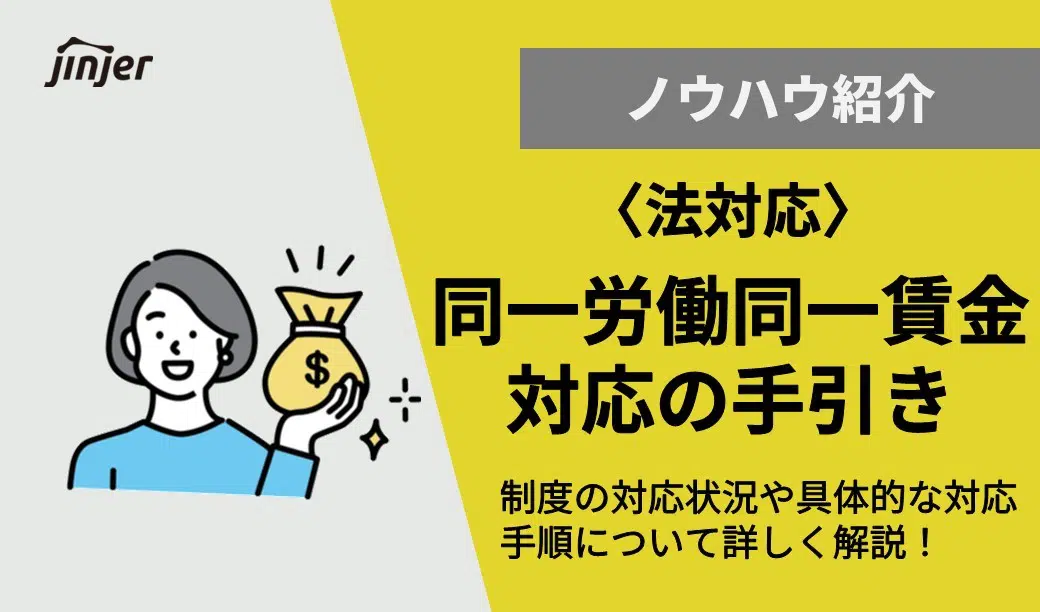同一労働同一賃金の抜け道とは?非正規雇用労働者の対応についても紹介

有期雇用労働者・パートタイム・派遣労働者などの非正規雇用労働者と、フルタイムかつ無期雇用で働く正規雇用労働者の待遇差を解消するため、新たに同一労働同一賃金が導入されました。
パートタイム・有期雇用労働法として大企業では2020年4月1日から、中小企業では2021年4月1日から施行されています。また、派遣労働者の格差を解消するために、労働者派遣法は企業の規模を問わず2020年4月1日より施行されています。
格差を解消するための大きな一歩として見て取れますが、中には対応から漏れ、待遇差がなかなか解消されないケースもあります。
今回は、そんな同一労働同一賃金の抜け道の内容や非正規雇用労働者の対応、助成金、相談先について、詳しく解説していきます。
▼そもそも「同一労働同一賃金とは?」という方はこちら
同一労働同一賃金とは?適用された理由やメリット・デメリットについて
目次
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 解消すべき同一労働同一賃金の抜け道とは?

同一労働同一賃金は正規雇用労働者と非正規雇用労働者との格差を是正することが目的です。しかし、同一労働同一賃金には次のように解消すべき抜け道が存在しています。
- 大企業と中小企業の抜け道
- 性別ごとの雇用形態の違い
- 同一労働同一賃金から除外されるフルタイム無期雇用労働者
- 定年延長によって正社員として雇われる高齢者の賃金格差
- 正規社員と非正規社員を別々の会社で雇用する場合
このような抜け道は会社や社会が是正していく必要があります。それぞれについて詳しく解説します。
1-1. 中小企業は適用までに猶予期間があった
同一労働同一賃金は大企業と中小企業とで導入タイミングが異なりました。そのため、2020年4月1日~2021年4月1日までの1年間は、中小企業では同一労働同一賃金に対応する必要がないという歪みがありました。しかし、2021年4月1日を過ぎた時点で、中小企業にも同一労働同一賃金が適用されています。
関連記事:同一労働同一賃金が中小企業に適用されどう変わった?
1-2. 性別ごとの雇用形態の違い
同一労働同一賃金によって賃金格差が解消され始めていますが、性別ごとの待遇差はまだ解消できていない部分があります。
総務省統計局がおこなった2018年の労働力調査では、男女合計の正規雇用労働者は62%ですが、女性の正規雇用労働者が44%、男性の正規雇用労働者が77%と、女性のほうが圧倒的に少なくなっています。
雇用形態同士の賃金格差は解消されつつありますが、性別間の賃金格差については一部取り残されている部分があるため、自社で適切に対応していく必要があります。
1-3. 同一労働同一賃金から除外されるフルタイム無期雇用労働者
同一労働同一賃金の抜け道として指摘されているのが、フルタイムで働く無期雇用労働者です。無期雇用とは、有期雇用が通年で5年を超えた場合、労働者の申請によって契約期間が無期限になる制度で、安定して働き続けられるメリットがあります。
しかし、フルタイムで働く無期雇用労働者には同一労働同一賃金が適用されません。また、待遇は有期雇用の状態から引き継がれるため、給与や福利厚生の待遇差が解消されていない場合はトラブルにつながりかねません。そのため、従業員が不満を抱かないような対応が求められるでしょう。
関連記事:無期雇用は同一労働同一賃金の対象外!リスクや高齢者の特例措置も解説
1-4. 定年延長によって正社員として雇われる高齢者の賃金格差
労働人口は減少しており、定年が延長されました。企業の中には定年に近い年齢になると賃金を少し下げる所もあるため、延長後の定年まで働き続ける高齢者には、待遇差が生じる可能性があります。
同一労働同一賃金は正社員とそうでない社員の格差を解消する制度なので、正社員として雇われている高齢者には適用されません。定年を延長した従業員が納得できる待遇を設ける必要があります。
関連記事:定年後再雇用は同一労働同一賃金の対象になる?メリット・デメリットも解説
関連記事:同一労働同一賃金における60歳以上の定年後再雇用の扱いとは
1-5. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者を別々の会社で雇用する場合
同一労働同一賃金の問題点として指摘されているのが、同一労働同一賃金は同じ企業内にのみで適用されるという点です。
仮に、正規雇用労働者をA社で、非正規雇用労働者をB社で雇っている場合は、同一労働同一賃金が適用されません。同一労働同一賃金はあくまでも同一企業内の正社員と比較する制度なので、以上のケースは同一労働同一賃金の問題点として考えられます。
2. 同一労働同一賃金で非正規雇用労働者の対応はどうなった?

同一労働同一賃金が適用されてからしばらく経ちますが、まだ「正社員の方が待遇が良いと感じる」という声が上がっています。従って、同一労働同一賃金で待遇差が解消されていない企業が存在することがわかります。
仮に同一労働同一賃金によって待遇差が解消される場合、適用されている終業規則が変更されます。終業規則には賃金や各種手当、福利厚生に関する項目があるため、同一労働同一賃金に則って待遇差を改善する際は、変更が必要です。
また、「不合理な待遇差ではないか」と短時間・有期雇用労働者・派遣労働者が感じる場合は、使用者に対して説明することを求められます。説明を求められた使用者は必ず待遇差が生じる理由を説明しなければなりません。
説明の義務も同一労働同一賃金によって得られた新しい対応の一部です。 当サイトでは、同一労働同一賃金が適用されたことによる対応の変化や、説明責任の具体的な内容に関して解説した資料を無料で配布しております。自社の同一労働同一賃金の対応に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「同一労働同一賃金 対応の手引き」をダウンロードしてご確認ください。
3. 非正規雇用労働者の待遇改善には助成金が活用できる

同一労働同一賃金によって非正規労働者の待遇を改善する場合は、助成金が活用できます。同一労働同一賃金の助成金として活用できるのが、キャリアアップ助成金です。
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の職能を改善するために支給される助成金で、
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
以上の6つのコースがあります。
助成金の利用によって企業の負担が軽くなる点がポイントです。実際に待遇差を改善する場合は、助成金を活用しましょう。
4. 同一労働同一賃金の対策をおこなう際の相談先

同一労働同一賃金で不合理な待遇差の判断基準や、賃金引上げ、待遇改善などに戸惑う場合は厚生労働省が運営している無料相談窓口や、改正法個別相談窓口の他、各自治体が独自で対応している相談窓口などがあります。
このうち、厚生労働省が運営している働き方改革推進支援センターでは、無料相談窓口を設けています。また、先ほど紹介した助成金の案内や、中小企業の対応例も紹介しているので、支援が手厚いうちに頼るのがおすすめです。
その他、弁護士事務所でも同一労働同一賃金導入における待遇格差の相談を受けています。
▽同一労働同一賃金の相談先
- 働き方改革支援センター(厚生労働省)
- 改正法個別相談窓口(厚生労働省)
- 自治体が対応する無料相談窓口
- 弁護士事務所
5. 同一労働同一賃金における待遇差を解消するためには、助成金や無料相談を活用しよう

同一労働同一賃金によって非正規雇用労働者の格差は解消されつつありますが、雇用形態や待遇差の理由によっては、抜け道と呼ばれる格差が解消されないケースがあります。労働者自ら待遇差解消のために動くことも大切ですが、裁判沙汰に発展しないように企業側から待遇差を解消するための働きが大切です。
待遇差の解消について疑問が生じた場合は、無料の相談窓口を活用してみてください。また、待遇差を解消する際に助成金を申請すると、負担を軽減できます。
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。 自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
同一労働同一賃金の関連記事
-

労使協定方式や同一労働同一賃金における派遣会社の責任について
人事・労務管理公開日:2022.02.05更新日:2024.04.02
-

同一労働同一賃金で業務における責任の程度はどう変化する?
人事・労務管理公開日:2022.02.04更新日:2024.04.02
-

同一労働同一賃金における60歳以上の定年後再雇用の扱いとは
人事・労務管理公開日:2022.02.03更新日:2024.10.15