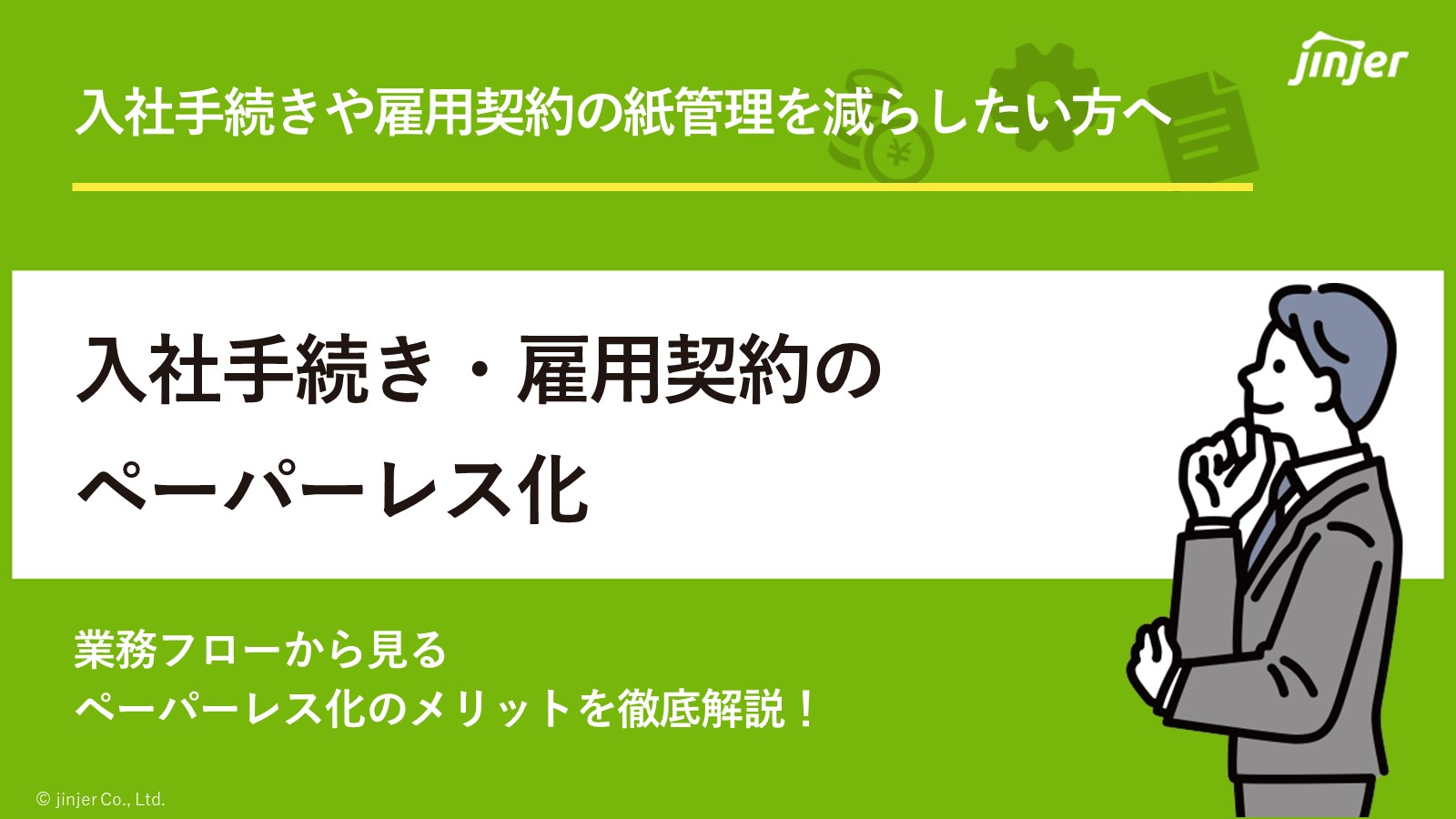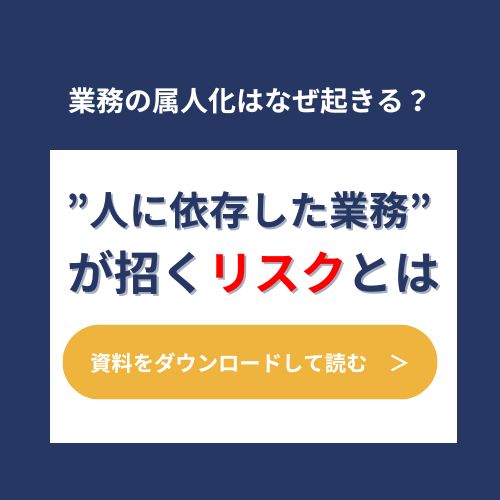就業規則に賃金規程は必須ではない?必要になるケースや定める事項とは
更新日: 2024.7.11
公開日: 2022.2.11
OHSUGI

就業規則とは、労働者と企業の間で締結する独自の規則を指します。就業規則では労働時間や労働環境、退職時の定めだけでなく一部の賃金に関する規程についても定める項目があります。ただし、就業規則はすべての企業に作成義務があるわけではなく、常時10人以上の従業員がいる企業にのみ作成が義務付けられているのがポイントです。
また、就業規則には必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項があり、一部賃金の計算方法や支払い方法に関する項目もその一つ。加えて、事業場ごとに必要があれば記載しなければならない相対的必要記載事項もあります。
今回は、就業規則に賃金規程が必要になるケースや定める事項、作成後すぐに届け出をするべき理由や手続きの流れ、トラブル防止策について詳しく解説していきます。就業規則は罰則も定められているため、ぜひご一読ください。
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
目次
1. 就業規則に賃金規程は必須ではない!必要になるケースとは
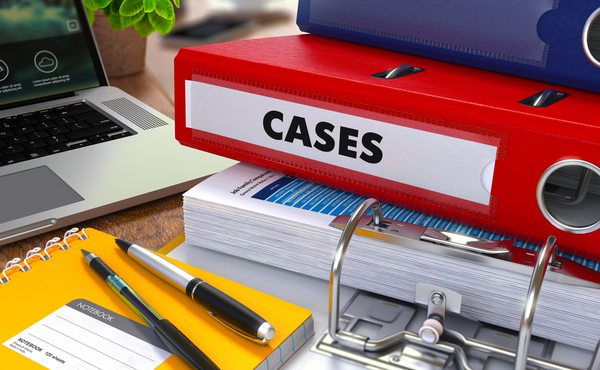
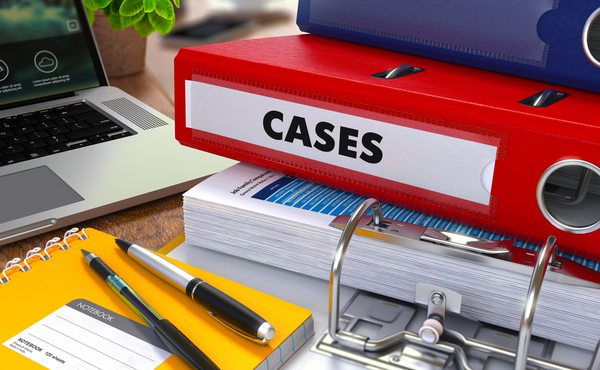
就業規則を定める場合には、賃金に関する項目を必ず記載しなければなりません。ただし、全ての賃金に関する項目を記載しなければならないわけではなく、退職手当や臨時の賃金などは必要がある場合にのみ記載すれば問題ありません。
必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項のうち、賃金に関する項目は次のとおりです。
- 賃金の決定方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払い方法
- 賃金の締め切り
- 賃金の支払い時期
- 昇給に関する事項
加えて、事業場ごと規則を定める場合には記載が必要な、相対的必要記載事項の賃金に関する項目は次のとおりです。
- 退職手当が適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定方法・計算方法
- 退職手当の支払い方法
- 退職手当の支払い時期
- 臨時の賃金
- 最低賃金額
就業規則は労働者が常時10人以上いる事業場のみが就業規則の作成を義務付けられるため、10人未満の事業場や個人事業主の場合には就業規則を定める必要がありません。従って、賃金規程も定める必要がありません。
関連記事:就業規則がないとどうなる?その違法性やリスクを解説
2. 賃金規程に定める事項


賃金規程に定める事項を説明する前に、賃金規程の重要なポイントをご紹介します。賃金規程は就業規則の中で必ず記載しなければならない項目ですが、複数の賃金規程を作成したり、細かく別規程を定めたりすることには、問題ありません。例えば、パートタイムやアルバイト労働者に対しては、正社員とは別の賃金規程を定めることは、正式に認められています。
賃金規程に定める事項として、以下のものなどが一般的に採用されます。
- 基本給
- 手当
・家族手当
・通勤手当
・技能・資格手当
・精勤手当
・役付手当 - 割増賃金
・時間外労働割増賃金
・休日労働割増賃金
・深夜労働割増賃金
上記以外にも定めたい賃金があれば、別途記載してください。
また、賃金規程を定める際は対象となる人物の選出方法や条件、詳しい計算方法なども明記するのが大切です。ここからは、賃金規程に定める事項で、重要なポイントをご紹介します。
2-1. ポイント①賃金から天引きする項目を記載する
社会保険料や税金などは、賃金から控除をおこなう場合がほとんどです。しかし、労働基準法において、賃金は全額支払わなければならないという原則があるため、給料から控除する項目を定めたい場合には、就業規則内に必ず記載しましょう。
2-2. ポイント②賃金の計算方法は明確に記載する
賃金の計算方法は、明確に記載しておかないと後々トラブルに発展する可能性があります。
計算方法は以下の種類があります。
- 時給制
- 年俸制
- 日給制
- 月給制
これらの中から採用する計算方法を記載するとともに、雇用形態ごとに異なる場合は別途その雇用形態向けの就業規則を定めましょう。
2-3. ポイント③雇用形態の違いは詳細を明記する
雇用形態ごとに異なる賃金形態を定める場合には、雇用形態の違いをしっかり記載しましょう。労働基準法では正社員と短時間・有期雇用労働者の違いが定められていないため、誤解を生まないためにも「労働時間が〇時間以上かつ出勤日数が〇割を下回る場合は短時間労働者として取り扱う」などの記載が必要です。
2-4. ポイント④ノーワーク・ノーペイに関する項目も記載する
賃金規程には、ノーワーク・ノーペイに即した規程も盛り込むのがおすすめです。ノーワーク・ノーペイとは、労働の事実がない場合には賃金を支払い義務が生じないという原則を指します。
仮に労働者が遅刻や欠勤した場合、その分だけ給料を支払いたくない場合には賃金控除として計算方法と概要を記載しましょう。労働に対して相応な賃金を支払えるだけでなく、労働者同士の不平等さも解消できるのがポイントです。
3. 作成したらすぐに届け出をするべき


就業規則の作成に関しては、30万円以下の罰金刑が定められています。
▽就業規則に関して罰則が科せられる場合
- 常時10人以上の従業員がいるのにもかかわらず就業規則の作成義務を怠った
- 就業規則を作成・変更した際に労働基準監督署に届け出をおこなわなかった
以上のとおり、就業規則は企業が一方的に作成して完了するのではなく、労働者の意見書を添えて労働基準監督署に届け出をおこない、正式に認められなければ就業規則として認められません。従って、就業規則の届け出をおこなわずにいた場合、労働基準法違反として別の罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
ちなみに、労働者と交渉をおこなったり、意見書を作成してもらう場合には、労働者の過半数を代表する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者が企業とやり取りをおこないます。労働者の代表を選出する際も、適切な方法でなければ交渉や作成した書類も無効になってしまうため、十分に注意しましょう。
また、届け出後は労働者全員に徹底した周知をおこないましょう。就業規則は作成義務と同時に周知義務もあるため、周知をおこなっておらず労働者が知り得ない就業規則は無効とみなされます。また、周囲義務を怠ったとして30万円以下の罰金を科される可能性もあります。
▽就業規則の作成・変更の流れ
- 就業規則案を作成する
- 労働者に周知する
- 労働者の過半数を代表する労働組合または代表者に意見書を作成して貰う
- 意見書を添付し、労働基準監督署に届け出をおこなう
- 労働者に周知をおこなう
4. 賃金規程でのトラブルを防ぐための対策


最後に、賃金規程でトラブルを防ぐための対策方法をご紹介します。
先ほども少しご紹介しましたが、トラブルを防ぐための対策は次のとおりです。
- 社員区分の定義は正確に
- 残業代の規程や計算方法はしっかり理解してから
- 就業規則を労働者に周知していない
- 就業規則と労働契約書の整合性を確認する
社員区分や就業規則の周知義務無視、就業規則と労働契約書に相違点があるなどは、労働者からの指摘を受け大きなトラブルに発展する可能性があります。また、労働者に周知していない就業規則は罰則の対象となる上、就業規則として認められないので注意が必要です。
5. 就業規則を定める場合には賃金規程を定めよう


従業員が常に10人以上いる企業では、労働条件を記載した就業規則の作成が義務付けられます。賃金規程は就業規則の中でも必ず定めなければない、絶対的必要記載事項の一つです。
トラブルを避けるためにも、詳細かつ正確に記載することを心がけましょう。加えて、就業規則を作成する場合には労働者の意見書を添付したうえで、労働基準監督署に届け出をおこなう必要があります。
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08