人事評価における目標設定とは?書き方や職種別の設定例文・サンプルを紹介
更新日: 2025.4.10 公開日: 2022.4.26 jinjer Blog 編集部

人事評価制度を運用する際、必ずおこなう必要があることが、従業員の「目標設定」です。適切な目標設定をおこなうことで、従業員のやる気やモチベーションを高められます。また、目標設定を通じて取り組むべき課題が可視化されるため、より確実な成長につながります。
逆に目標を設定しなければ、ゴールにたどりつくための道筋がわからず、人事評価制度が思うように機能しなくなる可能性があります。人事評価制度の運用成功のカギを握るのは「目標設定」です。
この記事では、人事評価において目標設定が欠かせない理由や、代表的な目標管理制度、目標設定をおこなうときのポイントについて解説します。
関連記事:人事評価はなぜ必要?導入して考えられるメリットやデメリット
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 人事評価において目標設定は重要!

人事評価制度は、企業が従業員の業務実績や能力を評価するための仕組みであり、昇進や給与、賞与、人材育成に深く関与しています。この制度は、個々の従業員が自身に求められる役割や能力を理解し、自らの成長へとつながる重要なステップを形成します。
また、人事評価には企業の方向性を示す役割があります。これによって組織全体のビジョンや戦略に基づいて、各従業員に求められる目標や行動が明確にされます。よって、これにより従業員は自身の業務が企業全体にどう貢献するかを理解することができ、仕事に対する意欲が向上するため人事評価において目標設定は重要なのです。
1-1. 人事評価と人事考課の違い
人事評価と人事考課は、企業における人材管理において不可欠なプロセスですが、その目的や内容に明確な違いがあります。
人事評価は、主に従業員の配置や能力開発に役立てるために、業績や成果を出すための取り組みを評価するプロセスです。評価の対象となるのは従業員の行動や成果であり、これに基づいてそれぞれの能力を伸ばしたり、より効果的に活用したりすることが目指されています。たとえば、定期的な評価面談を通じて業務プロセスやスキルを洗い出し、次のステップへの成長を促すことが一例です。
一方で、人事考課は、従業員の能力や業績に基づいて昇給、昇進、賞与などの報酬を決定するためのプロセスです。このプロセスでは、主に評価された結果をもとに、具体的な報酬やキャリアの進展に直結する判断が行われます。例えば、年間の業績評価で高いスコアを得た従業員には、昇進や賞与が支給されることが多く、こうした評価と報酬の連動が人事考課の特徴といえます。
このように、両者は密接に関連しながらも、それぞれの目的が異なります。公平で透明性のある報酬体系を設けるためにも、これらの違いを理解し活用することが重要です。
2. 業績向上のため人事評価の目標設定を取り入れるべき理由3つ

人事評価制度で大切なのが、被評価者の「目標設定」です。適切な目標を設定し、従業員がたどりつくべきゴールを可視化することで、従業員のやる気やモチベーション向上につながります。
また、従業員自身が目標を設定することで、目標管理を通じて自己を振り返ることができ、着実な能力開発につながります。
長期的に見た場合、人事評価における目標設定は企業の業績にも影響を及ぼします。ここでは、目標設定を取り入れるべき3つの理由を解説します。
関連記事:人事評価の「目標設定」の重要性や代表的な手法について解説
2-1. 従業員のモチベーションが向上するため
適切な目標設定をおこなうことで、従業員のやる気やモチベーションの向上が期待できます。目標が設定されていなければ、従業員は「自分になにが期待されているのか」「業務を通じ、どのようなことを実現できるのか」がわからず、日々の業務の意義を理解しづらくなります。
しかし、従業員が自ら目標を設定し、目標達成に向けて計画的に業務に取り組むことで、日々の業務が「自分ごと化」されます。このように、金銭などの外的要因によらず、内なる意欲によって動機づけられた状態を「内発的動機づけ」と呼びます。
人事評価における目標設定は、内発的動機づけを生み出し、従業員のやる気やモチベーションを生み出す効果があります。
2-2. 従業員の能力開発につながるため
人事評価制度の目的は、従業員の成果や実績を査定することだけでなく、従業員の能力開発の促進にもあります。人事評価制度を導入し、従業員に自発的な目標設定を促すことで、能力やスキルをより効率的にレベルアップさせることが可能です。定期的に目標達成度を振り返ることで、従業員の取り組むべき課題や、習得すべき能力・スキルが可視化されます。
また、もし目標を達成できた場合、内発的動機付けの構成要素である「自己効力感」「自己決定感」が得られ、さらなる挑戦に向けた動機付けが生まれます。従業員の能力開発を促進する意味でも、適切な目標設定が必要不可欠です。
実は、目標設定の他にも、人事評価の効果を高めるためには、被験者に対する人事評価マニュアルの作成、評価結果のフィードバックなど必要な手順が複数存在します。
当サイトはでは、人事評価制度をより良いものにするための情報を、より詳しく知りたいという方に向けて「わかりやすい!人事評価の手引き」という無料のガイドブックを作成しました。
人事評価をおこなうメリットや注意事項についても網羅的に解説していますので、こちらからダウンロードして、人事評価制度作成の参考書としてご活用ください。
2-3. 上長との信頼関係構築につながるため
一般的な人事評価制度では、原則として従業員自身が目標を設定し、上長が目標達成度の評価やフィードバックにて目標管理をおこないます。
面談やミーティングを通じ、上長と従業員がコミュニケーションを取り合いながら、「適切な目標設定かどうか」「目標設定が成長につながっているか」を共に判断していくのが人事評価制度です。そのため、目標成果や目標管理の手法を取り入れることで、上長と従業員との信頼関係の構築につながります。
3. 人事評価の代表的な目標管理制度3つ

人事評価の代表的な目標管理制度として、「KPI(Key Performance Indicator)」「OKR(Objectives and Key Results)」「MBO(Management By Objective)」の3つがあります。一見するとよく似た制度ですが、それぞれ異なる目的や考え方を持った制度です。KPI、OKR、MBOの3つの目標管理制度の特徴を解説します。
関連記事:人事評価制度で重要な3つの基準の評価項目について解説
関連記事:人事評価制度を導入する前にチェックすべきポイント
3-1. KPI(Key Performance Indicator)を導入する
KPIとは、日本語で「重要業績評価指標」といい、プロジェクトの最終的なゴールを実現するため、段階的に数値目標を設定する手法を指します。
| 最終目的 | プロジェクトを成功に導く |
| 期待される目標達成度 | 100% |
| 目標を共有する範囲 | 部署やプロジェクトチーム全体 |
| フィードバックの頻度 | 毎月 |
3-2. OKR(Objectives and Key Results)を導入する
OKRは、GoogleやFacebookなどのGAFAも導入していて、近年注目を集めている目標管理制度です。OKRの目的は、組織全体の生産性やパフォーマンスの向上です。企業の経営課題から逆算し、従業員一人ひとりがこなすべきタスクを細分化していきます。
| 最終目的 | 組織の生産性やパフォーマンスを向上させる |
| 期待される目標達成度 | 60~70%程度 |
| 目標を共有する範囲 | 組織全体 |
| フィードバックの頻度 | 四半期 |
3-3. MBO(Management By Objective)を導入する
MBOは、多くの企業の人事評価制度で採用されている目標管理方法です。従業員本人が業務目標を設定し、上長が目標達成に向けたサポートをおこないます。プロジェクトの成功を目指すKPIや、組織全体の生産性向上を目指すOKRに対し、人材開発や能力開発の強化を目指すのがMBOの特徴です。
| 最終目的 |
個人で設定した業務目標を実現する 人材開発や能力開発を強化する |
| 期待される目標達成度 | 100% |
| 目標を共有する範囲 | 上長と従業員 |
| フィードバックの頻度 | 1年 |
4. 人事評価の目標設定をおこなうときのフレームワーク

人事評価の目標設定をおこなうときに役に立つのがSMARTの法則、FASTの法則という2つのフレームワークです。
4-1. SMARTの法則
SMARTは「Specific(明確性)」「Measurable(計量性)」「Achievable(現実性)」「Agree on(合意可能性)」「Relevant(関連性)」「Timely(適時性)」の6つの単語の頭文字をとった言葉です。それぞれ次のようなポイントがあります。
| Specific(明確性) | 誰が見ても内容を理解できるよう、明確でわかりやすい目標を設定する |
| Measurable(計量性) | 勤務態度や業務への向き合い方など、数値化が難しい目標を設定する場合も、あらかじめ評価基準を決め、目標達成度を客観的に評価できる仕組みを整える |
| Achievable(現実性) | 非現実的なものではなく、本人が達成できそうな目標を設定する |
| Agree on(合意可能性) | 上長(評価者)とコミュニケーションをとり、双方が納得する目標を設定する |
| Relevant(関連性) | 企業の経営理念と関わりのある目標を設定する |
| Timely(適時性) | 定期的に目標達成度を評価する |
関連記事:人事評価における目標設定は具体例を参考にすると進めやすい
4-2. FASTの法則
SMARTの法則と同じく目標設定に用いられるのがFASTの法則です。FASTの法則は次のような要素で構成されています。
- Frequent:頻繁に
- Ambitions:野心的な
- Specific:具体的な
- Transparent:透明性のある
FASTの法則はSMARTの法則よりも挑戦的な目標設定の際に活用されます。FASTの法則もSMARTの法則のように、目標を設定したら頻繁に立ち返ることが大切です。また、目標に透明性を持たせることで、周囲からの協力も得やすくなるでしょう。
5. 人事評価目標設定のポイント

人事評価目標を設定する際は次のようなポイントを押さえておきましょう。
- 個人の目標は上長と擦り合わせる
- 従業員の目標設定をサポートする
- PDCAを回す
5-1. 個人の目標は上長と擦り合わせる
従業員個人が設定した目標は上長と擦り合わせることが大切です。上司が目標を設定しては一方的になってしまい、従業員のモチベーションは向上しません。一方、従業員だけで目標を設定しては組織が目指すべき所と乖離しかねません。そのため、個人の目標は上長と擦り合わせて設定しましょう。
5-2. 従業員の目標設定をサポートする
上述のように従業員が個人で目標設定をすると、組織の目標とずれてしまう恐れがあります。そのため、上長や評価者は従業員の目標設定をサポートしてあげましょう。従業員が目標設定で悩んでいたら、本人の努力で達成できる難易度が少し高い目標を設定することが大切です。少し高い目標を達成できれば、従業員本人のモチベーション向上につながります。
5-3. PDCAを回す
人事目標を設定したらPDCAを回しましょう。PDCAを高い頻度で回すことで、目標達成までのスピードや確実性を高めることが可能です。その結果、プロジェクトの成功や企業の売上の向上といったメリットにつながる可能性があります。
6. 人事評価における目標設定シートの書き方
 それでは、実際に目標設定をおこなうフェーズで必要になってくる人事評価における目標設定シートの書き方を説明します。
それでは、実際に目標設定をおこなうフェーズで必要になってくる人事評価における目標設定シートの書き方を説明します。
6-1. 仕事上の役割から個人目標を記載する
目標設定をする際、まずは個々の業務内容に基づいた具体的かつ明確な目標を設定すべきです。
例えば、営業職の従業員であれば「四半期売上700万円達成」という目標を設定するとします。この売上目標は、組織全体の利益に影響を与えるため、役割を理解した上での数値的な目標は評価されやすいでしょう。また、こうした具体的な数字があることで、達成度を測定しやすくし、次のステップへと進むための指針となります。
さらに、個人目標は単に数値的なものだけに限るわけではありません。職務上のスキル向上や新しい資格取得といった非数値的な目標も含めることが重要です。
例えば、「今年度中に簿記2級を取得する」といった目標は、経理職の従業員が自分の職務をより効果的に遂行できるようになるためのステップとして位置付けられます。このように、業務に関連性のある目標を設定することで、従業員の自己成長にもつながることが期待されます。
また組織の目標と一貫性を持たせることも重要です。例えば、会社の方針として「顧客満足度の向上」が掲げられている場合、個々の従業員は「顧客からのフィードバックを月に3回取得し、その結果を分析する」という目標を設定することで、組織全体の目標達成に貢献できるのです。
このように、目標を設定する際は従業員の成長と組織の成果が連動していることがポイントになります。
6-2. 査定までの期日を明確に設定する
続いて評価期間として、実際に査定がされるまでの期日を明確に記載・設定することは、人事評価の目標設定において非常に重要です。具体的な期限を設けることで、従業員は自分の目標達成に向けたアクションプランを立てやすくなります。詳細な期限がなければ、計画そのものがあいまいになり、実行力が低下する恐れがあります。
また、目標設定においては、長期的な期限だけでなく短期的な期限も設けることが求められます。これにより、目標達成のための進捗を定期的に確認し、必要に応じて調整を行うことが可能になります。短期間での達成感を得ることも、モチベーションの維持に寄与し、より良い成果につながるでしょう。
6-3. 目標達成までの行動計画を記載する
目標達成には、具体的な行動計画が必要です。この計画は、日々の業務においてどのように目標に向かって進むかを示すものです。まず、目標を日常の行動に落とし込むことが重要です。例えば、目標達成に向けた短期的なタスクを設定し、役割に応じて行動を細分化します。
次に、具体的な行動を記載します。「毎日1時間の勉強」や「週に1回の進捗共有会」など、明確にわかる内容にすることが肝要です。このようにすることで、実行可能な計画が形成されます。
さらに、進捗を確認できる定量的なアクションを意識することがポイントです。数値で測定できる指標を設けることで、自己評価や上司との評価がスムーズになります。これにより、目標達成に向けた道筋が明確になります。
7. 【職種別】人事評価の目標設定の例文・サンプル
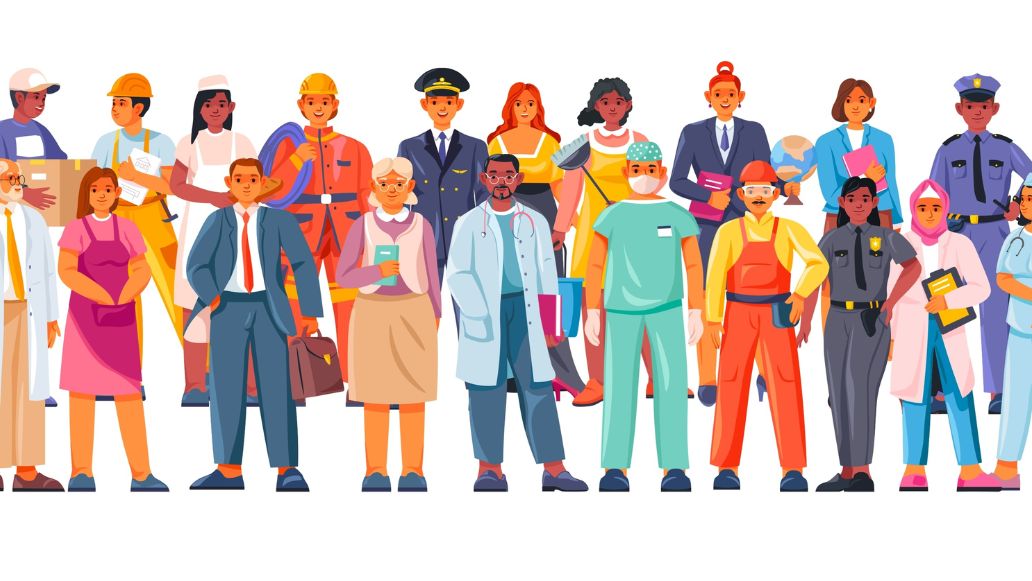
ここまで、人事評価の目標設定の仕方や管理手法ついて解説してきました。実際は、職種によって業務内容が異なるため、業務内容と照らし合せて目標に落とし込んでいく必要があります。ここでは、職種別に目標設定のポイントと具体例を紹介します。
7-1. 営業職の目標設定の例
営業職は、売り上げに直結する職種であるため目標の数値化がしやすいです。目標を立てる際は、部署の目標数値と連動させる必要があるため、事前に上司と相談して決めると良いでしょう。
- 上期の契約数を前年比120%を達成する
- 成約率を40%以上を達成する
- 1週間で5件以上のアポイントを獲得する
- ヒアリングの結果や内容を社内で共有
7-2. 事務職の目標設定の例
事務職は書類作成やデータ入力、電話応対などバックオフィス業務が中心であるため、数値による目標設定が難しい職種です。そのため、目標設定する際は、コスト削減に目を向けると目標が立てやすくなるでしょう。
- ダブルチェックをおこない毎月の計算ミスをなくす
- データ入力作業の工数を月あたり7時間削減する
- 日々の業務効率を上げて残業を10%削減する
- 今上期にMOSの資格を取得する
7-3. 総務の目標設定の例
総務は売り上げと直結しない間接部門であるため、業務の成果を数値に置き換えるのが難しい部分があります。目標設定をする際は、経費の削減や業務の効率化に焦点をあてて設定していくと良いでしょう。
- 消耗品の購入先を見直して消耗品費を10%削減する
- 2か月以内に従業員向けのFAQを作成して公開する
- 社内FAQを拡充し問い合わせ件数を20%減らす
- 福利厚生を見直してコストを10%削減する
7-4. 経理の目標設定の例
経理の目標設定は、財務の健全性を保ちつつ、業務の効率化を図ることが求められます。具体的には、予算の厳守や正確な財務報告を目指すことが中心となります。
- 前年よりも経費を5%削減することを目指す
- 毎月の財務報告を納期通りに提出し、期日を厳守する
- 会計システムの更新や自動化により、業務の生産性10%を向上させる
- 異常な取引や不整合を早期に発見するための内部監査を強化する
- 経理処理誤りの発生を10%以下に抑える
7-4. 人事・労務の目標設定の例
人事・労務は、従業員の採用や育成、配置など、業務内容が多岐にわたります。そのため、自分が担当する業務内容に合わせた目標設定が必要です。まずは、現状を数値で把握した上で、現実的に達成可能な目標を設定しましょう。
- 自社採用サイトを立ち上げ、エントリー数を前年比5%増やす
- 面接の連絡手段を見直して面接設定率を50%に引き上げる
- 有給休暇取得率を政府目標の70%に近づける
- 教育訓練への参加者数を前年比10%増を達成する
7-5. 管理職・マネジメント職の目標設定の例
管理職やマネジメント職は、部下の行動や部署の数字を管理する立場にあるため、マネジメントに関することが目標設定の中心となってきます。目標の具体例としては以下のとおりです。
- 業務の効率化をはかり、チーム全体の残業時間を月5時間削減する
- 勉強会を毎月開催して売上を前年比で10%増加させる
- チームランチ会を1週間に1回開催し、コミュニケーションを活性化させる
- プロジェクトリーダー育成のため研修会を月に1回実施する
7-6. 新卒の目標設定の例
新卒の目標設定を考える際は、自身が担う具体的な業務とキャリアビジョンを意識することが重要です。目標は実現可能で達成感を味わえる内容にすることで、モチベーションを維持しやすくなります。
- 業務を通じて3か月以内に特定の業務マニュアルを作成し、業務の標準化を進める
- 1年以内に特定のスキルを身に付けるための研修を受講し、資格取得を目指す
- チーム内のコミュニケーションを円滑にするために月1回の意見交換会を実施し、その結果を業務改善に活かす
7-7. 企画・マーケティングの目標設定の例
企画・マーケティングは、事前にプロジェクトの目標に基づいて計画を実行するため、目標を立てやすい職種と言えます。競合他社の状況も加味しながら、具体的に目標設定していきましょう。
- メールマガジンの登録者数を半年で30%UPさせる
- 広告出稿を強化しECサイトの閲覧数を前年比2倍にする
- 自社ブランドのSNSを立ち上げてフォロワーを半年で1万人獲得する
- 自社サイトの記事の60%が検索上位3位内に入るようにする
7-8. システムエンジニア(SE)・技術職の目標設定の例
システムエンジニア(SE)は、専門的な知識や技術を磨く必要があることから、長期的な視点で目標を設定を進めていきます。目標例としては次のようなものが挙げられます。
- 業務に関連する専門資格を半年以内に取得する
- 新たな言語を1年以内に習得する
- 担当システムの詳細設計から結合テストまで独力で完成できるようにする
- クラウドなどの先端技術を学んで習得する
7-9. 医療事務の目標設定の例
医療事務は、業務が定型化されている部分が多いため、目標を数値で表しづらいところがあります。そのため、業務の無駄をなくすなど、業務改善に重点をおくと目標設定がしやすくなるでしょう。
- 事務作業をスピードアップし平均待ち時間を5分削減する
- 計算ミスを10%以下に減らす
- 1年以内に資格を取得する
- セミナーや勉強会に月1回以上参加する
7-10. 公務員の目標設定の例
公務員は、一般企業の従業員とは異なり、利益を追求しない立場にあるため、目標設定が難しく思われるかもしれません。公務員の場合は、効率性やコスト削減、サービス提供の質向上などの観点から、具体的な内容を目標に落とし込んでいきましょう。
- 業務を効率化し残業時間を10%削減する
- 丁寧な説明や対応により住民からのクレーム0件を目指す
- 新制度○○に関する知識を身に付け、問い合わせにスムーズに対応する
- ペーパーレス化を推進して紙書類を30%削減する
7-11 .保育士の目標設定の例
保育士は、園から期待されている役割を理解した上で、自分の目標を決める必要があります。目標例は次のようなものが挙げられます。
- 子どもたちの個性や能力を伸ばせるような声かけを心がける
- 保護者とのコミュニケーションを図り信頼関係の構築に取り組む
- 後輩へ丁寧に指導をおこない相談しやすい雰囲気作りを心がける
- 新しい遊びを考えて毎月実践する
7-12. 看護師の目標設定の例
看護師の目標設定は、患者への質の高い医療提供と業務効率の向上に重要です。具体的には、看護業務の中での目標は、患者ケアの向上や業務プロセスの改善を重視することが効果的です。
- 患者の満足度を測るためのアンケートを実施し、その結果を基にサービス向上を図る目
- 健康管理に関する教育を提供し、患者の健康状態の改善を目指す
- チームワークの強化を目的としたジョブローテーションを導入し、チーム全体のスキル向上を図る
これにより、看護師自身の成長につながり、結果として患者へのサービス向上にも寄与するでしょう。
8. 人事評価制度の運用成功には、適切な「目標設定」が必要不可欠!

人事評価制度の運用を成功させるためには、適切な「目標設定」が欠かせません。従業員が各自で目標を設定し、目標達成に向けて主体的に行動することによって、能力やスキルのレベルアップにつながります。また、目指すべきゴールが可視化されることで、従業員のやる気やモチベーションの向上といった効果も期待できます。
人事評価制度は、ただ目標を設定するだけではうまくいきません。目標管理制度を取り入れ、上長と連携しながら目標を適切に管理することによって、期待通りの運用成果を挙げることができます。
関連記事:人事評価制度の作り方!納得感のある評価基準でモチベーションアップ

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































