サバティカル休暇とは?企業のメリット・デメリットと事例を紹介
更新日: 2025.9.29 公開日: 2024.12.30 jinjer Blog 編集部

「サバティカル休暇はどのような制度?」
「企業にどのようなメリットがある?」
上記の疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
サバティカル休暇は目的を問わず自由に活用できる長期休暇制度で、近年日本でも注目を集めつつあります。詳しい内容や注目されている背景を知り、自社への導入を判断しましょう。
この記事では、サバティカル休暇の基本的な意味やメリット・デメリットを解説します。
記事を読めば、自社がサバティカル休暇を導入した際の効果や、導入の流れをイメージしやすくなるはずです。
目次
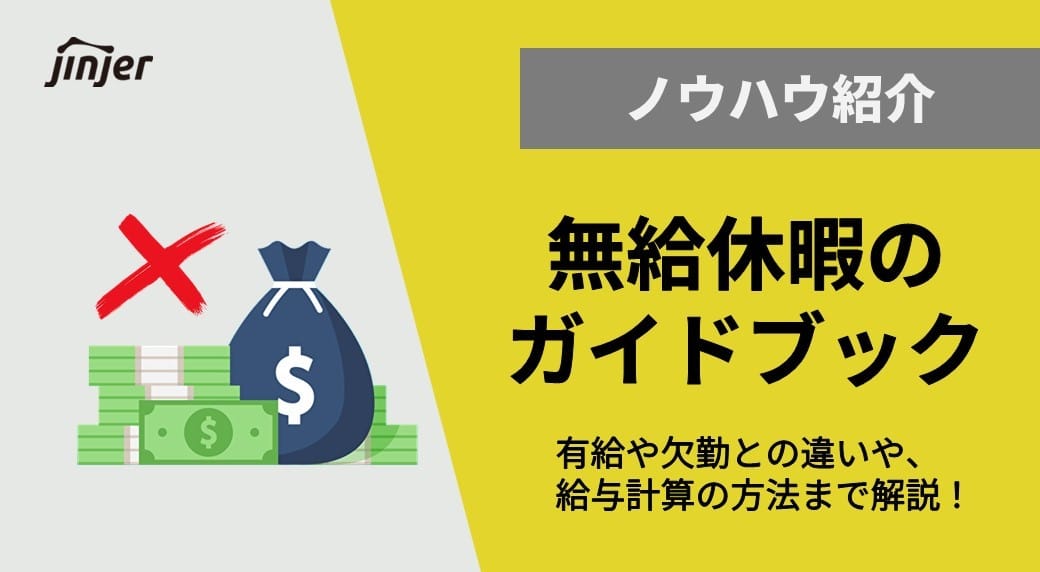
従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. サバティカル休暇とは?意味を解説


サバティカル休暇とは、自己成長やリフレッシュのために取得できる長期休暇です。詳しい制度の内容と、日本で導入している企業の一例を紹介していきます。
1-1. 長期勤務している従業員に対する長期休暇のこと
サバティカル休暇とは、長期間勤務している社員に対して与えられる長期休暇のことです。特定の理由を必要とせず、自己成長やリフレッシュのために自由に使うことができます。
企業によっては1年近くの休暇を許可することもあり、主にワークライフバランスの充実やスキル向上が目的です。
例えば、サバティカル休暇を取得する人の中には、海外での学び直しや新分野の学習をおこなう人も多くいます。
サバティカル休暇は欧米で普及している一方、日本では導入している企業がまだ少ない状況です。しかし、経済産業省も導入を推奨しており、今後の普及が期待されています。
参考:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~ (案) 令和4年3月|経済産業省
1-2. 日本でも導入する企業が出てきている
サバティカル休暇は日本ではまだまだ浸透していませんが、富士通株式会社・ANA(全日本空輸株式会社)・LINEヤフー株式会社などでは導入されています。
働き方改革の促進やライフワークバランスの改善を目的としているとともに、働く人に選ばれる企業であり続けることもサバティカル休暇を導入する理由のひとつだと考えられています。
日本は高齢化が進んでおり、それに伴って就労期間も伸びてきています。その途中での長期間の休息やリフレッシュは、心身の健康を維持とともに企業と従業員の信頼関係を深めるためにも非常に有用です。
また、若い世代はこうした新しい取り組みに敏感であるため、よりよい人材を取得するためにもサバティカル休暇を導入する企業は増えていくでしょう。
2. サバティカル休暇が注目されている背景


なぜサバティカル休暇が注目されるようになったのか、現代の日本が置かれている状況を考えながら見ていきましょう。
2-1. リカレント教育の推進
サバティカル休暇が注目される背景の一つに「リカレント教育」があります。リカレント教育とは、社会人が働きながら学び直しをおこない、必要なスキルを再び身につける教育のことです。
少子高齢化や人手不足が進行する日本では、労働力の質の向上が急務となっており、サバティカル休暇がスキルアップの機会として重要視されています。
特にデジタル技術が加速度的に発展する現代では、サバティカル休暇を利用して知識を習得し、職場復帰後に活用することが求められているのです。
2-2. 人生100年時代の到来
前項でも少し触れましたが、平均寿命の延びにより、私たちは「人生100年時代」に突入しています。長寿命化により働く期間が長くなる一方、シニア層の増加で人手不足も深刻です。
そのため、長期間働き続けるには定期的に休暇を取り、キャリアの見直しやリフレッシュを図る機会が重要とされています。
サバティカル休暇を活用してキャリアアップやリフレッシュをおこなうことで、長く働ける環境づくりが実現しやすくなるのです。
2-3. 働き方改革の推進
働き方改革の一環で「仕事よりも私生活も重視する」という考え方が広まりつつあります。
従来の日本では、仕事中心の働き方が推奨され、長時間労働が当たり前とされていました。しかし、近年は労働者の生活の質を高めることが、企業の成長にもつながると考えられるようになりました。
サバティカル休暇は、社員が自分の生活や学びの時間を確保できるため、仕事と生活のバランスをとる上でも有効です。
3. サバティカル休暇のメリット


サバティカル休暇のメリットは、従業員だけでなく企業側にもあります。4つの大きなメリットを紹介していきます。
3-1. 新たな知識や経験が得られる
サバティカル休暇を活用すれば、普段の仕事だけでは得られない新たな知識や経験が得られます。できた時間を自己研鑽に使えるためです。
企業側も、スキルを向上させた社員が戻ってくることで、さらに高い成果を期待できるため、双方にメリットがあります。
具体的には、長期的な目標に向けた留学やボランティア、資格取得などの活動が可能です。
サバティカル休暇は、社員にとって自己成長やキャリアアップの機会となります。
3-2. アイデアやひらめきのきっかけになる
長期の休みをとれるサバティカル休暇では、長期の旅行や留学をする人や、仕事をしながらだと難しい観劇や趣味への没頭など、いつもとは違う環境に身を置く人も多いです。
そうした新鮮な環境や体験では新しいアイデアが生まれることが多く、刺激を受けて思わぬひらめきが発生することもあるでしょう。
仕事に対するモチベーションも上がり、異なる視点から問題へのアプローチをできるケースもあります。そうした従業員の変化は企業の発展につながることもあるはずです。
3-3. 企業イメージの向上と優秀な人材確保ができる
サバティカル休暇を導入することで、企業イメージの向上と優秀な人材確保が期待できます。社外に対して「働き方の多様性を尊重している企業」の印象を与える効果があるためです。
特に、まだ導入企業が少ない日本では、柔軟な働き方を認めることで他社と差別化でき、優秀な人材を引きつけやすくなるでしょう。
また、会社が福利厚生を充実させていると実感することで、社員の職場への帰属意識も高まります。
3-4. 離職率の低下が期待できる
サバティカル休暇のメリットとして、離職率の低下も挙げられます。社員の不安を取り除き、安心して働ける環境を提供することで離職防止につながるためです。
近年、仕事と家庭の両立が社会的に求められる一方で、介護や育児のために離職を余儀なくされるケースが増加しています。サバティカル休暇制度を活用すれば、介護や育児、突発的な病気など、個人の事情に対応しやすいです。
例えば、社員が親の介護のために一定期間仕事を離れる必要が生じた場合、サバティカル休暇があれば、介護に専念できます。
サバティカル休暇があることで、社員は「会社は自分の事情を理解してくれている」と感じ、職場への愛着や忠誠心も向上するでしょう。
4. サバティカル休暇のデメリット


サバティカル休暇にはメリットが多くありましたが、長期間の休暇に入ることで現場や本人の収入面などデメリットが生じる部分もあります。
4-1. 職場復帰時の適応が難しくなる
サバティカル休暇から復帰した際、職場環境や業務内容の変化に適応するのが難しくなる場合があります。
サバティカル休暇は長い場合だと1年ほどになることもあり、その間に職場内にはさまざまな変化が発生するでしょう。休暇中に業務内容やチーム構成が変わることで、以前と同じパフォーマンスを発揮するまでに時間がかかる可能性があります。
また、長期休暇によって昇進・昇給が遅れることもあるため、復帰後のフォロー体制が整っているかを確認することが大切です。
4-2. 収入が減少する場合が多い
多くの日本企業では、サバティカル休暇中に給与や手当が支給されないため、休暇期間中は収入が減少します。これはノーワークノーペイの原則に従ったものであるため、違法ではありません。
しかし、収入が減るということには変わりはなく、生活費やローンなどの支出がある場合、長期にわたって無収入で過ごすのは想像以上に大きな負担です。
従業員側は休暇の計画段階で十分な資金計画を立てておく必要があり、企業側はあらかじめ社員に給与や手当について伝えておくことが大切です。
4-3. 現場の人手不足や混乱が起きることがある
サバティカル休暇に入った従業員のポジションには、当然空きができます。人材が十分にそろっている場合はよいですが、人手不足の現場では業務が追いつかなくなる恐れがあります。
また、専門的な知識を持っている人や、替えがきかない立場の人などがサバティカル休暇に入ると、トラブルへの対応が遅れたり、現場が混乱したりする可能性も考えられます。
そうした事態にならないように、サバティカル休暇に入ることは関係部署に早めに伝えて備えておく必要があります。
また、サバティカル休暇中の連絡や緊急時の対応などはどのようにするか、この部分も決めておくと安心です。
5. サバティカル休暇の制度を導入する際の4つのポイント


サバティカル休暇の制度を導入する際のポイントは以下のとおりです。
- 取得しやすい環境を整える
- 給与・手当の有無を明確にする
- 復職後のサポート体制を整える
それぞれ、詳しく解説します。
5-1. 取得しやすい環境を整える
サバティカル休暇を円滑に取得できる環境を整えることは、制度導入の成功に欠かせません。
スウェーデンやフィンランドでは、休暇中の代員として失業者を雇う制度が整っていますが、日本では存在しないため企業側で対策が必要です。
具体的には、業務の分担や引継ぎ体制を整え、長期休暇による業務の滞りがないようなシステムを構築することが必要です。
環境整備により社員が安心して休暇を取得でき、企業としても業務の混乱を防止できます。
5-2. 給与・手当の有無を明確にする
日本では、サバティカル休暇中の給与支給は企業の裁量に任されています。無給とするケースが一般的ではあるものの、休暇の目的に応じて手当を支給する企業も少なくありません。
休暇目的に応じて給与支給の有無を決めたり、有給休暇と組み合わせたりして、社員の生活に支障が出ないよう工夫することも検討しましょう。
また、無給の場合でも社会保険の在籍継続が必要となります。そのため、保険料や住民税などの支払いに関する取り決めも社員に周知することが大切です。
5-3. 復職後のサポート体制を整える
休暇後にスムーズに業務復帰できるよう、復職者へのサポート体制を整えることも重要です。可能であれば、休暇前と同じ業務に復帰できるよう配慮しましょう。
復帰後のフォロー体制が整っていることで、社員も安心して休暇を取得でき、復職後もスムーズに業務に戻れます。
また、こうしたフォロー体制が整っていることを周知することも大切です。「休暇を取ったら復帰しにくくなるかも」という懸念からサバティカル休暇を取得する人がでなければ制度も形骸化してしまいます。
5-4. サバティカル休暇を導入する目的を決める
サバティカル休暇を導入する場合は、目的を決めておくとより有意義な休暇をとってもらいやすくなります。
たとえば
- ライフワークバランスを図る
- 業務に関係する分野の学習をして知識を深める
- さまざまな経験から新しい視点や考え方を身に着ける
などの目的が挙げられます。
企業側がどのような目的でサバティカル休暇を導入しているのか、従業員にも伝えることでサバティカル休暇がただの休みになってしまうリスクを減らせます。
ただし、サバティカル休暇中の行動を会社側が指定することはできません。あくまでも自由意志で過ごしてもらうものであるため、実際の行動は従業員の判断にゆだねる形になります。
6. サバティカル休暇のメリットとデメリットを理解して導入を検討しよう


ワークライフバランスの充実が重要視される中、サバティカル休暇は企業と社員の双方にメリットをもたらす素晴らしい制度です。
従業員は長期的な休暇を取得することでリフレッシュし、新しい知識や経験を積むことができます。休暇制度が整っている企業は、優秀な人材を惹きつけやすく、採用力の向上も期待できるでしょう。
従業員の成長を支えるためにも、サバティカル休暇の導入を積極的に検討し、働きやすい環境づくりを進めてみてはいかがでしょうか。
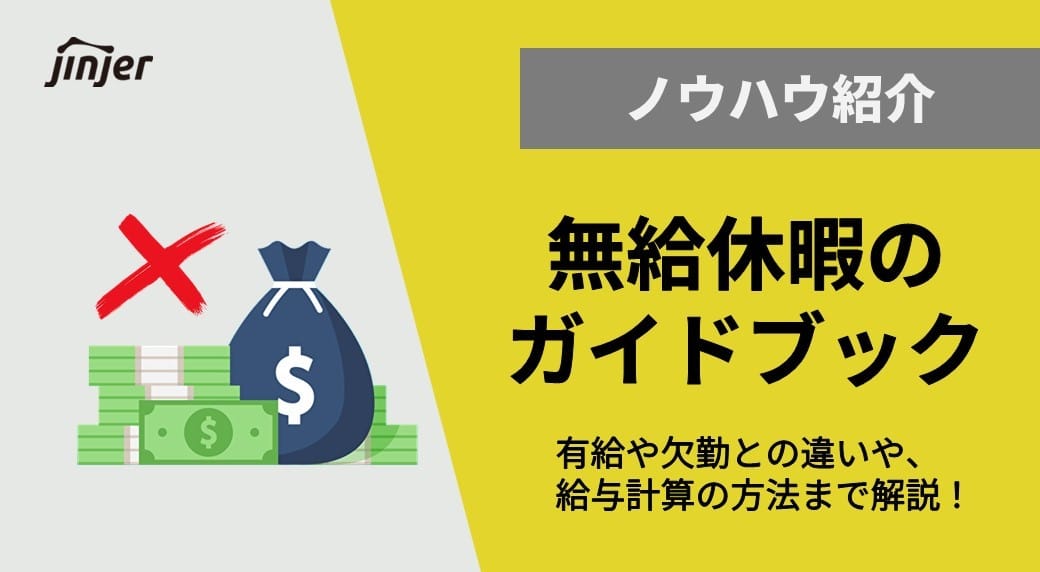
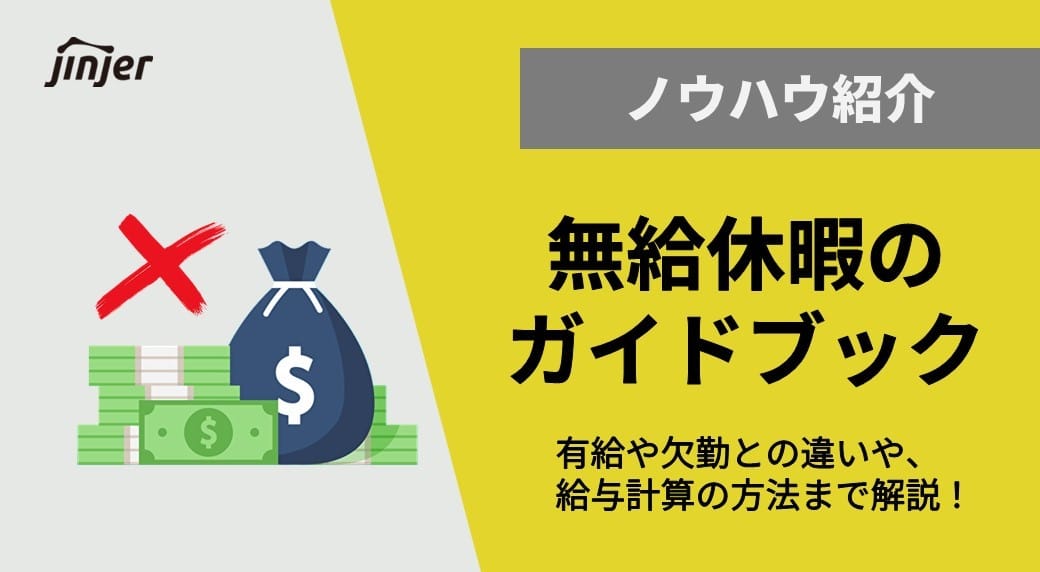
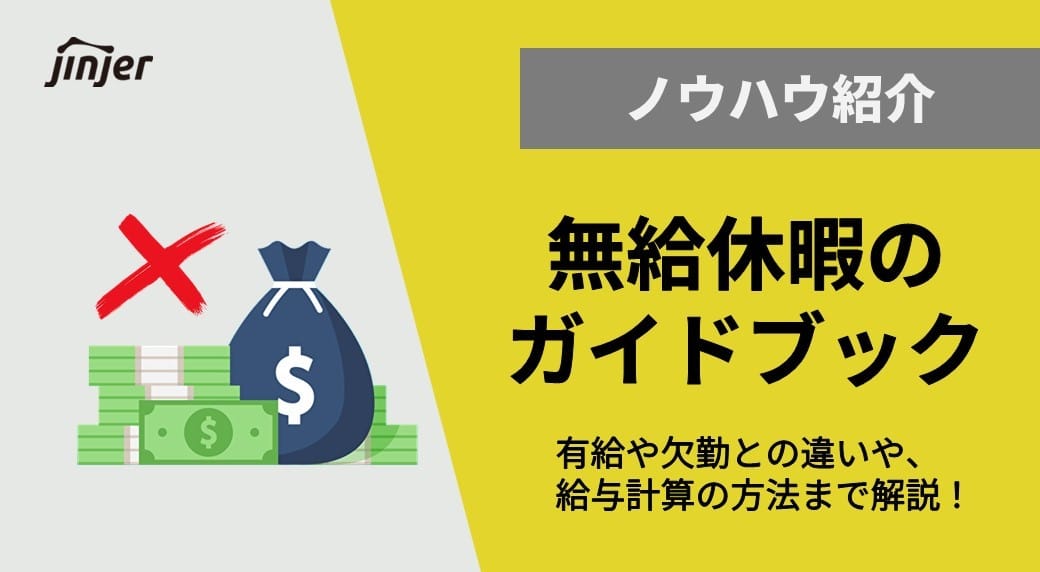
従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30





















