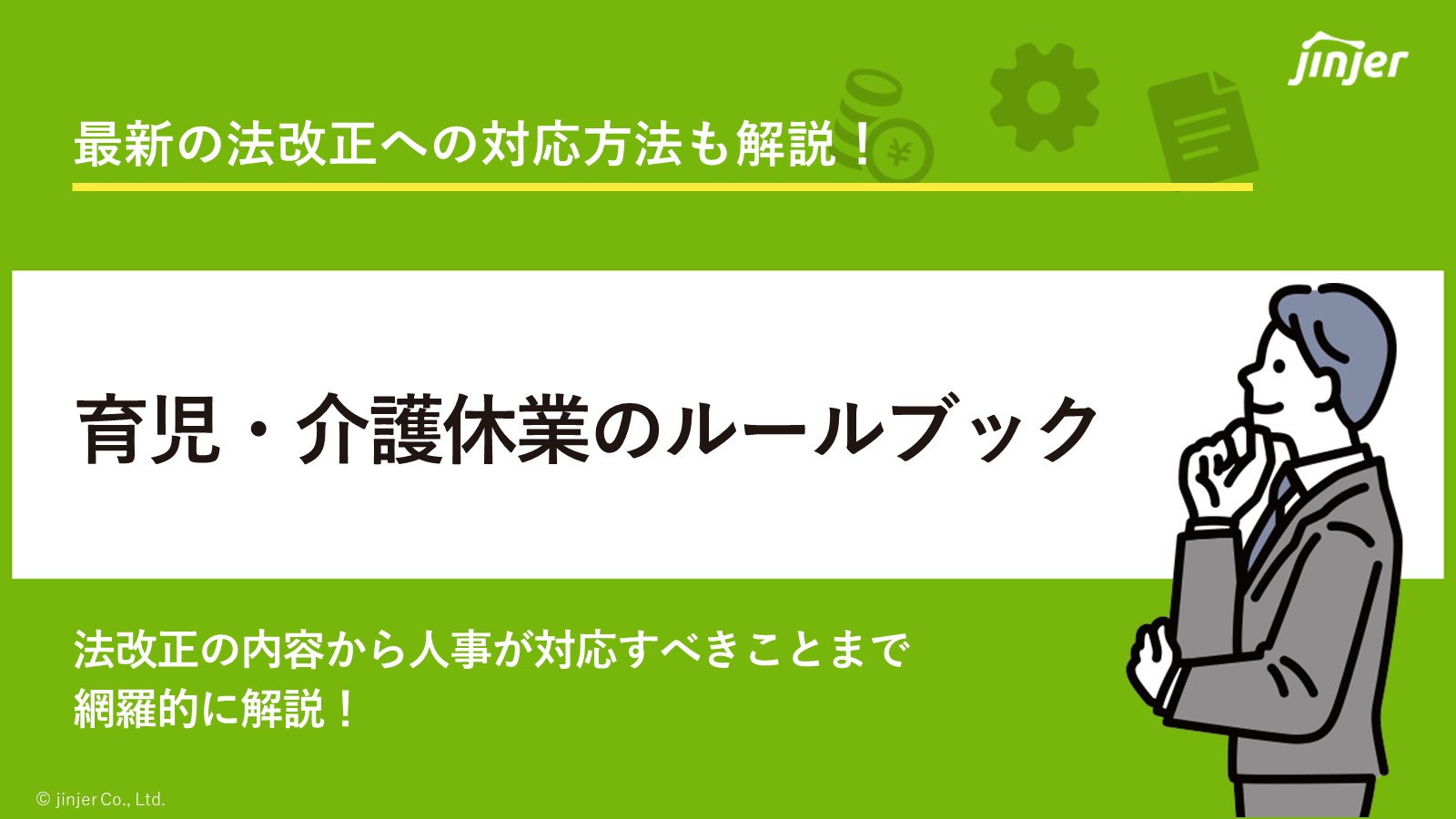産休中は社会保険料が免除される?期間と費用、申請手続き方法を解説

従業員が産休を取得することになった場合、申請を行うことで従業員と会社側の両方が社会保険の免除を受けることができます。従業員から産休の申し出があった際は、申請手続きに必要になる内容を確認しましょう。
本記事では産休で社会保険が免除される期間や、免除される金額の具体例、申請手続きと提出方法について解説します。
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与・保険料の計算方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
目次
1. 社会保険料とは


社会保険料とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の保険料を総称したものです。広義にはこれら全ての保険料を指しますが、狭義では健康保険、介護保険、厚生年金保険を主に指します。一般的に、雇用されている従業員はこれらの社会保険料を会社と折半で負担し、毎月の給与からこれらの社会保険料が控除される仕組みです。
1-1. 産休中は社会保険料が免除される
産前・産後休業を取得する際の社会保険料は、会社が所定の手続きを行うことで一定期間免除されます。
この従業員の産休により、社会保険料が免除される制度を「産前産後休業保険料免除制度」と言います。この制度を会社が日本年金機構へ申請することで、従業員だけでなく会社側も社会保険料が免除を受けられます。
従業員は社会保険免除期間中でも、保険料を納めた期間として扱われるため、将来受け取る年金額は変わりません。さらに社会保険料の免除期間中も被保険者資格に変更はありません。
1-2. 受取年金への影響
産休中に社会保険料が免除されることで、将来受け取る年金額に影響があるのではと心配する方もいるかもしれませんが、免除されている期間中も納付記録がしっかりと残ります。そのため、将来受け取れる年金が減額される心配はありません。
また、この期間中も被保険者資格は失効しないため、産休を取得する従業員は安心して子育てに専念することができます。
2. 産休による社会保険料免除期間はいつからいつまで?


従業員が産休に入る間、社会保険が免除されます。社会保険の免除が適用される期間は、従業員が産前休業を取得した日が含まれる月から、産後休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までとなります。
2-1. 産前産後休業の数え方
また産前産後休業の期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から産後56日のうち、妊娠・出産を理由に働かなかった日を指します。産後休業の56日は、出産日の翌日から数えます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します。
計算例
産前産後休業の数え方は以下の通りです。
出産予定日:6月21日
産前休業:5月11日~6月21日
産後休業:6月22日~8月16日
2-2. 社会保険料免除期間の数え方
社会保険料免除期間の数え方は以下の通りです。
出産予定日:6月21日
産前休業:5月11日~6月21日
産後休業期間:6月22日~8月16日
産後休業最終日の翌日:8月17日
社会保険免除期間:5月〜7月
数え方がわからない場合は産前と産後の期間を計算してくれるツールもあるので、そちらを活用するとよいでしょう。
3. 産休中に出産がずれたら社会保険料の免除期間はどうなる?


産休中の社会保険料免除期間について、出産がずれた場合の具体的な対応方法をご紹介します。出産予定日どおりに出産できない場合、産前休業と社会保険料の免除期間が変動することがあります。 詳しくみていきましょう。
3-1. 予定日より早く出産した場合
出産予定日より早く出産すると、産前休業の期間が短縮され、その結果、社会保険料の免除期間も変更されます。具体例を挙げて説明します。
例えば、出産予定日が5月15日である場合、通常の産前休業はその42日前から始まります。しかし、実際に出産日が5月1日になった場合、産前休業の期間は短縮されます。そのため、社会保険料免除の対象期間も短くなることに留意が必要です。
特に注意する点は産後休業の終了翌日の日付です。仮に出産が4月25日で、産後休業が7月中に終了したとします。その翌日が前月の6月30日となる場合、社会保険料の免除期間が短縮される可能性があります。このように、出産予定日より早く出産がずれる場合は、社会保険料免除期間に関して詳細を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
3-2. 予定日より遅く出産した場合
予定日より出産が遅れると、その分産前休業が延長され、社会保険料免除の対象期間も長くなります。例えば、予定日より1週間遅く出産した場合、その1週間分も産前休業として認められ、社会保険料免除の期間が延長されます。
具体的には、1週間遅れて出産すると、その1週間分の免除期間も追加されるため、合計で産前休業が12週間となる可能性があります。
また、この期間延長が月をまたいだ場合、例えば出産予定日が6月末で出産が7月初めにずれ込んだ場合、7月分の社会保険料も免除されることになります。このように、予定日より遅れて出産することで、予想以上の期間、社会保険料の負担が軽減されるメリットが生じます。手続きとしては、出産予定日の変更があった場合には、速やかに事業所や社保担当者に報告し、必要な書類を提出することが重要です。具体例を挙げると、出産予定日より10日遅く生まれ、かつ月をまたいだ場合、社会保険料免除の期間がさらに1ヶ月延びることになります。
3-3. 予定日からずれた場合は手続きが必要
出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、会社から年金事務所に届出を提出する必要があります。これは、産休による社会保険料免除の対象期間を正確に反映させるための手続きです。
予定日よりも早く産休に入った場合、社会保険料免除が開始される期間も前倒しされるべきです。その際、有給や欠勤を利用して産休に入ることも考慮に入れて、会社に保険料免除の対象期間を前倒ししてほしい旨を明確に伝えましょう。
既に保険料を納付している場合でも、変更届提出後に保険料調整が行われるため、手続きが完了すれば速やかに調整が反映されます。手順が複雑に感じるかもしれませんが、適切な手続きを踏めば、産休中の経済的負担を軽減する重要な助けとなることでしょう。
4. 産休により社会保険料が免除される費用
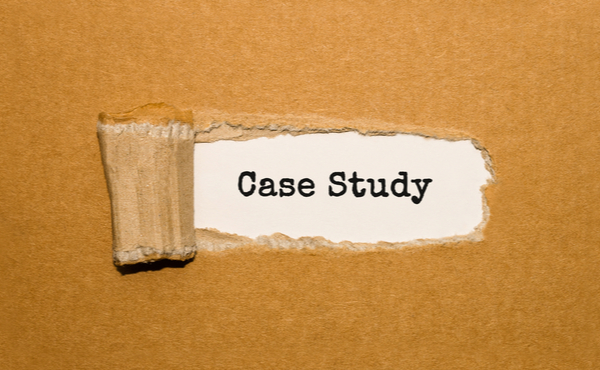
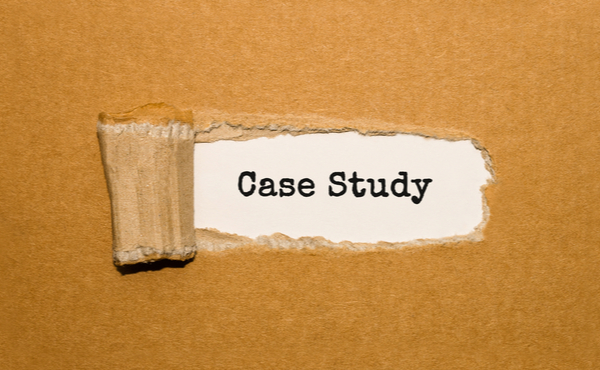
申請により免除となる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。
これらの社会保険料は従業員と会社が折半で負担しています。
ここで「産前産後休業保険料免除制度」を申請することで、具体的にいくら免除になるのかを解説します。[注1]
[注1]令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
4-1. 東京勤務年収350万円の従業員の場合
月額給与:約30万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:14,760円
免除期間:3ヶ月
免除額:44,280円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算
毎月の厚生年金保険料の負担額:27,450円
免除期間:3ヶ月
免除額:82,350円
※利率18.3%で計算
4-2. 東京勤務年収500万円の従業員の場合
月額給与:約41万円(通勤手当、残業手当など含む)
毎月の健康保険料の負担額:20,172円
免除期間:3ヶ月
免除額:60,516円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合の利率9.84%で計算
毎月の厚生年金保険料の負担額:37,515円
免除期間:3ヶ月
免除額:112,545円
※利率18.3%で計算
2つの例からわかるように、これだけの額が免除されます。
免除期間であっても保険料が納められた期間としてカウントされるので、将来受け取れる年金の額に変動はありません。
関連記事:産休を取得した従業員の給与計算の方法は?ルールや注意点を解説
5. 産休中の社会保険免除の申請手続きや提出方法


それでは実際に会社が対応すべき産休中の社会保険免除の申請手続きの手順や必要書類、その提出方法を解説します。
5-1. 申請手続きを行う流れ
まずは従業員の出産予定日を確認し、産前産後休業期間を計算します。
この際、従業員の出産予定日が変更になった際には、再度産前産後休業期間計算をします。
次に産前産後休業取得者申出書を記載します。
産前産後休業取得者申出書は日本年金機構のホームページよりダウンロードができます。
産前産後休業取得者申出書を記載後、年金事務所へ提出します。
提出先は管轄の事務センターで、電子申請・郵送・窓口持参(年金事務所のみ)などの提出方法があります。
5-2. 申請手続きに必要な書類
産前産後休業保険料免除制度は、従業員から産休の申し出を受けた後に会社側が「産前産後休業取得者申出書」を記入し、日本年金機構へ提出して申請する必要があります。
この「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に日本年金機構へ提出します。
万が一、提出後に産前産後休業期間の変更や、産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
「産前産後休業取得者変更(終了)届」も日本年金機構のホームページよりダウンロードでき、提出方法は産前産後休業取得者申出書の際と同じです。参照:健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届|日本年金機構
6. 産休中の社会保険料免除における注意点


それでは申請手続きを行う際の注意点や知っておくと活用できるポイントを紹介します。
6-1. 社会保険料免除の申出タイミングは出産直後がおすすめ
産休中の社会保険料免除を受けるためには「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要です。
この書類には出産予定年月日、産前産後休業開始年月日、終了予定年月日を記載する欄が設けられており、正確な情報の提供が求められます。出産前にこの申出書を提出すると、実際の出産年月日と予定日が異なる可能性があり、その場合は再度変更届を提出しなければならないため、手続きが二度手間になることがあります。したがって、申請にかかる手間を少しでも減らしたい方は、出産後に正確な日付を記載して提出することをおすすめします。
出産直後のタイミングで申請することで手続きがスムーズになり、結果的に社会保険料免除の恩恵を確実に受けられるでしょう。
6-2. 2022年10月より社会保険料免除の取り扱いが変更されている
2022年10月より、産休中の社会保険料免除の取り扱いが大きく変更されました。それまでの制度では、月末の時点で育児休業を取得していれば、その月の社会保険料が免除されていました。しかし、この制度では、月末をまたがない場合に社会保険料が免除されないという不平等が生じていました。また、賞与についても、月末に休業を取得しているかどうかで免除額が大きく変わる問題がありました。
新しい制度では、月末条件に加えて以下の要件が追加されました。まず、同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していることが必要です。さらに、賞与に係る社会保険料については、1ヶ月を超える育児休業等を取得していることで初めて免除の対象となります。このため、賞与支払月の末日を含む連続した1ヶ月を「超える」育児休業が必要であり、ちょうど1ヶ月の育児休業では免除の対象にはならない点に注意が必要です。
7. 産休中の社会保険料免除に関するよくある質問


また正しく産休中の保険料を免除するために、よくある質問をまとめました。参考にして対応しましょう。
7-1. 社会保険料が免除されていないことが発覚した場合の対応は?
もし社会保険料が免除されていないことが発覚した場合、速やかに対応しましょう。
会社が「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を適切なタイミングで提出し忘れた場合、一時的に社会保険料が徴収されることがあります。この場合、事後的に調整を行うことで、最終的には対象期間の保険料の支払いが免除されます。
この場合正式な書類の再提出や訂正が必要です。この手続きが完了すれば、過剰に支払った分の保険料は後日返金されるか、次回の支払いに充当されることになります。産前産後の期間は特に重要な時期ですので、早めの対処が必要です。
7-2. 産休中の社会保険料免除の申請を忘れていた場合の対応は?
産休中の社会保険料免除の申請を忘れていた場合、まず落ち着いて次の対応を行いましょう。
たとえ「産休申請書」を会社に提出し忘れ、会社が年金事務所に社会保険料免除の申請を行えなかった場合でも、産休中や産後でもまだ対応することは可能です。産休中または産休の終了日から1カ月以内に、「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出してください。
この書類を提出すれば、社会保険料の免除が認められます。また、この場合、一度徴収された社会保険料は後から調整されるます。
状況によっては一時的に社会保険料が引き落とされることがありますが、最終的に調整されるため、過度の心配は不要です。
7-3. 産休中にボーナスが支給された場合に社会保険料は徴収すべき?
産休中、給与は基本的に支払われないものの、ボーナスを受け取ることができる場合があります。
この場合、産休中の社会保険料免除の対象期間内にボーナスが支給された場合、そのボーナスも社会保険料免除の対象となります。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料は免除の対象となり、徴収されません。しかし、所得税については通常通り徴収されます。
したがって、産休中にボーナスが支給される場合でも、これらの社会保険料の負担はなくなり、安心して休暇を取ることができます。不明点や詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。
8. 産休による社会保険の免除は会社側にも適用される!忘れずに提出を


この記事では従業員から産休の申し出があった際に会社側で申請できる制度や申請方法について解説しました。
免除期間であっても、保健資格に変更はなく、納付されたものとして記録されます。
また、社会保険の免除は従業員だけでなく、会社にも適用されるので、メリットの多い制度です。
しかし「産前産後休業取得者申出書」の提出を忘れてしまった場合は、通常通り請求されますので、注意しましょう。
申請することで確実に社会保険料の免除を受けられるため、申し出を受けた後は速やかに申請できるように、普段から制度の仕組みや必要な対応について確認しておくことが大切です。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与・保険料の計算方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08