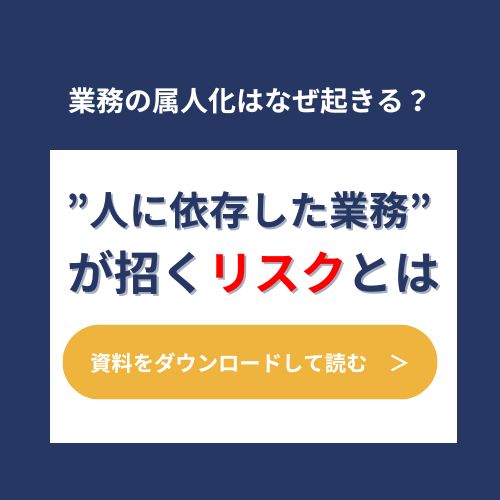年末調整の代行サービスとは?気になる費用とその内容を紹介
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.3.8
OHSUGI

年末調整の時期になると経理や人事部門の方は大変な時期と思います。
さて、そんな年末調整の問題を解決する「年末調整の代行サービス」は知っていますか。給与計算は1円でもミスしてはいけない非常に難しい業務です。
ぜひ、専門家に依頼をして、売上に貢献する業務に時間を費やしてはいかがでしょうか。
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説
「システム化で変わる年末調整の2つのポイント解説BOOK」を無料配布中!
「書類収集から計算、提出まで工数がかかりすぎる」「電子化の義務化に対応したい」などの理由から、年末調整の電子化をお考えではありませんか?
しかし、電子化といっても、これまでのやり方と異なるため具体的なイメージがつかないご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトではシステムを導入して電子化することによって、年末調整の業務がどのように変わり、工数削減ができるのかまとめた資料を無料で配布しております。
実際のシステムの画面をご確認いただけるため、電子化の具体的な方法についてイメージを付けたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 年末調整の代行サービスとは?

年末調整の代行サービスとは、年末調整で発生する実務の一部を第三者が代わりにおこなうサービスのことです。
まずは、年末調整の代行サービスがどのようなものかを把握するために、
①年末調整
②納税額の計算の仕組み
③年末調整の代行サービス
の順で確認をしていきましょう。
1-1. 年末調整とは?
毎月の給与計算では、源泉徴収税額は概算によって計算がおこなわれています。年末調整とはその不一致を精算するために、年間の源泉所得税を正しく計算しなおす手続きのことです。
年末調整で発生した差額は、後日の給与で源泉所得税を追加徴収又は還付して調整をします。
関連記事:年末調整とは?その必要性や基本的な書き方について解説
1-2. 納税額はどうやって決めているの?
年間の納税額は、1月1日から12月31日までの1年間に会社から支給された給与収入から各種の所得控除額を差し引き計算されます。
その差し引かれた所得金額に、所得の水準で適用される所得税法に決められた税率を乗じて、年間の所得税が計算されます。
毎月の給与支給額から引かれる源泉所得税額には、「生命保険料控除」「地震保険料」「住宅ローン控除」などの年末調整で控除される金額について考慮されていません。考慮されているのは、扶養控除くらいです。
そのため、年末に年末調整で年間の給与収入に対する所得税を改めて計算し、差額がある場合に最後の給与で調整する必要があります。
会社が年末調整をすることで、税務署へ納めた所得税の金額が払い過ぎていた場合には還付されることになります。
逆に、納付した所得税が不足している場合は、追加で徴収されるという流れです。
このように、年間の源泉所得税の納税が完了するという仕組みになっています。この手続きは会社の義務となっており、源泉徴収義務と呼ばれています。
1-3. 年末調整の代行サービス
年末調整と年間の所得税を計算するイメージをご説明しました。
実際に年末調整の手続きや給与計算を正しくおこなうためには、次の知識が必要になります。
- 源泉所得税(所得税法)
- 年末調整(所得税法)
- 住民税(地方税法)
- 社会保険(健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法など)
- 雇用保険(労働保険など)
会社は、従業員に対して給与の支払義務があり、円単位であろうと間違うことは許されません。
しかし、スタートアップの会社や新人の人事・経理担当者では十分な知識を有していない可能性があり、誤りが発生する可能性があります。
そこで、そのような会社に対して、年末調整や給与計算の代行サービスを提供している会社があります。
代行サービスとは、税理士や社労士といった有資格者や経理代行サービスなどの会社が、アウトソーシングを受け、他の会社の給与計算や年末調整の業務を一括して引き受けるサービスです。
アウトソーシングした場合には、年末調整という専門的な知識が必要な業務を、人事部や経理部から切り離すことが可能です。
そのため、12月の繁忙期に経理部や人事部の業務負担を軽減させることができるので、多くの企業で活用されているサービスとなっています。
2. 年末調整の手続きをかわりにおこなってもらうサービス

年末調整の代行サービスは、主に税理士事務所、社労士事務所や経理代行サービス会社に依頼することができます。
ここでは、3つの年末調整代行サービスのメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。
2-1. 税理士事務所に依頼する場合のメリット・デメリット
税理士事務所に年末調整の代行サービスを依頼するメリットは何といっても、税法に強いので、年末調整を適切に計算することができます。後日、税務調査があった場合でも、必要なサポートを受けることができるでしょう。
また、所得税が節税となるような、アドバイスをもらえるかもしれません。
デメリットは、比較的顧問料が高いことがあるようです。ただし、顧問料以上に節税となるアドバイスをしてもらえる可能性があるので、自社の業種にあった税理士事務所をよく検討することが大切です。
税理士試験は約10科目の税金や会計の試験のうち、5試験に受かれば税理士登録が可能です。
医者で内科と外科があるように、税理士も個人所得税が得意な税理士と、法人税が得意な税理士がいることを認識しておき、自分の会社や業務に見合った税理士に依頼するように心がけましょう。
関連記事:年末調整を税理士に依頼すべき3つの理由や依頼する方法
2-2. 社労士事務所に依頼する場合のメリット・デメリット
社労士事務所に給与計算を依頼している場合に、年末調整も依頼する場合があると思います。
メリットは、補助金や助成金の知識が豊富で顧問料以上のノウハウを教えてくれるかもしれません。
また、近年、残業規制や有給休暇の消化等で労務の規制が厳しくなっているため、そちらのサポートもしてくれるでしょう。
デメリットは、原則的として税理士法で年末調整は税理士の専門業務とされている点です。社労士事務所と税理士事務所が協力している場合は問題ないため、念のため確認しましょう。
税務調査でミスが判明した際に社労士のみに依頼している場合は、問題となりかねません。
2-3. 経理代行サービス会社に依頼する場合のメリット・デメリット
経理代行サービスに依頼する場合のメリットは、コストが安いことです。人数が少ないスタートアップの会社や、アルバイトやパートが多い会社など、計算ボリュームが比較的少ない場合には、費用対効果が高くなるかもしれません。
デメリットとしては、税務調査等でミスが指摘された際に対応が難しいことがあるでしょう。
また、節税となるアドバイスや助成金等のコンサルを受けることは難しいかもしれません。それぞれ、メリットとデメリットを比較検討し、自社のニーズにあった会社を選択しましょう。
これらの方法以外にも、年末調整の電子化をおこなうことで、必要な書類の提出依頼と回収・計算をすることができるものもあります。外注でおこなう場合は外部とのやり取りに時間がかかる場合もあるため、年末調整をラクにおこないたい方は電子化をするのもひとつの手段です。
当サイトでは、紙でおこなう年末調整から電子化との違いまでをわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。システム化した際の年末調整業務についてイメージをつけたい方は、こちらから「3分でわかる!システム化で変わる年末調整」をダウンロードして、比較検討にお役立てください。
関連記事:年末調整の電子化はここまで進んでいる!気になる手続きの方法
3. 年末調整の代行サービスの費用

年末調整の代行サービスを利用しようと考えた際に気になるのがコストのことです。
ここでは、年末調整の代行サービスの費用相場について解説します。導入を検討する際に、目安としてご参考下さい。
3-1. 年末調整の代行サービスの費用
年末調整の代行サービスの費用は大きくわけて、基本料金と1人あたりの追加料金があります。
多くの代行サービスのホームページは次のような料金体系です。
(具体例:1名~5名の場合)
基本料金(目安) 8,800円~11,000円/回
1人あたりの追加料金(目安) 1,650円~2,200円/1人
つまり、5人の会社の場合は17,050円~22,000円となります。
裏技としては、1人あたりの追加料金となっているので、計算が簡単な103万円以下のパートやアルバイトは自社で計算したほうがいいでしょう。
逆に、難しい外国人駐在員や住宅ローン控除のある正社員のみを外部にアウトソーシングすることにより、費用対効果が最大になると思います。
3-2. 年末調整に付随するサービス費用
年末調整に関連する業務として、会社がしなければならない業務は次のようなものがあります。
- 給与支払報告書(住民税の計算のために、それぞれ従業員の市区町村へ提出するもの)
- 法定調書合計表(税務署に会社の源泉所得税の支払いの概要を表す資料)
こちらは年末調整で、会社の従業員の年間給与支払金額、源泉所得税額を確定させることにより、付随して簡単に作成することができます。
年末調整のデータによって作成するため、年末調整をアウトソーシングした場合には、その依頼した会社にオプションとして追加で依頼するしかないです。
あらかじめ予算等に含めて考えましょう。
多くの代行サービスのホームページでは、そのオプションの顧問料は次のような料金体系です。
- 法定調書合計表作成 (目安)11,000円~16,500円/件 (税務署へ提出)
- 給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 1市町村(目安)1,100円~2,750円/件
つまり、5人の会社の場合で、従業員が別々の市区町村に住んでいる場合は次の計算式となります。
- 法定調書合計表 11,000円~16,500円
- 給与支払報告書 5,500円~13,750円
- 合計(①+②) 16,500円~30,250円
新規で経理の方を雇った場合や新入社員に依頼する場合は、月額20万円前後はかかることが考えられます。
そのため、従業員数の多い会社が、年末調整とその付随業務をアウトソーシングしても10万円前後となる場合が多く、メリットがあると言えます。
また、クラウド給与計算ソフトなどへのデータ入力が済んでいることや同じシステムを使用していることを条件に、年末調整の代行サービスを値引きしてくれるケースもあります。
4. 年末調整の代行サービスの内容

最後に年末調整の代行サービスをする場合の具体的な流れをみていきましょう。
ここでは、代行サービスを利用するにあたって準備が必要となる書類の種類、実際のサービスの流れについて詳しく解説します。
4-1. 年末調整で必要となる資料
代行サービスで、必要となる資料は次の資料です。
外部にアウトソーシングする場合には、従業員から取りまとめたものを郵送する流れとなることが多いです。
- 「扶養控除等(異動)申告書」
- 「給与所得者の保険料控除の申告」とその生命保険料控除証明書などの添付書類
- 「給与所得等に対する源泉徴収簿又は給与台帳」
- 「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
2020年から「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となりました。 - 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「その借入金の年末残高等証明書(残高証明書)」
これらの資料を準備して郵送すれば、後はすべて手続きをしてくれることが多いです。
4-2. 年末調整の代行サービス
主な年末調整の代行サービスは次の流れでおこなわれます。
- 年末調整の資料の内容や証明書のチェック後、各種控除金額の計算
- 源泉所得税の年間の税額計算、12月最終給与への過不足税額の情報を通知
- 源泉徴収票の発行
資料を従業員から取りまとめて郵送すれば、基本はすべて計算をしてくれます。
そして、過不足税額を12月給与へ反映させ、源泉徴収票を本人に渡せば完了します。
代行サービスは時間が節約できる上、正しく計算してもらえるので、メリットが大きいと言えるでしょう。
また、代行サービス会社によっては次の業務もおこなってくれるようです。ぜひ、契約する際に確認をしてみましょう。
- 会社の従業員への年末調整の説明・資料依頼文書の作成やレビュー
- 間違いがあった資料や提出されていないもののリストアップ
- 法定調書合計表の作成や提出(電子申告など)
- 給与支払報告書の作成と各従業員の市区町村へ提出(電子申告など)
多くの場合は、オプション契約となる可能性があります。
その場合は、自社でやるのがいいか、依頼するほうがいいかを判断して決めましょう。
5. 年末調整代行サービスは業務効率化に加え採用コストも抑えられる

年末調整の代行サービスとは、所得税や社会保険の専門的な知識を必要とする年末調整の計算手続きをほとんど全てやってくれる、経理の方にとっては夢のようなサービスです。
また費用も新規で正社員を採用する場合や、新卒社員に依頼するよりも、割安となる場合が多いです。
税理士系、社労士系、代行サービス会社などいくつか種類があるため、自社に合いそうな会社に見積りを出してもらい、実際に面談などをして、比較検討することが大切です。
「システム化で変わる年末調整の2つのポイント解説BOOK」を無料配布中!
「書類収集から計算、提出まで工数がかかりすぎる」「電子化の義務化に対応したい」などの理由から、年末調整の電子化をお考えではありませんか?
しかし、電子化といっても、これまでのやり方と異なるため具体的なイメージがつかないご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトではシステムを導入して電子化することによって、年末調整の業務がどのように変わり、工数削減ができるのかまとめた資料を無料で配布しております。
実際のシステムの画面をご確認いただけるため、電子化の具体的な方法についてイメージを付けたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08