年末調整に必要な書類は?種類や入手方法を解説
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.1.14
OHSUGI

年末調整には複雑な業務が多く、提出先も税務署と市区町村で分かれており、慣れている人でも業務負担が増えてしまいます。
また、年末調整に関係する書類はどれも税額の計算上必要となる大切な書類であるため、内容を理解していない場合やそろっていない場合はさらに時間がかかってしまうでしょう。このような事態を防ぐためには、早い段階からの準備が必要となってきます。
そこで今回は、年末調整に必要な書類や書き方、年末調整に関する書類を手に入れる方法まで、年末調整担当者側の視点から詳しく解説していきます。
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整に必要な書類

年末調整に必要な書類というのは、従業員が会社に提出するものと会社が税務署などに提出するものに分かれています。
担当者は、従業員が提出する書類に不備がないか、足りないものはないかを確認し、その後税務署などに提出する書類を作成しなければならないので、すべての必要書類を把握しておく必要があります。
ここでは、年末調整に必要な書類について解説していくので、すでに知っているという方も確認しておきましょう。
1-1.従業員が会社に提出する書類
従業員が会社に提出する書類は、以下の5種類になります。
- 保険料控除申告書と控除証明書
- 扶養控除等(異動) 申告書
- 配偶者控除等申告書
- 源泉徴収票等の法定調書合計表(対象者)
- 住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書(対象者)
ここでは、それぞれの書類について解説します。
保険料控除申告書と控除証明書
給与所得者の保険料控除申告書は、地震保険料や生命保険料などの各種保険料を支払っている際に保険料控除を受けられる申告書のことです。そのため、支払ってある保険料の金額や、保険会社名等が記載してある、[給与所得者の保険料控除申告書]が必要となります。
また、保険料を支払っていることを証明するための控除証明書なども必要なので、申告書と併せて提出してもらいましょう。
| 生命保険や地震保険料の支払い | 控除証明書 |
| 小規模企業共済等掛金の支払い | 掛金払込証明書 |
| 社会保険料 | 証明書もしくは領収書 |
これらの証明書がないと支払いが証明されないので、申告書の内容が証明書に裏付けされているかをしっかり確認してください。
▼社会保険控除についてはこちら
年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険の種類まとめ
扶養控除等(異動) 申告書
給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書は、扶養控除などの諸控除を受けるために必要な書類です。
年末調整では、扶養している家族の人数によって控除額が異なります。
そのため、扶養している配偶者や親族の名前と生年月日、マイナンバーなどの情報が記載してある[給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書]が必要になります。
配偶者控除等申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要な申告書です。
控除額を決定するには、給与所得者の配偶者に関する情報が必要になるため、配偶者の名前や生年月日、マイナンバーやその年の所得などの情報を記載しなければなりません。そのため、配偶者がいる従業員には「配偶者控除等申告書」も必ず提出してもらいましょう。
関連記事:年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント
源泉徴収票等の法定調書合計表(対象者)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、1年間の給与額の合計や、その給与から徴収した所得税額、税理士や弁護士などの外部へ支払いをした年間報酬額や、その報酬から徴収した所得税額等が記載されている書類です。
これは、翌年1月31日までに作成をして、提出をする必要がありますが、対象者以外は提出をしなくていいので事前に確認しておきましょう。
住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書(対象者)
住宅借入金等特別控除申告書は、マイホーム取得の際に住宅ローンを利用した人が「住宅借入金等特別控除」もしくは「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けるために必要となる申告書です。この申告書を提出すれば、従業員は住宅ローンの年末残高合計額を基に計算した金額を、所得税額から控除することが可能です。
住宅借入金等特別控除申告書には、下記の添付書類も必要になります。
- 住宅金融支援機構が発行した融資額残高証明書
- 住宅ローンをおこなっている金融機関が発行した年末残高等証明書
ただし、特別控除を受けられるのは2年目からで、控除1年目には適用できません。控除1年目の場合は確定申告が必要なので、従業員への周知を徹底しましょう。
1-2.会社が税務署に提出する書類
会社が税務署などに提出する書類は、源泉徴収票と支払調書、法定調書合計表の3種類です。
ただし、源泉徴収票や支払調書には種類があるので、対象となっている従業員のものは確実に提出しなければなりません。
ここでは、書類の種類と概要を解説していくので、間違えないようにチェックしておきましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は、会社の役員やその従業員などに、年間支払い金額を個々にまとめた帳票です。
提出が必要な源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の2種類になります。
給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、個々に給与や賞与などの年間金額や、社会保険料控除などの所得控除の金額情報を記載してある徴収票です。年末調整で1年間の支払いが、会社役員であれば150万円を超える役員の分、従業員であれば500万円を超える従業員の分を提出します。
退職所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票は、その年に退職金の支払いがあり、退職金や退職所得控除などの情報を記載した徴収票です。一般的には、法人企業の役員に対して支払った退職金のあった際に提出します。
▼退職者がいる場合はこちらも併せてチェック
年末調整で退職者がやるべき手続きを分かりやすく解説
支払調書
支払調書は、税理士や会計士の報酬等、組織の外部に支払ったとされる報酬等の記載されている調書です。
ある一定の支払額を超える場合には、支払調書を法定調書合計表などに添付をして、提出をしなければいけません。
支払調書は一定金額を超える場合に提出をする必要がありますが、複数種類が存在するため、漏れや間違いがないように種類を把握しておきましょう。
不動産の使用料等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書は、地代や家賃など、不動産の賃借料を支払っているときに作成する必要のある支払調書のことをいいます。
借主や、借りている不動産の情報、支払金額などを記入する調書で、家賃は1年間の使用料の支払いが15万円を超えており、尚且つ個人に支払っている際に提出をします。
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書は、弁護士や会計士など、源泉徴収の対象となり得る報酬や金額の支払いをした場合に作成する必要のある支払調書です。1年間の報酬金額や、源泉徴収税の金額を記入して提出します。一般的には、1年間に5万円を超える金額が提出範囲とされています。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は、不動産に関するあっせん手数料を支払った際に作成する支払調書です。法人あるいは一定の不動産業者である個人に対して、1年間の支払金額が15万円を超えるときに提出が必要になります。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書は、不動産を購入した際に作成する支払調書です。購入した不動産の情報や、金額等を記入していきます。法人あるいは一定の不動産業者である個人に対して、1年間の支払金額が100万円を超えるときに提出をする調書です。
法定調書合計表
法定調書合計表は、従業員に発行した源泉徴収票や支払調書について、それぞれの支払い額や源泉徴収税、人員数の合計と総数を記載する書類です。
徴収票は「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」で、支払調書は下記の5点になります。
- 報酬、料⾦、契約及び賞⾦の⽀払調書
- 不動産の使⽤料等の⽀払調書
- 不動産等の譲受けの対価の⽀払調書
- 不動産等の売買⼜は貸付けのあっせん⼿数料の⽀払調書
全ての合計、総数を記載しなければならないので、漏れがないように注意しましょう。
「」「不動産の使⽤料等の⽀払調書」「不動産等の譲受けの対価の⽀払調書」「不動産等の売買⼜は貸付けのあっせん⼿数料の⽀払調書」などについて、それぞれ人員数や支払い額、源泉徴収税の各合計、総数を記載します。
1-3.会社が市区町村に提出する書類
会社が市区町村に提出するのは、給与支払報告書です。
給与支払報告書には、総括表や個人別明細書の2種類がありますが、どちらも必要となるのでしっかり準備しておきましょう。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(総括表)は、市区町村ごとに作成をするもので、給与支払報告書の表紙のような報告書のことをいいます。給与を支払う会社名やその所在地などの情報、会社の全ての従業員のうちの何人が、その市区町村に居住しているのかという情報を記入していきます。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)は、給与や賞与などの年間金額や、社会保険料控除などの所得控除額やその情報等の記載されている報告書のことです。一般的に、記載内容は源泉徴収票と同様のものになります。
書類の種類が多いため、年末調整に抜け漏れがないか確認するのに時間がかかっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトではそのような方に向けて、必要な手続きごとに必要な書類を一覧で確認できるガイドブックを無料でお配りしています。抜け漏れなく年末調整業務をおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、業務にお役立てください。
2. 年末調整に必要な書類の書き方
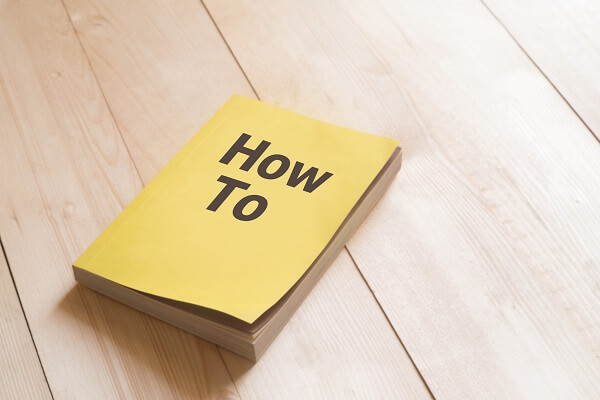
年末調整に関係する書類には幾つかの種類がありますが、書類ごとに控除となる対象が定められており、それぞれにおいて控除額を確定していく必要があります。
控除額の確定にはそれぞれの税制も関わってくるので、新たな税制改正点に注目をしながら、年末調整に必要な書類の中で特に重要なポイントに絞って確認しておきましょう。
2-1. 地震保険料控除
地震保険料控除の書き方は、保険会社の名前や保険の種類を記載し、地震保険料と、旧長期損害保険料の金額を明記し、控除額として合計額を出します。
2-2. 生命保険料控除
生命保険料控除の書き方は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分で計算をしていきます。
まず、支払いを済ませている保険に関して、[保険会社・保険の種類など]欄を、保険料控除証明書をもとに、記載していきます。それぞれの区分ごとに控除金額を計算し、最後にそれらを合算した金額が、保険料控除の金額となります。
2-3. 社会保険料控除
社会保険料控除の書き方は、給与より天引きされている社会保険料を明記する必要はなく、代わりに扶養配偶者や親族の分を支払っているとき等の金額を記載します。それらの全額が、控除の対象です。
関連記事:年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険の種類まとめ
2-4. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除には、支払ったそれぞれの保険料を記載します。確定拠出年金の掛金が給与より控除されているケースなど、企業で把握できている分は、記載する必要はありません。
3. 電子データ提出が可能な書類

年末調整に関連する書類のうち、以下の書類は電子データで提出が可能です。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
無償アプリ「年調ソフト」を使用することで、紙ベースで提出するよりも業務負担を軽減することが可能です。また、税務署長からの事前承認も不要になったため、デジタル化の一環としてぜひ電子データによる提出を進めていきましょう。
4. ダウンロードできる年末調整書類について

年末調整に必要な書類は、法定調書とともに、10月下旬より11月上旬にそれぞれの税務署より企業に向けて郵送されます。また、税務署から書類が届く前に準備したい場合は、国税庁の公式ホームページからダウンロードをすることも可能です。
ダウンロードできる書類は、以下の5種類です。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 源泉徴収票
他の書類は、年末調整ソフトに会社名や従業員の情報を入力し、印刷をしたのち配布をおこなうことができます。
このように、年末調整に必要とされる書類はすべて事前に入手することができるので、それにおける準備を万全にし、スムーズに取り組んでいきましょう。
関連記事:年末調整の必要書類一覧|記載する内容や書類の集め方を徹底解説
5. 2024年からの年末調整でで変更となる項目

2024年の年末調整では、保険料控除申告書の記載事項やと扶養親族の適用要件に大きな変更がなされています。この2点について十分に把握して正しく年末調整をおこないましょう。
5-1. 「保険料控除申告書」の 記載事項について
令和6年10月1日以後に「保険料控除申告書」を提出する場合、記載事項が簡素化される予定となっています。
簡素化されるのは、以下の記載事項です。
- 生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者との続柄
- 申告者が生計を一にする配偶者とその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合のこれらの者の申告者との続柄
変更に伴い、申告書の様式も変更になると考えられるので、事前に国税庁のホームページで確認しておきましょう。
5-2. 「扶養控除等申告書」の提出について
令和7年1月1日以後に支払いを受ける給与等について提出する「給与所得者の扶養控除申告書等申告書」では、前年の申告内容と変更がない場合、また前年度に提出した「従たる給与についての扶養控除等申告書」で記載した事項に異動がない場合場合は「変更がない」という記載のみで提出できるようになります。
これは、源泉徴収手続きを簡略化することを目的とした改正で、納税者の利便性を向上させることが狙いです。この簡略化した申告書は「簡易な申告書」となります。
5-3. 国外居住親族への「送金関係書類」の提出書類について
電子決済手段の移転にともない、国外居住親族(非居住者となる親族)への「送金関係書類」には、支払を証明する書類が追加されます。
具体的には、下記のような書類が必要となります。
- 金融機関が発行した書類もしくは写しで、金融機関の為替取引により非居住者となる親族に支払をしたことを証明する書類
- クレジットカード会社が発行した書類もしくは写しで、非居住者の親族が、そのクレジットカードを使って商品を購入した場合、その代金の金銭を従業員から受領もしくは受領する予定となっていることを証明する書類
- 電子決済取手段等取引業者の書類もしくは写しで、電子決済手段の移転によって非居住者となる親族に支払したことを明らかにする書類
参考URL:令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁
5-4. 住宅ローン控除適用に係る手続きについて
住宅ローン控除適用に関して、令和5年1月1日以降に住宅を取得した場合、金融機関から発行される年末残高証明書ではなく、年末残高調書を提出する「調書方式」に変更とになりました。
調書方式というのは、金融機関から税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出してもらい、国税局から住宅ローンの年末残高情報を提供してもらうという方式です。
ただし、方式変更は統一しておこなわれるわけでなく、各金融機関によって移行時期が異なります。金融機関側の負担を軽減するため、システム改修にすぐに対応できない場合は経過措置が設けられているので、事前に確認しておきましょう。
6. 早期の段階より入念な準備を

年末調整には、さまざまな書類やデータが必要となりますし、提出してもらう書類や提出しなければならない書類もたくさんあるので漏れやミスがないように注意しなければなりません。
また、法改正により適用範囲や控除率が変更になる可能性もあり、例年よりも業務負担が増えてしまうケースも考えられます。
年末調整は必ずおこなう必要のある業務であるため、早い段階から準備をして計画的に取り組んでおくようにしましょう。
電子データ提出を活用すれば業務負担を減らせるため、従業員数が多かったり業務負担が大きい場合は、デジタル化を検討するのもおすすめです。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























