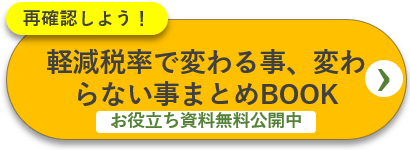軽減税率の導入による領収書の書き方の変化を解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2020.12.1
jinjer Blog 編集部
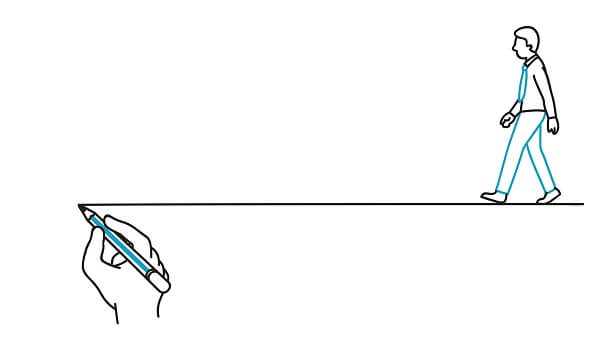
2019年10月1日から軽減税率が導入されたことによって、領収書の書き方も変わりました。
領収書を作成して渡す場合は、今まで記載していた合計金額や宛名などに加えて、軽減税率の対象品目やそれぞれの税率ごとの合計金額なども明記しなければなりません。
そこでこの記事では、軽減税率の導入による領収書の書き方の変化や、領収書を正しく作成するためのポイントについて紹介します。軽減税率に対応した領収書の書き方を知りたい方は、ぜひチェックしてください。
2019年10月に軽減税率制度が実施されました。
軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。
その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。
資料には、以下のようなことがまとめられています。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務
軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。
1. 軽減税率の導入による領収書の書き方の変化

軽減税率が導入される前の領収書には、購入された商品の金額とともに、領収者の名称や日付、品目や宛名などを記載するのが一般的でした。
軽減税率が導入された2019年10月以降は、状況に応じて追加で記載すべき項目があります。ここでは、軽減税率に対応した領収書の書き方を具体的に見ていきましょう。
1-1. 軽減税率の対象品目がわかるよう領収書に記載する
軽減税率の導入により、基本的には「区分記載請求書等保存方式」に従って領収書を作成することが求められるようになりました。この方式は、領収書だけではなく、請求書や納品書などにも適用されます。
区分記載請求書等保存方式で領収書を作成する場合は、軽減税率の対象となる品目と対象外の品目がわかるように記載しなければなりません。
たとえば、軽減税率の対象になる牛乳と、対象にならないワインが一緒に購入されたケースを考えてみましょう。この場合、領収書には、以下のように税率ごとに分けて記載するのが基本です。
| 項目 | 数量 | 単価 | 税抜金額 |
| 牛乳(※) | 5 | 200 | 1,000 |
| ワイン | 2 | 500 | 1,000 |
| 小計 | 2,000 | ||
| 合計金額 | 2,180 | ||
| 10%対象 | 1,100 | ||
| 8%対象 | 1,080 | ||
※は軽減税率対象品目
領収書には、合計金額だけではなく、軽減税率の対象となる商品と対象外の商品の税込合計金額もそれぞれ記載します。※印などを付け、軽減税率の対象商品を明記することも必要です。
この例の場合は、牛乳だけが軽減税率の対象商品ですので、項目欄の横に※印を付けています。※印の意味がわかるような説明書きも記載しておきましょう。領収書を受け取った側が理解できれば、※印以外の記号でも問題ありません。
その他、日付や領収者の名称、宛名なども従来どおりに記載します。軽減税率の対象となる商品を販売する場合は、上記の項目が記載された領収書のフォーマットを準備しておくと手間が省けます。
1-2. 手書きの領収書の場合も税率ごとに分けて記載する
手書きの領収書を渡す場合でも、税率ごとに分けて合計金額を記載する必要があります。
前述のような領収書のフォーマットをExcelなどで作成しておけば、税率ごとの合計金額を記載するのは比較的簡単ですが、市販の領収書には複数の税率を記載する欄がない場合もあるでしょう。
その場合は、領収書を2枚発行することでも対応できます。軽減税率の対象となる品目のみの領収書と、対象外の品目のみの領収書を2枚発行するのです。
多少の手間はかかりますが、今使っている領収書が残っている場合は有効といえるでしょう。
1-3. 軽減税率の対象品目を扱わない場合は税率ごとに分けて書く必要はない
軽減税率の対象品目をまったく扱わない場合や、逆に、軽減税率の対象品目しか扱わない場合は、それぞれの税率に分けて記載する必要はありません。
※印などで軽減税率の対象品目を明示することも不要です。税込価格をそのまま合計金額の欄に書きましょう。
ただし、8%の税率となる場合は、「すべての商品が軽減税率対象」などと但し書に記載しておくと、受け取る側に対して親切です。
関連記事:軽減税率の対象品目は?その線引きや気をつけるべきポイント
1-4. そもそも区分記載請求書等保存方式は義務ではない
そもそも、区分記載請求書等保存方式で領収書を作成することは、事業者側の義務ではありません。税率ごとに分けずに領収書を作成しても、ペナルティなどを受けるわけではないのです。
ただ、領収書を受け取る側は、税率ごとに分けて記載してほしいと感じるケースも多いでしょう。
軽減税率制度は複雑で、どの品目が対象になるのかわかりにくい場合も多いからです。領収書の正しい書き方を理解し、できる限り対応できるようにしておきましょう。
2. 軽減税率に対応した領収書を作成しよう!

2019年10月1日から2023年9月30日までは、基本的に区分記載請求書等保存方式にて領収書を作成しなければなりません。領収書を受け取る側にも配慮し、正しい領収書を作成しましょう。
また、2023年10月からは「インボイス方式」が導入される予定です。
インボイス方式においては、税率の区分記載の義務化、適格請求書発行事業者の名称や登録番号の記載など、区分記載請求書等保存方式よりも厳しい決まりが設けられています。
実施はまだ先ですが、基本的な領収書作成方法についてはしっかりと理解しておくことが大切です。
関連記事:軽減税率導入後の納品書ってどうやって書くの?わかりやすく解説
軽減税率はすべての企業が関係します!
2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。
また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。
「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。
資料では
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法
など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。
「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。
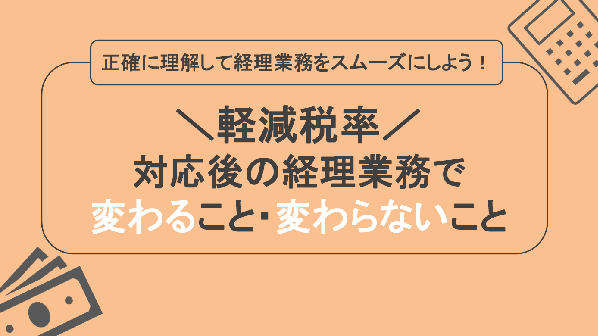
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04