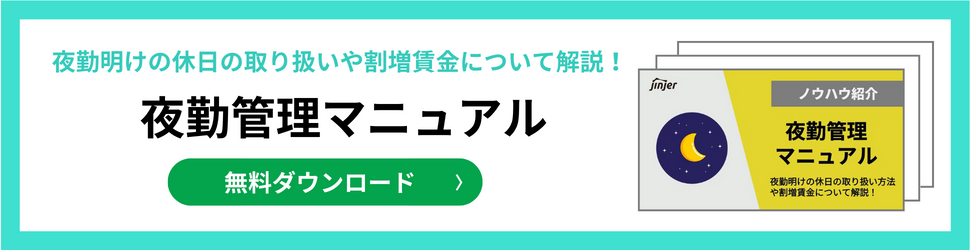夜勤明けは休みの日扱いになる?その仕組みを詳しく紹介
更新日: 2024.9.26
公開日: 2021.9.3
OHSUGI

医療関係や運送業など、夜勤が必要になる職種は数多く存在しています。このような職種の方やその使用者・管理者が気をつけなくてはいけないのが、「夜勤明けの休みは休日に含まれるのかどうか」というポイントです。
夜勤の際は労働時間が不規則になりやすいため、通常の休日とは考え方が異なってしまい、混乱してしまう人も多いでしょう。
この記事では、夜勤明けにおける休日の考え方について解説します。夜勤勤務者に適切な休日を与えて、法令を遵守したシフトの作成をおこないましょう。
「夜勤管理マニュアル」無料配布中!
労働基準法は基本的な内容で細かい運用方法の解説はないため、「夜勤明けの適切な休日のとらせ方は?」「夜勤明けから次の勤務はいつからしてよい?」など夜勤と休日の関係性と正しい管理の方法がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤と休日の取らせ方のルールについて、本記事の内容をまとめた資料を無料配布しております。例を挙げてわかりやすく解説しているので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 夜勤明けは休みの日扱いになるのか


さっそく、夜勤明けが休みの日扱いになるのかについて見ていきましょう。夜勤明けは基本的に休みの日扱いにはなりませんが、例外として休みの日として扱えるケースもあります。
まずは、それぞれのケースについて解説します。
1-1. 夜勤明けの休みは原則休日扱いにならない
大前提として、夜勤明けに休日を取らせる場合、夜勤明けの日は原則として休日扱いにはなりません。厚生労働省の通達では、休日について「午前0時~午後12時までの暦日」で与えるものとしています(昭和23年4月5日 基発535号)。
したがって、たとえ夜勤明けで次の勤務まで24時間空いていたとしても、休日を与えたことにならないため注意が必要です。
たとえば月曜日の午後8時に夜勤を開始し、火曜日の午前5時に勤務を終えたとしましょう。次回の出勤が水曜日の午前8時であるときは、火曜も水曜も「午前0時から午後12時までの休み」を取れていません。
したがって、次回の勤務まで27時間空いていても休日を与えたことにはならないのです。この場合、次に働かせることができるのは、木曜日の午前0時からです。
労働基準法に定められた、週に1日もしくは4週に4日の法定休日を満たすためには、夜勤明けの日とは別に休日を4日与えなくてはいけません。夜勤明けの日を法定休日に設定しても、法定休日を与えたことにはならないため、注意しましょう。
1-2. 夜勤明けが休みの日扱いになるケース
上記のように、夜勤明けの日は原則休みの日扱いにはなりません。ただし、例外として夜勤明けを休日として扱えるケースがあります。
それは、企業が三交代勤務を採用しているケースです。三交代勤務とは、1日24時間を8時間ずつに分け、3つのグループをローテーションする働き方のことです。
「日勤・夜勤」の二交代制ではなく、「日勤・準夜勤・夜勤」といったように3つのシフトが組まれるときは、三交代勤務に該当します。
三交代勤務のでは、夜勤明けから連続した24時間を休日として扱うことができます。そのため、この場合は夜勤明けを休日としても法律違反にはならないのです。ただしこれは特例なので、原則は0時~24時の暦日単位で休日を与えることが基本であると理解しておきましょう。
休日を取得させることは労働基準法にも定められたルールであるため、適切に与えることができるよう、しっかりと理解しておく必要があります。ここまでの解説で「文字だけだとイメージがつかない…」という方に向け、本記事の内容を図解でわかりやすく解説した資料を無料で配布しておりますので、夜勤の休日の取らせ方や夜勤の後に働かせてもよい日を正確に理解しておきたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2. 夜勤の考え方について

夜勤の仕組みについてより深く理解するために、ここからは夜勤の考え方についてもう少し詳しく見ていきましょう。
2-1. 夜勤の労働日数
夜勤のときは深夜0時をまたいで勤務することになるため、「勤務日が2日になるのか」という疑問を抱く人は多いかもしれません。この疑問に対し、労働基準法では以下のように規定しています。
「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
引用:改正労働基準法の施行について|厚生労働省
つまり、深夜0時をまたいで勤務したときは、始業を開始した日におこなった1回分の出勤としてカウントされるということになります。前日分と翌日分を分けて2日勤務したことにはならないため注意しましょう。
2-2. 夜勤の休憩時間
夜勤をおこなうときの休憩時間の考え方は、日勤のときと同様です。労働基準法34条では6時間を越えて8時間以内の勤務で45分以上、8時間を越える勤務で1時間以上の休憩を与えることを義務付けています。
夜勤でも、この法令を遵守して休憩を与えるようにしましょう。
関連記事:夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方
2-3. 夜勤明けの日に夜勤で出勤することは可能か
夜勤明けの次の勤務はいつからさせてもよいかを判断するには、翌日を休日とするのか労働日とするのかで変わります。
夜勤明けの次の日を休日としたいのならば、先述した通り午前0時から午後12時までまるまる1日の休みを与えなくては休日とならないため、勤務が可能になるのは夜勤明けの日の翌々日0時からとなります。
一方、労働基準法では、週に1回もしくは4週に1回の法定休日を与えれば問題ないとされているため、夜勤明けの次の勤務についての制限はありません。夜勤明けの日を労働日とする場合、たとえば、月曜日の午後8時から火曜日の午前5時まで勤務し、火曜の午後9時から勤務をスタートしても問題はありません。
夜勤の次の勤務に関する法の規定はなく、少なくとも週に1日は午前0時から午後12時までの法定休日を与えれば適法となります。ただし、無理なシフトは従業員の健康を損ない、最悪の場合労働災害を引き起こす可能性もあるため、十分な休息を取れるようにシフトを組むことが何よりも重要です。
2-4. 夜勤明けの日に日勤・準夜勤で出勤することは可能か
夜勤明けの日に日勤で勤務させることは、結論として法律上は可能です。ただし、従業員への負担が大変大きくなるため避けたほうがよいでしょう。
先述の通り、夜勤明けの次の勤務に関して規制する法律はないため、休日としないのであれば、法律上は夜勤明けの日に日勤や準夜勤をさせることは可能です。
しかし、使用者には「安全配慮義務」があります。これは労働契約法第5条に定められた使用者の責務で、労働者が身体や生命の安全を守りつつ労働ができるように配慮しなくてはならない義務です。夜勤明けの日に日勤、準夜勤をさせることは従業員にとって非常に負担が大きく、心身の健康を損なう可能性もあるため、安全配慮義務を順守しているとは言い切れないでしょう。
採用を強化し夜勤から日勤が発生してしまうような人手不足を是正するほか、勤務間インターバル制度を取り入れるなど、従業員の負担を減らせるようにしましょう。
2-5. 夜勤明け休みを有給処理することは可能か
夜勤明けの休日と同様で、有給休暇に関しても夜勤明けに付与することはできません。
労働基準法では、年次有給休暇を取得するのは1日単位で取得することが原則です。前章でも示したように、休日は「午前0時から午後12時までの休み」のことを指します。
たとえば、火曜日の午後7時に夜勤を開始し、水曜日の午前4時に勤務を終えた従業員に対して、水曜日に有給を付与することは「午前0時から午後12時までの休み」には該当しないため、有給を取得することはできません。
従業員が、夜勤明けの日に有給取得の申請をしてきた際には、誤って与えないよう注意しましょう。
3. 夜勤の割増賃金の計算方法


夜勤をおこなうときは、日勤と同様に一定の条件を満たせば割増賃金の対象となります。ここでは、夜勤をするときに押さえておきたい割増賃金について解説します。
本章では、主に夜勤の場合の割増賃金について取り上げていますが、休日出勤した場合も割増賃金が発生します。下記の記事では休日出勤した場合の割増賃金について解説しており、割増になる条件はもちろん、割増率の計算方法についても触れています。興味のある方はぜひご覧ください。
関連記事:休日出勤手当はもらえない場合も?条件や割増率の計算をわかりやすく解説
3-1. 法定外労働時間の割増賃金
労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間が限度に設定されています。この時間を超えて働かせるときは36協定の締結が必要になり、さらに25%の割増賃金が必要です。
夜勤でも、この割増賃金は適用されます。たとえ日をまたいでも、1回の勤務時間が8時間を超えると割増賃金の対象となるため、正確な給与計算を心がけましょう。
関連記事:深夜残業とは?今さら聞けない定義や計算方法を徹底解説
3-2. 深夜手当
深夜手当とは、22時から翌朝5時まで労働したとき、基礎賃金に25%の割増賃金が加算される手当のことです。夜勤では、該当の時間に労働した分について、この割増賃金が適用されます。加えて深夜労働と時間外労働の時間が重なったときは、「25%+25%=50%」の割増賃金を支払わなくてはいけません。
たとえば、14時~24時まで労働し、18時~19時で休憩を1時間取得した場合、勤務時間は8時間を超えているため、1時間分が時間労働になり、割増賃金が発生します。ただし、時間外労働が発生した23時~24時は深夜業の時間にあたるため、時間外労働と深夜労働に対する割増賃金の両方が発生し、割増率は50%となります。22~23時までは労働時間が8時間以内であるため、深夜労働に対する割増賃金のみが発生します。
3-3. 夜勤手当
夜勤手当とは、企業ごとに設けられた独自の制度です。
支給が義務付けられている賃金ではないため、企業の判断で支給するかどうかを決められます。
夜勤手当の支給がある企業では、夜勤をすると3,000~4,000円程度の手当を上乗せした賃金が支給されているようです。
3-4. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で決め、平均して労働時間が週40時間以内におさまれば、法定労働時間を越えて働かせてもよい制度です。
変形労働時間制では、所定労働時間(シフト)が8時間を超えている場合、法定労働時間ではなく所定労働時間を越えたところからが時間外労働(残業)となります。したがって、8時間を越えればすべて時間外労働(残業)になるというわけではないため、注意が必要です。
月単位で変形労働時間制を採用する場合、法定労働時間内で就業時間を定める必要があり、年単位では、1年間の変形労働時間制では、1ヶ月以上1年未満で労働時間を設定する必要があります。
4. 夜勤明け以外で休日を取らせるには
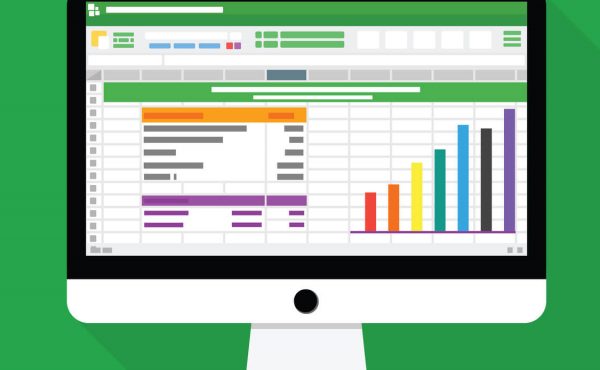
法令順守しつつ、夜勤以外で休日を取らせるにはどうしたらいいのでしょうか。労働基準法に抵触しないためにも、正しい休日の与え方を押さえておくことが大切です。
夜勤明け以外で休日を取らせるには、暦日単位で休みを取らせる必要があります。暦日単位の休みとは、午前0時から午後12時までの1日を通して休みを与えることです。
たとえば、月曜日の午後8時から火曜日の午前5時まで勤務したとき、休日の取り扱いは以下のように考えられます。
・休日と認められるケース
夜勤明けの火曜から水曜日一日を休みとし、木曜日の午前0時以降に出勤させる
・休日と認められないケース
夜勤明けの火曜を休みとし、水曜日中に出勤させる
特例を除き、夜勤明けから次の勤務まで24時間以上確保するだけでは、休日とはみなされません。必ず、夜勤明け+暦日単位の休みを与えることを意識してください。
この暦日単位の休みが週に1回もしくは4週に4回あれば、法令で定められた休日の要件は満たせます。ただし、夜勤明けは疲労が溜まりやすいため、十分な休息時間を与えることが大切です。
労働基準法の要件を満たすだけでは十分な休息を与えたことにはならないため、無理のないシフトを組むことを意識しましょう。
5. 夜勤明けは休みの日にならないため注意!

夜勤明けは、たとえ次回の勤務まで24時間の休みがあっても、休日とすることはできないため注意が必要です。休日と認められるためには「午前0時から午後12時まで」の休みを与えることが必要であるため、この点を理解したうえでシフトを組むようにしましょう。
ほかにも、夜勤には日勤と異なった考え方をするポイントがいくつかあります。法令を順守した企業経営のためにも、夜勤の仕組みや考え方を押さえたうえで、従業員の健康を守れるようにシフトを組みましょう。
「夜勤管理マニュアル」無料配布中!
労働基準法は基本的な内容で細かい運用方法の解説はないため、「夜勤明けの適切な休日のとらせ方は?」「夜勤明けから次の勤務はいつからしてよい?」など夜勤と休日の関係性と正しい管理の方法がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤と休日の取らせ方のルールについて、本記事の内容をまとめた資料を無料配布しております。例を挙げてわかりやすく解説しているので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
夜勤の関連記事
-


深夜残業が多い人に必要な健康診断とは?診断項目や基準、回数を解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.09.26
-


深夜残業が出る時間は何時まで?早朝分の処理の仕方を解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.10.18
-


深夜労働が許される年齢は?労働基準法に関わる注意点
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.09.26