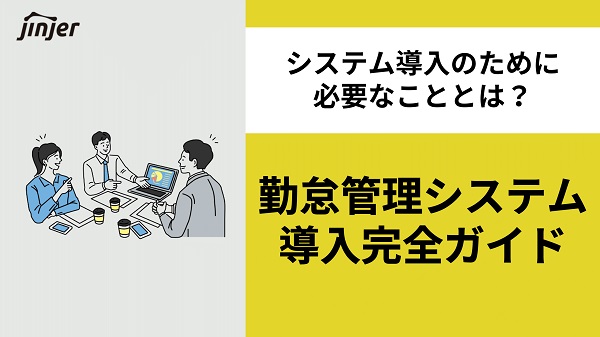【建設業向け】打刻が簡単にできる勤怠管理システムとは?機能やメリットを解説

ほかの業界と違い、建設業界では従業員が打刻した勤務データを元にして、人件費に対する予実管理や、プロジェクトの工数管理などをおこなう必要があります。
事務作業やオフィスワークの負担が肥大化しやすい構造で、業務生産性の向上の妨げとなっているケースが少なくありません。
勤怠管理を効率化するなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
この記事では、建設業において勤怠管理システムを導入する2つのメリットを解説します。
関連記事:なぜ打刻は必要なのか?打刻忘れによるリスクを知り、必要性を理解しよう
複数の現場で業務を行っている従業員の勤怠管理や、出勤簿への記入ミス、現場単位での報告の信憑性など、建設業界の勤怠管理は解決しなければならない課題が多くあります。
建設業における勤怠管理の課題を解決するには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
とはいえ、「システムが便利そうなのはわかるけど、そもそもどのようなもので実際に何ができるのか、どう課題が解決されるのかイメージがつかない」という方も多いでしょう。
そのような方に向け、当サイトでは勤怠管理システムとは何かや、実際にどのようなことができるのか、導入までに何をしなくてはいけないのかをまとめた資料を無料で配布しております。
勤怠管理システムについてこれ一冊で情報収集できる資料ですので、システム化に興味がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 建設業向けの勤怠管理システムとは?


建設業向けの勤怠管理システムとは、クラウド型のもので、従業員の勤怠や現場の進捗をリアルタイムで記録できるツールです。
このシステムを利用することで、手間をかけずに正確に勤怠情報を集計・管理することが可能になります。従来の労働環境が整備されていなかった建設業において、こうしたシステムの導入は、勤怠管理の課題解決や現場作業員のワーク・ライフ・バランスの向上に寄与します。もし勤怠管理に悩んでいるなら、ぜひクラウド型勤怠管理システムの導入を検討してみてください。
1-1. そもそもなぜ勤怠管理は必要?
勤怠管理は、働き方改革の一環としての労働安全衛生法改正により、企業が従業員の労働時間を客観的に把握することが義務化されたことから必要不可欠な要素となりました。正確な労働時間管理を実現するためには、勤怠管理が重要です。
勤怠管理システムは、法定三帳簿の保存、労働時間の詳細な管理、自己申告の勤怠管理といったポイントを備え、建設業に限らず、すべての業界で求められる正確な労働時間管理を手助けします。これにより、企業はストレスフリーに労働時間を管理できるようになります。
2. 建設業の勤怠管理に役立つシステムの機能

勤怠管理システムを導入する際は、給与計算に必要な項目がしっかりと算出できるかや、就業規則に対応した管理ができるか、サポート体制が整っており、運用にのるイメージがつくかを基準にして選ぶのがおすすめです。
ここでは、建設業の企業が勤怠管理システムを選ぶ際に、特にチェックしておきたい機能をご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。
2-1. GPS打刻機能
現場への直行・直帰が多くなる建設業では、スマホを利用した打刻がおすすめです。現場に簡易的な事務所があれば、タブレットを設置して打刻してもらうことも可能です。
スマホでの打刻をするときにチェックしておきたいのが不正打刻を防止する機能です。GPS打刻ができるシステムであれば、どこで打刻したのかが分かったり、特定の場所でしか打刻できない設定にできるため、不正打刻を防止することができます。
2-2. 工数管理・日報機能
日報などによって工数管理を常におこなっている建設業では、「勤怠管理システムで工数管理も一緒にできたら便利だ」と思われる方が多いでしょう。
工数管理機能が実装されている勤怠管理システムも存在しますが、工数管理機能そのものがない勤怠管理システムでも、給与計算用に集計する労働日数や労働時間などの項目を出力することで、工事原価や工数の管理に役立てることができます。
工数管理については、システムによってどの程度対応できるかに差があるため、勤怠管理と工数管理を同じシステムでおこないたい場合は、注意して確認しておくとよいでしょう。
2-3. 労働時間の自動集計
労働時間の自動集計はどの勤怠管理システムでも備わっている機能ですが、集計できる項目はシステムによって異なるため、就業規則に合わせて必要な項目が集計できるかを必ずチェックしておきましょう。
特に、工数管理をおこなう建設業では、現場ごとで労働時間を分けて集計することが可能かをチェックしておくと安心です。
また、長時間労働になりやすい建設業では、残業時間が上限規制を超えないように管理することも重要です。勤怠管理システムであればリアルタイムで労働時間を把握することができますが、設定した労働時間数を超えると従業員・管理者双方へアラートを出せるシステムもあるため、チェックしておくとよいでしょう。
関連記事:打刻まるめとは?考え方やルールの設定方法について詳しく解説
3. 建設業向け打刻管理がしやすいシステムの選び方


建設業向けの打刻管理がしやすいシステムを選ぶ際には、まず自社の勤務形態や現場の特性に応じた機能を明確に把握することが重要です。
現場への直行直帰が頻繁にあるため、スマホやタブレットでの打刻に対応しているシステムを選ぶと、従業員が手軽に利用でき、打刻漏れを防ぐことができます。また、操作が簡単で、従業員がストレスなく使えるインターフェースも重要です。さらに、自社の運用に合わせてカスタマイズできる機能があると、より効果的な勤怠管理が実現できるでしょう。
3-1. スマホやタブレットに対応していること
建設業向けの打刻管理がしやすいシステムを選ぶ際、スマホやタブレットに対応していることは非常に重要です。
現場作業が多い建設業では、従業員が簡単に打刻できることで、打刻漏れを防ぎ、業務の効率化に繋がります。特に、GPS打刻機能を有するシステムは、不正打刻の防止に役立ち、災害時には従業員の位置をリアルタイムで把握することも可能です。このような機能を備えたシステムは、現場の状況に応じた柔軟な対応が可能となり、全体的な業務の円滑化を促進します。
3-2. 従業員にとって操作しやすいこと
従業員にとって操作しやすいことは、勤怠管理システム選びにおいて非常に重要です。
特に、パソコンやスマホに苦手意識を持つ従業員が多い場合、直感的に操作できるインターフェースや簡単な入力方法のシステムが求められます。このようなシステムを使用することで、従業員の入力負担を軽減し、ストレスなく打刻が行える環境を整えることができます。また、サポート体制が充実しているシステムを選ぶことで、操作不安を解消し、従業員が安心して利用できるようになります。積極的に端末を触れる機会を提供し、従業員が自信を持って操作できるように促すことで、全体的な業務の効率向上につながります。
3-3. 自社の運用に合わせてカスタマイズできること
自社の運用に合わせてカスタマイズできることは、建設業向けの打刻管理システムを選ぶ際の重要なポイントです。
特に、業務の特性や従業員の多様性を考慮することで、無駄を省いた効率的な勤怠管理が実現します。例えば、特定の労働条件やシフト制度に合わせた設定を行うことで、自社のニーズに応じた管理が可能となります。これにより、従業員の勤務状況を正確に把握し、適切な工数管理や報告ができることが期待されます。自社に合ったカスタマイズ機能を持つシステムを導入することで、建設業特有の課題を解決しやすくなります。
4. 建設業が打刻・勤怠管理で直面しやすい4つの課題
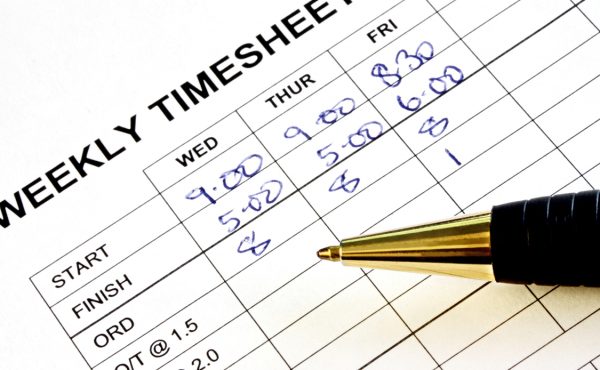
建設業での勤怠管理は、ほかの業界よりも工夫が求められます。まずは建設業界で起こりがちな4つの課題を整理しておきましょう。
4-1. 日報による勤怠報告の信憑性・客観性が乏しい
建設業の従業員の打刻は、ほとんどが作業現場などの外出先からの打刻です。
現場へ向かう前に会社に寄ってもらい、タイムレコーダーで打刻してもらうケースもありますが、多くの場合は作業現場で日報などを書いてもらい、後で事務員が回収するといった勤怠管理がおこなわれています。
手書きの日報は第三者の改ざんや、虚偽報告、従業員の記憶を頼りにした報告などが可能なため、業務記録としてそれほど信憑性が高いわけではありません。
一方で、2019年4月1日から、働き方改革にともなう労働安全衛生法の改正により、使用者は労働時間や残業時間などを正確かつ客観的に記録することが求められるようになりました。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、客観的な記録として「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録」などが挙げられており、やむをえず自己申告による労働時間の把握をおこなう場合は、正確な実態調査や適正な報告がおこなわれるようにするため、ガイドラインに定められている措置を必要としています。
4-2. 勤怠の集計に時間がかかる
人手不足に悩む建設業界では、勤怠管理に多くの人員を避けず、勤怠の締め作業が毎月パンクしてしまう企業も少なくありません。
1日で複数の現場を回ることも多々あるため、従業員一人ひとりの労働時間を把握するだけでも大変です。
また、作業現場で作成した日報や、事務員によるタイムカードの代理打刻で労働時間を把握することが多く、打刻漏れ・不正打刻が起きやすい傾向にあります。
日報やタイムカードが虫食い状態の従業員がいると、出勤時間や退勤時間などの事実確認をする必要があり、さらに集計作業の工数が増加してしまいます。
人手不足だからこそ、勤怠管理の生産性を上げ、無駄な工数をなるべく減らす必要があります。
4-3. 建設業では「勤怠管理」と「工数管理」の連携が必要
建設業界の勤怠管理は、各現場やプロジェクトの「工数管理」とも連動しています。
プロジェクトに必要な工数を見積もったうえで、予定工数に対しどれだけの実績工数があるかをモニタリングするには、従業員一人ひとりの勤務データの管理が欠かせません。
手書き日報やタイムカードを使ったアナログ勤怠管理では、この「勤怠管理と工数管理の連結」自体にかなりの工数を必要としてしまいます。
とくに工場やプラントの建設現場など、厳格な工数管理を必要とするケースでは、外部ツールやサービスを利用するなどして、勤怠管理と工数管理の「見える化」をおこなうことが大切です。
関連記事:裁量労働制の従業員の打刻管理で注意すべき2つのこと
関連記事:労働時間を正しく理解してタイムカード打刻のミスをなくそう
4-4. 残業時間の適切な管理が難しい
2018年に働き方改革関連法が成立したことにより労働基準法が改正され、新たに「時間外労働の上限規制」が2019年4月に規定されました。
建設業界においては5年間の猶予期間が設けられていましたが、2024年4月からはいよいよ建設業界にもこの規制が適用されます。
「時間外労働の上限規制」は罰則つきの残業に関するルールです。違反すると「6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が科される恐れがあります。
そのため、建設業界も例外なく、これまで以上に残業時間を正確に把握する仕組みや体制が求められることになります。
5. 建設業が勤怠管理システムを導入する3つのメリット

建設業界が勤怠管理システムを導入するメリットは2つあります。勤怠管理システムなら、作業現場からでも正確に打刻でき、勤務状況を自動で集計してくれます。
1日に複数の現場を回るケースや、シフト制・フレックス制を導入しているケースでも、勤怠管理システムがあれば事務作業が複雑化しません。人手不足に悩む企業の心強い味方となるのが、勤怠管理システムです。
5-1. 勤怠管理システムなら自動で勤務状況を集計できる
勤怠管理でもっとも手間やコストがかかるのが、従業員一人ひとりの労働時間や残業時間の計算です。とくに建設業界はタイムカードや手書きの日報などを使い、アナログで勤怠管理をおこなっている企業が多く、事務員が少ない場合は月末の締め作業が長期化しやすい傾向にあります。手作業だと計算ミスや入力ミスが発生しやすく、残業時間や年休消化状況の把握が遅れ、慢性的に法令違反の状態となっているケースも少なくありません。
勤怠管理システムの最大の特長の1つは、従業員の打刻データが蓄積され、自動で労働時間や残業時間を集計できる点です。タイムカードや日報を転記し、電卓を叩いて計算する必要がないため、事務作業を大幅に簡略化できます。2019年4月1日に施行された改正労働基準法に対応したシステムなら、残業時間や年休消化状況の異常値を自動で検出し、アラートを鳴らすことで迅速なケアも可能です。
5-2. 打刻漏れや不正打刻が起きにくい
建設業界で課題となるのが、打刻漏れや不正打刻を防ぐ仕組み作りです。オフィスワーカーを除き、多くの従業員は作業現場に直行直帰し、出勤時刻や退勤時刻を外出先から報告します。多くの企業では、手書きの日報などでの事後報告や、事務員に代理で打刻してもらうといった方法をとっており、打刻漏れや不正打刻の温床となっています。
勤怠管理システムなら、スマホやタブレット、フィーチャーフォンなどを使った打刻方法と連携し、従業員に外出先から手軽に打刻してもらうことが可能です。出勤・退勤と同時に、従業員自身の手でリアルタイムに打刻してもらうため、「誰が」「いつ」打刻したかがはっきりします。また、近年注目を集めている「GPS打刻」なら、携帯端末のGPS機能を利用し、打刻時刻と同時に位置情報を送信するため、「どこで」打刻したかもわかります。
たとえば、「現場に行っていないのに出勤したかのように報告する」「遅刻しそうになり、事務員に頼んで始業時間に打刻してもらう」といった不正ができなくなるため、不正打刻の防止策としても効果的です。以下のページでは、建設業界における勤怠管理システムの活用方法を解説しています。
勤怠管理システムを導入しようか検討されている方や現状の勤怠管理に課題を感じる方はぜひご覧ください。
関連サイト:建設業界の勤怠業務効率化|勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」
関連記事:打刻忘れが起きてしまう原因とは?対策方法も合わせて解説
関連記事:外出先からでも正確な打刻を可能にする勤怠管理の3つのポイント
5-3. 2024年問題へ対応できる
建設業が勤怠管理システムを導入するメリットの一つとして、2024年問題への対応が挙げられます。
2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、改正労働基準法によりその遵守が義務付けられました。従来、長時間労働が常態化していた建設業界において、ワークライフバランスの確保が重要視されています。
勤怠管理システムを利用することで、コンプライアンスを遵守しながら適正な労働時間の管理が可能となり、企業イメージの向上にも寄与します。また、社会保険労務士との連携により、法令遵守の体制を整えることができ、安心して運営を進めることができます。導入を通じて、課題解消を目指すことが求められるでしょう。
6. 建設業で勤怠管理をするなら「勤怠管理システム」の導入がおすすめ

今回は、建設業界が勤怠管理システムを導入する2つのメリットを解説しました。日報やタイムカードなどを使った、従来型のアナログ勤怠管理をしている企業が少なくありません。
アナログ勤怠管理だと、労働時間・残業時間の集計作業に手間がかかり、予実管理や工数管理との連携もスムーズにおこなえません。勤怠管理システムを導入すれば、作業現場からでもスマホ・タブレット・フィーチャーフォンなどを使って手軽に打刻でき、勤務状況をリアルタイムに把握することが可能です。
給与計算システムや工数管理システムとの連携もしやすく、業務生産性の向上につながります。人手不足に悩む建設業界だからこそ、勤怠管理システムを導入して事務作業やオフィスワークを効率化しましょう。
関連記事:従業員のタイムカード打刻忘れ対策として企業がおこなうべき3つのこと
複数の現場で業務を行っている従業員の勤怠管理や、出勤簿への記入ミス、現場単位での報告の信憑性など、建設業界の勤怠管理は解決しなければならない課題が多くあります。
建設業における勤怠管理の課題を解決するには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
とはいえ、「システムが便利そうなのはわかるけど、そもそもどのようなもので実際に何ができるのか、どう課題が解決されるのかイメージがつかない」という方も多いでしょう。
そのような方に向け、当サイトでは勤怠管理システムとは何かや、実際にどのようなことができるのか、導入までに何をしなくてはいけないのかをまとめた資料を無料で配布しております。
勤怠管理システムについてこれ一冊で情報収集できる資料ですので、システム化に興味がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
打刻の関連記事
-

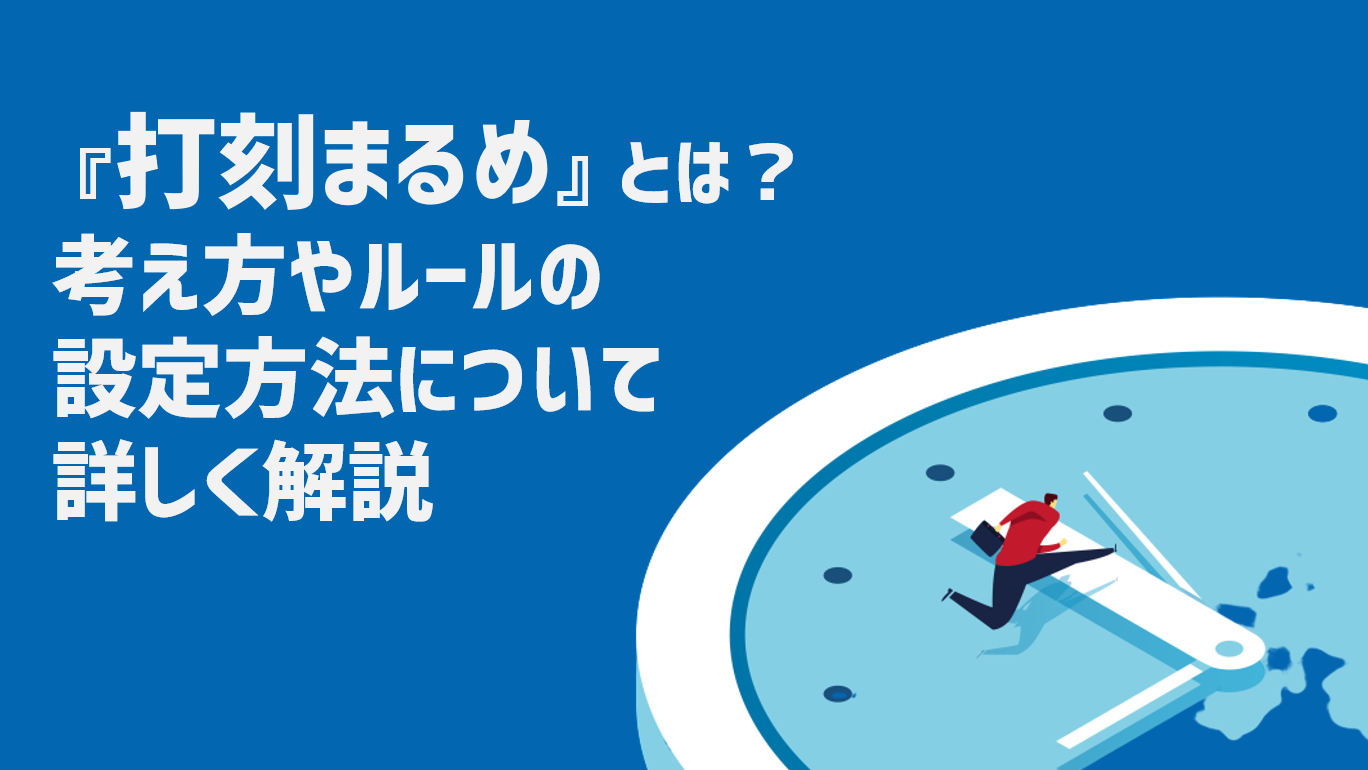
打刻まるめとは?考え方やルールの設定方法について詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2020.03.10更新日:2024.07.22
-

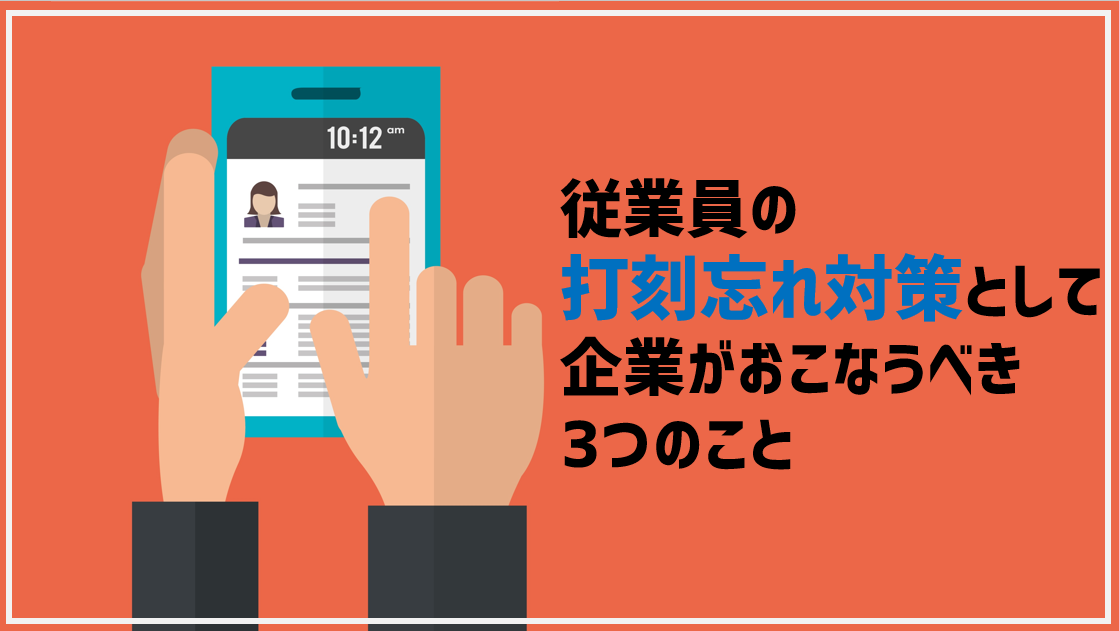
タイムカードの打刻忘れ対策・漏れ防止策として企業が行うべき勤怠管理とは?
勤怠・給与計算公開日:2020.03.05更新日:2024.08.29
-


外出先からでも正確な打刻を可能にする勤怠管理の3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.03.03更新日:2024.05.14