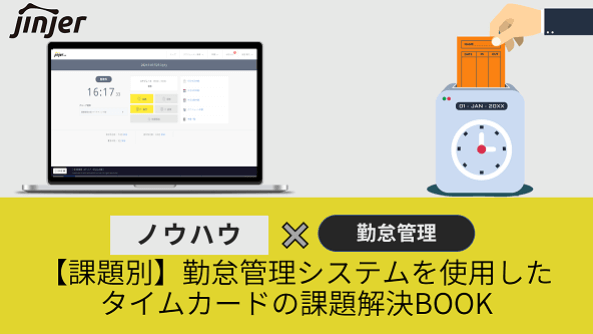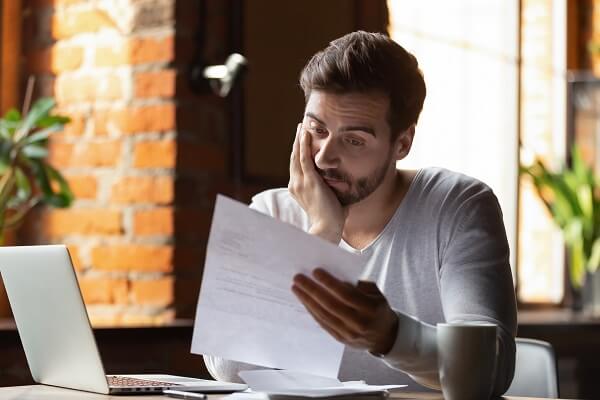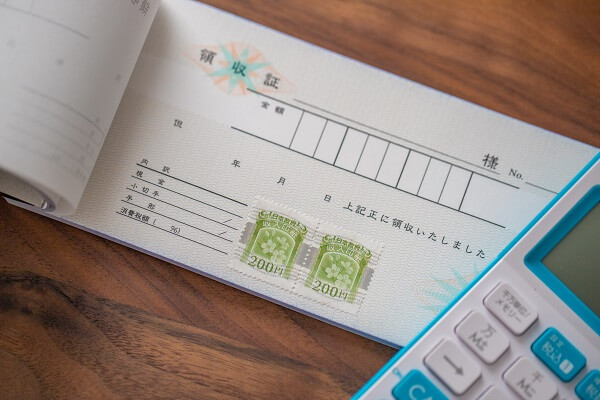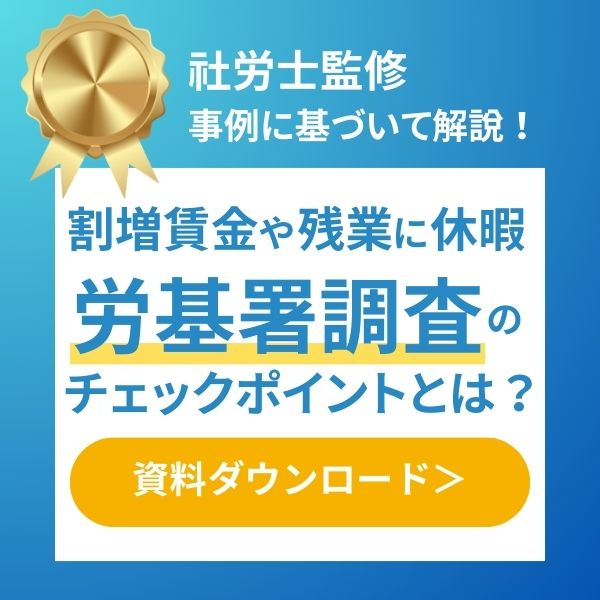労働時間を正しく理解してタイムカード打刻のミスをなくそう

タイムカードによる打刻は、労働時間を記録するものとして重要です。しかし、使用者が「労働時間」の正確な定義を理解していないと、従業員に正しく出退勤の打刻をさせることができず、残業代未払いなどの問題が発生しかねません。
本記事では、労働時間の定義と、それに基づきタイムカードはいつ打刻させればよいのかを詳しく解説いたします。
関連記事:なぜ打刻は必要なのか?打刻忘れによるリスクを知り、必要性を理解しよう
システムを利用した課題解決BOOK!
タイムカードや出勤簿を使って手作業で労働時間を集計している場合、記入漏れや打刻ミスの確認に時間がかかったり、計算ミスやExcelへの転記ミスが発生したりと、工数がかかる上にミスが発生しやすいなどお悩みはありませんか?
そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入を検討することで、
・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる
・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに
・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働時間の法的な定義とタイムカードの押し方

「労働時間」とはよく耳にする言葉ですが、その定義を理解している人は意外と少ないです。労働時間の法的な意味を理解していなければ、使用者と労働者との認識に齟齬が生まれ、トラブルに発展することもあります。
1-1. 正しい労働時間の定義と出退勤の時間とは
労働時間は厚生労働省が出しているガイドラインによって、以下のように定義されています。
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
つまり、使用者が明示・黙示した指示により従業員が業務に従事していた時間は、全て労働時間とみなされ、賃金を支払わなければなりません。
例えば、直接業務をおこなっていなくとも、参加が義務付けられている研修や使用者に指示されておこなった学習時間などは労働時間に含まれます。
労働時間の定義に照らし合わせると、出勤(始業)時間は「労働者が使用者の指揮命令下に入った時間」であり、退勤(終業)時間は「労働者が使用者の指揮命令下から外れた時間」となります。
したがって、事業場にタイムカードを設置して従業員に打刻をさせる場合は、労働が始まった時間と終わった時間にタイムカードを押させなければなりません。
1-2. タイムカードを押すタイミングとは?
タイムカードは給与計算の元となる情報であるため、労働が始まった時間と終わった時間に打刻させなければなりません。残業代未払いの裁判でも、会社が立証できなければ、基本的にはタイムカードに印字された時間が実労働時間とみなされます。
とはいえ、多くの企業ではタイムカードに打刻された時間は労働の始まりと終わりの時間というよりも「事業場にいた時間」であることが多いでしょう。
そのため、労働が始まって終わった時間ぴったりに打刻させることは現実的ではなく、運用方法を工夫する必要があります。次の章にて、タイムカードで正しく労働時間を管理するための方法をご紹介します。
2. タイムカードで労働時間を正しく管理するためには

「会社に来たら押す」「会社を出る前に押す」というルールでタイムカードを運用している場合、タイムカードに打刻された時間と実際に労働のあった時間にずれが生じ、従業員の実労働時間を正確に把握することができません。
そのため、タイムカードを使って従業員の実労働時間を正確に把握するには、運用に工夫が必要になります。ここでは、タイムカードで労働時間を正確に把握するための方法をご紹介します。
2-1. 残業事前承認制や、時間外勤務指示書を導入する
始業時間の前や終業時間の後に打刻がある場合、タイムカードの情報だけでは実際に労働があったのかどうかがわかりません。そこで、始業時間の前や終業時間の後に業務をおこなう必要がある場合は、「残業事前承認制」や「時間外勤務指示書」を導入しましょう。
残業事前承認制とは?
残業申請書ともいいます。正当な残業すべき理由をまとめ、上司に提出することで残業を認めてもらう制度です。
時間外勤務指示書とは?
上司から部下に対して残業するように指示する書類です。上司から残業を言い渡すため、当然超過分の支払いが発生します。
2-2. 打刻にずれが発生した場合は報告書を提出させる
実際の労働時間と出退勤の時間にずれが発生している場合は、なぜずれが発生しているのか報告させる方法もあります。
例えば、「朝早くに来て新聞を読んでいた」「社内のクラブ活動で退勤時間が遅くなった」など、使用者からの指示に基づいた業務をおこなっていないのであれば、その理由をタイムカードに簡単に記載させるとよいでしょう。
ただし、「強制参加の社内研修があった」「仕事の引き継ぎをしていた」など、使用者からの指示によって事業場にいたのであれば「労働時間」として扱わなくてはいけません。
2-3.打刻の重要性や打刻ルールを伝え打刻ミスを防ぐ
正確な労働時間の管理は、従業員がきちんと打刻をしてくれなければ成り立ちません。
そもそも、労働時間の定義やなぜ正確に打刻する事が重要なのかを従業員全員が理解して行動に移せなければ、労働時間を正確に管理することはできないでしょう。
従業員への啓蒙をおこなうと同時に、自社内で正確に労働時間を管理できるような打刻ルールを作り、周知して徹底させるようにしましょう。
関連記事:従業員のタイムカード打刻忘れ対策として企業がおこなうべき3つのこと
3. こんな時はいつタイムカードを押す?

ここまで、労働時間の定義とタイムカードを押すタイミングや運用方法について解説してきました。
しかし、「これは労働時間に含まれるの?」「こんな時はいつタイムカードを押すの?」など、状況によっていつタイムカードを押すのが適切かは変わるため、疑問も多いでしょう。ここでは、代表的な疑問4つにお答えいたします。
3-1. 着替えの時間は「労働時間」に含まれる?
製造業や食品を扱う職場の場合、衛生管理のためにユニフォームが用意されていることがほとんどです。その場合、私服で出社しユニフォームに着替える前と後、どのタイミングで打刻するべきでしょうか?
「着替えてからが仕事の始まりだから、着替えの時間まで考えて早く出社するべきだ」という会社も多く見受けられます。
しかし、業務上必要な所定のユニフォームや制服に着替えることが義務付けられている場合は、「業務」としてみなされるため、着替え時間は労働時間に該当します。
したがって、タイムカードを押すのは「着替える前に打刻する」のが正しいタイミングです。私服で出社し、タイムカードを押した時点で「労働時間」として考えます。
一方、会社員や事務業務の様に、特定の制服に着替える必要がない場合はどうでしょう?自由に服装を選べる場合は、私服から自前の仕事着に着替えてもその時間は労働時間に含まれません。「着替えた後」にタイムカードに打刻すべきなので注意してください。
3-2. 休憩は労働時間に含まれる?勤務時間との違い
勤務と労働、同じような意味に思われがちですが、正確には少し違います。勤務は「会社が定めた始業時間から終業時間までの時間」です。労働は「実際に働いた時間」なので、全く別物になります。
例えば、勤務時間が午前9時から午後18時、間に1時間の休憩があるとしましょう。その場合は、「休憩も含めて9時間が勤務時間」とされます。
しかし、労働時間は休憩を視野に入れず、「実際に労働した8時間を労働時間」とみなされます。
3-3. 始業時間よりも少し早めにタイムカードを切ってもいい?
「労働が始まった時間に打刻すべき」といっても、業務が始まる前に今日の仕事を整理したりメールのチェックをおこなったりするために、始業時間よりも早めに出社する従業員は多いでしょう。
この時、「少し早めに打刻されると、本当は必要のない残業代も必要になってしまうのでは」と考えられるかもしれませんが、時間外勤務申請書を提出させる、15分以上の乖離があった場合は報告させるなどの運用で対処すると、実際に労働があったのかどうかが判断できるでしょう。
3-4. 出退勤の時間ぴったりにタイムカードを押すことは問題ない?
タイムカードは給与計算のために労働時間を記録するものであるため、労働が始まる始業時間や労働が終わる終業時間ぴったりに打刻すること自体は問題ありません。
ただし、業務の性質や就業規則などによっては遅刻や早退とみなすこともあります。例えば、タイムカードが事務所の入り口に設置してあり、実際の労働場所と事務所に距離があって移動が必要な場合は、出勤時間ぴったりに打刻したとしても実際の業務が始められていないため、遅刻とみなすことになるでしょう。
どのような場合を遅刻や早退とみなすかは企業によって異なるため、まずは就業規則を確認してみましょう。
また、従業員が正しく打刻をしたとしても、労務管理の担当者が集計ミスをしてしまっては元も子もありません。手計算で今もおこなっているようだと、人的ミスは避けられないでしょう。
まずは無料でできる範囲で対策をしたいという方向けに、無料で公開されている勤怠管理用のテンプレートや無料の集計サービスを使用して集計する方法を書いた記事がありますので、無料のサービスを検討中の方は、以下の関連記事からご確認ください。
【関連記事】「え、こんなに簡単なの?」タイムカードを簡単に集計する方法をご紹介!【無料テンプレ付き】
4. 労働時間の定義を理解しタイムカードの打刻を適切に管理しよう

会社は、法律が定めた労働時間を守らなければなりません。しかし、全ての会社が完璧に法律通りの環境を整えることは簡単ではありません。
それゆえ、会社が決めたルールを設けるケースも多いのですが、会社のルールは独自性の強いものであり、「これは本来の労働条件ではない」と従業員が不満に思うこともあるでしょう。
人事担当者は、会社と従業員の間に入り、問題が大きくなる前に先に手を打つ必要があります。そのためにも、人事担当者は会社のルールと労働時間の細かい定義をしっかり把握しておくことが大切です。
システムを利用した課題解決BOOK!
タイムカードや出勤簿を使って手作業で労働時間を集計している場合、記入漏れや打刻ミスの確認に時間がかかったり、計算ミスやExcelへの転記ミスが発生したりと、工数がかかる上にミスが発生しやすいなどお悩みはありませんか?
そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入を検討することで、
・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる
・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに
・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.11.15
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.11.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.10.31
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.11.19
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
打刻の関連記事
-

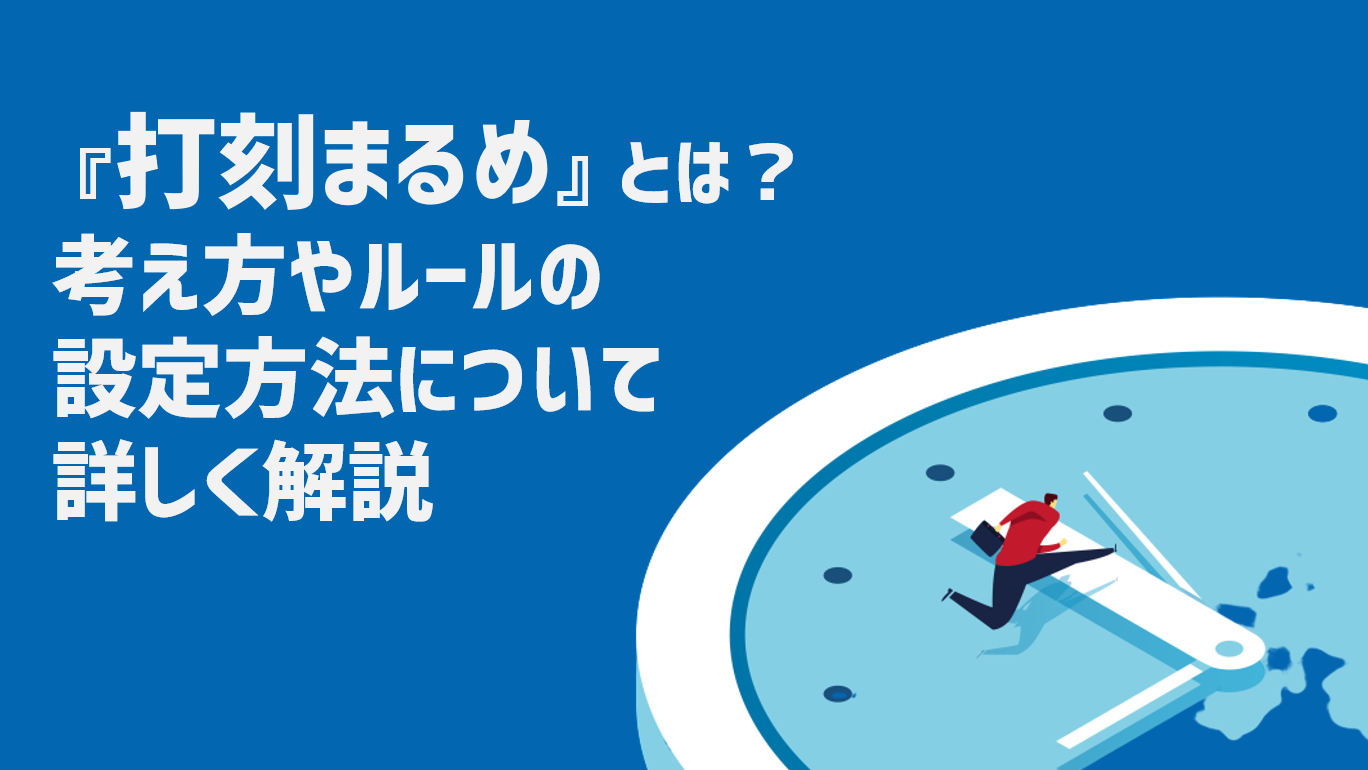
打刻まるめとは?考え方やルールの設定方法について詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2020.03.10更新日:2024.11.26
-

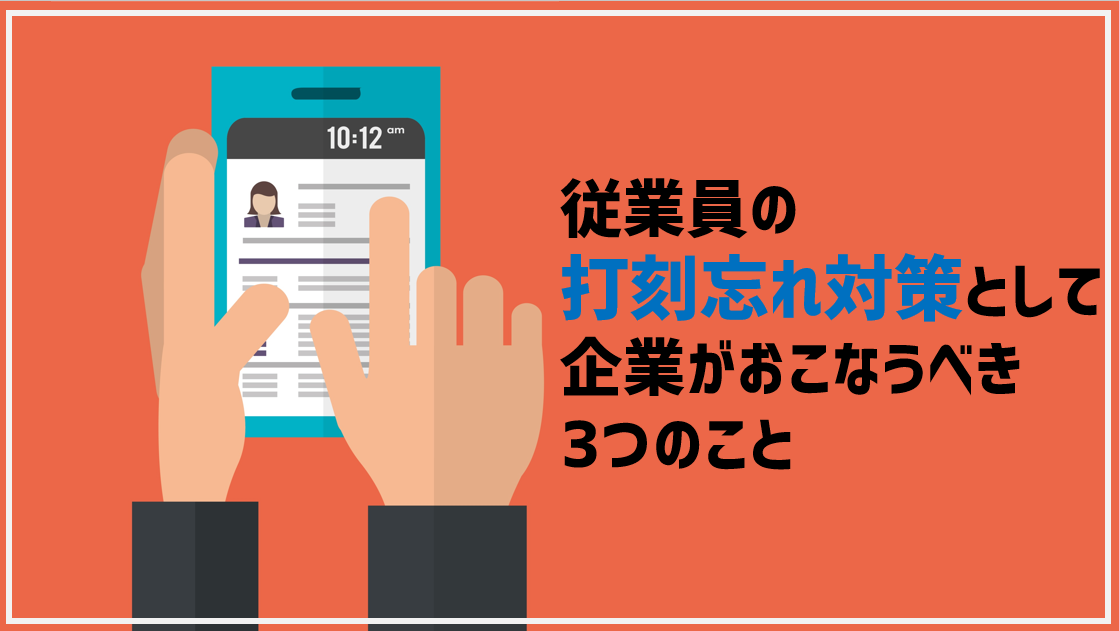
タイムカードの打刻忘れ対策・漏れ防止策として企業が行うべき勤怠管理とは?
勤怠・給与計算公開日:2020.03.05更新日:2024.11.20
-


建設業向けの打刻が簡単にできる勤怠管理システムとは?機能やメリットを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.03.03更新日:2024.12.03