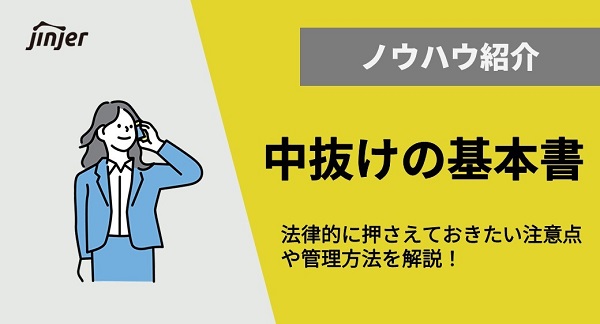なぜ打刻は必要なのか?打刻忘れによるリスクを知り、必要性を理解しよう

勤怠管理をおこなう上でとても重要な打刻は、従業員の業務の1つでもあります。しかし、「就業規則に従って出勤・退勤している」従業員からすると、打刻に対する認識は管理担当者よりも甘いかもしれません。
1人だけであれば確認作業もそれほど負担になりませんが、従業員が多い会社の場合、1人ひとりの打刻状況を確認するのは大きな業務負担になります。また、打刻忘れの積み重ねは利益損失にもつながるので、重要性を理解してもらう必要があります。
ここでは、打刻の必要性や忘れが発生する理由、打刻忘れを防止する方法などを解説します。
目次
中抜けは、適切に扱わなければ労働時間集計や残業代の計算に誤りが発生するため、正しい管理方法を把握しておかなくてはなりません。
当サイトでは、中抜けの扱い方や法律的におさえておきたいポイントなど本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
中抜けを適切に管理したい方は、こちらから「中抜けの基本書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 打刻とは


打刻という言葉には、「金属など硬い材料に文字や模様を刻む行為の意味の打刻」と「時間や出勤・退勤などの記録を取るための行為を指す打刻」の2つの意味があります。
前者の打刻は、彫金や刻印といった技術の一部であり、金属の表面に文字やデザインを彫り込むことで、装飾や識別、記念品の制作などに使用されます。
後者の打刻は、労働者が出勤や退勤の時間を正確に記録するための行為です。職場では、出勤時間や退勤時間が正確に記録されることで、勤怠管理や給与計算などを適切におこなえます。
本記事では、後者の勤怠管理という文脈での「打刻」について解説します。
2. なぜ打刻は必要なのか?


打刻が必要な一番の理由は、「正確な給与計算」をおこなうためです。従業員の勤務時間が正確に記録されていなければ、当然ですが労働に準じた給与を支払うことができません。出勤と退勤の時刻が正確に打刻されることで、残業手当なども正確に算出でき、給与計算を適切におこなえるのです。
また、打刻データ収集・分析すれば、従業員の勤務実績を把握することができます。本当に必要な残業であったのか、業務負荷が偏っていないかなど、客観的な情報から従業員のコンディションを推察できます。従業員が、健康な状態かつ安心した環境で労働を続けられるように整備するための材料とも言えます。
さらに、労働法の遵守も打刻の大きな目的のひとつです。労働時間や休憩時間など、従業員の権利を守るための法的要件を満たされているかを確認するには、正確な打刻が必要不可欠です。
最後に、打刻データは業務の進行状況やプロジェクトの管理にも役立ちます。従業員の出勤状況や勤務時間の記録を通じて、業務のスケジュール調整やリソースの適切な配分が可能となり、生産性の向上や業務の効率化がはかれます。
このように、「打刻」は従業員にとっても会社にとっても重要な業務の1つなので、打刻忘れは徹底して防ぐ必要があるのです。
関連記事:打刻忘れはなぜ起きるのか?打刻忘れ発生時の対応や防ぐための対策を徹底解説
3.打刻忘れが起こる理由


打刻には以下の通り、さまざまな方法があります。
- タイムカードによる打刻
- エクセルなどの表計算ソフトを用いた打刻
- 無料打刻アプリの利用
- 勤怠管理システムの利用
それぞれ具体的にどのような違いがあるのか解説します。
3-1.打刻機器の動線が悪い
打刻機器までの動線が悪いと、従業員が忘れてしまうリスクが高くなります。
例えば、入り口から遠く離れた場所にあったり、そもそもオフィス内になかったりすると、従業員はタイムレコーダーのある場所まで移動するしなければなりません。すぐに業務を始めなければいけない場合や、出勤時に上司に呼ばれたりすると、打刻を忘れることも少なくないでしょう。
管理者からすると、「打刻は従業員の責任でおこなうもの」というイメージがあるかもしれませんが、スムーズに仕事を始められるようにするためにも、打刻機器までの動線は考慮する必要があります。従業員は時間に追われたり急いだりすることもあるので、打刻機器は従業員の動線上に配置するのがベストです。
3-2.打刻の習慣がない
打刻する習慣がない、というのも打刻忘れの原因になります。人は、習慣になっていない行動は、当たり前のことであっても忘れてしまいます。
オフィスに常勤している従業員であれば習慣化されているかもしれませんが、直行直帰をすることが多い営業職や通常は店舗勤務となる運営部などは、習慣になっていないため打刻忘れをしてしまいます。
このように職種や業務によっては習慣化するのは難しいですが、業務の1つであることをしっかりと説明し、認識してもらうことが重要です。また、習慣化しやすいように、打刻機器をオフィスやロッカールームのドア付近に配置するなども対策も効果的です。
3-3.打刻機器の不具合
いくら従業員がしっかり打刻をしていても、打刻機器の不具合のせいで打刻忘れが起こることがあります。
例えば、タイムカードを使っている場合、タイムレコーダー本体の日時がズレていたり、印字機能に不具合があったりすると、記録上では「打刻忘れ」となってしまいます。
また、ちゃんと印字できず2回打刻をおこなってしまうと、正しい時刻がわからなくなることもあるかもしれません。
タイムレコーダーのせいで正確な打刻ができない、というのは管理担当者に責任が生じるので、正しく打刻できるか定期的に確認してください。また、時間や日時を2重刻印してしまった場合は、その場ですぐに修正申請をするよう、従業員に周知しておくと良いでしょう。
4. 打刻に関する注意事項


「打刻の必要性」を見てもわかるように、打刻は従業員の給与や会社の利益に大きく関わっています。だからこそ打刻忘れを防止することが重要なのですが、打刻に関する注意点もあります。ここでは3つの注意点を解説するので、担当者の方はチェックしておきましょう。
4-1.手書きのタイムカードは打刻にならない
手書きでタイムカードを記入する場合、打刻としては扱われない可能性があります。
労働時間の把握について曖昧な部分が多く、その結果長時間労働による過労死問題や未払いの残業代問題など社会問題が多発していました。この問題を受け、働き方改革の一環で2019年4月に労働安全衛生法が改正され、従業員の労働時間を「客観的な記録によって把握すること」が義務付けられました。
そのため、企業は従業員の労働時間を客観的に把握しなければなりません。今のところ罰則はありませんが、手書きのタイムカードでは労働時間を客観的に把握できるとは言い切れないため、手書きによる勤怠管理を導入している企業は別の方法に切り替えましょう。
関連記事:勤怠管理において客観的記録をつけるための方法やポイントとは
関連記事:タイムカードの改ざんは違法!正しい対処法や対策をご紹介
4-2.打刻まるめは違法の可能性がある
「打刻まるめ」とは、給与計算に必要な勤務時間の集計作業の負荷を軽減するために、出退勤の時刻などの端数を切り捨て・四捨五入することを意味します。5分単位・15分単位・30分単位などで数字をまるめる(整える、調整する)ケースが多いです。
「打刻まるめ」は、勤務時間の計算業務を効率化できるものの、正しく運用しなければ法律違反になる可能性があります。
労働基準法の24条第1項の「賃金全額払いの原則」で考えれば、残業代を含め給与は1分単位で計算して支払わなければなりません。そのため、「打刻まるめ」によって労働時間が実態よりも短くなるというような運用は、違法になる可能性があります。
「打刻まるめ」の詳しい内容や、正しい打刻まるめの方法などは以下の記事で解説しているので、気になる方はぜひご一読ください。
関連記事:打刻まるめとは?考え方やルールの設定方法について詳しく解説
4-3.労働時間の上限を超過する可能性がある
正しい打刻がおこなわれないと、従業員の労働時間が把握できず、気づかないうちに労働時間の上限を超過してしまい法律に違反していた、ということが起きてしまうかもしれません。
従業員の労働時間は、「1日8時間、週40時間まで」と労働基準法で定められています。この時間を超えた労働は時間外労働となり、36協定と呼ばれる労使間の協定を結ばなければ時間外労働はおこなえません。36協定を結ぶことにより原則月45時間、年360時間を上限とする時間外労働が許可されます。
さらにこの時間を超えた労働が必要な場合は、特別条項付き36協定を締結しなければなりません。加えて、時間外労働に対しては決められた割増率を乗じた割増賃金の支払いが必要になります。
このように時間外労働は多数の観点で管理しなければならない事項があり、これらに対応するためには正確な労働時間の把握が必要です。
従業員が正確に打刻しないことにより、企業が法律に反してしまう可能性があるため、従業員にも打刻の重要性を理解してもらう必要があります。
関連記事:労働時間の上限は週40時間!法律違反にならないための基礎知識
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
5. 打刻忘れが発生するとどうなる?


打刻は従業員の勤務状況を把握するために、必要な作業です。しかし、毎日勤務しているとついつい打刻漏れが発生してしまう可能性があります。このような打刻漏れが発生してしまうと、人事労務担当者への負担増加や未払い残業代の発生が考えられます。
関連記事:労働時間を正しく理解してタイムカード打刻のミスをなくそう
5-1. 人事労務担当者の業務負担が増える
打刻忘れが発生してしまうと、該当の従業員に修正や確認を依頼しなければなりません。
従業員への修正や確認依頼を怠ってしまうと、その後の給与計算に影響を及ぼしてしまい、人事労務担当者の業務負担が増えてしまいます。
また、打刻忘れによって長時間残業が重なっている従業員の場合、人事労務担当者の確認が漏れてしまうと、過重労働などが原因となり離職につながるかもしれません。従業員が離職すると、退職手続きや新規採用の手続きなどの負担も発生することになります。
5-2. 未払いの残業代が発生してしまう
打刻忘れにより、従業員の勤務状況を正確に管理できていないと、未払いの残業代が発生する可能性があります。正しく打刻されていなければ管理できないのは当然ですが、従業員は残業代が少ないことに気が付きます。
そのまま放置してしまうと、裁判で未払い請求を起こされる可能性もあり、従業員の不信感や不満を引き起こすことになるので注意が必要です。
また、残業代の未払いは、例え支払った後であっても企業のブランドイメージを損なう恐れがあります。企業のブランドに傷がつくと、離職者が増えたり採用活動に影響が出たりするリスクも高まります。
6.打刻忘れを防止する方法
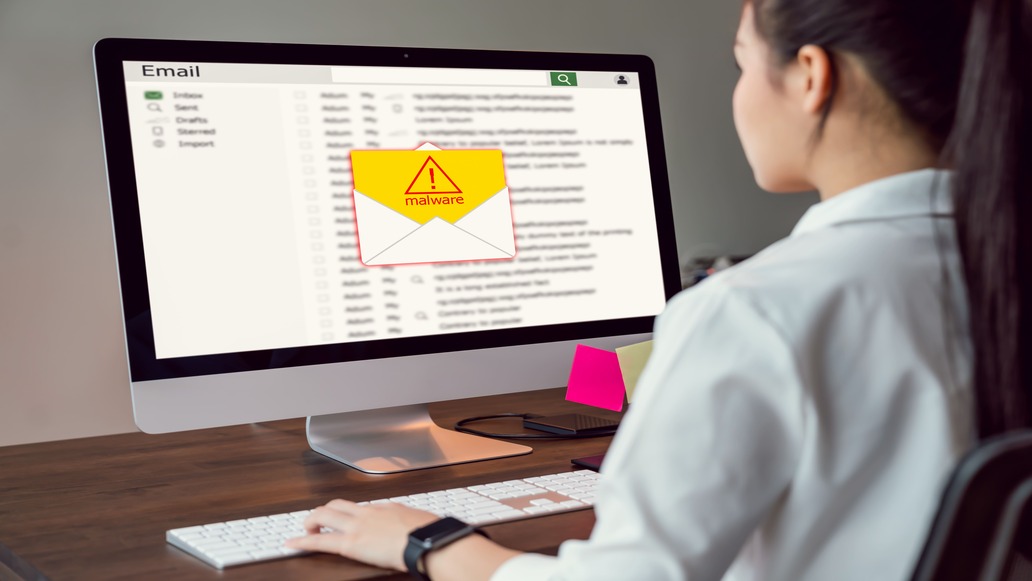
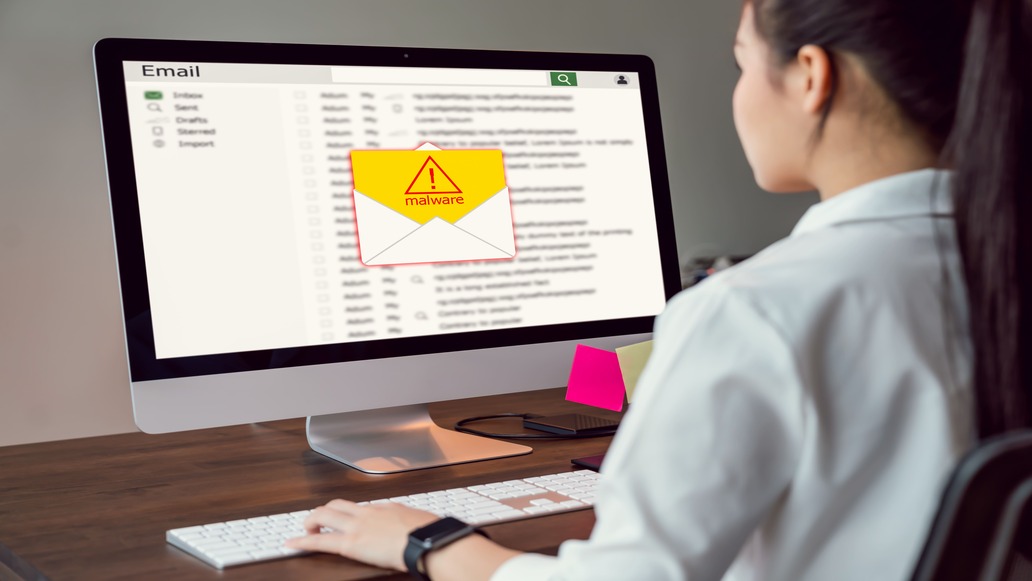
打刻忘れは、人事労務担当者に負担が発生してしまう、未払いの残業代が発生してしまうというデメリットにつながってしまいます。そのため、次のような工夫を凝らして打刻漏れを防止しましょう。
- 打刻しやすい場所にタイムレコーダーを設置する、打刻を啓発するポスターを設置する
- 従業員が打刻漏れがないかを確認してもらう
- ペナルティを設ける
- 勤怠管理システムを導入する
関連記事:従業員のタイムカード打刻忘れ対策として企業がおこなうべき3つのこと
関連記事:打刻忘れが起きてしまう原因とは?対策方法も合わせて解説
6-1. 打刻しやすい場所にタイムレコーダーを設置する
打刻忘れを防止するには、打刻しやすい場所にタイムレコーダーを設置しましょう。普段の業務では通らないような場所にタイムレコーダーを設置してしまうと、従業員が億劫になり打刻をしなくなってしまうかもしれません。そのため、従業員の動線に沿ってタイムレコーダーを設置するのがおすすめです。たとえば従業員の出入口や部署の出入口などにタイムレコーダーを設置しましょう。
タイムレコーダーを移動させるのが難しい場合は、打刻の重要性を啓発するポスターを設置するという方法もあります。更衣室のドアやロッカーの壁など、従業員の目につく場所に設置すると打刻忘れの防止に効果的です。ただし、同じポスターを貼ったままにしていると効果が薄れてしまうので、定期的に変化を加えるのがおすすめです。
6-2.従業員に打刻忘れがないかを確認してもらう
人事労務担当者だけで打刻忘れを確認していると、負担が大きく確認ミスのリスクも高くなります。このようなミスを防ぐには、従業員自身に打刻状況を確認してもらうという対策がベストです。
従業員自身が状況を確認すれば、担当者の業務負担やミスの軽減になるだけでなく、打刻への意識の高まりが期待できます。やり方としては、部署やグループごとに「確認時間」や「確認担当者」を決めて、毎日打刻状況をチェックしてもらうという方法がおすすめです。
6-3.ペナルティを設ける
タイムレコーダーの設置場所や打刻の啓蒙などをおこなっても改善がみられない場合は、ペナルティを設けることも検討してみましょう。打刻を忘れた場合は反省文の提出、繰り返し打刻を忘れている場合は始末書の提出などがペナルティとして挙げられます。
なお、ペナルティで減給処分を科すのであれば懲戒処分にあたるため、事前に従業員に周知しておく必要があります。ただし、いきなり減給処分とするのは従業員からの反発が起こる可能性があるので、戒告処分などを経てから科すのが一般的です。
また、1度のペナルティで減給できる上限は、1日の平均賃金の半分です。減給の総額は、月の賃金の10分の1を越えられないので、減給のペナルティを科す場合は金額に注意しましょう。
6-4.勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システム導入も、打刻漏れにつながります。勤怠管理システムのなかには打刻漏れを防ぐためにアラートが鳴るシステムがあります。このようなシステムであれば、打刻忘れを早い段階で把握できるでしょう。
また、スマホやタブレットから打刻できるシステムであれば、忙しい始業時であってもスムーズに打刻可能です。
従業員にとって、打刻は毎日行わなければならない業務です。しかし、職種や業務内容によっては外出が多く、打刻のためにわざわざオフィスに立ち寄らなければならない従業員もいるかもしれません。必要性を理解していても、不便な環境では継続が難しいものです。
勤怠管理システムであれば、オフィス勤務であっても現場に直行する勤務形態であっても、それぞれの働き方にあわせて打刻することが可能です。無理なく継続して打刻しやすい環境作りをすれば、打刻忘れを防ぐ効果が期待できます。
関連記事:タイムカード打刻を電子化!勤怠管理システムとの比較やシステム導入のメリットを解説
関連記事:勤怠管理システムを導入する目的とは?メリット・デメリットも確認
関連記事:外出先からでも正確な打刻を可能にする勤怠管理の3つのポイント
関連記事:建設業従業員の打刻に勤怠管理システムを活用する2つのメリット
7. 打刻忘れを防いで人事労務作業を効率的に進めよう


打刻は給与を正しく計算するため、従業員の適切な労務管理をするために欠かせません。打刻忘れが発生してしまうと、人事労務担当者の負担増加や、未払いの残業代の発生につながる可能性があります。
打刻忘れを防ぐには、タイムレコーダーをわかりやすい場所に設置する、ペナルティを設けるなどの対策が有効です。ただし、従業員任せの対策ではヒューマンエラーが起こることもあるので、さらに効果的な対策を取るのであれば勤怠管理システムを導入しましょう。
勤怠管理システムは、「打刻漏れがあればアラートが鳴る」「スマホやタブレットから打刻できる」など便利な機能が搭載されているので導入を検討してみることをおすすめします。
中抜けは、適切に扱わなければ労働時間集計や残業代の計算に誤りが発生するため、正しい管理方法を把握しておかなくてはなりません。
当サイトでは、中抜けの扱い方や法律的におさえておきたいポイントなど本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
中抜けを適切に管理したい方は、こちらから「中抜けの基本書」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25