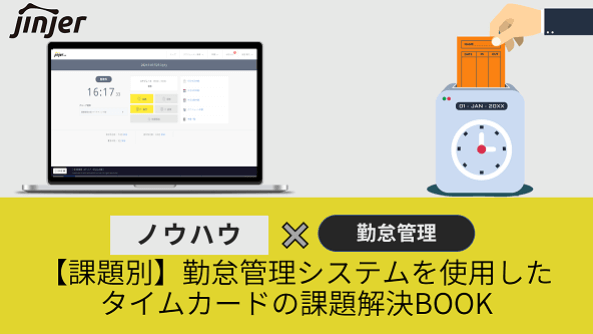打刻が重要な理由とは?打刻忘れが起きる原因や防止する方法も解説
更新日: 2024.7.25
公開日: 2019.12.20
OHSUGI

打刻は、労働環境における正確な時間管理や労働時間の記録を確保する上で非常に重要です。
正しい打刻がされないと正確な勤務時間が分からず、正しい給与計算ができなくなります。
また、従業員の労働時間が正確に把握できないことにより、過労や時間外労働の管理も難しくなっていくでしょう。
しかし、打刻を忘れる従業員は一定数存在し、打刻忘れをゼロにすることは困難です。
本記事では、打刻忘れが発生する根本的な原因や打刻忘れを減らす対策を中心に解説します。打刻忘れの根本的な原因を知り、対策の検討に役立てば幸いです。
関連記事:なぜ打刻は必要なのか?打刻忘れによるリスクを知り、必要性を理解しよう
目次
システムを利用した課題解決BOOK!
働き方改革が始まり、「タイムカードの勤怠管理は面倒な作業が多くてなんとかしたいけど、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入には、以下のようなメリットがあります。
・多様な打刻方法により、テレワークなどの働き方に柔軟に対応できる
・リアルタイムで労働時間を自動で集計できるため、月末の集計工数が削減される
・ワンクリックで給与ソフトに連携できる
働き方改革を成功させるため、ぜひ「【課題別】勤怠管理システムを使用した タイムカードの課題解決BOOK」をご参考ください。
1. 打刻とは?重要性を理解しよう
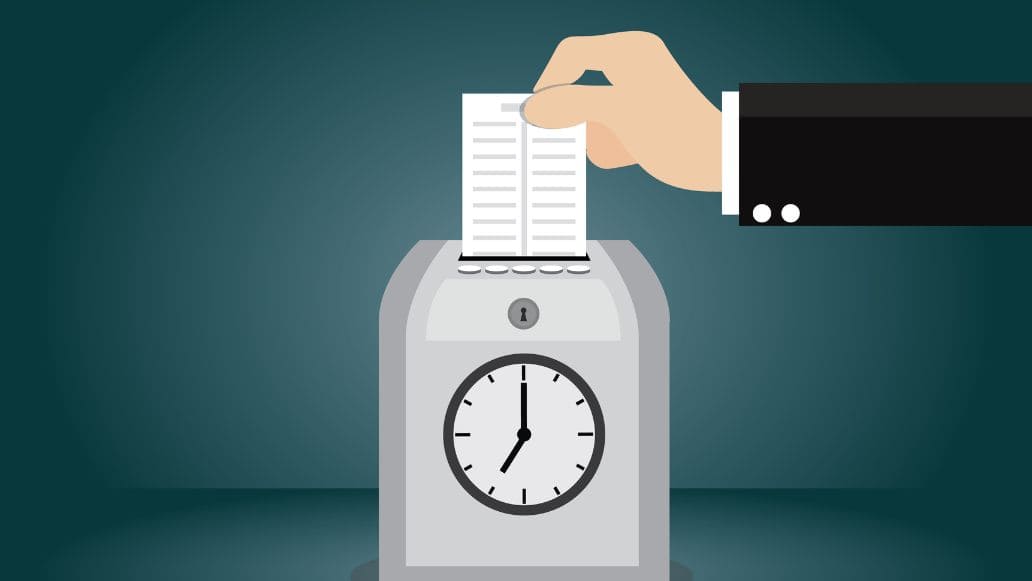
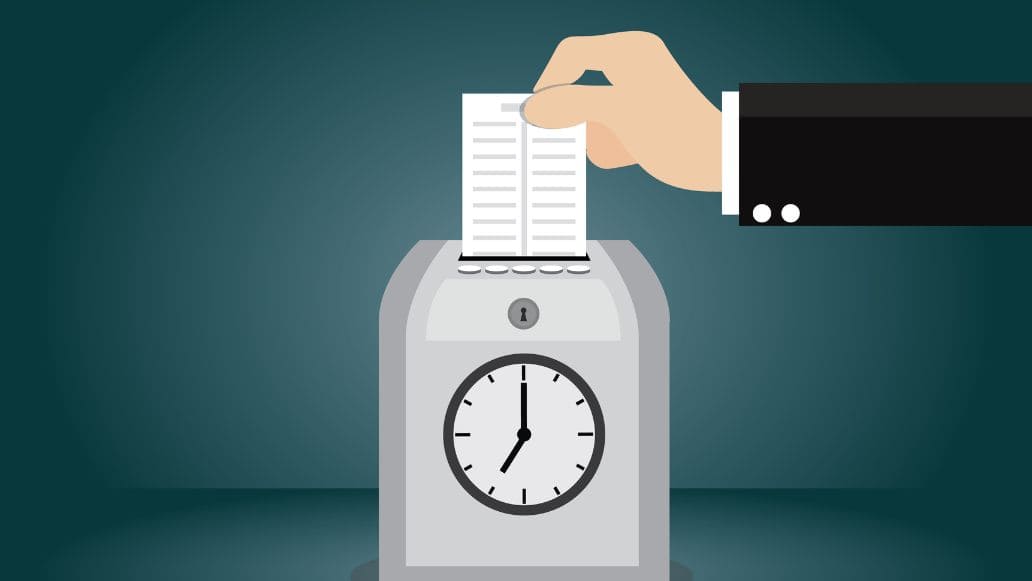
まずは打刻とは何か、その重要性を正しく理解しておきましょう。打刻の重要性がわかると、打刻忘れの深刻さも見えてきます。
1-1. 打刻とは出勤・退勤を記録するシステム
打刻とは、従業員の出勤と退勤を記録する作業やシステムを指します。打刻機にタイムカードを入れて打刻するシステムや、専用のアプリやシステムを使う方法が主流です。
企業によっては休憩の開始と終了も打刻し、適正な休憩時間がとれているか確認することもあります。
どのような形式であっても、打刻は勤務時間を正確に記録するために重要な作業です。
1-2. 打刻が重要な理由
勤務時間を把握するための打刻が重要な理由は、主に3つあります。いずれも非常に重要なポイントであるため、人事や労務担当者は理解しておきましょう。
①労働時間を正確に把握するため
勤務開始と終了や休憩時間を記録する打刻は、労働者の労働時間を正確に把握するために欠かせません。
打刻をしていないと「いつ・だれが・何時間働いているか」を把握することが困難になり、自己申告では虚偽申請や勘違いをはじめとした多くの問題が発生する恐れもあります。
労働時間を正確に把握して、労働者の働きすぎを防いで労使ともに公正な労働環境を守るために打刻は非常に重要な役割を担っています。
②給与計算を正しくおこなうため
前述したように打刻は労働時間を把握するために欠かせないシステムです。
労働時間の記録が正確であれば、勤務時間や残業時間が間違いなく管理でき、実態と相違のない給与計算が可能になります。
打刻がされていない場合は、残業したのにその時間が計算されていなかったり、反対に遅刻や早退をしたのにマイナスがされていなかったり、労使双方にとって多くのリスクが発生します。
③法令を遵守するため
労働基準法では、使用者は労働者の労働時間を適切に管理しなければならないと定められています。
適切な管理には、使用者による確認と記録や、タイムカードなどによる客観的な記録が求められます。打刻は後者の客観的な記録に該当するため、労働基準法を守るうえでも打刻は重要です。
2. 打刻忘れによる悪影響
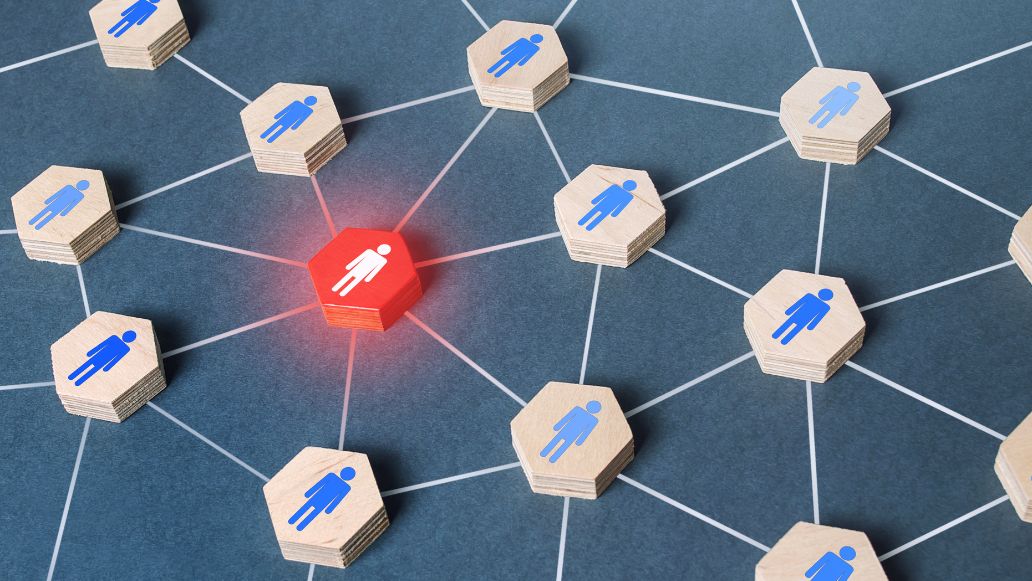
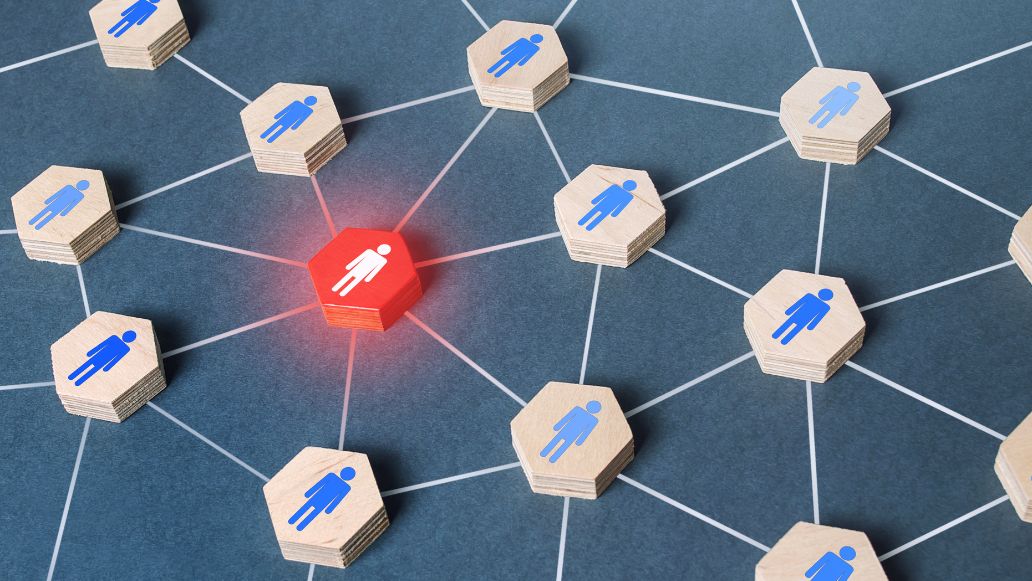
打刻忘れを防ぐには、まず打刻忘れよってどのような悪影響が発生するのかを知り、事前に従業員に周知しておくことが大切です。企業への影響と人事労務担当者への影響を解説します。
2-1.『打刻忘れ』が与える企業への影響
政府が熱心に進めている働き方改革により『労働安全衛生法』が改正され、2019年4月からすべての企業に対してパートやアルバイトなど雇用形態を問わずすべての従業員(高度プロフェッショナル人材を除く)の労働時間の把握が義務化されました。労働時間の把握の義務化には罰則はないものの、労働時間の上限規制を超えることになれば、罰則が生じます。
タイムカードの打刻忘れがあると、正確に労働時間を把握できず、労働時間の上限を超えてしまう恐れがあります。故意でなかったとしても罰則が発生する可能性があり、企業イメージの低下につながってしまうでしょう。
2-2.『打刻忘れ』が与える人事労務担当者への影響
タイムカードで勤怠管理をしている中で、打刻忘れや打刻ミスが多いと、通常でさえ給与計算をするために集計する作業が煩雑になります。さらに、ミスや修正をリカバリーする作業もプラスされます。
打刻忘れが増えれば負担も増加するため、業務が集中する月末の人事労務担当者への影響が非常に大きくなるでしょう。
3. 打刻忘れが発生する2つの理由
 打刻忘れが起きる原因として、大きく以下の3つが考えられます。
打刻忘れが起きる原因として、大きく以下の3つが考えられます。
- 従業員側の問題:業務が忙しすぎて打刻を忘れてしまう、十分にルーティン化がされていないなど。
- 環境の問題:タイムカードやタイムレコーダーの設置場所が目立たない、打刻方法が煩雑で分かりにくいなど。
- システム上の問題:タイムレコーダーが故障などの不具合で未打刻になってしまうなど。
東京都産業労働局による『労働時間管理に関する実態調査』によると、タイムカードで勤怠管理をしている企業は全体の過半数を超えています。
タイムカードは、レコーダーを設置するだけ導入ができ、使い方も比較的シンプルであるため導入しやすいシステムです。しかし、一方で『打刻忘れ』や『退勤打刻するはずが出勤打刻をしてしまう』など、打刻ミスが起こりやすい一面もあります。タイムカードによる管理をおこなう場合は、打刻忘れが起こらないように特に注意をしながら運用しなくてはいけません。
3-1. 従業員側の問題
打刻忘れでは、従業員側に問題があるケースも少なくありません。
よくあるのは、新入社員が打刻を忘れるケースです。打刻がまだルーティン化されておらず、うっかり忘れてしまうこともあるでしょう。
また、急なトラブルが発生して打刻を忘れてしまう、交通渋滞などにより始業時間ギリギリになって忘れてしまうなど、突発的な原因も挙げられます。
3-2. 環境やシステムの問題
打刻機の設置場所や打刻システムそのものに問題があり、打刻忘れを引き起こしている可能性もあります。
打刻機が目立たない場所や、奥まった場所にある場合は、目につかずに忘れてしまう人が増える原因になるかもしれません。
また、打刻する手間がかかって後回しにして忘れてしまう、打刻機やシステムに問題が発生していて打刻が正確にできないなど、システム側に問題があるケースも考えられます。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
4. 打刻忘れを防ぐ5つの方法
 タイムカードの打刻忘れをなくすための具体的な対策は、どのようなものがあるのでしょうか。人為的ミスが起こりやすいタイムカードでの勤怠管理を軸に、本項目では対策を5つ紹介します。
タイムカードの打刻忘れをなくすための具体的な対策は、どのようなものがあるのでしょうか。人為的ミスが起こりやすいタイムカードでの勤怠管理を軸に、本項目では対策を5つ紹介します。
4-1. 注意喚起のポスターを張り出す
アナログ的な方法ですが、従業員の目に付きやすい場所に『タイムカードの打刻忘れをしない』という注意喚起のポスターを張り出しましょう。
自分の席や身の回り、よく人が集まるような場所などにポスターを張り出して自然と目に入るようにすると効果的です。
ただし、長期間同じ場所に同じデザインのポスターを貼っていると景色の一部になってしまいます。ときどきポスターを貼りなおして、効果を維持するのがポイントです。
4-2. 出入り口に打刻の機械を設置する
出入り口や従業員が必ず通る通路など、目立つ場所に打刻機を設置するのも効果的です。
出勤時と退勤時にしか使わないため、隅の方に打刻機が置かれているケースが多々あります。そうした環境で打刻忘れが多い場合は、場所を変えるだけで改善するかもしれません。
ポスターと同様に視覚的な刺激で打刻のことを思い出させるとともに、打刻しやすい環境づくりにもつながります。
4-3. 打刻を習慣化しやすい形に変える
若い世代の従業員はタイムカードを打刻する習慣がまだ身についていないことがあります。
打刻を忘れないように注意喚起すると共に、使い慣れているスマートフォンを使った打刻や指紋認証、ICカードリーダーを利用した打刻など、簡単で受け入れやすい打刻方法に変えて改善を狙ってみましょう。
4-4. タイムカード打刻の確認者を決める
どのような打刻方法を採用したとしても、正確に打刻しているか確認できるのは人の目のみです。そのため、打刻の確認者を配置するのも効果的です。
例えば、部署単位で従業員の打刻履歴を確認する担当を決めておき、打刻をしているかどうかの最終チェックをおこなうことで、月末の集計の際に差し戻しの工数を減らすことができるでしょう。
また以下の記事では、上記の内容以外の具体的なルールを紹介しております。考えうる方法の中から最適解を選びたいという方は、こちらの記事をぜひご覧ください。
▶タイムカードで打刻ミスをなくすために用意しておきたい打刻ルールの具体例
4-5. 打刻の重要性を周知する
新入社員や若手社員は、打刻の重要性を正しく認識していないことがあります。打刻忘れをした場合、どのような問題が発生し、自分にはどのような不利益があるのか、正しく周知することも大切です。
重要性がわかれば打刻を軽視しなくなり、意識が改善して打刻忘れが減るはずです。
5. 打刻忘れが発生した際の対応
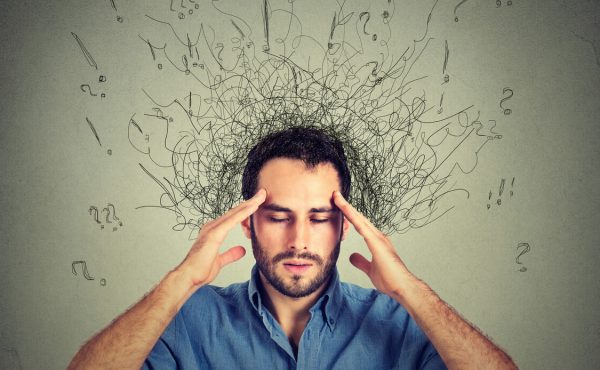 打刻忘れの防止策をとっていても、人為的ミスは起きてしまうものです。打刻忘れが起こった際に、勤怠管理者が取るべき対応や科すことができるペナルティを知っておきましょう。
打刻忘れの防止策をとっていても、人為的ミスは起きてしまうものです。打刻忘れが起こった際に、勤怠管理者が取るべき対応や科すことができるペナルティを知っておきましょう。
5-1. 必ず事実確認をおこなう
企業の人事担当者がタイムカードの打刻忘れに対処する際には、独断で判断して処理することは避けましょう。
打刻忘れをした本人へのヒアリングをし、事実確認をした上で打刻修正をおこないます。これによって、打刻を忘れた場合は従業員本人も面倒な作業が増えるという認識がうまれます。トラブル防止だけでなく、打刻忘れの予防にもつながるため、この点は徹底して守りましょう。
5-2. 事実に基づいて打刻修正をする
打刻漏れがあった場合は打刻修正が必要になります。その際に「打刻時間を訂正することは、労働時間の改ざんにあたるのではないか」と不安を感じることがあります。
打刻修正により労働時間が増える分には、従業員にとって不利益がないため特に問題はありません。しかし、減る場合には注意が必要です。残業代の未払い問題への発展や、賃金台帳に虚偽の記載をしたとして罪に問われる可能性があります。
打刻修正によってトラブルを起こさないためには、従業員にしっかりと事実確認をしてから打刻修正をする必要があります。また、手書きで修正する場合は本人確認に加えて、上長の許可も必要です。
【関連記事】タイムカードを押し忘れたら手書きはあり?手書き対応で注意したい3つのこと
5-3. 打刻忘れが再発しないための対策を講じる
打刻忘れが頻繁にある従業員に対しては、何らかのペナルティも必要かもしれません。
タイムカードの打刻を忘れた場合には、どのようなペナルティを従業員に課すことができるでしょうか。ペナルティによって減給する場合は労働基準法第91条でその上限金額が定められています。
1回につき減給できるのは「平均日給の半分程度」まで、総額も「給料1ヶ月分の10分の1」に収めることが定められています。打刻忘れを理由に減給する場合は、就業規則に定めたうえで従業員にアナウンスしておきましょう。
企業によってペナルティの内容はさまざまで、反省文や始末書などの提出を求める企業も多いようです。タイムカードの打刻忘れに対してペナルティを科す場合は、あらかじめルール化して就業規則に明記し、従業員への周知をしておく必要があります。
また、タイムカードの打刻忘れでその日1日を欠勤扱いにすることは違法になります。
これはアルバイトやパートタイムの従業員でも同様です。必ず事実確認をし、実際に働いた労働時間分の報酬を支払いましょう。
▼タイムカードの打刻漏れに関する記事を見ている方にオススメの記事
タイムカードの打刻忘れの正しい対応を解説!打刻漏れを防ぐための対策をご紹介
6. 勤怠管理システムなら打刻漏れの防止や業務負担の軽減が可能

これまでご紹介してきたような打刻忘れへの対応は、有効ではあるものの完璧ではありません。タイムカードでは間違いのない勤怠管理をすることは難しいです。
企業が従業員の勤怠管理を正しくおこなうためには、勤怠管理のシステムを導入することをおすすめします。勤怠管理システムは、人事や総務担当者の業務負担を大幅に減らします。
本項目では、タイムカードから勤怠管理システムに移行すると、どのようなメリットがあるのか紹介していきます。
6-1. 打刻忘れや不正打刻を減らすことができる
従業員の勤怠管理をする上で大切なことは、正確な労働時間の把握です。従業員の勤怠情報を把握できれば、間違いのない給与計算は難しくありません。
しかし、タイムカードは機械に通すだけで簡単に誰にでも打刻することが可能です。この誰にでも打刻できるという点が、労働時間を把握する上での問題になります。
例えば、『遅刻しそうな際に同僚にタイムカードの打刻をお願いする』、『タイムカードで退勤を打刻してから残業をする』などの不正が簡単にできてしまいます。
誰も見ていない場所でおこなわれていたとすれば、正確な労働時間の把握は難しいでしょう。
勤怠管理システムではこうした不正が発生しにくく、打刻忘れに対するアラートも設定できます。また、出退勤の履歴を勤怠管理システムで確認できるようになると、管理する側の負担も軽減され、効率よく集計作業ができるようになるでしょう。
【関連記事】従業員がタイムカードを押し忘れる理由で意外と多い3つのポイント
6-2. 従業員の正確な労働時間を把握できる
例えば、営業担当者は外回りが多いため、直行直帰をする可能性があります。この場合、会社で直接打刻することができないため、正確な労働時間の把握が難しくなります。
管理不足によるオーバーワークも発生しやすく、従業員にとっても企業にとっても良い状況ではありません。
出先でもスマートフォンやタブレットから勤怠管理ができるシステムを導入すれば、こうした問題は解決できます。
6-3. 業務の効率化を実現できる
会社の規模が大きく、従業員の数も多くなるとタイムカードの場合は集計作業に多くの工数がかかってしまいます。
タイムカードの打刻忘れやミスなどがあった場合は、通常の集計以外に確認や修正作業が増えて、更に手間と時間が必要になります。勤怠管理のシステムを導入すれば、集計ミスを防ぎ、月中の従業員の労働時間を把握できます。
集計や給与計算の負担も減り、人事や総務の担当者の業務を効率化できるでしょう。
また、シフト勤務を採用している企業の場合、労働時間の把握が煩雑な作業になりがちです。紙ベースのシフト表を使っている場合は、さらに作業が増えます。
勤怠管理システムであればシフト変更への対応や給与計算も自動でおこなえるため、大幅に業務の効率化が可能です。
当サイトでは、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に勤怠管理をどのように効率化できるのか解説した資料を無料で配布しております。タイムカードで管理している際に起きうる課題と照らし合わせて説明しているため、システムの導入でどのように変わるのか具体的にイメージしていただけるでしょう。打刻忘れやずれがシステムの導入によって低減されそうだと感じられたご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
7. タイムカードの打刻を習慣化して給与計算の正確性を維持しよう
 タイムカードで勤怠管理をすることは、『打刻忘れ』の他にも打刻ミス、不正打刻などのリスクを伴うことになります。
タイムカードで勤怠管理をすることは、『打刻忘れ』の他にも打刻ミス、不正打刻などのリスクを伴うことになります。
働き方改革の影響も受け、正確な労働時間の把握が企業の義務になり、今後の勤怠管理はますます重要になります。
勤怠管理における企業のリスクを減らすためにも、しっかりとした勤怠管理が必要になります。タイムカードの運用から勤怠管理システムに移行することで、人事担当者にとっても従業員にとっても有益で、より管理の正確性や効率化を図ることができるでしょう。
システムを利用した課題解決BOOK!
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25