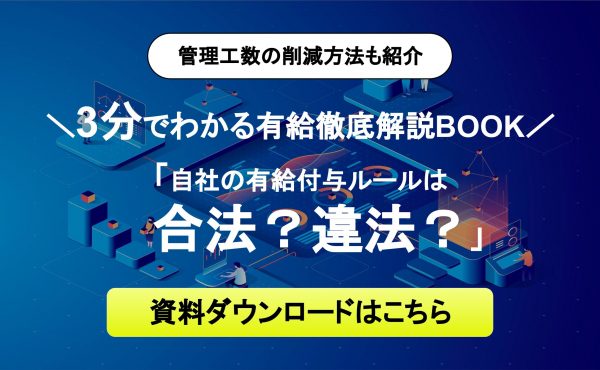有給休暇の買い取りは違法?退職時の対応やトラブル事例を解説
更新日: 2024.9.26
公開日: 2021.9.1
OHSUGI

有給休暇は、心身のリフレッシュを図り、働きすぎを防止する目的で、雇用形態にかかわらず一定の条件を満たした労働者に付与することが義務化されています。
しかし、なかには休むタイミングがなかったり退職までに消化しきれなかったりして、「有給休暇はいらないから買い取ってほしい」と従業員が有給休暇の買い取りを希望する場合があります。このような場合、企業はどのような対応をすれば良いのでしょうか。
本記事では有給休暇の買い取りについて、買い取りの違法性や買い取りをする場合の対応方法・注意点について解説します。有給休暇の買い取りに関するルールをしっかりと把握し、トラブルを未然に防ぎましょう。
関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 有給休暇の買い取りは違法になる場合がある

まずは、有給休暇の買い取りが可能かどうかをみていきましょう。
大前提として、有給休暇の買い取りは原則違法です。なぜなら、有給休暇の買い取りは本来の制度の趣旨に反する行為であるためです。
有給休暇は本来、年に付与された日数を取得させて従業員の心身のリフレッシュを図る目的で設けられている制度です。そのため、買い取って金銭にかえることは本来の働きすぎを防ぎ「心身のリフレッシュを図る」という目的から逸脱しています。
多忙などの理由でなかなか有給休暇を消化できないため、有給休暇を買い取ってほしいと考える従業員もなかにはいるでしょう。
しかし、有給休暇の買い取りは労働者が休む機会を奪うことになるため、原則禁止されています。実際、昭和30年11月30日の行政通達(基収4718号)では、労働基準法第39条(法第39条)を挙げ、以下のように言及されています。
「年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である(昭30.11.30基収4718号)。」
これにより、会社が強制することはもちろん、労働者の同意があったとしても有給休暇の買い取りは原則として違法となるのです。
ただし、すべての有給休暇の買い取りが違法というわけではなく、一部のケースに関しては買い取りが許可されています。次章で買い取りが可能な有給休暇に関して詳しく説明します。
関連記事:有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説
2. 有給休暇の買い取りが許されるケース

前項で有給休暇の買い取りは原則違法と紹介しましたが、場合によっては買い取りが可能なケースもあります。ここでは、有給休暇の買い取りが違法にならない3つのケースについて説明します。
2-1. 退職時に有給が余る場合
退職するときに有給休暇が余っているときは、企業に買い取ってもらうことが可能です。この場合は、従業員と企業がよく話し合ったうえ、双方の同意があれば買い取りが違法になることはありません。
退職が決まると、引き継ぎや退職の準備で有給休暇を消化することが難しくなります。有給休暇は労働者の権利ですが、企業は退職する従業員から未消化日数分の有給休暇の買い取りを求められた場合、会社は買い取る義務まではありません。
2-2. 有給日数が法定よりも多い場合
年次有給休暇は、勤続日数に応じて6ヵ月で10日、1年6ヵ月で11日という風に毎年増えていきます。この日数は法律で定められた休日日数であるため、買い取りをすることはできません。
しかし、福利厚生の一環などにより労働基準法で定めているよりも多めに有給休暇を与えている場合は、年次有給休暇を超えた分の日数を買い取ることができます。多めに付与された有給休暇は、法律の制限を受けないものであるためです。
例えば、年次有給休暇が10日で福利厚生として定めた休暇が5日あるときは、10日間は有給休暇を消化してもらわなければなりませんが、5日間は買い取りが可能ということになります。
2-3. 期限が切れた場合
年次有給休暇は、付与されてから2年を過ぎると消失してしまいます。1年間は繰り越せますが、繰り越しても有給休暇が余ってしまった場合は、効力を失う有給休暇を買い取ってもらうことが可能です。ただし、このケースは会社側が買い取りを拒否できます。
ただし、働き方改革法案の成立によって、企業は最低でも年間5日の有給休暇を消化させることが義務付けられました。そのため、「有給休暇が余ってしまう」ということは今後減っていくかもしれません。
なお、有給の繰り越しの仕組みや保有できる最大日数について確認しておきたい方には、以下の記事がおすすめです。
3. 有給休暇買い取り時の企業側のメリット


ここまで有給の買い取りについて解説してきましたが、買い取りは一見すると従業員側にばかりメリットがあるように感じるかもしれません。しかし実は、企業側にも大きなメリットが2点あります。
3-1. 社会保険料の負担を軽減できる可能性がある
従業員の退職が決定したとしても、在職中、つまり有給休暇取得中は、社会保険料を負担しなければなりません。しかし、残りの有給休暇を買い取り退職を早めることにすることで、在職期間が短くなる分負担額を減らすことが可能です。
買取金額は「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬月額」のいずれかになりますが、あらかじめ就業規則で定めておかなければなりません。そのため、まずは自社の買取金額がいくらになるのか確認し、負担額との差額でより安く抑えられる方を選ぶのが合理的でしょう。
3-2. 労使間トラブルを回避できる
有給休暇の取得は、労使間のトラブルで起きやすい内容になります。
有給休暇取得中は雇用関係が継続しているので、従業員は労働者としての権利を有しています。そのため、従業員が退職の取り消しを求めるなどのトラブルが発生するリスクもあります。
未消化の日数が、退職日までの期間以上に残っている場合は、退職までに消化しきることができません。
本来、有給取得に会社の許可は不要のため、そこまで未消化で残っている場合は、職場内が有給の取りづらい環境になっていることが考えられます。溜まってしまったことはしょうがないので、そのまま退社させることで起こりえるトラブルをあらかじめ想定し、どのように対処するのが最適かを考えることが重要です。
例えば、有給休暇を巡って裁判沙汰になってしまうと、会社のブランドイメージの低下や本来考えなくも良い業務に追われる可能性も無きにしも非ずです。
このような問題も、有給の未消化分を買い取って従業員に円満に退職してもらうことで、避けることができるでしょう。
4. 有給を買い取る際の計算方法と金額相場


前項でも言及しましたが、有給休暇の買い取り額についてはあらかじめ就業規則や書面で規定しておく必要があります。具体的な買い取り金額の計算方法は、以下の3パターンのいずれかであるケースが多いです。
4-1. 通常賃金での計算方法
3つの計算方法のうち、多くの企業で取り入られているのが通常賃金での計算方法です。月給制や日給制、時給制によってそれぞれ計算方法が異なります。
- 月給制の場合:(月給額÷所定労働日数)×有給買取日数
- 日給制の場合:日給額×有給買取日数
- 時給制の場合:(時給額×1日の所定労働時間)×有給買取日数
計算方法が簡単であるだけでなく、従業員側からしてもいつも通りの賃金で支払われるため、最もトラブルが起こりにくい計算方法だといえるでしょう。
4-2. 平均賃金での計算方法
平均賃金での計算方法は、直近3ヵ月の賃金の合計額を休日も含めた3ヵ月の総日数で割り引いて単価を求める計算方法です。ただし、休業などによって直近3ヵ月の賃金が少ない場合、この方法だと単価が非常に低くなる恐れがあります。そのため、この計算方法には最低保証額が決められています。最低保証額の求め方は以下のとおりです。
直近3ヵ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×0.6
最低保証額を求める際は、総日数ではなく実際に働いた労働日数で割るのがポイントです。平均賃金で計算する際は、この最低保証額を下回らないよう注意しなくてはいけません。
4-3. 標準報酬月額での計算方法
保険料額を算定する際の標準報酬月額を用いて計算することも可能です。標準報酬月額を月の日数で割ることで、1日当たりの金額を求めることができます。
健康保険に加入している従業員であれば計算が簡素化されて便利ですが、未加入である場合は標準報酬日額を一から算出しなくてはいけないため、逆に計算が面倒となることもあります。
なお、標準報酬月額での計算方法は、労使協定をあらかじめ結んでおく必要があるため、合わせて注意しましょう。
記事:有給休暇取得日の賃金計算で知っておきたい3つのポイント
4-4. 有給休暇の買い取り金額相場
有給休暇の買い取り額は従業員の賃金によって金額が変動するため、明確な相場といったものがありません。上述でも触れましたが、一般的には通常賃金にもとづいた計算方法を取っている企業が多いようです。
また企業によっては、「正社員は1万円、契約社員は8千円」などあらかじめ就業規則に明記している企業もあります。
5. 有給休暇買い取り時の注意点


有給休暇を買い取る際は、事前に気をつけておきたいポイントがいくつかあります。次に順を追って確認していきましょう。
5-1. 有給休暇の買い取り予約は違法となる
従業員に有給休暇の買い取りを予約し、有給休暇の日数を減じるまたは与えないことは法律で禁止されているため注意しましょう。
有給休暇には労働者の心身をリフレッシュさせる目的があるため、本来の趣旨に従って取得させることが原則です。退職など上述で挙げた特別な理由がない限りは、計画的に有給を取得させるようにしましょう。
5-2. 有給休暇の買い取りは義務ではない
上述で解説したとおり、有給休暇の買い取りは法律で義務づけらたものではありません。有給休暇が金銭で売買されるようになってしまうと、労働者の心身の健康が危ぶまれる事態に陥ってしまうためです。
そのため、従業員から「有給休暇を買い取ってほしい」と要求されても、上述で挙げた特別なケースを除いて原則断ることができます。
5-3. 有給休暇の買い取り時の計上に注意とデメリット
有給休暇を買い取った際は、計上の仕方が異なる点も注意すべきポイントです。在職中に支払う場合は給与所得の賞与、退職の起因して支払う場合は退職所得として計上します。
また、賞与で処理する場合は、賞与支払届の届け出も同時におこなわなくてはいけません。支給日から5日以内に所轄の年金事務所や事務センターへ忘れずに届け出るようにしましょう。
6. 有給休暇の買い取りでよくあるトラブルと対策


有給休暇の買い取りをおこなうときは、トラブルが生じやすいため注意しましょう。最後に、よくあるトラブルと対策法について解説します。
6-1. 買い取り可否についてのトラブル
そもそも、有給休暇の買い取りが可能かどうかを知らない従業員は多いです。あとになって「買い取りができると知らなかった」といったトラブルが生じることがないように、あらかじめ買い取りの可否についての書面を作成し、労働者と交わしておきましょう。就業規則に有給の買取について記載しておくこともおすすめです。
作成するのは合意書や誓約書、雇用契約書などの形式を問いませんが、基本的には以下の内容を記載しておく必要があります。
- 買い取りの対象となる有給休暇
- 有給休暇の買い取り金額
- 支払日
- 支払の方法
また、実際に買い取りするときは書面に条件を記載し、双方に認識の違いがないことを確認しておくことが大切です。
6-2. 買い取り金額に関するトラブル
有給休暇の買い取り金額には、法律上の決まりがありません。そのため、企業は自社の基準に沿って有給休暇の買い取り金額を決定できます。
しかし、買い取り金額を有給休暇消化時の給与よりも低く設定している場合、金額が原因でトラブルに発展する可能性が高いため、注意しましょう。
正しい計算方法については上述しておりますので、そちらをご確認ください。
6-3. 税法上のトラブル
有給休暇を買い取るときは、税務処理を間違えるトラブルが起きやすいため注意しましょう。企業は、買い取った有給の税法上の扱いを理解しておくことが大切です。
退職にともなう有給休暇の買い取りは、退職することに起因して支払われる賃金であると考えられるため、「退職所得」扱いになります。このほかのケースの場合は、「給与所得」扱いです。本来は有給休暇の消化時に支払う給与であったことを考えると、納得しやすいでしょう。
また、従業員にもあらかじめこのことを周知しておくと、混乱が生じにくくなります。
7. 有給休暇の正しい知識をつけてトラブルのない買い取りを


労働者が休暇を取る権利である有給休暇は、原則として買い取ることができません。しかし、「退職時に有給休暇が余った」「年次有給休暇よりも多い日数を付与している」「消滅してしまう」といった場合は、買い取ることができます。
有給休暇の買い取りは、従業員と企業で認識をすり合わせておかないとトラブルが生じやすいため注意が必要です。スムーズな買い取りができるように、あらかじめ書面などで詳しい条件を提示しておくことが大切です。
関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
有給休暇の関連記事
-


時季変更権とは?行使するための条件や注意点を徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.10.18
-


時季変更権は退職時まで行使できる?認められないケースとは
勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.09.26
-

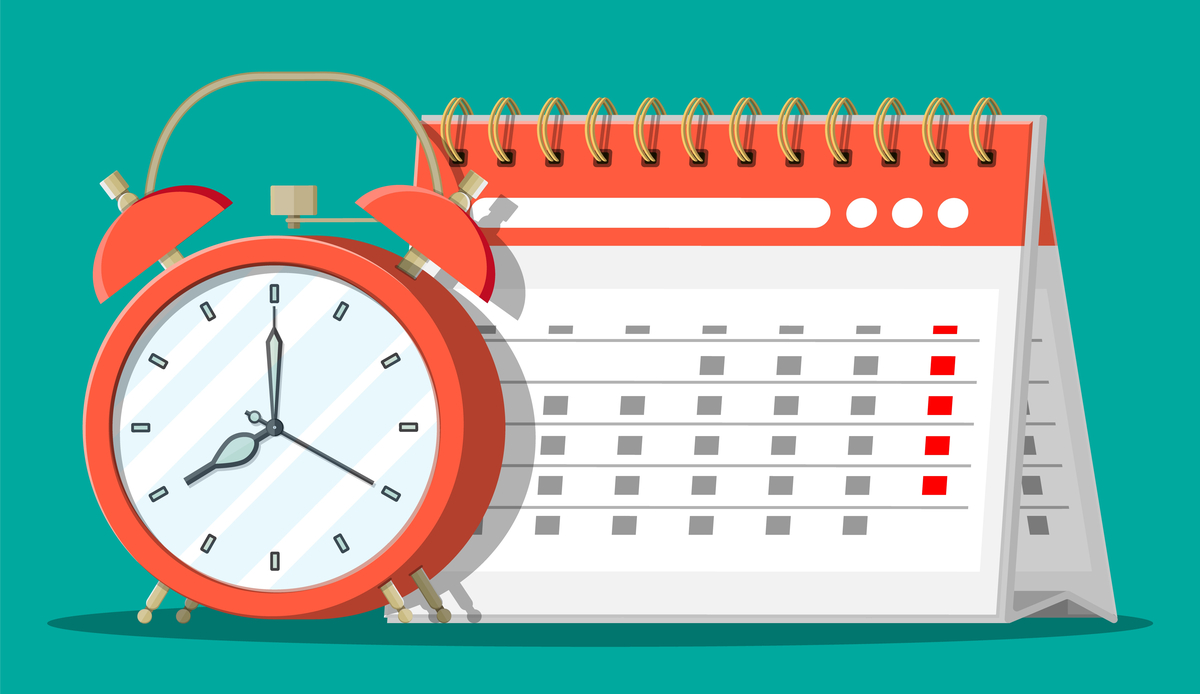
有給休暇の前借りは違法になる?従業員から依頼された場合の対応方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.03更新日:2024.09.26