有給休暇義務化のペナルティを徹底解説!労働者とのトラブルを回避する3つの対策

2019年4月に働き方改革関連法が施行され、有給休暇を取得して、1年以内に5日間の有給休暇を取得することが義務化されました。これに対して企業が必要な措置を講じなかった場合、ペナルティが科されます。
何も対策をしていないと、「今は繁忙期だから、有給休暇を後にズラしてほしい」「もうすぐ有給休暇を取得して1年経つけど、まだ1日も有給休暇を取っていない」といった事態になり、ペナルティを受けてしまうかもしれません。
今回は、有給休暇取得の義務化に関連する罰則や、ペナルティを回避するために効果的な方法をわかりやすく解説します。
関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説
2019年4月より有給休暇の年5日取得が義務化されました。
しかし、以下のような人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
・有給の取得が義務化されたのは知っているが、特に細かい社内ルールを設けて管理はしていなかった…
・どうやって有給を管理していけば違法にならないのかよくわかっていない…
・そもそも義務化の内容について細かいルールを知らない…
そのような人事担当者様に向け、当サイトでは年次有給休暇の義務化についてまとめた資料「3分でわかる!有休休暇」を無料で配布しております。
資料では、有給休暇関する改正労働基準法の内容と、それに対して行うべき管理、取得義務化に関してよくある疑問とその回答などを紹介しておりますので、社内の有休管理に問題がないか確認する際にぜひご利用ください。
目次
1. 有給休暇取得の義務化で知っておくべきペナルティ
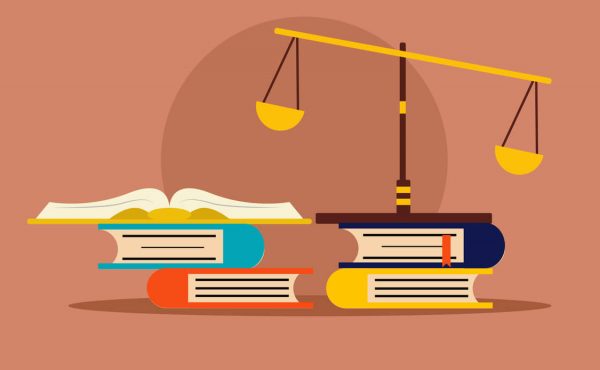
2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法のなかの一つに、「有給休暇取得の義務化」があります。この有給休暇取得の義務化を守らなかった場合、労働基準法の2つの条項に違反する可能性があります。
ここでは、有給取得の義務化関して発生する「違反に該当する内容」「ペナルティの内容」をご紹介します。
1-1. ポイント①:年5日以上、有給休暇を取得していない
労働基準法第39条第7項に、有給休暇取得日数が10日以上の労働者には、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇の取得が義務付けられています。
違反すると、労働基準法第120条1項に基づき、違反者1人につき30万円以下の罰金が使用者に科されます。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)第三十九条第七項(省略)の規定に違反した者
仮に100名の従業員が未取得であった場合、最大で3,000万円の罰金を支払わなくてはいけません。会社にとっては大きな損失となるため、必ず全従業員に取得させる必要があるでしょう。
1-2. ポイント②:時季指定が就業規則に記載されていない
労働基準法第39条第7項には、「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」と記述があります。この記述は、取得が義務付けられている5日間に関しては、あらかじめ取得日を定める必要があるという意味です。
ただし、従業員数が10人を超える企業が、従業員の有給休暇の時季指定をおこなう場合、あらかじめ就業規則への記載が義務づけられています。
もし就業規則に記載せずに時季指定の権利を行使した場合、労働基準法第89条の規定に違反し、1件につき30万円以下の罰金が科されます。
年5日以上の有休取得は、このような決まりを厳守したうえでおこなわなければなりません。
「有休の取得が義務化したことは知っていたが、自社のルールがきちんと対応しきれているか不安」という方に向け、当サイトでは有給休暇の年5日取得を含め、働き方改革に対応した勤怠管理対策について解説した資料をご用意いたしました。無料で配布しておりますので、有休取得の義務化への対応に不安のある担当者様は、こちらよりダウンロードしてご確認ください。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項・・・引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説
関連記事:有給休暇は消滅する?時効や未消化分の取り扱いの注意点
2. 時季変更権による有給休暇取得日の調整

「今は、忙しい時期だから、有給休暇の取得を後にズラしてほしい・・・」
このように感じるときもあるのではないでしょうか。労働者から有給休暇の申請をあった場合、基本的には拒否することはできません。
しかし、業務の運営に著しい支障をきたす場合には、企業は時季変更権を使うことができます。時季変更権とは、労働者が申請してきた日を、他の日に変更してもらうことです。
「業務の運営に著しい支障をきたす」とは、特定の労働者じゃないとできない重要な業務を任せていて、その業務が進まなければ、経営や事業に支障が出る場合です。
【労働基準法第39条第5項】
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
時季変更権を使用できるケースは限られており、場合によっては従業員とトラブルに発展することもあります。従業員から理解を得られやすくするためにも、就業規則に有給休暇や時期変更権について記載しておくことが必要です。
関連記事:年次有給休暇義務化にともなう管理簿とは?作成方法と保存期間を解説
3. 有給休暇義務化の対象

有給休暇取得義務の対象となるのは、年に10日以上の有給休暇が付与されているすべての労働者です。労働者というのが正社員だけではないという点に注意しましょう。パートやアルバイトであっても、年に10日以上有給が付与されていれば、取得義務の対象となります。
なお、有給休暇が年に10日以上付与されるタイミングは次の4とおりです。その後も雇用条件が変わらない限り、毎年10日以上付与されます。
- 入社後6か月継続勤務し、6か月間の全労働日の8割以上出勤した正社員
- 入社後6か月継続勤務し、6か月間の全労働日の8割以上出勤した週30時間以上のパート・アルバイト
- 入社後3年半以上勤務の週4日出勤(週30時間未満)のパート・アルバイト
- 入社後5年半以上勤務の週3日出勤(週30時間未満)のパート・アルバイト
上記いずれかの条件を満たす労働者に対しては、雇用形態に関係なく年間5日以上は有給休暇を取得させなくてはいけません。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
4. ペナルティや労働者とのトラブルを回避するためのポイント

企業へのペナルティや従業員とのトラブルを回避するためには、有給休暇の取得状況を正確に把握し、労働者と良好な関係を築き、年5日分の年休を計画的に消化してもらうことが大切です。
ここでは、ペナルティや労働者とのトラブルを回避するためのポイントをご紹介します。
4-1. 「計画年休」の実施
計画年休とは、企業側が労働者の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる制度です。計画年休を実施することで、企業が意図しない有給休暇の取得を防ぐことができます。
たとえば、夏季休暇や年末年始の休暇にプラスする計画年休です。休みを固めることで、事業への影響を最小限に抑えることができます。
しかし、労働者と相談した上で計画年休を実施しないと、トラブルに発展する恐れがあります。そのため、注意が必要です。
4-2. 「年次有給休暇取得計画表」を作成する
有給休暇の取得状況を推進するためには、「年次有給休暇取得計画表」を作成し、社内で情報共有をおこなうことが効果的です。年次有給休暇取得計画表とは、部署やグループごとの年休取得数や取得予定を一覧化した表を指します。
年次有給休暇取得計画表を社内で共有することで、従業員一人ひとりの取得状況が可視化され、互いのスケジュールを調整しやすい環境を作ることができます。
4-3. 従業員と良好な関係性を築く
時季変更権の行使は、「業務の運営に著しい支障をきたす場合」と決まっています。そのため、多くのケースでは時季変更権を行使することは難しいでしょう。
つまり、有給休暇取得日の変更は、労働者の判断にゆだねられます。時季変更権を行使せずに有給休暇の変更に応じてもらうためにも、日頃から従業員との良好な関係を築くことが大切だといえるでしょう。
関連記事:労働基準法で義務化された有給休暇消化を従業員に促す3つの方法
5. 有給休暇の取得を促しペナルティを回避しよう

今回は、有給休暇取得の義務化のペナルティやその回避方法について解説しました。
2019年4月の働き方改革関連法の施行により、従業員に年5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。違反した場合は1人あたり30万円以下の罰金が科されるため、違反者が多いと大きなペナルティとなる可能性があります。
「計画年休」や、「年次有給休暇取得計画表の作成」、「従業員と良好な関係性を築く」などの対策を講じて、企業にも、労働者にも良い形で有給休暇を消化しましょう。
関連記事:【有給がない!?】有給休暇なしの会社は違法?有給がもらえない時の対処法|LibertyWorks
2019年4月より有給休暇の年5日取得が義務化されました。
しかし、以下のような人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
・有給の取得が義務化されたのは知っているが、特に細かい社内ルールを設けて管理はしていなかった…
・どうやって有給を管理していけば違法にならないのかよくわかっていない…
・そもそも義務化の内容について細かいルールを知らない…
そのような人事担当者様に向け、当サイトでは年次有給休暇の義務化についてまとめた資料「3分でわかる!有休休暇」を無料で配布しております。
資料では、有給休暇関する改正労働基準法の内容と、それに対して行うべき管理、取得義務化に関してよくある疑問とその回答などを紹介しておりますので、社内の有休管理に問題がないか確認する際にぜひご利用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25




















