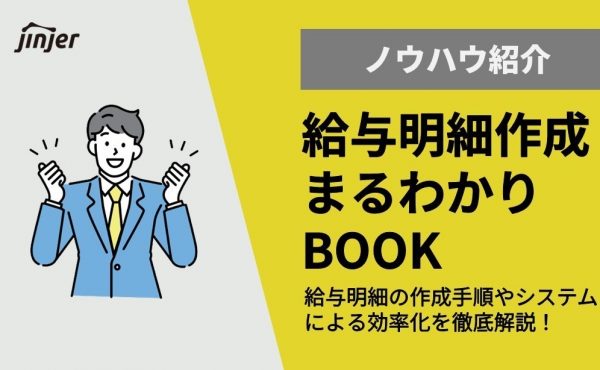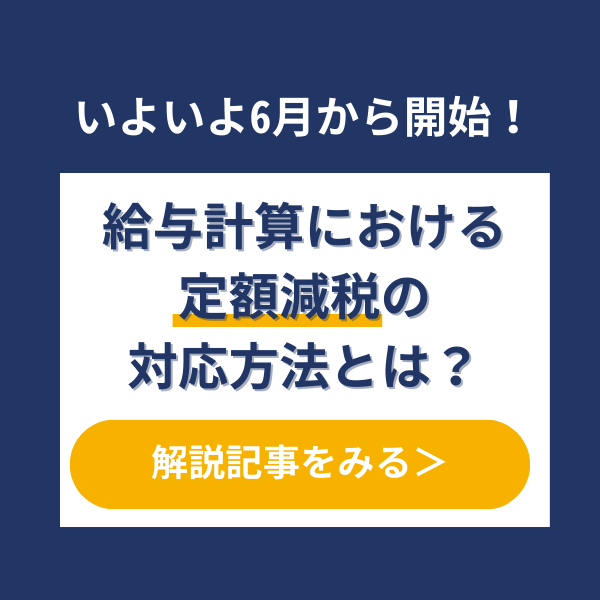給与明細の作成方法を解説!ツールやエクセルで効率的に作成するには?
更新日: 2024.5.8
公開日: 2021.11.16
OHSUGI
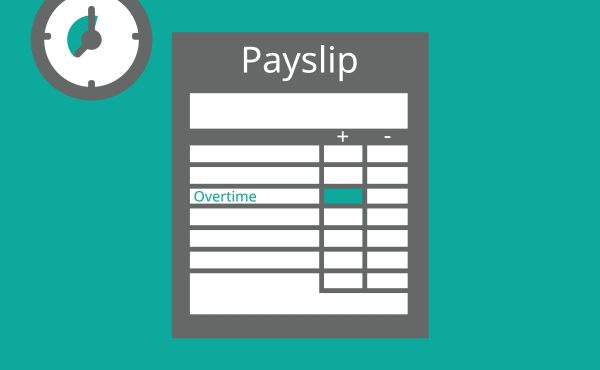
給与明細は、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿の法定三帳簿とは異なり、労働基準法のうえでは記載方法が定められていません。
しかし、社会保険料や所得税などの控除項目は従業員に通知することが所得税法のうえで義務付けられているので、給与明細の発行および記載は必要です。
この記事では、給与明細の作成に必要なものや明細に記載する基本事項・作成方法や効率的に作成するコツを紹介します。
▼給与明細について詳しく知りたい方はこちら
給与明細とは?発行の必要性や記載する項目を詳しく紹介
目次
毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
そこで本資料では、給与明細の複雑な作成ステップやその一連のフローをシステムの導入により、どのように効率化できるかなどを、実際の管理画面をお見せしながら解説しております。
「給与明細関連の業務を自動化したい」
「いつでも従業員が給与明細を見れるようにしたい」
このような悩みを抱えている担当者の方は、「給与明細作成まるわかりBOOK」をぜひご覧ください。
1. 給与明細の作成はなぜ必要?
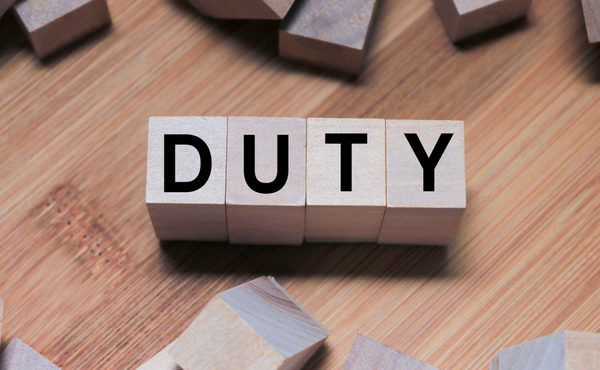
給与明細は、労働基準法のうえでは作成の義務はありませんが、所得税法など他の法律のうえでは給与明細や計算書を作成し交付することが義務付けられています。
企業の観点と従業員の観点の2つの面から給与明細の作成義務について解説します。
1-1. 企業の義務
所得税法第231条では、給与明細の作成について「給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならない」と定めています。したがって、企業は従業員の給与明細を作成し、交付する義務があるのです。
また、所得税法以外にも、健康保険法や厚生年金法、労働保険徴収法では、「計算書を作成して控除額を通知する義務」が定められています。
なお、労働基準法では、給与明細発行の義務について明文化されている記載はありません。
このように、従業員に関する対応は労働基準法以外でも義務付けられている場合があるため、注意しましょう。
また、電子データにて給与明細の交付をおこなう場合には、従業員の承諾を得る必要があります。
万が一のトラブルを避けるためにも、適切なフローを経て、給与明細の交付をおこないましょう。
関連記事:給与明細の電子化とは?導入するメリット・デメリットを徹底解説!
関連記事:給与明細の電子化に同意書が必要な理由や反対された場合の対応
関連記事:給与支払報告書とは?その内容や提出方法・期限を解説
1-2. 従業員にとっても重要
給与は従業員の労働に対する報酬であり、仕事の評価や成果が反映されているものです。適切な給与を受け取ることで、従業員は自分の努力やスキルが認められていると感じることができます。それにより、自己成長やパフォーマンスの向上につながり、最終的には事業の生産性向上や企業の成長・発展へと繋がります。
給与明細がなかったり、内訳が分からず不透明な状態だと、基本給や手当、ボーナス、控除などの詳細を確認できず、給与に関する疑問や不明点が発生してしまいます。最悪の場合、企業への不信感へと繋がる可能性もあります。
給与明細は、給与制度が公正で透明性があることを従業員に伝える役割を持っている一面もあるのです。
2. 給与明細に記載する基本項目

給与明細には、さまざまな情報が記載されていますが、一般的には大きく「勤怠項目」「支給項目」「控除項目」「差引支給額」の4つで構成されています。
各項目にどのような情報を記載するのか解説します。自社の給与明細と照らし合わせて項目の意味を理解し、給与明細のみかたを把握しましょう。
2-1. 勤怠項目
勤怠項目には、出勤日数・欠勤日数・労働時間・残業時間・有給休暇取得日数・有休残日数などを記載します。
給与計算期間中の労働時間を示し、時間外手当や欠勤に対する控除額は勤怠項目に書かれている日数に基づいて計算します。同時に、計算に用いた日数を給与明細上で示すことで、給与明細を受け取る従業員に対して計算の根拠を示せます。
2-2. 支給項目
支給項目には、基本給・時間外手当・通勤手当・住宅手当・家族手当などを記載します。
時間外手当は前項の勤怠項目で示した労働時間を元に算出します。時間外手当の割増率は条件によって異なるため、勤怠項目および支給項目を時間外労働の種別ごとに用意しておくと、計算する担当者も明細を受け取る従業員も分かりやすくなるためおすすめです。
基本給と各手当を合算した額面が「総支給額」となります。
2-3. 控除項目
控除項目には、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料、所得税・住民税などを記載します。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は従業員の標準月額報酬をもとに算出し、従業員と企業で分担して支払いますが、給与明細に計算式や企業側の支払額までは掲載せず、従業員の支払う分のみ記載していることが一般的です。
雇用保険料はその月の給与の総支給額に雇用保険料率を乗じて算出しますが、こちらも同様に従業員が支払う分の記載で十分でしょう。労災保険料は会社が全額負担するため、給与明細には載せません。
所得税は、個人の所得(総支給額から非課税手当を除いたもの)に掛かる税金です。計算ミス防止のためにも、総支給額から非課税手当を除いた金額を課税対象額として記載しておくことをお勧めします。
住民税は、毎年6月頃に届く通知書に書かれた金額を記載します。
2-4. 差引支給額
差引支給額とは従業員が実際に受け取る金額のことで、「手取り給与」と言われることもあります。
差引支給額は、総支給額から各種控除を引くと算出することができます。
一般的に、差引支給額は総支給額の8割ほどになると言われています。
3. 給与明細の作成に必要なものは?

給与明細の作成にあたり、必要な書類・データは以下の通りです。
それぞれの書類・データの詳細を見ていきましょう。
3-1. 勤怠記録
給与明細は、勤務時間数や出勤・欠勤時刻が確認できる勤怠記録をもとに作成します。
従業員の始業時刻と終業時刻を打ち込むことができるタイムカードを使用するのが一般的です。
タイムカードはタイムレコーダーに差し込み、時刻を打刻して記録します。
勤怠管理システムを導入している企業の場合は、ICカードや生態認証・アカウントなどを使用します。
3-2. 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書
毎年7月になると、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届を提出しなければなりません。
その情報を基に、標準報酬決定通知書の作成がおこなわれ、企業宛てに送られてきます。
通知書には、新たな標準報酬月額が記載されているため、その標準報酬月額を基に、毎月の給与から差し引く社会保険料を計算しましょう。
新しい標準報酬月額が適用となるのは、9月からとなります。
3-3. 住民税課税決定通知書
毎年1月31日までに、地方自治体に給与支払報告書を提出すると、従業員ごとの毎月の住民税納付額を計算した「住民税課税決定通知書」が送られてきます。
住民税課税通知決定書は毎年5月31日までに送られてくるため、その後の6月から翌年5月の1年間にわたり、毎月の給与から差し引きましょう。
3-4. 健康保険と厚生年金保険の保険料額表
健康保険料は、全国健康保険協会の「都道府県枚の保険料額表」に記載がある標準報酬月額に当てはめて求めます。健康保険料率は毎年改定がおこなわれるため、最新の保険料率を自社が加入している保険のWebサイトなどで確認しましょう。
介護保険料率も、健康保険と同じく定期的に改定されるため最新の情報の確認が必要です。
3-5. 雇用保険料率表
求職者給付や就職促進給付などの給付を得られるのが雇用保険です。雇用保険は毎月発生する賃金(通勤手当、家族手当などの手当てを含む)に雇用保険料率を乗じて算出します。健康保険と同様に雇用保険料率も毎年変動します。そのため、最新の情報を確認しておきましょう。
3-6. 源泉徴収税額表
所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するために必要なのが、源泉徴収税額表です。
所得税及び復興特別所得税は、総支給額から控除額や非課税支給額を差し引いて算出される「課税対象支給額」を基に、扶養親族の人数によって決まります。
源泉徴収税額表には、課税対象支給額と扶養人数の組み合わせ毎の税額が一覧になって掲載されています。毎年国税庁が最新の源泉徴収税額表をWebサイトに掲載しているので、最新の情報を確認しましょう。
4. 給与明細を作成する方法

給与明細に必要な書類とデータ、記載する基本項目を理解したところで、実際に作成する方法を見ていきましょう。
4-1. 勤務時間を集計する
まずは勤怠情報をもとに、実際の出勤日数と勤務時間を計算します。
遅刻や早退など不就労や欠勤が発生している場合には、支払う予定の賃金から遅刻・早退・欠勤の時間分を差し引きましょう。なお、不就労控除や欠勤控除は労働基準法による明確な定義がないため、企業ごとに就業規則や賃金規定によって定めておくとよいでしょう。
有給休暇の付与日数と失効日数の記載は任意ですが、従業員とのトラブルを避けるためにも記載しておく方が望ましいです。
4-2. 残業時間の集計、および時間外手当を算出する
次に、集計した勤怠情報から普通残業と深夜残業、休日労働の時間を集計します。
時間数が確認できたら、割増賃金を上乗せして時間外手当を計算しましょう。
時間外手当は、時間外労働時間数×1時間当たりの賃金×割増率で算出することができます。
法定労働時間を大幅に超えた場合や、深夜や休日に働かせた場合には割増率が異なるので気を付けましょう。
以下の記事では、残業における割増率の違いを詳細に説明しています。
参考:法定外残業とは?残業代の計算方法や割増について解説 | ジンジャーBlog
4-3. 通勤費などの各種手当を計算する
通勤手当・資格手当・役職手当など、企業によって手当の種類はさまざまです。
多くの場合、各種手当は固定で支給されています。
ただし、企業によっては欠勤日数によって日割り計算をおこなうことがあるため、自社のルールをきちんと把握しておくことが大切です。
特に重要なのは、各種手当が所得税の課税対象外に当てはまるかどうかです。通勤手当は、交通機関を利用している場合なら15万円まで、自動車や自転車を利用している場合なら4,100~31,600円までが課税対象外の上限と定められています。上限を超えて課税対象外として扱わないように注意してください。
4-4. 給与の総支給額を計算する
以上の計算が完了したら、すべて合算して総支給額を計算しましょう。
総支給額は基本給+時間外手当+各種手当で求められます。
4-5. 保険料・税金の控除額を計算する
総支給額をもとに、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・所得税・住民税などの控除項目を集計して控除合計額を計算します。
控除となる項目の詳細は以下の通りです。
社会保険料
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料といった社会保険料を計算します。それぞれの算出方法は次のとおりです。
| 社会保険料の種類 | 計算方法 |
| 健康保険料 | 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2 |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2 |
| 介護保険料 | 標準報酬月額 × 介護保険料率÷ 2 |
| 雇用保険料 |
総支給額×雇用保険料率(労働者負担分) |
上記のとおり、社会保険料は標準報酬月額にそれぞれの保険料率を乗じれば算出可能です。なお、社会保険料は会社と従業員本人が折半します。そのため、給与計算における控除では2で割ります。
所得税
年間所得に対し、企業があらかじめ税金を差し引くことを源泉徴収といいます。
給与から源泉徴収をおこなう場合は、国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を参考にしてください。
関連記事:給与明細における所得税の計算方法を分かりやすく解説
住民税
企業が住民税を給料から差し引き、代わりに納付することを「住民税の特別徴収」といいます。
従業員ごとの住民税の納付額は、市区町村から企業宛てに毎月5月末までに送られてくるのが一般的です。
その納付書を参考に、給料から差し引いておきましょう。
4-6. 控除額を除いた差引支給額を計算する
先述した通り、差引支給額は総支給額から総控除額を引くことで求められます。
5. 給与明細を効率的に作成する方法

毎月生じる給与明細の作成に、できる限り時間をかけたくないと考えている企業も多いはずです。
ここでは、給与明細を効率的に作成する方法を3点紹介します。
5-1. Excelなどで給与明細のテンプレートを使用する
エクセルなどのテンプレートを使用することで、比較的簡単に給与明細が作成することができます。
インターネット上には、Excelの無料テンプレートなどが多く配布されているため、ダウンロードして活用しましょう。Excelであれば給与計算専用のソフトや作成ツールを使わずに無料で作成可能です。
必要項目を入力するだけで、簡単に給与明細を作成することができます。
5-2. 給与明細の発行を代行してもらう
給与明細の発行を思い切って代行業者に依頼してしまえば、自社で給与明細に関する作業を行う必要はほとんどなくなります。
給与計算が負担でより重要な業務に時間が割けなくなっているなど、とにかく手間を削減したいという場合には、代行の依頼がおすすめです。
業者にもよりますが、従業員10名あたり月15,000円程度が平均費用であるようです。
代行を依頼する人数が多ければ多いほど、従業員一人あたりにかかる費用は抑えられる傾向にあります。
ただし、年間を通すと代行にかかる費用はかなり高額になってくるので、費用対効果を考慮した上で導入を検討しましょう。
5-3. 給与計算システムを使用する
給与計算システムとは、保険料率や税率など定期的に生じる法改正にも自動で対応し、給与計算ができるシステムです。
システムにもよりますが、給与計算に加えて給与明細のWeb発行をおこなうことも可能です。
自動でアップデートされるシステムであれば、法改正に対応できていなかったなどのミスを防ぐことができます。
また、給与明細の作成代行を依頼するよりもコストを低く抑えられます。
サポートが手厚いシステムを選べば、操作方法や社内に浸透するかどうか不安を感じる方でも、安心して利用できます。また、アプリ版もリリースされている給与計算システムであれば、スマートフォンからでも給与計算について確認可能です。
当サイトでは、各種明細をワンクリックでWeb上へ公開したり、PDFで出力したりすることが可能な給与計算システム「ジンジャー給与明細」を参考に、給与明細作成がどのように効率化されるか解説した資料を無料で配布しております。システムの導入により給与明細の業務が効率化されそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
6. 給与明細の作成を毎月効率的におこなおう

給与明細は毎月作成し、発行する必要のある書類であるため、できる限り手間をかけずに作成したいものです。
しかし、従業員の給与に関係してくる内容なので、ミスがないように細心の注意を払いながら作成しなければなりません。
できるだけ手間を省きながらも正確に作成できるように、エクセルのテンプレート活用やシステムの導入など、自社にあった効率的な方法を検討するとよいでしょう。
毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
そこで本資料では、給与明細の複雑な作成ステップやその一連のフローをシステムの導入により、どのように効率化できるかなどを、実際の管理画面をお見せしながら解説しております。
「給与明細関連の業務を自動化したい」
「いつでも従業員が給与明細を見れるようにしたい」
このような悩みを抱えている担当者の方は、「給与明細作成まるわかりBOOK」をぜひご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25