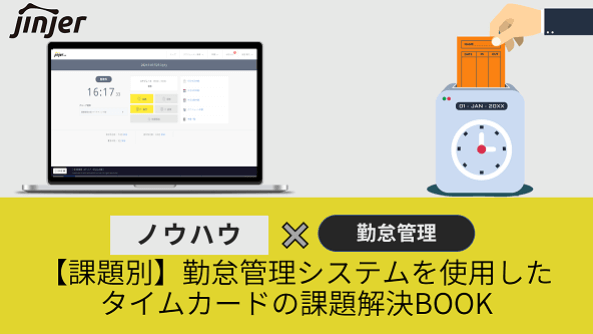タイムカードを打刻し忘れてしまった場合は?従業員への対策と防止策をご紹介
タイムカードを使うことで、従業員の出勤・退勤時間を正確に把握することができます。
しかし、従業員が打刻を忘れるとトラブルが起きてしまう可能性もありますので、この記事では打刻忘れが発生した場合におこなうべき対応と、未然に防ぐための方法について紹介します。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」
という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1.タイムカードの打刻忘れが発生してしまう理由
タイムカードの打刻忘れが発生してしまうのは、次のような理由のためです。
- タイムカードの打刻が習慣になっていない
- 出退勤時にわかりづらい場所にある
- 打刻に手間がかかる
ここではそれぞれの理由について詳しく解説します。
1-1. タイムカードの打刻が習慣になっていない
タイムカードの打刻忘れが発生してしまう理由として挙げられるのが、打刻が習慣になっていないという点です。打刻が習慣化されていない場合、そもそもタイムカード打刻のルールが策定されていないかもしれません。
タイムカードの打刻を習慣化し、打刻忘れを防止するためにはルールを策定に努めましょう。
1-2. 出退勤時にわかりづらい場所にある
タイムカードは出退勤時に打刻するのが一般的です。そのため、出退勤時にわかりづらい場所にタイムカードが設置されていると、打刻を億劫に感じてしまい打刻忘れにつながりかねません。
打刻忘れを防止するためにもタイムカードは出退勤時に分かりやすい場所に設置しましょう。
1-3. 打刻に手間がかかる
タイムカードの打刻に手間がかかってしまう場合も打刻忘れの原因になりかねません。打刻に手間がかかってしまうタイムカードの場合、打刻を後回しにしようとして、そのまま退勤してしまうなどのケースが考えられます。タイムカードの打刻の負担を減らすために、手間がかからない仕組みを作りましょう。
2. タイムカードの打刻忘れは本人に直接確認する
タイムカードの打刻忘れがあった場合は、本人に直接確認してみましょう。この場合、忘れた理由や勤務状況をあわせてたずねる必要があります。なぜなら、それらは勤務時間の管理や給与計算に関わるためです。
たとえば、勤務したにも関わらず打刻を忘れていた場合、その日に働いた分が給与に含まれなかったというトラブルを引き起こします。そのようなことを引き起こさないためにも、しっかりと本人から話を聞きましょう。
3. 勤怠記録を管理する打刻の必要性を再確認
打刻を忘れてしまった従業員に対しては、ペナルティを課すか始末書を書かせるという2つの対応策があります。
3-1.打刻を忘れた従業者にペナルティを与える
タイムカードの打刻を忘れた従業員に対してペナルティを課すことはできますが、1回で減給できる額も1日分の平均賃金における半額と決まっています。
また、あらかじめペナルティに関することを就業規則に記載しておくとスムーズです。
3-2. 始末書を書かせる方法も有効
ペナルティを与えるのではなく、始末書を従業員に書かせる方法も使えます。ただし、無理やり書かせることはできません。そのため、従業員が自主的に始末書を書くように伝えることが大切です。ペナルティのように厳格なルールは定まっていないため、一般的な対応策となっています。
3-3. ただし賃金を払わないのはNG
タイムカードの打刻を忘れたからといって賃金を払わないのは、労働基準法違反として扱われる恐れがあります。あくまでタイムカードは従業員の勤務時間を管理するためのものです。賃金をもらうためにはタイムカードの打刻が絶対必要というわけではありません。
▼タイムカードの押し忘れで給料なしや減給、欠勤扱いの処分は妥当?労働基準法の規定に注意!
4. タイムカードの打刻忘れを防止するための対策法とは
従業員の打刻忘れを防ぐ方法を3つご紹介します。どの方法が自社に合うのか考えたうえで、気になるものを実践してみてください。
4-1.タイムカードの打刻忘れの理由に対策法が隠されている
自社にぴったりと合うような対策法を見つけたいのであれば、打刻を忘れた従業員の理由を分析してみましょう。分析することで、打刻忘れが起きてしまう原因が見つけられます。例えば「タイムレコーダーが見当たらなかったから」という理由であれば、タイムレコーダーが設置されている場所が問題です。
そのような問題であれば、入り口部分といった目立つところに設置することで防げることでしょう。
4-2. タイムレコーダーの近くにポスターを掲示
タイムレコーダーの近くに打刻忘れに関するポスターを貼ることで、打刻忘れを防げる可能性が高まります。それ以外の場所でも問題ありませんが、目立つところへ貼るようにしましょう。
たとえば上記で述べたように、会社の入り口であればポスターが目立ちます。目立つことで従業員の目に止まりやすくなり、打刻忘れの防止が期待できます。
4-3.正しい勤怠管理の重要性を周知する
タイムカードの打刻忘れが多い場合、その理由の一つとしては従業員が勤怠管理の重要性を知らないということが挙げられます。この場合は、改めて従業員に勤務時間の重要性を啓蒙する必要があります。
勤怠管理は給与計算の大きく関わるほか、長時間労働の抑制などに繋がるため、従業員一人ひとりが正しくタイムカードを打刻しなければなりません。勤怠管理の重要性を伝えることで、従業員の意識が改善されることでしょう。
4-4.打刻忘れのないシステム導入を検討する
打刻忘れを防ぐために、タイムカードから勤怠管理システムへ切り替えてみる方法も検討してみましょう。勤怠管理システムによっては打刻を忘れてしまった場合に知らせてくれるアラート機能が搭載されているものもあります。ただし、全ての勤怠管理システムに搭載されているわけではないため、導入する際には必ず機能面を確認しましょう。当サイトでは、アラート機能が搭載されている勤怠管理システムである「ジンジャー勤怠」を例に、実際にどのようなアラームがでるかなどを紹介した資料を無料で配布しております。システムの導入を具体的にイメージしたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
本章では対策を3点ご紹介しましたが、根本的に決まり事にしてしまうこともおすすめです。以下の記事にタイムカードを打刻する際の具体的なルールを6点紹介していますので、気になる方はご確認ください。
▶タイムカードで打刻ミスをなくすために用意しておきたい打刻ルールの具体例
5. タイムカードの打刻忘れを防止して適切な労働管理を!
今回は、タイムカードの打刻忘れへの対応方法や対策方法などについて紹介しました。打刻を忘れた従業員に対してはペナルティや始末書の提出などがおこなえますが、その分注意点があります。
対策方法はポスターの掲示や勤怠管理システムへの切り替えなど、さまざまな方法があります。自社の働き方や雇用形態などを把握したうえで、打刻を忘れた従業員への対応方法や対策方法を考えてみてください。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」
という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25