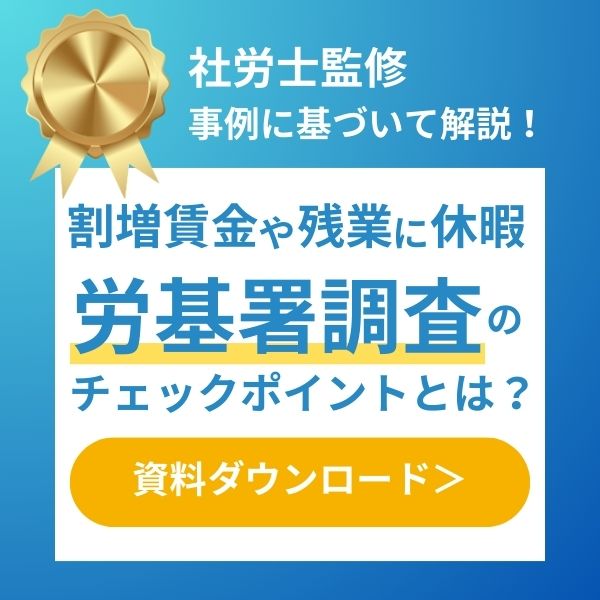在宅勤務(テレワーク)では何が経費になる?自宅以外で働く場合は?
更新日: 2025.5.16 公開日: 2021.11.12 (特定社会保険労務士・中小企業診断士)

在宅勤務に関係なく、従業員に対する給与も含めて、事業に必要な費用はすべて会社にとっての経費です。
しかし従業員側からすると、仕事で使った費用を経費精算してもらうのか、手当として支給してもらうのか、この双方では意味合いが大きく異なります。
それぞれで各従業員の税負担が変わってくるので、十分に注意しなければなりません。
そこで今回は、在宅勤務にかかるコストについて、従業員からの経費精算として対応すべきケースを詳しく見ていきましょう。
それではまず、経費精算の基本的な考え方を以下で解説します。
▼在宅勤務・テレワークについて詳しく知りたい方はこちら
在宅勤務の定義や導入を成功させる4つのポイントを解説
目次

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 在宅勤務で経費と認められるのは貸与品が基本


では在宅勤務時の費用を経費精算と認めるべきケースには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
仮に在宅勤務用に新しく何か物品を購入した場合、それらをあくまで会社所有として従業員に貸与するのであれば経費精算ができます。もし従業員側で購入した際にも、会社からの貸与品扱いにするのであれば、立て替え分は給与ではなく経費です。たとえ業務に必要なくなるまで使い続けられるとしても、最終的に返却するなら会社所有と考えて問題ありません。
従業員側の判断によって処分できないもので、会社に返すことが前提のものは、課税対象とせずに原則は経費精算が認められます。
また経費精算ができる代表的な例には、次のようなものがあります。
- 貸与品のポケットWi-fi
- 貸与品のパソコン
- 必要な業務ソフトウェアのライセンス
- 文房具や事務用品などの消耗品
これらのアイテムは、業務を行う上で必須となるもので、その使用が会社の業務目的に合致しているため、経費として認められるのです。一方で、従業員が自ら購入したものについては、領収書を添付し、会社の承認を得ることが大切です。その他の経費と認められる項目についても詳しくみていきましょう。
1-1. 業務用ツール
先ほども出てきたパソコンをはじめ、Webカメラ・スマートフォン・携帯電話といった各種ツールは、会社からの貸与が前提であれば経費精算が可能です。
従業員自身で選定して購入した場合でも、貸与品にするなら同様に経費扱いができます。
1-2. 環境整備品
在宅勤務での環境整備は、業務効率を大きく向上させる要素となります。そのため、快適に働けるスペースを確保するための道具や設備は、積極的に整備することが望まれます。
また、各従業員が必要な設備を自宅に設置する際の費用についても注意が必要です。必要に応じてオフィスチェアや作業デスクを購入する場合、これらの費用も経費として認められます。
業務に支障をきたさないためにも、職場環境を整えるための投資は企業にとって重要な意味を持ちます。ただし、これらの経費精算に際しては、必ず領収書を保存し、どのような目的で使用されるのかを詳細に報告することが求められるでしょう。
このプロセスを通じて、従業員の在宅勤務環境が一層整い、業務の効率化につながることが期待されます。
1-3. 事務・消耗品
事務・消耗品に関しては、ここまでの物品とは扱いが異なるため注意する必要があります。
いずれも「貸与」という条件がありましたが、事務・消耗品の場合、実質的には返却が困難です。
そのため文具や宅配・郵送用品類などは、業務上必要なものとして、会社が負担する経費にできます。
出社・外出時のマスクといった消耗品も該当しますが、あくまで通常業務を遂行する上で欠かせないものに限ります。
例えば従業員の家族用のマスクを支給した場合には、課税対象になるので気を付けておきましょう。
2. 従業員が経費負担する場合は就業規則での規定が必須


今までにご紹介した必要品については、必ず会社負担にすべきというわけではありません。
仮に会社が立て替えなくても違法ではなく、従業員の自前でも良いものです。
しかし労働基準法においては、何かしらの業務用品を従業員負担にする場合には、就業規則による定めが必要とされています。
もし在宅勤務に向けた必要物品を従業員自身でそろえてもらう際には、就業規則の確認が欠かせません。
従業員が自己負担で経費を負担する場合、必要な物品が業務に関連していることを明確に示すため、それに関するルールを明文化しておくことが重要です。
状況に応じて就業規則を変更しなければならないので、十分に注意しておきましょう。その他にも勤務時間や残業規定の変更など、在宅勤務の導入時には就業規則の見直しが必須です。
当サイトでは、導入の際によくある悩みやその解決法、在宅勤務時の正しい運用方法などをまとめた「テレワーク課題解決方法ガイドBOOK」を無料で配布しております。在宅勤務の導入を検討中の方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:在宅勤務の就業規則の在り方や見直しのポイントを解説
3. 在宅勤務での経費扱いで特に注意したいもの


ここまでにご紹介してきたのは、オフィス勤務でも必要になる有形の物品例で、白黒が分かりやすくあまり判断に困ることはないでしょう。
しかし在宅勤務になると、自宅で仕事をするからこそ発生する経費も出てきます。
特に以下のような無形コストは、取り扱いが非常に複雑なので、しっかりと社内で検討しておきましょう。
3-1. 通話・通信料金
仮に従業員本人が所有するスマートフォンを業務に使う場合、その使用料を経費精算するには、合理的かつ精密な計算方法で適切な金額を算出しなければなりません。
より詳細な規定がある場合には、各企業独自の計算でも問題はありませんが、基本的には次のような計算式に当てはめて経費額を出します。
- (1ヵ月間の基本料金+インターネット接続料の有料分)×各従業員の月の在宅日数/該当月の暦日×1/2
※上記に加え、業務に使用した分の通話料を上乗せ
通話料については、明細書にて業務に使用した分が把握できるため、その分をそのまま経費精算として問題はありません。
ただし基本料金やインターネット接続料は、私的利用分と分ける必要があるため、上記計算式に当てはめて算出します。
またインターネット接続料の有料分とは、例えば「3GBまで基本料金に含む」などの場合なら、その超過分に該当するものです。
なお1円未満は切り上げで考えます。
3-2. 電気料金
電気料金も同じように、私的利用分と分けて考慮しなければなりません。
こちらも会社独自の計算方法でも問題はありませんが、原則以下の計算式に当てはめて算出します。
- 1ヵ月間の電気料金×業務に要する床面積/自宅の総床面積×従業員の月の在宅日数/該当月の暦日×1/2
なお通話・通信量でも同じように出てくる「1/2」という比率は、1日の平均睡眠時間(8時間)を除いた、日中の労働時間の割合を示しているものです。
3-3. 感染症対策関連
もし感染が疑われる従業員において、会社からの業務命令でホテルを利用させたりPCR検査を受けさせた場合には、交通費を含んだ各種料金は経費精算が可能です。
ただし自己判断で利用しているケースで会社が負担する際には、給与として課税対象となるので注意しておきましょう。
感染症対策として、従業員の健康を守るために会社が医療費や健康管理のための費用を負担することは、正当な経費として認められます。 この際にも明確な基準を設けて、どのような場合に経費として計上できるのかを社内で共有しておくことが重要です。
また、感染症対策に関連する備品や消耗品の購入も、業務の継続のために必要な支出として、経費精算の対象となります。 例えば、除菌スプレーやマスク、防護具などの購入は、業務遂行におけるリスク回避のための支出として認められるでしょう。
関連記事:在宅勤務に交通費は必要?クリアにしておきたい線引や注意点
4. 自宅以外でテレワークを行った場合


自宅以外でテレワークを行った際の経費については、業務を行うために必要な費用が経費として認められます。
例えば、コワーキングスペースの使用料やカフェでの飲み物代は、領収書などの証明書類があれば「会議費」として計上可能です。しかし、食事目的でカフェを利用する場合は経費として認められません。
また、セキュリティリスクを考慮し、従業員が独自に判断して業務を行うことには注意が必要です。そのため、会社としては自宅以外での業務に関するルールを明確に定めておくことが推奨されます。
5. 在宅勤務で会社支給にする場合は給与として課税


在宅勤務の経費についてさらに詳しく見ていきましょう。
テレワークが一般的になってきた今、従業員が自宅での業務に必要な経費を正しく計上することが重要です。例えば、仕事用の部屋の電気代や通信費は、会社負担として経費精算できる可能性があります。しかし、この場合も従業員がこれらの費用をどのように使用しているか、またその具体的な金額を証明する必要があります。領収書や通信明細など、具体的な証拠があれば、スムーズに経費として認められるでしょう。
また、テレワーク社員の環境によっては、仕事用とプライベート用の費用を明確に区分することが難しい事例もあります。このような場合、あらかじめ社内で按分の基準を定めておくことが利便性に直結します。特に、在宅勤務における通信費や光熱費の精算方法は、企業ごとに異なるため、就業規則での明文化が求められます。これにより、従業員に対する透明性と公平性が保たれ、安心して働ける環境を整えることができます。
さらに、今後のテレワークの普及に伴い、新しい経費に関する形態も出てくるでしょう。これにしっかりと対応するためにも、経費精算のルールを定期的に見直し、柔軟に適応させていくことが大切です。
6. より適切な処理によって快適な在宅勤務に


在宅勤務でなるべくスムーズに業務を進めていくためには、備品をはじめとしたさまざまな準備が必要です。
また状況に応じて、滞りなく仕事をしてもらうための費用負担が求められるケースも発生します。
そうした場合に備えて、手当を支給するのか経費精算で立て替えるのか、前もって十分に検討しておかなければなりません。
従業員への影響も大きいため、しっかりと計画を立てた上で、適切な処理をしていくのがベストです。
関連記事:在宅勤務手当とは?支給額の相場や支払い方法を詳しく紹介
関連サイト:KASHI KARI



人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
在宅勤務の関連記事
-


在宅勤務手当(テレワーク手当)とは?課税・非課税や金額相場を解説!
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.12.25
-

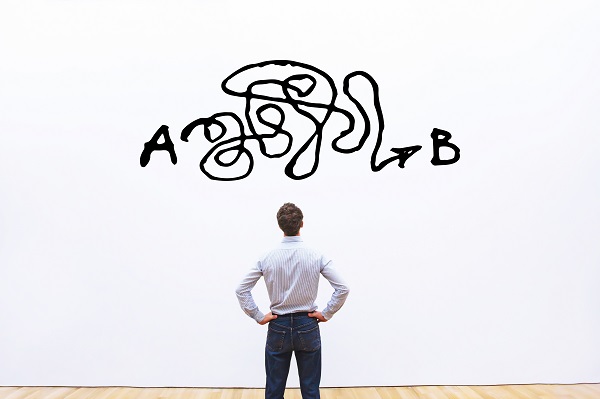
在宅勤務導入のデメリットとは?問題点から見える課題や解決策を紹介
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.02.12
-


在宅勤務とは?定義やテレワークとの違い・導入を成功させる4つのポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.09.29