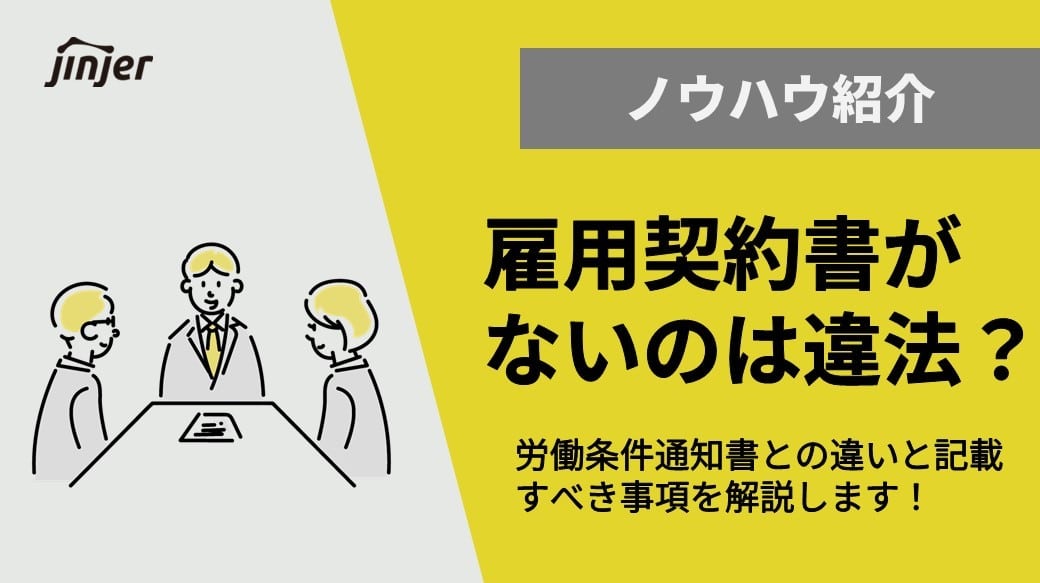雇用契約書がないのは違法?考えられる4つのトラブルとその対処法
更新日: 2024.7.8
公開日: 2020.11.19
OHSUGI

雇用契約を締結する場合、雇用契約書を交付する企業とそうでない企業が存在します。では、雇用契約書を交付しない企業の場合、違法性はないのでしょうか。
本記事では、雇用契約書の交付が法的に義務付けられているのか、雇用契約書がないことによるトラブルにはどのようなものがあるか解説します。
関連記事:雇用契約書とは?法的要件や雇用形態別に作成時の注意点を解説!
雇用契約は必要?ない場合は違法になるの?リスクは?
電子署名でも法的に問題ない?
そもそも「雇用契約書」と「労働条件通遺書」との違いは?
このように、雇用契約書について、自社の運用が法律的な観点から見て正しく管理できているのか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは雇用契約についてまとめている資料を無料配布しています。
「法的な観点から今更聞けない正しい雇用契約書の運用について知りたい」という方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用契約書がないのは違法?

雇用契約書は、雇用主と労働者が契約内容に合意したことを示す書面で非常に重要なものです。この雇用契約書を交わさないことは違法であるのか、まずは確認していきましょう。
1-1. 雇用契約書がなくても直ちに違法にはならない
雇用契約書には労働条件や給与の計算・支払い方法、福利厚生、休日などが記載されていることが多く、雇用主・労働者双方にとって非常に重要な書類です。
しかし、雇用契約書の作成義務に関して言及している法律はないため、作成していなくても違法ではありません。
労働契約法第6条では、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定められています。
つまり、雇用契約書がなく口約束のみであっても、労使双方が合意していれば雇用契約は成立します。
1-2. 労働条件通知書の未交付は違法
雇用契約書と並んで重要な書類が労働条件通知書です。その名のとおり労働条件を労働者に明示する書類ですが、この書類は法律で交付する義務が定められています。なお、労働条件通知書の交付は雇用形態に関わらずおこなわなければなりません。契約社員やアルバイト、日雇い(スポット)労働者など、全従業員に対して交付・伝達をしましょう。
2019年4月以降は労働条件通知書を電子化することが可能になりました。しかし、交付が義務付けられていることに変わりはありません。労働条件通知書が交付されない場合には違法になります。
労働条件通知書に明示すべき事項
労働条件通知書には明示すべき事項が決まっています。労働条件通知書を交付していなかったり、必要事項を伝達していなかったりすると、最悪の場合、従業員側から訴えられる可能性がありますので注意が必要です。
雇用主が労働者に必ず知らせなければならない項目としては、たとえば労働契約期間や就業場所、始業・終業時間、賃金の決定・計算・支払い方法、昇給・退職に関する事柄などです。さらに文書でなくても口頭で伝えなければならない項目もいくつかあり、2024年4月1日から労働条件の明示ルールも変更されました。
当サイトでは、このような明示すべき事項がわからない、最新の法改正に伴う変更点を再確認したいという方に向けて、雇用契約や解雇に関する法律やルールをまとめた資料を用意しています。参考にしたい方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
2. 雇用契約書がないことによるトラブル
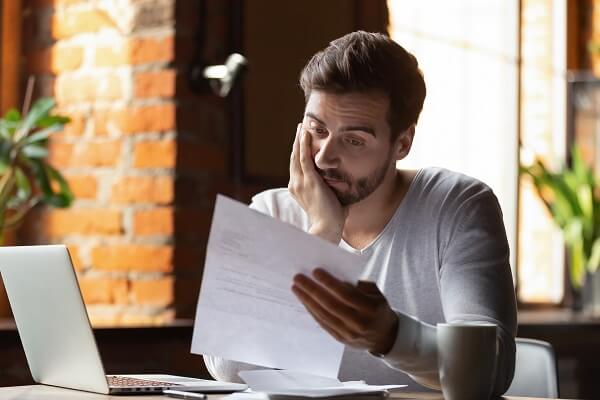
雇用契約書は法律的には不要ですが、雇用契約書を作成していない場合、トラブルが発生しやすくなります。雇用契約書がないことによるトラブルの例を知っておきましょう。
2-1. 求人情報と実際の労働条件が異なる
雇用契約書がないことで起こるトラブルの中で多いのが、提示されていた労働条件と実際の待遇が異なるというものです。
求人情報に掲載されていた給与や休日などの労働条件と、実際に働き始めて感じる労働条件が異なるのはそれほど珍しいことではありません。求人情報に掲載されている情報はあくまで概要だからです。
しかし、雇用契約書や労働条件通知書に記載されている労働条件と異なる条件下で従業員を働かせた場合、訴訟問題になりかねません。
雇用契約を口約束で結ぶことも可能ではありますが、「聞いていない」と言われてしまえば、書面での締結と比べると、容易に破ることができます。
労使間で労働条件の認識の違いによるトラブルを防ぐためにも、雇用契約は書面や電子で締結し、形に残すようにした方がよいでしょう。
2-2. 就業規則が一方的に雇用主に有利
雇用契約書や労働条件通知書がない場合、就業規則が業務をおこなううえでの指針になります。
基本的に就業規則は労働基準法に則った内容であることが大前提ですが、法改正前に定めた就業規則を使い続けている場合など、違法な内容になっている可能性があります。
たとえば、残業代が不当に少ないみなし残業制を導入している、就業規則に違反した場合即解雇する、有給休暇は自由に取得できないなど、こうした就業規則は雇用主に有利な内容です。
この場合は違法となり、従業員から訴訟を起こされかねません。また、裁判における雇用主側の立場は圧倒的に不利になり、企業イメージにも傷がつきます。
関連記事:雇用契約書と就業規則の優先順位とは?見直す際の2つのポイントをご紹介
2-3. 雇用者と労働者で認識のずれや誤解が生じる
雇用契約書や労働条件通知書には、試用期間の有無や期間、休日出勤や残業の取り扱いなど、さまざまな項目が明示されています。とくに試用期間中は、本採用時とくらべて給与が低かったり待遇が悪かったりすることも少なくありません。
こうした細かい取り決めは雇用契約書がない場合、雇用する側とされる側とで試用期間についての認識にずれが生じる恐れがあります。トラブルに発展する可能性が高くなるため、後から確認できるように雇用契約書という形で残しておくのが得策です。
関連記事:雇用契約における試用期間の意味とよくあるトラブルを紹介
2-4. 解雇や雇止めに関するルールが不明瞭になる
雇用契約を締結している労働者の場合、雇用主が解雇を言い渡すためには正当な事由がなければなりません。試用期間中であってもそれは同様です。
試用期間中も雇用契約が結ばれており、雇用主側が労働契約解除権を留保している状態です。労働契約解除権を行使することはできますが、どんな理由でも解除できるわけではありません。
たとえば、病気やけがで復職することができない、無断欠勤が多く指導しても直らない、入社時に経歴を偽っていたといったケースでは労働者を解雇することが可能です。
雇用契約書がないと、こうした正当な事由以外で雇用主が労働者に退職を求めることが起こり得ます。労働者側が安心して業務につくためにも、雇用契約書は重要なものです。
3. 雇用契約書は作成した方が安全

雇用契約書がない場合のトラブルを見ると、雇用契約書は交付しておいた方が安全であることが分かります。雇用契約書は労使双方の労働条件に関する認識の違いをなくし、気持ちよく働くために雇用契約はとても重要なものです。
また、雇用契約書は訴訟問題になった際、大きな効力を発揮します。雇用主が労働者に対して一方的に交付する労働条件通知書に対し、雇用契約書は労使が労働条件に合意して契約したことを示す署名捺印があるためです。
労働条件通知書だけを交付した場合、労働者側が「労働条件通知書の内容が間違っている」と主張することもあり得ます。しかし、雇用契約書に同じ内容が記載されており、労使双方の署名捺印があれば、こうした主張はできなくなるでしょう。
3-1. 雇用契約書の締結は書面でも電子でも可能
雇用契約書の締結は書面に限らず、2019年の法改正により電子締結をおこなうことも可能になりました。
昨今ではテレワークが普及していることもあり、電子締結の方がより書類の管理や確認がしやすくなります。
また、記入ミスなども防ぐことができるため、まだシステムが整っていない場合はメリットを踏まえて導入を検討することをおすすめします。
雇用契約書は、最初の出社日もしくは内定から入社までの期間に締結するのが一般的です。早めに収集したいのであれば、内定が出たタイミングでほかの入社書類とともに、雇用契約書の締結も済ませておくとよいでしょう。
システムを用いた雇用契約の電子化が気になる方は、労働条件通知書の交付を電子化できるシステム「ジンジャー人事労務」のサービス紹介ページを以下のリンクよりご覧ください。
▶クラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の雇用契約サービスの紹介ページを見る
3-2. 事務処理を減らすためには労働条件通知書兼雇用契約書がおすすめ
会社によっては雇用契約書と労働条件通知書を別々に作成するところもあります。2つの書類を作れば、法律を遵守している会社として評価されるでしょう。
しかし、人事採用をするたびに2つの書類を作っていては事務処理の手間が増えます。負担が大きい場合は、労働条件通知書兼雇用契約書を作成して労働者に交付することで業務を最小限に抑えることが可能です。
現在では、電子データをメールで送付することもできるようになっています。労働条件通知書兼雇用契約書をPDFファイルで作成すれば、メールでの交付が可能になり、さらに効率よく作業を進められるでしょう。電子化について気になる方は以下の記事をご覧ください。
後のトラブルを防ぐためにも、書類であれば直筆の署名、電子データであれば電子署名を確実におこないましょう。
参考記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
4. 雇用契約書を作成し、労使間のトラブルを防ごう

雇用契約書は雇用に関して労使双方の同意を示す重要な書類ですが、雇用契約書を作成していないことは違法ではありません。
しかし、雇用契約書があれば避けられるトラブルも多いです。追加でトラブルに対応する手間などを考えると、雇用契約書は作成しておくべきと認識しておいたほうがよいでしょう。
雇用契約の内容を書面という形で残すことは、使用者と労働者双方を守ることにつながります。電子化も検討し、業務負担を減らしながら交付するようにしましょう。
雇用契約は必要?ない場合は違法になるの?リスクは?
電子署名でも法的に問題ない?
そもそも「雇用契約書」と「労働条件通遺書」との違いは?
このように、雇用契約書について、自社の運用が法律的な観点から見て正しく管理できているのか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは雇用契約についてまとめている資料を無料配布しています。
「法的な観点から今更聞けない正しい雇用契約書の運用について知りたい」という方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08