雇用契約書に印紙は不要?派遣や出向・業務委託のケース、課税・非課税文書とは
更新日: 2025.9.12 公開日: 2020.11.19 jinjer Blog 編集部

雇用契約書は労使間のトラブルを防ぐために重要な書類です。法的な書類には収入印紙を貼りつけるものが多いですが、雇用契約書にも印紙が必要なのでしょうか。
本記事では雇用契約書作成における印紙の必要性を解説し、課税文書と非課税文書の違いについても紹介します。
関連記事:雇用契約書に印紙は必要?課税文書と非課税文書の違いとは
目次

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 雇用契約書に印紙は必要ない

結論からいえば、雇用契約書には印紙が必要ありません。収入印紙は、法的に重要な文書を作成したときに税金を納める手段として用いられます。印紙を貼らなければならない文書は印紙税法別表第一に定められており、雇用契約書はそのなかに含まれていません。
ただし契約形態によっては、必要になってくる場合もあるため、この章では派遣契約・出向契約・業務委託契約のケースに分けて印紙の必要性を解説していきます。
1-1. 派遣契約書のケース
派遣契約書においては、収入印紙は必要ありません。これは、派遣契約自体が派遣元企業と派遣先企業との間で締結される契約であり、派遣元の従業員が派遣先の業務をおこなう際に、その指揮と命令が派遣先によっておこなわれるからです。
一般的に、契約書はその内容によって印紙税がかかる場合がありますが、派遣契約書は印紙税法の観点から見ると「委任に関する契約書」と分類されます。このため、印紙税の課税対象には該当せず、印紙を貼付する必要がないのです。多くの人が「請負関連の契約書」と誤解しがちですが、実際にはその性質が異なるため、印紙税が発生しないことが明確に定められています。
1-2. 出向契約書のケース
出向契約書は、雇用契約の一形態でありながら、印紙税が不要な特性を持っています。
出向契約書は、主に出向元である企業と出向先である企業、そして出向する従業員との間で締結されます。出向には「在籍出向」と「転籍出向」の2つの形態があります。在籍出向の場合、従業員は出向元の企業に在籍したまま出向先で業務に就きます。この形では、出向元が従業員の労働条件を定めた契約を締結します。一方、転籍出向では、従業員が出向先に籍を移し、新たに雇用契約を結ぶことになります。
どちらのケースでも、出向契約書はあくまで労働条件や業務内容などを定めることを目的としているため、印紙税法で定める課税文書には該当しません。印紙税は、主に金銭の授受が発生する経済取引に関する契約にかかる税金であり、出向契約はそれに該当しません。
1-3. 業務委託契約書は印紙が必要
業務委託契約書は、委託企業と受託企業の間で締結される契約であり、受託企業が特定の成果物や役務を提供することを約束します。この契約は印紙税法上の「請負関連契約書」に該当し、一定の条件下では収入印紙の押印が義務付けられています。
業務委託契約書の契約金額によって印紙税は変動します。例えば100万円以下で200円、300万円超500万円以下で2,000円といった具合に、契約金額が高くなれば印紙税も高くなっていきます。
この区分けにより、業務を依頼する側と受ける側の権利と義務が明確になり、印紙税についても理解が深まります。したがって、業務委託契約書の作成や締結においては、要件や印紙税の規定を考慮することが重要です。
2. 印紙が必要な主な課税文書とは

契約書に限らず、法的に重要な文書とされるものは課税文書に該当し、印紙が必要です。印紙税法別表第一に記載されている20種類の文書、当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書、非課税文書でない文書が課税文書に該当します。
課税文書・非課税文書は、内容によって判断されるものです。。印紙を使わなくてもすむようにタイトルを考えても、内容が課税文書に該当する書類であれば印紙が必要になります。
印紙税法に定められている主な課税文書のうち、雇用や契約に関連する書類について見ていきましょう。
2-1. 第1号文書
印紙が必要な課税文書の筆頭に挙げられるのが、「第1号文書」に該当する種類の契約書です。
第1号文書に該当する書類は以下の通りです。
- 不動産
- 鉱業権
- 試掘権
- 無体財産権
- 船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書
これらに関する契約書が課税文書に該当します。
ただし、契約書の金額が1万円未満であれば非課税になり、印紙は必要ありません。金額がそれ以上になる場合、10万円以下で印紙200円分、10万〜50万円以下で400円と金額が決められています。
2-2. 第2号文書
第2号文書とは、請負に関する契約を指します。雇用主と労働者との間に指揮命令がある雇用契約とは異なり、請負の場合には請負人が成果物を注文者に提供する必要があります。
注文者は完成品に対して報酬を支払うことになります。工事請負契約、広告契約、映画俳優専属契約などが第2号文書に該当します。
第2号文書についても、契約金額によって印紙の金額が変わります。
契約金額が100万円以下、または契約金額の記載がない場合は200円、200万円以下は400円、300万円以下は1,000円、と細かく印紙税が定められています。実際に第2号文書を作成する際は、契約金額別に必要な印紙税を確認しましょう。
2-3. 第5号文書
第5号文書は会社の組織間における合併契約、吸収分割契約、新設分割契約などで作成される契約書です。会社の経営者であれば作成する可能性があります。
第5号文書の場合、契約金額にかかわらず印紙税は一律4万円分必要になります。そのため、会社の合併や分割といった重要な取引をする際には、印紙税の取り扱いに十分注意が必要です。
2-4. 第7号文書
第7号文書とは、継続取引をする際の契約書のことです。売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などがこの第7号文書に該当します。ただし、契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めがない場合の契約書は除外されます。
デザイナーやプログラマーとして契約する場合には、契約書が第7号文書に該当することもあるので注意が必要です。第7号文書の印紙税は一律4,000円です。
参考:印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
3. 印紙が不要な主な非課税文書とは
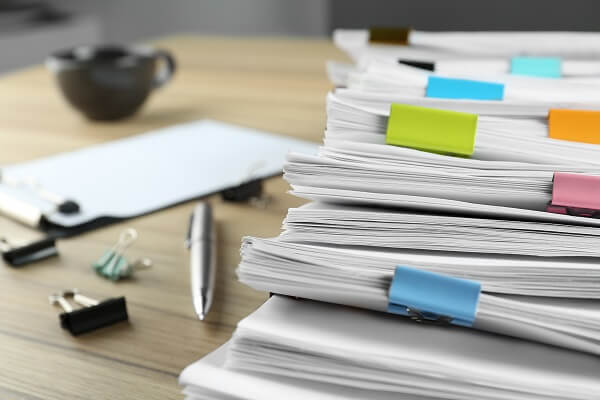
印紙が必要になる課税文書に対して、印紙が必要ない非課税文書もあります。
ここで注意が必要なのは、不課税文書と非課税文書の違いです。
- 不課税文書:そもそも課税対象になっていない文書
- 非課税文書:課税文書のなかで除外規定によって印紙税が免除されているもの
ここでは、非課税文書に絞ってその内容や種類を解説していきます。
3-1. 課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書
印紙税の課税対象は、課税物件表によって決められています。課税物件表の一番右には非課税物件の欄が設けられており、例外的に印紙税が課税されません。この非課税物件に該当する文書は非課税文書になります。
例えば、雇用契約書はその典型例であり、契約の性質上、税法上の課税文書として扱われないため、印紙を貼る必要がありません。
3-2. 国や地方公共団体が作成する文書
課税文書であっても、作成者が国や地方公共団体である場合には印紙を貼りつける必要がありません。
また、在日の外国大使館、領事館、公使館が作成した文書についても印紙税が課せられないことになっています。
3-3. 非課税法人が作成する文書
印紙税法別表第2に記載されている非課税法人が作成する文書も印紙が必要ない非課税文書です。学校法人や商工会議所、福祉施設などが該当します。
これらの法人が作成する文書は、公共の利益に資するものとして、印紙税の負担を免除されています。
3-4. 印紙税法以外の法律によって非課税になる文書
印紙税法以外の法律によって非課税になっている文書も印紙は必要ありません。たとえば健康保険に関する書類は健康保険法によって非課税になっているため、印紙を貼らなくてよい文書です。
また、地方自治体が発行する許可証や証明書も、関連法令によって印紙税が課せられない場合があります。
4. 雇用契約は印紙がなくても有効


雇用契約書に収入印紙がない場合でも、雇用契約自体は無効になりません。
雇用契約書は労働契約法第6条に基づいており、労働者と使用者が協定した内容に基づいて労働関係が成立することを示しています。この法条文によれば、労働者が使用者のもとで働き、使用者が賃金を支払うという合意があれば、書面での契約書が存在しなくても雇用契約は有効です。
したがって、企業と従業員の口頭による合意や単なる合意の内容だけで、契約が法的効力を持つことは明白です。ただし、労働基準法第15条では、雇用契約の内容を明示するために、労働条件通知書の発行を求められています。これは、労使間で認識の齟齬が起きないために必要です。
さらに、雇用契約は印紙税法では課税文書として指定されていないため、収入印紙を貼り付ける必要もありません。印紙税法において、雇用契約が非課税文書として扱われていることからも、印紙がなくても法律的に問題なく雇用契約が成立することが理解できます。しかし、だからと言って雇用契約書は軽視してよいものではありません。従業員との間での信頼関係の構築や合意内容の遵守が何よりも重要です。
5. 雇用契約を締結する際に割印は必要?


雇用契約を締結する際、割印を押すことは一般的な手続きですが、法的には必須ではありません。
通常、雇用契約書を2部用意し、両者が相互にその印影が残るように割印を押すことで、各々の契約内容の同意を確認します。しかし、法律上は割印がなくても契約は有効です。ここでは割印をおこなう場合について説明します。
5-1. 印鑑は会社の代表印を推奨
雇用契約書において割印をする場合、使用する印鑑は会社の代表印でおこなうことを推奨します。
これは、割印が契約の成立を示す重要な証拠として機能するため、信頼性の高い印鑑を選ぶことが必要だからです。法律上、印鑑の種類に関しては特別な規定がないため、企業は自社の判断で印鑑を選択できます。しかし、企業にとって代表印は最も公式な印鑑であり、企業名や代表者の役職が明記されているため、改ざんのリスクを低減することができます。
代表印を使用することで、契約の正当性と信頼性を高める効果があります。人事担当者などの認印を使用しても法的には問題ありませんが、契約の重要性から考えると、代表印の使用がより望ましいと言えます。例えば、信頼性が重視される取引先との契約であれば、代表印を選ぶことで相手方に安心感を提供でき、取引の円滑化につながることでしょう。
5-2. 割印ではなく署名でも法律上問題ない
割印の主な目的は、契約書の改ざんや不正コピーを防止することです。従業員と企業が正式な契約を交わす際、割印があることで信頼性を向上させる効果がありますが、必須というわけではありません。署名によって割印と同様の役割を果たすことができます。
さらに、割印や署名がなくても、法的には雇用契約書が無効になることはありません。つまり、実質的な内容が労使間で合意されている限り、契約は成立していると見なされます。これは実際に多くの企業が採用している方法であり、さまざまな事情から割印を用いることが難しいケースも少なくありません。
このように、雇用契約書において割印ではなく署名を使用することが法律上問題ない理由は、契約の本質的な意味合いとその実行性にあるのです。
6. 雇用契約書に印紙は不要!契約内容を守った働き方で労働環境を守ろう

雇用契約書は雇用主や労働者にとって重要な文書ですが、課税対象ではありません。したがって、雇用契約書に印紙が貼られていなかったとしても法的に問題はなく、契約内容が無効になることもありません。
ただし、雇用契約と就業規則の優先順位を間違えた場合で、労働基準法をはじめとした法律違反に該当してしまうと問題になります。労働契約の内容が無効になったり、裁判に発展したりするというリスクがあるため、雇用契約についての正しい理解が求められます。
当サイトでは、上記のような優先順位や雇用契約における禁止事項、よくある疑問などをまとめた資料を無料で配布しております。雇用契約に関して不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
また労働条件通知書も印紙が必要なく、雇用契約書とともに電子化をスムーズに進めることが可能で、作業の効率化が期待できます。中でも新入社員が多い、従業員の出入りが多いなどで手続きを手間に感じている人事労務の担当者の方は、一度は電子化を検討しましょう。より詳しく電子化について知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
雇用契約書に限らず、日常的に印紙を使う機会が多い場合は課税文書と非課税文書の違いをしっかり押さえておくとよいでしょう。



雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
雇用契約の関連記事
-


トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説
人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2025.06.11
-


労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.10.27
-


試用期間中の解雇は可能?解雇できる条件や必要な手続きを解説
人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2025.07.16





















