等級制度とは?制度の種類や活用するときのポイントを詳しく解説
更新日: 2025.4.17 公開日: 2023.5.26 jinjer Blog 編集部

等級制度には職能資格制度・職務等級制度・役割等級制度の3つがあり、それぞれ、能力・職務・役割により、社員をランク付けする人事評価制度です。制度により評価対象が人材そのものか、それとも仕事と成果のみかなどの違いがあるため、企業に適した制度の導入が大切です。
本記事では等級制度とは何か、種類別のメリット・デメリットや活用時ポイントなどを解説していきます。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 等級制度とは?

等級制度とは、能力や職務、役割などにより等級(ランク)を設け、社員を当てはめる制度のことです。社員のランク付けにより、給与や賞与を決定する人事評価に役立てたり、求める能力を明確にして人材育成に活用したりできます。
会社としては「社員に期待する仕事のレベルを示しやすい」「給与決定などの人事管理がしやすい」など、組織を運営しやすくなるメリットがあります。
また、社員にも「それぞれの役割が理解しやすく混乱が生じにくくなる」「キャリアイメージがしやすくモチベーションを維持しやすい」などの利点が生まれます。
1-2. 等級制度は人事制度を支える3本柱の一つ
人事制度は、企業が人材管理をおこなう仕組みを指し、「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3本柱で構成されています。この3本の柱が担う役割は以下のとおりです。
- 等級制度…社員に求める立場や役割、能力を決定する
- 評価制度…社員の業績や取り組みを適正に評価する
- 報酬制度…等級や評価に基づいて給与や賞与など待遇を決める
これら3つの柱は相互に強い関連性があるため、等級制度を導入する際は、評価制度と報酬制度とのバランスを保つことが重要となってきます。
2. 等級制度の導入目的

等級制度を導入する主な目的は、「人事処遇の基準とするため」「社員に求める業務レベルを提示するため」「社員の自律した成長を促すため」などが挙げられます。それぞれ、どのようなことなのか詳しくみていきましょう。
2-1. 人事処遇の基準とするため
昇進や昇給の明確な基準がないと、貢献している社員に対して適切な処遇をおこなうことはできません。しかし、等級制度を導入することで、社員の処遇や待遇を決定するための基準が明確になるので、根拠に基づき社員の処遇を適切に決定することができます。
明確な基準があることで、評価を実施する管理者の負担も軽減することができ、なおかつ公平性のある評価を実現することが可能です。また、評価に対する社員からの納得感も得られやすくなります。
2-2. 社員に求める業務レベルを提示するため
等級制度は、企業が社員に求める業務レベルの共有にも活用が可能です。各等級に達するために満たすべき条件を明文化することで、企業が期待する社員の姿を方向付けることができます。
等級を決める際に自社の経営理念や事業戦略等とすり合わせておけば、企業が社員とビジョンを共有するのにも役立つでしょう。
2-3. 社員の自律した成長を促すため
等級制度では、次の等級へ進むために必要な能力や役割を明示できるため、社員にとっては将来のキャリア形成がしやすくなるのも、等級制度の特徴の一つです。
将来のキャリアパスを考え目標設定ができることから、自発的な成長を促す効果が期待できるでしょう。これにより、社員のモチベーションを維持することができ、長期的な人材確保にもつなげることができます。
3. 等級制度の種類

等級制度は社員の能力・職務・役割のどこに軸を置き序列化するかにより、以下の3つの制度に分けられます。
- 能力:職能資格制度
- 職務:職務等級制度
- 役割:役割等級制度
各制度が重視する面やメリット・デメリットが異なるため、それぞれ詳しく解説します。
3-1. 能力:職能資格制度
職能資格制度は、能力や経験(勤務年数)により社員の等級を決定する制度で、「人」そのものに着目している点が特徴です。なお、ここでいう能力とは、特定の分野における専門資格などではなく、企業が抱えるすべての職務に共通して活用できる力を指します。
そのため、職務経験の豊富さが能力の高さと判断されやすい傾向があります。
職能資格制度は日本企業ならではの人事評価制度で、以前は企業文化を熟知したゼネラリストの育成に役立つことから、企業の発展を支えてきました。しかし、現在では人件費負担の増加などもあり、変化が進む制度のひとつです。
3-2. 職務:職務等級制度
職務内容に難易度を設定し、等級や賃金を決定するのが職務等級制度で、人材そのものではなく「仕事」のみに着目する点が特徴です。あらゆる職務とその職務に対する難易度はあらかじめ「職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)」に明記され、その内容を元に賃金が決定されます。
職務等級制度はアメリカで発展し、海外で普及している等級制度です。社員の人種・学歴・年齢・職歴などが一切考慮されない完全な成果主義であるため、同一労働同一賃金を実践しやすく、正規社員と非正規社員の不合理な待遇の解消にも役立ちます。
また、仕事ができる社員ほど賃金も高くなる等級制度であるため、スペシャリストを育成しやすい点も特徴です。
関連記事:職務等級制度の意味や職能資格制度との違いをわかりやすく解説
3-3. 役割:役割等級制度
役割等級制度では、等級で期待される能力と職務内容をかけ合わせた役割(ミッション)により、等級を決定する制度です。ミッショングレード制とも呼ばれ、人にも仕事にも着目した制度内容となっています。
職能資格制度と職務等級制度のメリットを融合させたような制度で、社員のモチベーションを保ちつつ、人件費をある程度コントロールできます。現在の日本企業で導入が進んでいます。
関連記事:役割等級制度のメリット・デメリットや導入方法を詳しく解説
4. 等級制度のメリット
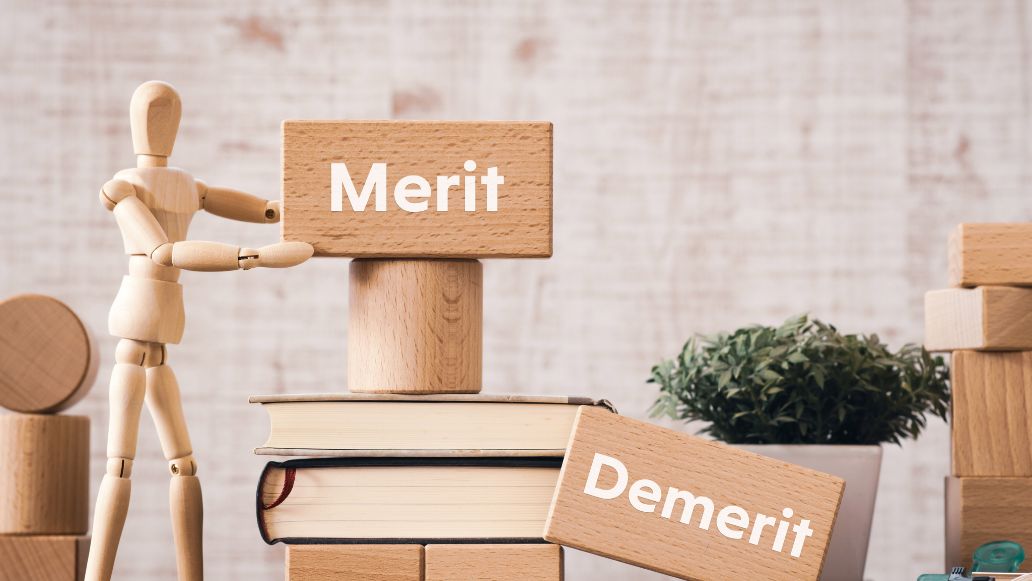
等級制度を導入するには、基準や等級数の決定、全社員への周知など手間と時間がかかります。しかし、手間がかかっても導入する企業が増えているのは、それなりのメリットを得られるからです。
ここでは、等級制度の種類ごとのメリットを紹介します。
4-1. 職能資格制度のメリット
職能資格制度のメリットは、人事異動・職務変更がしやすく人材を柔軟に活用できる点です。また、長期雇用が前提となるため、組織文化を形成しやすく、そこで育まれた社員の能力が企業の強みになるケースもあります。
また、職種や業務を問わず導入できるので、複数の事業を展開している会社であっても、人事制度を統一できるというのもメリットです。
社員のメリットは、安定性の高い働き方が実現でき、キャリアイメージが明確になることです。また、異動があってもキャリアを形成できるので、公平性が高いというのもメリットといえるでしょう。
4-2. 職務等級制度のメリット
職務等級制度のメリットは、職務内容に対応する賃金を明確にできることから、社員の納得感を得やすい点です。さらに、優秀な人材を集めやすくなり、年功序列型賃金に不満を持つ社員の離職防止にもつながります。
また、人材を適材適所に配置できるので、雇用形態や人種差別などで訴えられるリスクを減らせる効果も期待できるでしょう。
成果に応じた賃金体系を実現できるため、業績が伴わない人件費の高騰を防げるなど、人件費をコントロールしやすい点もメリットです。
4-3. 役割等級制度のメリット
役割等級制度のメリットは、職務内容だけでなく等級に期待される役割も設定できる点で、たとえば、管理職に期待される業務も設定できます。役割が上がるにつれ賃金も上昇するため、社員のモチベーション向上にもつながります。
年齢や勤続年数により単純に賃金が上がるわけではないため、企業は職能資格制度よりも総人件費を抑えやすくなる点もメリットです。また、職務等級制度ほど詳細な役割に対する設定が必要ないため、導入もしやすくなります。
5. 等級制度のデメリット
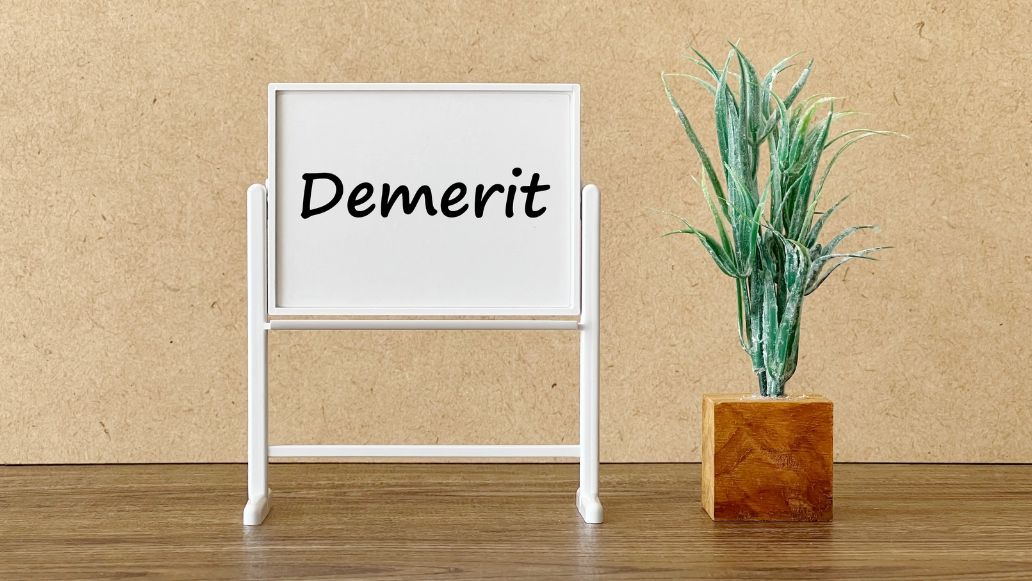
等級制度にはデメリットもあります。デメリットを考えずに導入してしまうと、目的とする効果が得られなくなるかもしれません。メリットだけでなくデメリットも把握し、デメリットが制度運用に大きな影響を与えないかをしっかり考慮しておくことが重要です。
ここでは、各制度のデメリットを紹介します。
5-1. 職能資格制度のデメリット
職能資格制度は、年功序列型に偏ってしまうため、経験値がない若手社員のモチベーションが上がりづらいのがデメリットです。年功序列型の制度は、長期間勤務しているベテラン社員と若手社員の隔たりになることもあり、フレッシュな人材が離職する要因になることもあるので注意が必要です。
また、勤務期間によって賃金を上げていくため、職能資格等級と実際の職務内容に対する賃金が見合わない可能性もあります。さらに、勤続年数により賃金も上昇するため、人件費の調整が難しく、負担が大きくなるのもデメリットといえるでしょう。
5-2. 職務等級制度のデメリット
職務等級制度のデメリットは、導入時に職務記述書を設定する際の煩雑さです。すべての職務内容に対する賃金を決定するため、多くの時間と手間がかかります。
運用にあたり、専門の人事・労務担当者が必要となることも少なくありません。
また、仕事が個人プレーに偏る傾向があるため、相乗効果やイノベーションのような、チームワークから生まれる利点が享受しづらくなります。さらに、業務が属人化しやすく、組織の硬直を招きやすい点も難点です。
5-3. 役割等級制度のデメリット
デメリットは、役割等級制度の運用方法が統一されておらず、企業によりそれぞれ設定が必要な点です。役割を設定するには時間がかかる上、設定ミスをしてしまうと社員のモチベーション低下を引き起こすリスクもあります。
また、役割に期待される仕事の定義が曖昧だと、それを元にした等級の信頼性が揺らぎ、降級もあることから社員の不満につながる恐れがあるのもデメリットといえるでしょう。
6. 等級制度の作り方

どの種類の等級制度を導入するにしても、効果的に運用していくためには、しっかりと計画を立てて作ることが重要です。
思いつきのままに作成してしまうと、評価基準と目的がずれてしまい、結果的に導入効果が得られなくなるかもしれません。等級制度の作り方はシンプルですが、一つひとつのステップに時間をかけて組立てていきましょう。
6-1. 導入目的を明確にする
まずは、等級制度を導入する目的を明確にしましょう。人事業務の効率化が目的とされることが多いですが、等級制度はさまざまなことに役立ってくれます。例えば、等級基準を決めることで目指す業務レベルが明確になるので、「社員のモチベーションがアップする」というメリットや、「適切な人材配置ができる」などのメリットがあります。
そのため、どのような企業風土を目指すのか、どういった人材が必要なのかなど、目的を定義しましょう。
6-2. 等級制度の種類を決める
目的が明確になったら、次はその目的に合った等級制度の種類を決めます。
等級制度の種類は、以下の3つです。
- 職能資格制度
- 職務等級制度
- 役割等級制度
職能資格制度は、継続年数によって等級を決めるので、どんな職種でも導入しやすいです。ただし、長期勤務の社員が増えるほど人件費の負担が大きくなります。
職務等級制度は、成果によって等級を決めるので公平性が高く、社員の納得感も得られます。ただし、成果がわかりづらい事務職などには向いていません。
役割等級制度は、能力と業務内容によって等級を決めるので、人件費が無駄に上がることもなく社員のモチベーションをアップできます。しかし、決める項目が多く、結果を出す手間もかかるので、専任の担当者がいないと運用が難しいかもしれません。
このように、それぞれの制度の特徴を踏まえつつ、自社に合った制度を選びましょう。
6-3. 等級数の確定
等級制度を決めたら、次は等級数を決めましょう。等級数は会社の規模や社員数などによって異なりますが、目安としては管理職が3つ、一般社員は4つもしくは5つとなります。
等級数は意外に重要なので、安易に作らないように注意してください。数が少ないと、等級幅が広くなってしまうため、同じ等級でも能力で差が出る可能性があります。逆に多すぎると、等級の差別化が難しくなるため、社員は等級制度の恩恵を感じられなくなるかもしれません。
これでは、等級制度導入のメリットが得られないので、会社の規模と社員数をしっかり考慮して決めるようにしましょう。
6-4. 各等級の定義を決める
等級数が決まったら、最後は等級ごとに能力基準や評価の定義を決めましょう。
定義は、すべての職種に対して共通にすることもできますが、部署によっては業務内容に大きな違いがあります。例えば、営業部と総務部の場合、片方は売上に直結する業務で片方は組織運営をおこなう業務なので、定義によっては共通にできないかもしれません。
そのため、全職種に共通させるのであれば、どのような業務でも当てはめられる定義を決める必要があります。共通の定義を作るのが難しい場合は、職種ごとに明確な基準を設定しましょう。
定義は公平な評価をおこなうために必要不可欠ですが、より具体的にすることで目標も明確になり、社員も理解しやすくなります。
7. 等級制度を活用するポイント

等級制度は種類により評価対象やメリット・デメリットが大きく異なるため、業種や業界なども考慮し、企業の状況にあった制度の導入がポイントです。
また、部門により等級制度を変えることで、より適した人材の獲得につながるケースもあります。
ここでは、それぞれの等級制度がどのような組織に適しているか紹介します。
7-1. 職能資格制度が適した組織
コアスキルがすでに競争力として確立している企業では、人材を長期間育成し、ゼネラリストを多く育成できる職能資格制度が適しています。人事異動が多い業界でも、人に着目した職能資格制度が役立つでしょう。
ほかにも、社員に対し、雇用の安定性やキャリアパスの明確さを示したい組織にもおすすめです。
7-2. 職務等級制度が適した組織
グローバル人材の採用が多い企業では、賃金の決定方法が明確な職務等級制度がおすすめです。昇進や降格がしやすく、不要な職務は圧縮できることから、成長過程にある企業にも適しています。
企業全体に導入するのではなく、特定の職種のみに導入するのもおすすめです。具体的にはチームワークよりも個の能力が重要な、専門性の高い職種が適しています。
7-3. 役割等級制度が適した組織
役割等級制度は、3つの等級制度のうち、とくに日本企業で採用されているため、多くの企業で導入しやすいでしょう。
この制度は、役割の価値の大きさが給与に反映されるので、はっきりと成果がわかる業種に向いています。
また、仕事だけで判断するのではなく、管理職など役割に応じて賃金を上げられるため、年功序列型賃金によって人件費が高騰している、負担が大きいという企業にもおすすめです。
8. 等級制度の導入事例

最後に、等級制度を導入した企業の事例をご紹介します。等級制度を導入したことによってどのような効果があったのか、他社の事例をチェックしてみましょう。
8-1. 自動車関連業界の導入事例
自動車の部品製造も担う金属熱処理加工業者では、以前より人事制度の改革が課題となっていたことから、社内プロジェクトを立ち上げて、等級制度の策定に乗り出しました。
コンサルタントから勧められた職業能力評価基準をベースに、自社の業務に合うように能力ユニットを独自に作成したり、社員の気付きを促すことに重点を置いたりなど、自社に合わせて制度設計が進められました。
等級制度を導入したことにより、社員の業務が見える化できただけでなく、社員がキャリアパスを描きやすい人材育成プログラムの体系化にも成功されています。
8-2. 教育業界の導入事例
学習塾等を運営する(株)京進の導入事例です。人事評価の考課基準が各部署で個別に設けられている状態であったことと、業績にだけ主眼を置いた制度であったことから、評価制度の見直しが図られました。
この際に、白羽の矢が立ったのが等級制度です。能力に焦点をあてた評価ができることで採用が決まりました。一般的な等級制度の内容をベースに自社の企業ビジョンを反映させ、自社のあった内容に制度がカスタマイズされています。
導入後は、社員の気づきを促せるようになり、キャリアアップを目指す社員に教育の場を提供するなど、社員の自発的な成長につなげています。
9. 等級制度は種類により評価対象が異なる点に注意

等級制度とは能力・職務・役割により社員をランク付けする人事評価制度で、評価対象により職能資格制度・職務等級制度・役割等級制度の3つに分けられます。それぞれ適した組織や運用方法も異なるため、導入時にはどのような特徴があるか確認し組織文化に適したものを選びましょう。
導入や周知には時間と手間がかかるかもしれませんが、適した等級制度の導入により、社員のモチベーションを向上する、人事管理を容易にするなどのメリットが生まれます。しかし、担当者の負担が増えすぎると運用も滞ってしまうので、そのような場合は人事評価システムなどを併用して負担を減らしていきましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































