労働基準法第9条に規定された労働者について詳しく解説
更新日: 2024.4.15
公開日: 2021.10.4
OHSUGI

労働基準法は「労働者」を守るための法律です。労働者とは会社と雇用契約を結んでいる従業員のことで、正社員や契約社員、アルバイトなどさまざまな雇用形態があります。
しかし、事業主や役員、役員報酬をもらっている管理職などは会社と雇用契約ではなく委任契約を結んでいるため労働者になりません。
この記事では、労働基準法第9条で規定されている労働者についての解説と、労働者と労働者ではない場合の違いについて解説しています。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 労働基準法第9条に規定された労働者とは?


労働基準法第9条には、以下のような記載があります。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この労働者は会社の指揮監督下にあり、賃金が支払われる従業員のことです。
近年では、正社員以外の雇用形態が増えています。
労働基準法では「労働者」に該当するにも関わらず、労働者として扱わない場合は処罰の対象となる場合があるので、次に労働者の種類や条件についても確認しておきましょう。
2. 労働基準法第9条に規定された労働者の種類


労働基準法では、労働者とは会社に雇用されていて賃金が支払われている者とあります。
労働者の種類は以下のものがあげられます。
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員(派遣元)
- アルバイト・パート
- 日雇い労働者
- 海外出張者 など
正社員だけではなく、契約社員や派遣社員などの就業期間が決まっている場合やアルバイト・パート、日雇い労働省などの就業日数が少ない場合も労働者に該当します。
ただし、派遣社員の取り扱いについては注意が必要です。
派遣社員は勤務先ではなく、派遣元の派遣会社のから賃金を受け取るため派遣会社の労働者になります。そのため、原則として就業規則や労働条件などは、派遣元の会社で定めたものに従わなければいけません。
3. 労働基準法第9条に規定された労働者に含まれない人
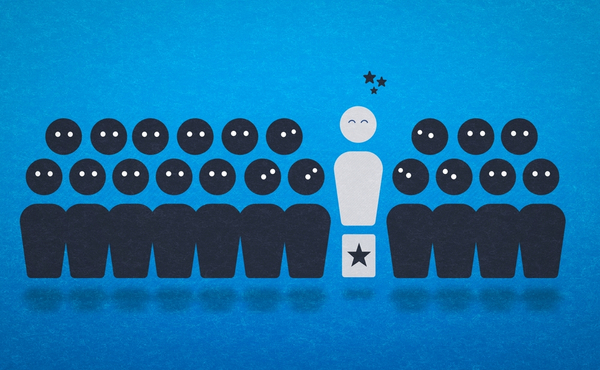
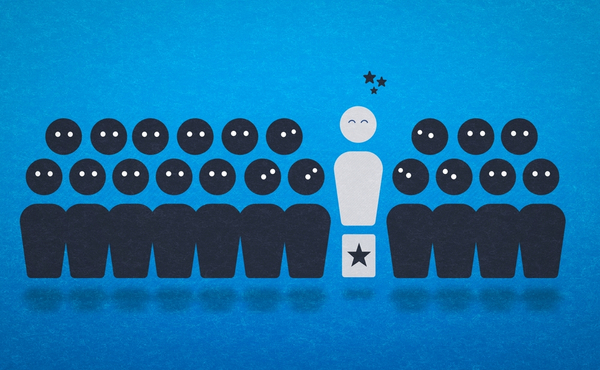
労働基準法の労働者に含まれない種類は以下の3つです。
- 事業主
- 役員報酬を得ている役員(賃金をもらっている役員は労災の対象者となる)
- 事業主の親族
労働者とは会社と雇用契約関係にある状態の従業員です。そのため、会社経営者の事業主は労働者ではありません。
そして、役員は委任契約関係、別の言い方をすると業務委託契約になります。雇用契約を結んでいない役員は労働者にはなりません。
また、事業主の親族の場合は少し複雑になります。親族が役員として働いている場合は、当然ではありますが労働者に含まれません。
しかし、勤務時間、休日日数、休憩時間、賃金などの決定がほかの従業員と同じで、同じように就労している場合は労働者として認められる場合があります。
個々の事情により労働者になるのか変わるため、労働者になるのか分からない場合は労働基準監督署に問い合わせて確認するのが確実な方法です。
3-1. 管理職は労働者になる?
役員報酬を得ていない課長や係長などは、管理職であっても労働基準法では労働者になります。
ただし、経営者と同じような立場にあり、ほかの従業員と違い重要な職務内容を有する管理監督者は、労働時間や休日などに関する労働基準法の一部が適用外になってしまう場合があります。
このような場合は労働基準法の一部が適用外になるというだけで、原則として労働者として扱われます。
関連記事:管理職の労働時間・休憩時間や休日についての基礎知識を徹底解説!
4. 労働基準法第9条で労働者と規定されると変わること


労働者は労働基準法に適用されますが、役員や事業主などの使用者は労働基準法の適用外になります。
しかし、労働者と役員は同じような環境で勤務する場合があるため、労働者と労働者ではない場合でなにが変わるのか覚えておくといいでしょう。
ここでは代表的なものを5つ解説します。
4-1. 時間外労働の制限
労働基準法では、労働者は繁忙期などの臨時的な特別の事情がない場合は、時間外労働(残業)の時間を原則「月45時間」「年間360時間」以内に収めるように規制されています。
また、特別な事情がある場合も時間外労働の時間は無制限ではありません。
特別な事情がある場合は、「年間720時間」の上限に加え、時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」かつ「2〜6か⽉平均80時間以内」を超えてはいけないと定められています。
これらの制限は労働者のみ適用されています。事業主や役員などは、時間外勤務の制限がなく、時間外手当がない場合があります。
4-2. 労働保険
労働保険とは、労働者を雇用した際に使用者に加入が義務付けられる労災保険と雇用保険の総称を指します。
労災保険は業務中や通勤途中に怪我や病気があった場合、治療費や休業時の賃金などを補償する制度です。
一方で、雇用保険は労働者の生活や雇用の安定を図るために、労働者が失業した際や会社側で雇用の継続が困難となった際などに、必要な給付がおこなわれる制度となっています。
いずれも、正社員やパート・アルバイトなど雇用形態を問わず、加入が義務付けられている強制保険です。ただし、雇用保険に関しては、以下の条件を満たす場合に限り、加入が求められます。
- 1 週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
労働保険は労働者の保証をおこなうための保険であるため、原則として事業主や役員は労働保険に加入することはできません。
関連記事:労働保険の加入手続き方法や計算方法を分かりやすく解説
4-3. 有給の義務化
会社は労働者に対し、入社日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の有給休暇を付与しなければいけません。
有給休暇は正社員だけではなく、派遣社員やアルバイト、パートにも付与されます。
勤務日数によって付与される有給日数が変わるため、週に数回しか出勤しないパートの場合はその分だけ付与される有給日数が少なくなります。
役員の場合は雇用契約ではなく委任契約を結んでいるため、役員には年次有給休暇は付与されません。
関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説
4-4.「解任」と「解雇」の違い
役員は会社と委任契約を結んでいるため、会社都合で会社を去るときは解雇ではなく解任になります。
解任は株主総会で解任決議をおこない、可決されると認められます。
一方の労働者が会社都合で会社を去るときは、解雇になります。
労働基準法第20条の規定により、解雇の場合は30日以上前に会社は労働者に対し、解雇通知をしなければいけないことになっています。
4-5. 就業規則
就業規則とは会社や労働者が守るべきルールを定めたものです。
就業規則は会社や従業員によってさまざまで、賃金の額や仕事内容、休日などが決められている非常に重要なものです。
労働者の場合は会社と雇用契約を結んでいるため、就業規則に従う必要がありますが、役員などのように委任契約の場合は就業規則に従う必要はありません。
ただし、大企業では役員用の就業規則である役員規定があることがあります。
関連記事:労働基準法第89条で定められた就業規則の作成と届出の義務
5. 労働基準法第9条の定義を正しく理解しよう
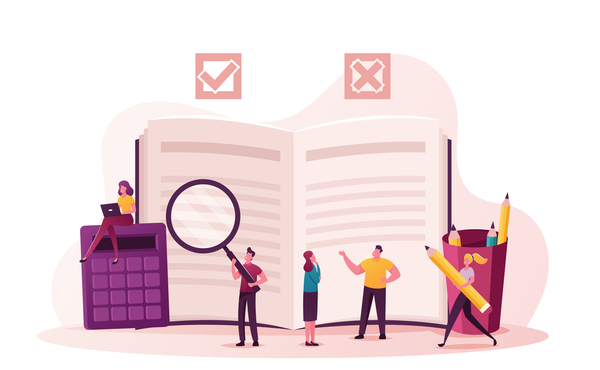
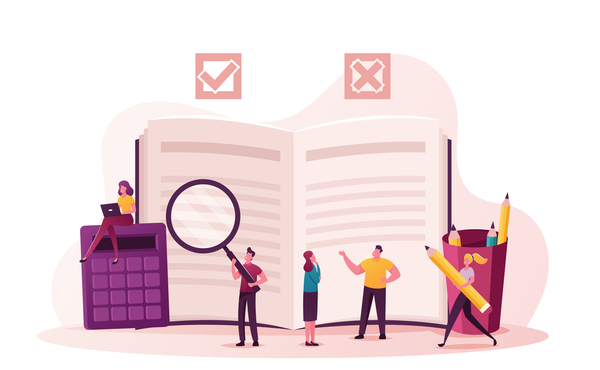
労働基準法では労働者は会社と雇用契約を結んでいる従業員と規定されています。事業主や委託契約の役員などは労働者には該当しません。
労働者は就業時間の制限や労働保険といった制度の対象となりますが、労働者でなくなると制度の対象外となります。
あとから大きなトラブルになるのを防ぐためにも、労働者から労働者ではなくなる場合にどのような変化があるのか覚えておくといいでしょう。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08






















