社会保険の被保険者資格喪失届が必要なケースや提出が義務付けられた書類とは

従業員が社会保険の資格を失ったときは、事象が発生した日から5日以内に、会社が手続きをおこないます。
この記事では、社会保険の被保険者資格喪失届を届け出るケースや添付書類がどこでもらえるか、資格喪失後でも従業員が受けられる給付の種類を解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 社会保険の被保険者資格喪失届が必要なケース


- 退職したとき
- 適用除外になったとき
- 資格喪失年齢に達したとき
- 死亡したとき
これらに該当するときなどは、速やかに社会保険の被保険者資格喪失届を届け出ましょう。
1-1. 退職したとき
退職したときは社会保険の喪失手続きが必要です。
本人に提出してもらう書類はあるものの、手続きはすべて会社でおこないます。
1-2. 適用除外になったとき
厚生年金や健康保険には、1週の所定労働時間や1ヵ月の所定賃金など、加入条件が定められています。
臨時雇用や、短時間のパート・アルバイトなど、加入条件を満たさない雇用契約に変更した際は届け出が必要です。
1-3. 資格喪失年齢に達したとき
厚生年金保険や健康保険など、それぞれ資格喪失年齢に達し、なおかつ社会保険に加入する従業員を雇用しているときは、届け出が必要です。年齢については後述します。
1-4. 死亡したとき
従業員が死亡した際も、会社から届け出が必要です。
なお、従業員が上記1-1~1-4のいずれかに該当し、資格喪失の手続きを行うこととなった際には、従業員に対し健康保険証(扶養親族がいたときは、扶養者分の健康保険証)を発行している場合には、忘れずに回収するようにしましょう。
2. 社会保険資格を失うときの提出書類とは?


- 年金保険と健康保険(協会けんぽ) →年金事務所のみ
- 年金保険と健康保険(健康保険組合)→年金事務所と健康保険組合
2-1. 厚生年金保険被保険者資格喪失届(社会保険被保険者資格喪失届 )
従業員が社会保険資格を失う際に届け出る書類で、正式には「被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」といい、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
書類には以下の内容を記入します。
- 提出する事業者情報(会社名・住所など)
- 被保険者情報(氏名・基礎年金番号・喪失理由など)
なお、健康保険組合に加入している場合、健康保険の資格喪失分はそれぞれの組合で手続きをおこないます。
各健康保険組合のホームページから該当する書類をダウンロードし、申請しましょう。
参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き | 日本年金機構
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースとは
2-2. 添付書類
添付書類は保険者により異なるほか、60歳以上の雇用(定年再雇用)では複数の書類が必要です。
【会社が協会けんぽに加入している場合】
従業員の状況に応じ、下記の書類を添付します。
- 従業員本人と扶養者分の健康保険被保険者証
※下記が公布されている場合は回収が必要です。
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用
- 標準負担額減額認定証
なお、添付する保険証などは原本が必要なため、回収漏れのないように注意しましょう。
【60歳以上の従業員の再雇用の場合】
60歳以上の従業員が退職後、1日も開けずに再雇用されたとき(定年再雇用)は下記の書類が必要です。
- 退職日が確認できる 「就業規則」や「退職辞令」の写し
- 継続して再雇用されたことが分かる「雇用契約書」の写し
- 「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
1と2、または3の書類が必要です。
【会社が各健康保険組合に加入している場合】
年金事務所に提出する届出への添付書類は不要です。
ただし、各健康保険組合にも保険証の返却が必要になるため確認しましょう。
3. 社会保険の被保険者資格喪失届の手続き方法


3-1. 喪失届をダウンロードして入手する
従業員が社会保険資格を喪失する場合、会社はまず社会保険の被保険者資格喪失届を準備する必要があります。期限内に提出するため、適切な用紙を早めに入手しましょう。
社会保険の被保険者資格喪失届の用紙は、日本年金機構の公式ホームページからダウンロード可能です。利用者はPDF形式の用紙を手に入れることができるほか、直接入力できるExcel(エクセル)形式の用紙も提供されています。この用紙を用いて、必要事項を記入し、提出に向けた準備を進めます。
3-2. 記入例の書き方を参考に記載する
被保険者資格喪失届の記入時には、各項目の指定された情報を正確に記入することが求められます。以下に、主要な項目に沿った記入方法を説明します。
| 項目名(欄) | 記入すること | ポイント |
| 事業者の名称・住所 | 事業主の正式名称と住所を記入 | 事業所整理番号や事業所番号は、資格取得時に新たに付与された番号であり、名称や所在地を変更した場合にも記入が必要です。この番号は、事業所に一意に割り振られるため、正確に記入することが重要です。 |
| 被保険者番号 | 資格を失う従業員の資格取得時に発行された番号を記入 | この番号は、その従業員を特定するためのものであり、間違いのないように慎重におこないましょう。 |
| 氏名 | 住民票に記載された通りの従業員の名前を記入 | 漢字やカタカナの表記を間違えないように注意が必要です。 |
| 生年月日 | 従業員の生年月日を正確に日付形式で記入 | 誕生日のミスがないよう確認しながら進めましょう。 |
| 個人番号・基礎年金番号 | 従業員から正確な個人番号を確認し、その番号を記入 | 基礎年金番号については、指示に従い左詰で記入しましょう。 |
| 資格喪失年月日 | 喪失の理由によって異なる日付を記入 | ※次の章で詳しく説明します。 |
| 資格喪失の原因 | 喪失理由に応じた番号に○をつける | 例えば、退職の場合は4、死亡の場合は5というように指示に従って記載します。 |
| 保険証の枚数 | 回収された保険証の枚数と回収できなかった枚数を記入 | これにより、正確な記録を残すことができます。 |
| 70歳不該当 | 70歳以上の被保険者が退職や死亡によって資格を喪失する際に記入 | この項目をしっかりと記入することで、特例の管理を円滑におこなうことができます。 |
記入が完了したら、提出前に誤りがないか必ず確認しましょう。
参考:記入例 | 日本年金機構
3-3. 提出先へ届出
なお、健康保険組合は、別途、健康保険の資格喪失の書類を組合へ送付します。提出先を間違えることがないよう押さえておきましょう。
4. 社会保険の被保険者資格喪失届における資格喪失日の注意点


社会保険の資格喪失事由によって資格喪失日は異なるため、社会保険の被保険者資格喪失届を提出する上でも資格喪失日の記載は間違えやすいポイントです。ケースごとにどのように異なるのか、具体例を交えながら確認しておきましょう。
4-1. 資格喪失日が翌日になるケース
事由発生の翌日に社会保険の資格を喪失するケースは、主に以下の2つです。
- 退職
- 死亡による退職
それぞれ詳しく見ていきましょう。
死亡・退職による資格喪失
退職の場合、被保険者資格は退職日の翌日に資格を喪失します。また、死亡の場合については、死亡日の翌日が資格喪失日となります。
このため、退職や死亡が発生した場合には、その日付を明確に把握し、速やかに社会保険の被保険者資格喪失届を提出することが重要です。こうした手続きを円滑に進めるためには、事前に情報を整理し、必要な書類を準備しておくことが求められます。
4-2. 資格喪失日が当日になるケース
事由発生の当日に社会保険の資格を喪失するケースはいくつかあります。
- 定年退職後に再雇用される場合
- 75歳に達した場合
- 65歳から75歳の被保険者が障害認定を受けた場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
定年退職後に再雇用される場合
定年退職後に再雇用される場合、特に給料が大きく下がることがあるため、社会保険の取り扱いには注意が必要です。この場合、再雇用時に従前の社会保険に継続加入していると、給料が減少しているにもかかわらず、社会保険料が変わらず高額になるという不均衡が生じることがあります。これを防ぐための手続きが「同日得喪」と呼ばれるものです。
同日得喪は、退職当日に被保険者資格を喪失し、その日のうちに新たに社会保険の資格を取得することでおこないます。この手続きは、主に60歳以上の被保険者を対象に実施され、再雇用された際に無理なく社会保険に加入し続けることができるための重要な方法です。これにより、再雇用後の不利益を軽減することが可能となります。
参考:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき | 日本年金機構
75歳に到達した場合
75歳に到達した場合、被保険者は後期高齢者医療制度に移行します。このため、通常の社会保険の被保険者資格は喪失されます。
資格喪失日については、75歳の誕生日の当日が明確に指定されており、この日をもって被保険者資格が消失します。なお、この際には社会保険の被保険者資格喪失届の提出が必要となります。移行後は、後期高齢者医療制度の適用を受けることになりますので、手続きについても確認しておくことが重要です。
高齢者医療制度への変更は、医療サービスや保険料に関して異なる扱いになりますので、詳しい内容を理解しておくことが求められます。そのため、各自の状況に応じた適切な対処が求められます。
65~74歳の被保険者が障害認定を受ける場合
65~74歳の被保険者が障害認定を受ける場合、後期高齢者医療制度に移行します。障害認定がおこなわれた時点で、65歳以上の被保険者はその障害状態が確認されるため、資格喪失日は障害認定日当日となります。
この制度においては、従来の健康保険から後期高齢者医療制度にスムーズに移行できる仕組みが整っています。つまり、障害認定を受けることによって新たな医療制度に入ることができ、その後の医療費の負担が軽減されます。
なお、障害認定の詳細な手続きや必要書類については、事前に確認しておくことが重要です。これにより、手続きが円滑に進むでしょう。
4-3. 被扶養者の資格喪失日について
被扶養者の資格喪失日は、被保険者の資格喪失日と同日となります。社会保険の被保険者が資格を喪失すると、被扶養者も自動的にその資格を喪失するためです。
これにより、被保険者が退職や適用除外、資格喪失年齢の到達、あるいは死亡に至った場合、被保険者と同じタイミングで被扶養者も資格喪失の手続きをしなくてはいけません。適切な対応をおこなうためには、被保険者の資格喪失時期を確認し、関係する手続きを迅速に進めることが求められます。
5. 社会保険の被保険者資格喪失届提出後に受けられる給付の種類


必要に応じて、従業員やその家族に伝えましょう。
以下では、4つの給付の種類と要件を紹介します。
5-1. 傷病手当金:1年6ヵ月を限度に支給
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失した際、傷病手当金の支給を受けていた、または受けられる状態であった
5-2. 出産手当金:出産の日以前42日(多児妊娠98日)から産後56日までの間
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失した際、出産手当金の支給を受けていた、または受けられる状態であった
5-3. 出産育児一時金:一児につき50万円
- 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった
- 資格喪失日以降、6ヵ月以内に出産した
5-4. 埋葬料:5万円の給付
- 傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けていた人が死亡した場合
- 傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けなくなってから、3ヵ月以内に死亡した場合
- 被保険者が資格喪失後、3ヵ月以内に死亡したとき
なお、請求は被保険者に生計を維持されていた者や、実際に埋葬した者がおこなえます。
6. 社会保険の被保険者資格喪失届についてよくある質問
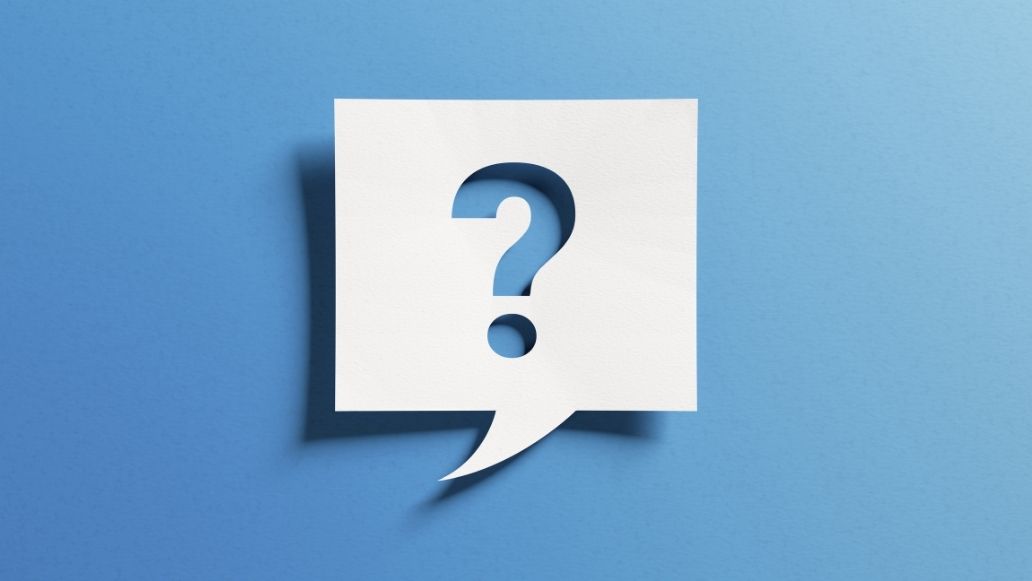
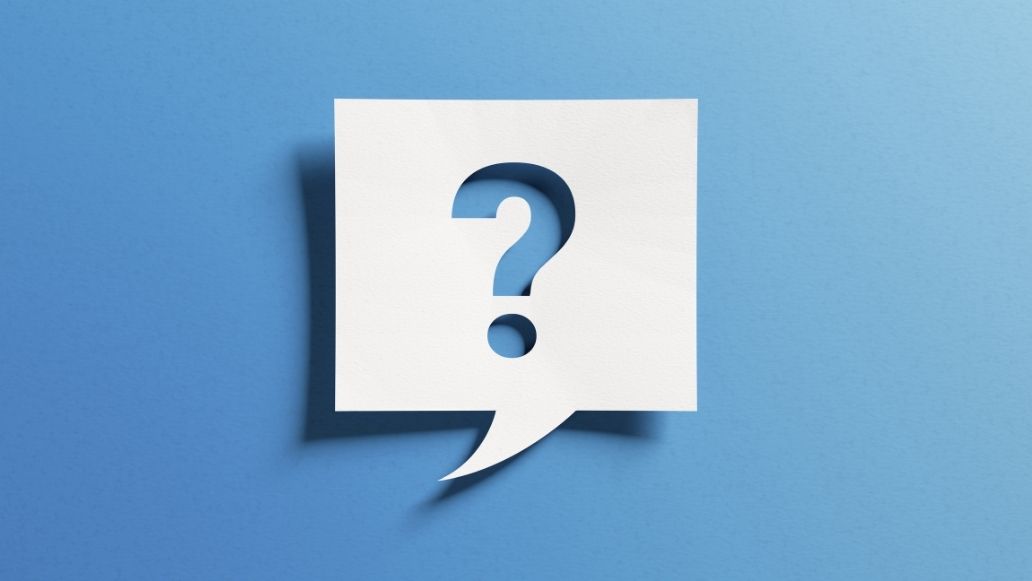
続いて社会保険の被保険者資格喪失届について、関連してよくある質問を紹介します。手続きを間違えることがないよう、事前によくある質問や間違いについて押さえておくことは担当者にとってとても重要です。
6-1. 会社側の提出期限はいつまで?
事実発生日から5日以内に手続きします。
事実発生日とは、資格喪失に該当する事象が発生したときです。
手続き上は、退職した日などの翌日(資格喪失日)から5日以内に処理すれば問題ありません。
当サイトでは、社会保険手続きの期限や手続きで必要な書類、担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きで不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
6-2. 健康保険証を紛失した際の手続き方法とは?
手続きの際、従業員によっては健康保険証を紛失しているケースもあるでしょう。
その際は、「健康保険被保険者証回収不能届」により申請しなくてはいけません。
もし、上記届け出提出後に保険証が見つかったときは、会社で破棄せず、各保険者に返却しましょう。
参考:日本年金機構 | 被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき
6-3. 従業員の家族に異動があった場合の対応は?
従業員が扶養している家族に移動(追加や除外)があった際も、会社で手続きが必要です。
その場合「健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届 国民年金第3号被保険者関係届」により手続きをおこないます。
参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき | 日本年金機構
6-4. 社会保険の被保険者資格喪失届の提出が遅れた場合の罰則は?
社会保険の被保険者資格喪失届の提出が遅れた場合にすぐに何らかの罰則が科せられるわけではありません。しかし、資格を喪失しているにも関わらず手続きをしないと、たとえば従業員が転職先の企業で社会保険に加入した場合、二重加入が起きるリスクがある点に注意が必要です。
企業側が社会保険料を余分に徴収されるだけでなく、従業員にも不利益が生じる可能性があります。特に年金を受給している従業員は、手取りの年金額が減る可能性が生じます。
手続きは期日通りにおこなうことが望ましいですが、万が一遅れてしまった場合には、速やかに年金事務所へ連絡を取り、早急に対応するようにしましょう。
7. 社会保険は資格喪失日を正しく理解し、速やかに必要書類を届け出よう


社会保険の資格喪失日は、通常、事実発生日の翌日です。
しかし、加入上限年齢に達した場合の喪失日は、保険制度により異なるため注意が必要です。
資格を喪失した際は、5日以内に年金事務所や健康保険組合で手続きをおこないましょう。必要な書類は日本年金機構の公式ホームページからダウンロード可能です。なお、健康保険組合は、別途、管轄の組合への送付が必要なため提出先を間違えないようにしましょう。
なお、従業員によっては健康保険証を紛失している可能性もあるでしょう。健康保険証を紛失しているのであれば、健康保険被保険者証回収不能届の申請が必要です。
傷病手当金や出産手当金など、資格喪失後も受けられる保険給付があるため事前に把握し、必要に応じて、従業員や家族に概要を伝えましょう。



従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
社会保険の関連記事
-


雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説
人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27
-


養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09
-


70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは
人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28






















