年末調整手続きの書類を郵送する方法や注意すべきことを紹介
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.4.5
OHSUGI

税務署に提出しにいく時間がない場合や、リモートワークを推進しているなどの理由で、年末調整書類の提出だけに税務署に行く時間を削減したいという考えを持つ人は少なくありません。
実は、年末調整の書類は郵送で税務署に送ることが可能です。この記事では、年末調整の手続き書類を郵送でおこなう方法や注意点について解説しています。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整の手続きは郵送でもできる

さまざまな場面で非接触・非対面型の対応が普及しており、年末調整の税務署への提出書類に関しても郵送で送ることが可能です。
その他の提出方法として、税務署に直接持参する方法や電子申請という方法があります。
電子申請は一部の企業で義務化されており、対象企業の場合、必ず電子申請で年末調整の書類を提出する必要があります。当サイトでは、年末調整の書類作成から電子申請までの方法を図などを用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。年末調整書類の提出方法を確認したい方は、電子申請義務化の対象もあわせて解説している「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご確認ください。
2. 年末調整手続きの書類を郵送する方法

年末調整の書類を税務署に郵送する場合は、自社で確実に必要書類をそろえて正しい方法で郵送しなくてはいけません。ここでは郵送する方法、必要書類、郵送先について解説します。
2-1. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出
年末調整の際には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」を税務署に提出しなくてはいけません。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票とは、法定調書を合計した表のことです。法定調書とは、給料や報酬を支払ったものが、支払先の住所、氏名、支払金額を記載した書類のことをいいます。
この法定調書があることで、支払いを受けたものが確定申告をしていなかった、または、受け取った額より少ない金額で確定申告をしていた場合に、支払った側、支払いを受けた側のどちらかが間違っていることがわかるようになっています。
国税庁に掲載されている所得税法に規定する法定調書の数は全部で60種類あります。そのうち、年末調整に必要な書類として以下の6種類の取引について作成が必要とされています。
それぞれ一定の金額を超えると添付書類が必要になり、必要書類も含めて翌年の1月31日までに提出が必要です。
必要な6種類の書類は以下の通りです。
2-1-1. 給与所得の源泉徴収票合計票
従業員や役員ごとに支払った給与や賞与の年間の合計や、所得控除の情報を記載します。
給与などの支払金額が従業員の場合は年間500万円。役員の場合は年間150万円を超える人の源泉徴収票の提出が必要です。
2-1-2. 退職所得の源泉徴収票
その年に退職者がいて、退職金を支払った場合に退職金や退職所得控除の金額を記載します。退職金の支払いがあればその人の源泉徴収票の提出が必要です。
2-1-3. 外注業者などへの源泉徴収票
執筆やセミナー講師代金、弁護士や税理士への報酬のように源泉徴収の対象となる報酬や支払いをする際に必要な書類です。
その人に支払った金額と源泉徴収をした金額を記載します。1人あたり年間5万円を超える支払いがあった場合はその人の源泉徴収票が必要です。
2-1-4. 不動産の使用料等の支払調書
事務所や店舗、駐車場などを毎月、または年払いで利用している場合に支払額を記載する必要があります。
2-1-5. 不動産の譲受けの対価の支払調書
その年に購入した不動産がある場合、購入金額を記載します。
2-1-6. 不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
その年に不動産の売買や貸し付けの斡旋手数料を支払った場合には、その金額を記載します。
関連記事:年末調整で退職者がやるべき手続きを分かりやすく解説
2-2. 年末調整手続きの書類は信書扱い
国税庁のホームページでは税務上の申告書や届出書は信書にあたるとされています。したがって「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付しなくてはなりません。
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは信書を送付することはできない点には注意が必要です。なおレターパック(レターパックプラス、レターパックライト)による信書の送付は問題ありません。
第一種郵便物には封筒も含まれるため、通常の郵便物として送ることは可能ですが、配達が遅れた場合のことも考えて郵便物の追跡ができるようにしておきましょう。
したがって、特定記録郵便、簡易書留、レターパックなどを利用することをおすすめします。ただし、一定の料金がかかるので注意が必要です。
2-3. 郵送先は管轄する税務署宛
年末調整の書類の送り先は管轄する税務署宛になります。宛名は「〇〇税務署 御中」と記載するだけです。なお、国税庁のホームページで、自社の事業所の郵便番号や住所を入力すれば管轄の税務署を検索することができます。
また、添え状として簡単な挨拶と内容物の解説を記した一枚を同封するケースもあります。
【参照】あえて税務署に書類を郵送するときの方法と注意点まとめ
3. 年末調整手続きの書類を郵送する際の注意点
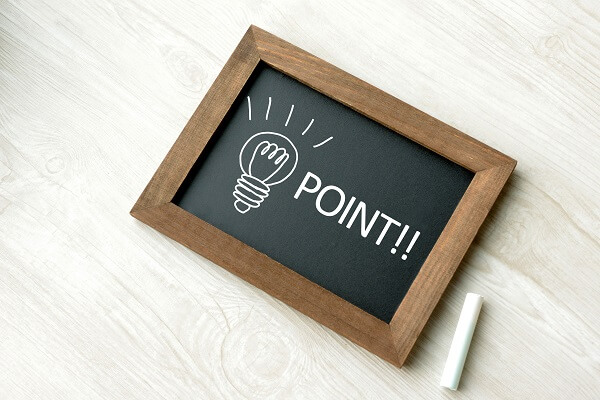
年末調整手続きの書類を税務署に郵送する際は、直接持ち込む方法よりも注意しなくてはいけない点があります。再提出にならないように、以下の点に注意しましょう。
3-1. 郵送は到着までに数日かかる
税務手続きに関する書類の提出日は原則「到達主義」です。到達主義では、文書が税務官庁に到着した日が提出日として扱われます。
しかし、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出日が1月31日のように提出日に具体的な成約がある書類は、郵便物や信書便物の通信日付印(郵便物に押される日付印)に表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
締め切りまでに提出をすれば問題ありませんが、郵送する書類は会社の税務に関する重大な書類です。締め切りを意識するよりも、少しでも早く提出すると言うスタンスで取り組むことを心がけましょう。
3-2. 書類の不備がないようにする
郵送で税務署に書類を送付した後、仮に書類に不備が発生した場合は不備を修正する必要があります。担当者が年末調整にまだ不慣れである場合は、書類の不備が発生する可能性が高いかもしれません。年末調整に不慣れな担当者であれば、書き方を事前に確認しておきましょう。
1度のやり取りで不備が解消すれば大きなロスはありませんが、不備が何度もあった場合、結局は実際に税務署に持参したほうが早かったということもあり得ます。
郵送で送る場合に限ったことではありませんが、郵送の場合は特に必要書類、記載内容を十分チェックした上で税務署に送るようにしましょう。
関連記事:年末調整のやり直しを税務署から通知されたときの対処法
3-3. 年末調整に関する制度変更に注意
毎年年末調整に関連する制度は少しずつ改正されています。令和5年度も変更点があるのでよく確認してから進めるようにしましょう。
ただし、押印の取り扱いや電子データの取り扱いなどはまだまだ浸透していません。間違いのない手続きができるように、再度確認しておくようにしましょう。国税庁のHPで、年末調整担当者向けに毎年「年末調整のしかた」を公開しています。
関連記事:年末調整の2020年変更点4つの重要ポイントをまとめて解説
3-4. ペーパーレスが義務化されている
IT化が進んでおり、すでに保険会社は生命保険料控除や地震保険料控除はデータで「控除証明書データ」として提出できる環境を整えています。
また、国税庁も各企業の従業員が自身で年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を無償で提供しています。郵送をすれば、税務署に行く手間が省けますが年調ソフトを利用すればさらに年末調整業務を簡略化することができるでしょう。
さらに、令和3年1月1日以降に提出する書類については、法定調書の枚数が100枚以上の場合はインターネットを利用したe-taxや光ディスク(CD,DVDなど)での提出が必須になりました。このように徐々に税務のペーパーレス化が進んでいることにも注意を払っておかなければいけません。
関連記事:年末調整のペーパーレス化とは?その背景や課題を詳しく解説
4. 郵送や電子化を上手に活用して年末調整の手続きを効率化しよう

年末調整の書類は税務署に郵送で提出することが可能です。税務署に訪問する時間や待ち時間などを短縮することができるでしょう。
ただし、不備が発生した場合には何度もやり取りが必要になるため、郵送で手続きをする場合はとりわけ内容や添付書類に不備がないかを慎重に確認をしましょう。
年末調整業務は担当の方にとっては大変な業務です。しかし、保険会社が保険料控除や地震保険料控除の書類のペーパーレス化が進み、国税庁も提出書類のペーパーレス化を推奨するなど少しずつIT化、簡素化の流れが進んでいます。 年末調整書類の郵送でもあまり業務が改善されない場合は、業務のペーパーレス化の流れにも注目してみましょう。
▼年末調整の電子化についてはこちら
年末調整の電子化はここまで進んでいる!気になる手続きの方法
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























