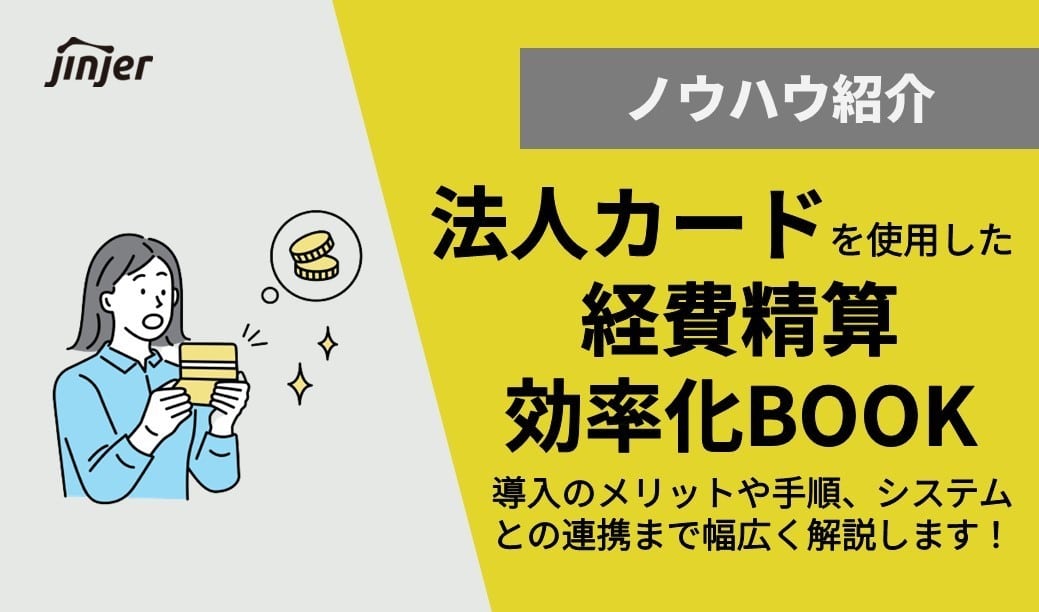法人カードを社員が使う(代表者以外)リスクやメリットについて解説
更新日: 2024.2.29
公開日: 2022.1.13
jinjer Blog 編集部

法人カードでは、メインカードに追加するという形で、社員用のカードを発行することができます。
社員カードを発行すると、メインカードの持ち主である会社の代表者だけでなく、その社員も法人カードを利用できるようになります。
社員の多い企業ほど、社員カードを追加発行するメリットは大きいですが、一方でいくつかのリスクも発生するため、社員カードのメリット・デメリットをよく理解してから導入することが大切です。
今回は、法人カードを社員が使うメリットやリスク、役職ごとの適した用途、社員に私的利用されないための対策について解説します。
目次
1. 法人カードとは

会社や経営者、個人事業主などの法人に対して発行されるクレジットカードのことを一般的に「法人カード」といいます。会社の「経費」を支払うためのクレジットカードなので、代表者や名義人となっている社員しか利用することはできません。また法人カードは一般的に使用されるクレジットカードと比べて、事業に有益な特典が多いことが特徴です。
1-1. 法人カードと個人カードの違い
法人カードと個人カードの違いについてもさまざまな違いがあります。
特に違いがわかりやすいのは、利用限度額です。法人で支払う金額は個人で支払う金額より大きい傾向があるので、それにともなって利用限度額も高くなる傾向があります。また法人カードは事業に有益な特典が多いことを言及しましたが、例えば接待の際に飲食店の割引があったり、出張する際に法人カードを利用することで、旅費交通費が割引されたりと、さまざまな特典があります。
1-2. 法人カードの追加カードの特徴
追加カードとは、「メイン契約しているカードに追加発行できるクレジットカード」のことです。法人カードは代表者本人が申し込みをするため、代表者以外の利用はできません。
しかし追加カードの申込みをすれば、代表者の家族や社員など、代表者以外でも法人カードを使うことが可能になります。社員の支払いで法人カードを利用したい場合は、追加カードの発行をおこないましょう。
また一度法人カードの審査が通れば、社員用として追加カードを申し込む際は基本審査がないケースが多いようです。
1-3. 法人カードの名義について
法人カードの名義は、法人の名義ではなく申し込みをおこなった代表者の個人の名義になります。しかし追加カードを発行した場合、その名義は、追加カードを持っている本人の名義になります。社員であれば社員本人の名義となります。
2. 法人カードを社員が使うメリット

追加カードの発行により、法人カードを社員が使用するメリットは大きく分けて4つあります。
1.経費精算の手間が省ける
2.人的ミスのリスクを軽減できる
3.大きなポイント還元を期待できる
4.経費の節約になる
それぞれ具体的にどういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
メリット1. 経費精算の手間を省ける
社員が法人カードを使用する最大のメリットは、経費精算の手間を大幅に省けるところです。
現金決済の場合、まず社員が経費を立替払いし、後に領収書をもとに精算書を作成→上司が承認→経理で精算という流れを辿るのが一般的です。
そのため、経費を使用した社員自身はもちろん、上司や経理担当者の負担も大きくなり、本来の業務に支障を来す原因になることも少なくありません。
法人カードで経費を決済できるようになれば、立替払いや精算の手間が省けるため、社員・上司・経理担当者それぞれの業務効率化に役立ちます。
関連記事:法人カードで経費精算をおこなうメリット・デメリットや手順とは
メリット2. 人的ミスのリスクを軽減できる
経費を現金決済すると、領収書の管理・精算書の作成・書類のチェック・経費精算システムへのデータ入力など、さまざまな作業をおこなわなくてはいけません。
これらをすべて手作業でおこなうと、領収書の紛失、記載漏れ、チェックミス、入力ミスといったヒューマンエラーが発生しやすく、経理精算業務が滞ったり、後から修正が必要になったりする場合があります。
法人カードと経費精算システムを連動させると、カードの利用データが自動的にシステムに取り込まれるため、記載漏れや入力ミスといった人的ミスを予防することが可能です。
関連記事:法人カードと会計ソフトを連携するメリットや使い方について
メリット3. 大きなポイント還元を期待できる
社員カードの支払いはメインカードに集約され、まとめて決済される仕組みになっているため、社員カードの利用分もポイント・マイル付与の対象となります。
ポイント・マイルは現金や金券、商品、航空チケットなどさまざまなものに交換できるので、実質的なキャッシュバックを受けらるのが特徴です。
社員の人数が多いほど、大きなポイント・マイル還元を期待できるようになるため、お得感がアップします。
メリット4. 経費の節約になる
経費を現金で決済すると、お金を下ろすときや、銀行振込をおこなうときに一定の手数料がかかります。
一回あたりの手数料はわずかでも、月に何度も決済をおこなうと、それなりのコストが発生してしまうでしょう。
法人カードの場合、一括払いなら原則として手数料は発生しないので、経費の支払いにかかるコストを節約することができます。
3. 法人カードを社員が使う際のリスクとは

社員が法人カードを使用することにはたくさんのメリットがある一方、いくつか注意しなければならない点もあります。
実際に導入してから後悔することのないよう、法人カードには以下のリスクがあることも覚えておきましょう。
リスク1. 社員カードにも年会費が発生する場合がある
法人カードのほとんどは年会費が有料に設定されていますが、追加発行する社員カードにも年会費がかかる場合があります。
メインカードに比べると年会費は安く設定されており、一枚につき1,000円~3,000円台くらいが相場となっています。
社員が多い企業の場合、社員カードの発行枚数も多くなるため、年会費だけでそれなりのコストになってしまうところがネックです。
ただ、法人カードの中には社員カードの年会費が無料に設定されているものもあります。
その場合、法人カードの維持費はメインカードの年会費のみで済むので、社員に法人カードを使わせるにあたり、なるべくコストは抑えたいという場合は、年会費無料の法人カードを中心に選定するとよいでしょう。
リスク2. 法人カードの使い回しはNG
追加発行できる法人カードの枚数は、カード会社によってそれぞれ異なります。
たとえば追加発行枚数の上限が10枚の法人カードを利用する場合、社員カードを交付できるのは10人までが限度です。
社員が11人以上いる会社では、当然社員カードの枚数が足りなくなりますが、だからといって他の人に交付された社員カードを使い回すと規約違反になってしまいます。
使い回しが発覚すると、法人カードの利用が強制停止させられる可能性があり、経費精算に大きな支障を来す原因になるので要注意です。
リスク3. 社員カードを私的利用される可能性がある
社員カードは通常のクレジットカードと同じ決済機能を備えており、カード決済に対応しているところならどこでも利用できます。
そのぶん、追加カードを交付された社員がこっそり私的な目的に不正利用するケースも少なくなく、無駄なコストが発生するリスクがあります。
そのため、社員カードを発行する場合は、私的利用を防ぐ何らかの対策をおこなうことが大切です。
社員カードの私的利用の対策について、詳しくは後述します。
4. 法人カードは役職ごとに使途を変えるべき

経費の使い道は役職によって異なるため、法人カードの使途も役職ごとに変えるのがベストです。役職に応じてカードの利用範囲を限定しておけば、不正利用の防止にもつなげられるでしょう。
ここでは、役職ごとの法人カードの使用例をご紹介します。
4-1. 営業社員の法人カード使用例
外回りや出張が多い営業社員は、社用車のガソリン代や高速代、公共交通機関の運賃・チケット代といった交通費がかさむ傾向にあります。
交通系ICカードを利用して移動する場合は、ICカードに社員カードを紐づけてチャージ入金することで、交通費を法人カードで決済することが可能です。
また、新幹線や飛行機のチケット支払いに関してもカード決済が使用できるので、県外や海外への出張費の決済・精算も楽におこなえます。
社用車で高速道路を走る場合は、ETCカードの発行に対応している法人カードを選ぶと、ICをスムーズに通過できる上、高速料金もキャッシュレスで支払えて便利です。
関連記事:法人カードを社員が使う(代表者以外)リスクやメリットについて解説
4-2. 役員の法人カード使用例
役員は、取引先や顧客を接待する際に法人カードを使用するケースが多いでしょう。
接待費は1回あたりの金額が高額になりがちで、個人が立替払いするのは負担が大きいですが、法人カードがあれば接待費は法人口座から直接引き落としになるので、支払い負担を軽減できます。
また、法人カードによってはレストランやゴルフ場を優待価格で利用できる付帯サービスがあり、上手に活用すれば接待交際費の節約につながります。
4-3. 総務担当の法人カード使用例
総務担当者は、会社で使う備品を仕入れるときに法人カードを利用すると便利です。
備品によっては複数の業者から仕入れる必要があり、その都度、領収書が発行されるので、領収書の管理や精算書の作成に手間がかかります。
法人カードを利用すれば、締め日までの決済を一元管理できるので、複数枚の領収書を管理したり、精算書の作成に追われたりする必要がなくなります。
特に大量の備品を購入する場合、多額の出費が発生しますが、カード利用料金の引き落とし日は翌月になるため、支払いに猶予があるぶん、キャッシュフローを改善させやすいところも利点です。
5. 社員に私的利用されないための対策

「3.法人カードを社員が使う際のリスクとは」でも説明しましたが、社員に法人カードを使わせると、私的利用されるリスクが少なからず存在します。
社員の私的利用が横行すると、余計なコストがかさんで経営を圧迫する原因になるため、追加カードを社員に交付する際は、事前に然るべき対策をおこなっておくことが大切です。
ここでは、法人カードを社員に私的利用されないための対策法を3つご紹介します。
対策1. ルールを事前に決めておく
社員カードを交付する際は、事前に法人カードの利用ルールを決め、周知しておくことが必要です。
たとえば、営業社員なら「交通費の支払いのみに使用」「飲食への利用はNG」といった具体的なルールを設けることで、法人カードを利用していいケース、NGなケースを明確化できます。
上記のように、役職ごとに細かいルールを設けると、それぞれのシーンに合わせて正確な判断をおこなえるようになるため、より効率的に私的利用を防ぐことができます。
同様に、貯まったポイントやマイルに関しても、事前に利用制限の取り決めをおこなうなどルールを策定しておくことが望ましいでしょう。
対策2. 利用限度額を低く設定する
法人カードでは、社員カード一枚一枚ごとに利用限度額を調整できるのが一般的です。
それぞれの役職ごとに必要最小限の限度額を設定して私的利用する余地を無くせば、法人カードの不正利用を未然に防ぐことができます。
ただ、月の途中で上限額を超えてしまうと、いざというときに決済ができなくなり、業務に支障を来す原因となります。
利用限度額を設定する際は、それぞれの役職の月間平均経費データをもとに、どのくらいの利用枠を設ければ必要十分かをしっかり検討することが大切です。
対策3. 経費の使い道を定期的にチェックする
法人カードと経費精算システムを連携させると、カードの利用データが自動的にシステムに入力されるため、明細書・計算書チェックの手間を省くことができます。
ただ、経費精算システムに任せきりにしていると、社員の私的利用を見逃す恐れがあることに注意が必要です。
特に注意したいのはガソリン代で、明細からはどの車に給油したのかわからないぶん、社員のマイカー給油に法人カードを利用しても、なかなか私的利用に気付くことはできません。
こうした私的利用を防ぐために、経費の使い道や社用車の走行距離・ガソリンメーターなどを定期的にチェックし、不正利用がおこなわれていないかどうか確かめるルールを設けた方がよいでしょう。
関連記事:法人カードの管理方法や不正利用を防ぐ社内ルールを徹底解説!
6. 法人カードの選び方

法人カードの社員カードを作成する際は、ビジネスや事業にメリットの多いクレジットカードを選択しましょう。
▼法人カードを選ぶ際の3つのポイント
1. 利用コスト
2. 付帯サービスの内容
3. 必要な枚数の追加カードが発行可能かどうか
これらの法人カードを選ぶ際の3つのポイントについて細かく説明していきます。
6-1. 利用コスト
法人カードを利用する上で大切な選定ポイントは「利用コスト」です。とくに社員用に追加カードを申し込む際は枚数ごとに年会費がかかる法人カードがあるので注意が必要です。
そのため社員用のカードを利用する際には、年会費の費用が少ない法人カードを選びましょう。社員カードは枚数が多くなればなるほど、年会費もかさんでしまいます。
最もおすすめなのは年会費無料の法人カードです。また年会費が永年無料ではなくても、比較的安価なものを選定しましょう。
6-2. 付帯サービスの内容
法人カードに付帯しているサービスや内容もカード選びの重要な要素です。
スポーツクラブの優待、またホテルやレストランなどの各種サービスが割引価格で受けられるようなコンテンツも多く、社員への福利厚生にもなるので法人カードを選ぶ際には重要なポイントになります。
6-3. 必要な枚数の追加カードが発行可能かどうか
法人カードの追加カードは、発行枚数に上限が定められている場合が多く、会社の規模によっては枚数が足りなくなるリスクもあるので、事前に発行枚数の上限をリサーチしておくことが重要です。
上限がある中で社員に付与する際は、どのような役職でどのような業務をおこない、なぜ法人カードが必要なのかを見極めて優先度をつけ、優先度の高い社員から付与していきましょう。例としてよく出張にいく営業や、会食が多い役員以上の方などに付与することが望ましいでしょう。
関連記事:法人カードを比較!選ぶポイントや特徴別でカードを紹介
7. 社員に法人カードを使用させる場合は、ルールの策定や周知が必要不可欠

法人カードを追加発行すると、社員ひとりひとりに社員カードを持たせて経費を一元管理できるようになります。
経費精算業務にかかる手間や時間、コストを大幅に削減できるので、会社にとって多くのメリットがありますが、一方で、年会費にコストがかかることや、私的な目的に利用される可能性があるなど、いくつかのリスクもあります。
そのため、法人カードを社員が使う場合は、年会費を考慮してカードを選ぶ、使用ルールを徹底するといった対策をおこなうとよいでしょう。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04