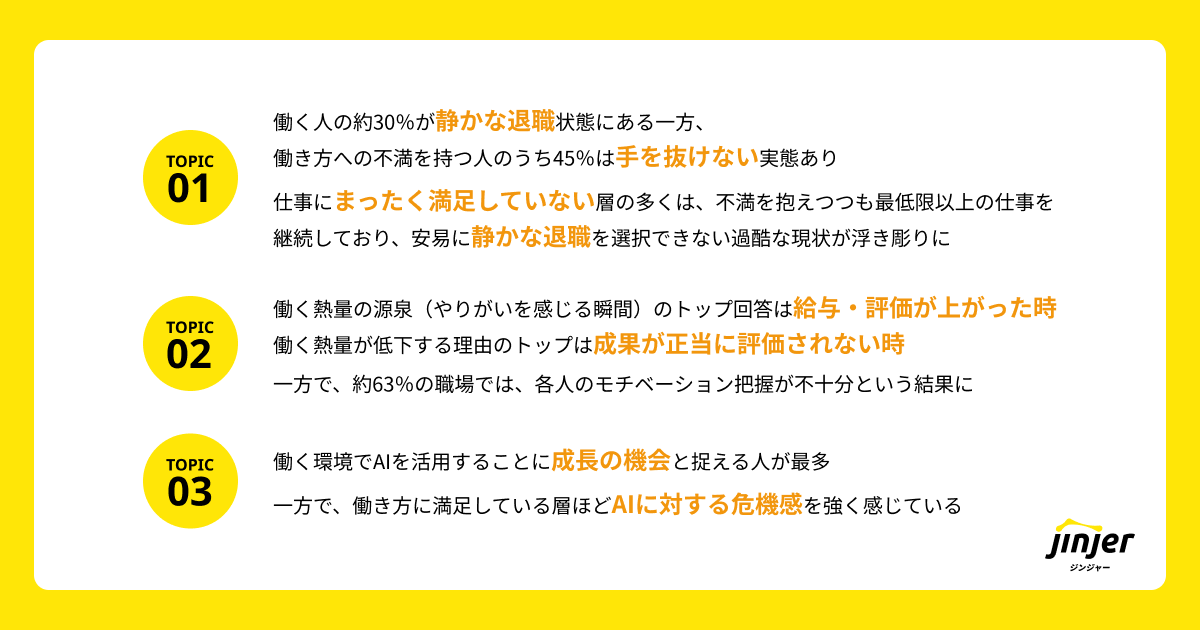労働時間に休憩は含まれる?労働基準法での休憩時間の定義と計算ルールを解説
更新日: 2026.1.29 公開日: 2020.3.25 jinjer Blog 編集部

労働基準法では、労働者の心身の健康を守るため、労働時間に応じた休憩の付与が義務付けられています。しかし、労働時間と休憩時間の区分は判断が難しく、誤ると給与計算のミスや法令違反につながる可能性があります。
本記事では、労働基準法における休憩時間の定義、具体的に何分休憩が必要かという計算ルール、そして休憩中に仕事をした場合の注意点について解説します。
目次
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の計算時間や付与ルールについて、本記事の内容をわかりやすくまとめた無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」
「必要な休憩時間数をいつでも確認できるようにしたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 労働時間に休憩は含まれない
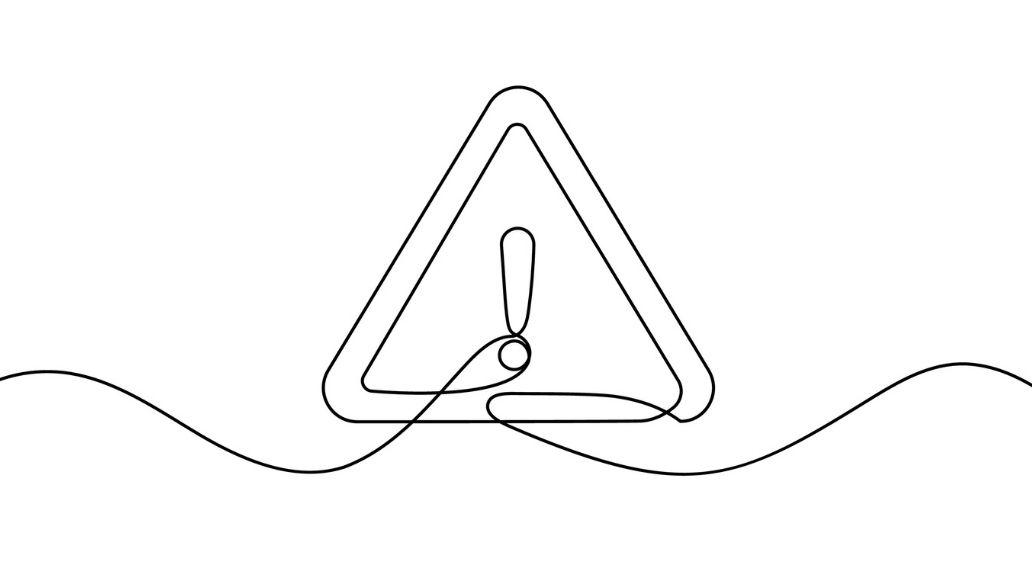
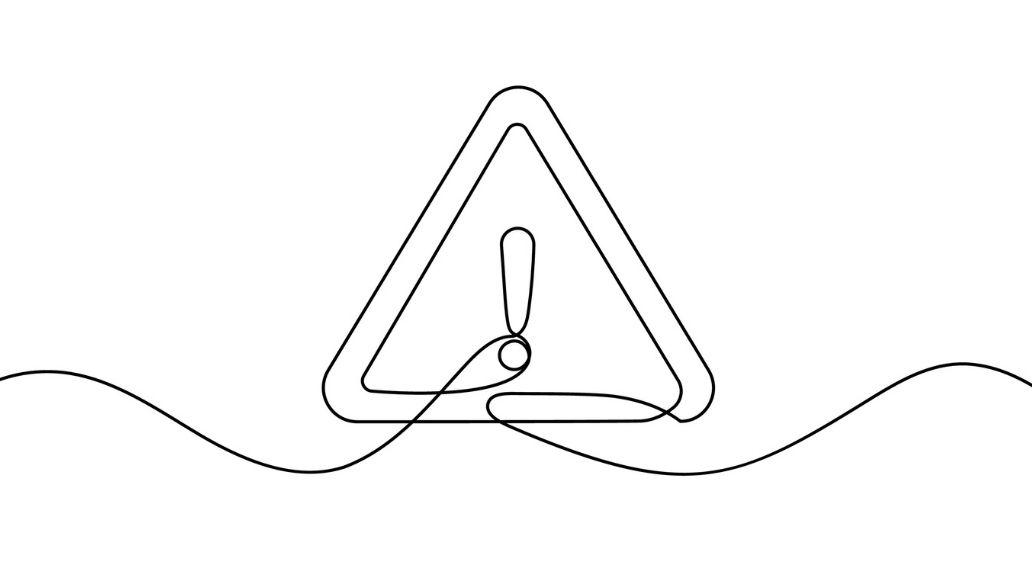
労働時間に休憩は含まれません。企業は、労働基準法第34条に基づき、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働者に与えることが義務付けられています。休憩時間中、従業員は労働から離れ使用者の指揮命令下にはいないため、休憩中の時間は労働時間に含まれません。したがって、使用者は休憩にあてられた時間に対して賃金を支払う義務もありません。
なお、労働時間に似た単語として勤務時間が挙げられます。明確な定義はありませんが、一般的には両者の違いは休憩を含むかどうかです。労働時間に休憩時間は含まれませんが、勤務時間には休憩時間が含まれます。例えば、始業時間が9時で終業時間が17時、休憩が1時間の場合、勤務時間は8時間ですが、労働時間は7時間となります。
1-1. 労働基準法上の休憩とは
労働基準法における休憩とは、「従業員が仕事から完全に離れている状態」のことです。使用者が従業員に対して、休憩時間中に何らかの業務を任せている場合は、休憩時間になりません。
労働基準法には、「休憩の3原則」が定められています。「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」の3つを満たすものが休憩です。
1-1-1. 労働時間の途中に付与する
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
例えば、労働時間が7時間の場合、最低45分の休憩が労働時間の途中で付与される必要があります。
従業員が「休憩時間を減らして早く帰りたい」と希望し、例えば「3時間働いた後に15分休憩を取り、その後さらに4時間働いて、終業時間より30分早く退社する」とした場合、休憩時間は労働の途中ではなく、勤務終了後に置かれることになります。
そのため、実際には15分しか法定の休憩を取得しておらず、労働基準法違反となります。このまま運用すると、企業は処罰の対象となる可能性があります。
1-1-2. 休憩時間は一斉に付与する
休憩時間は、一斉に与えなければなりません。そのため、休憩時間を労働者ごとに変えることは、制度上認められていないわけです。
ただし、労使間にて別途協定がある場合は、一斉ではなく交代などによる休憩時間の付与でも問題はありません。
さらに、労使協定がない場合においても、労働基準法別表第1に掲げる業種(運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健精製業、接客娯楽業、官公署の事業)に該当する場合、一斉休憩の例外が認められています。
関連記事:労働時間に休憩は含まれる?労働基準法での休憩時間の定義と計算ルールを解説
1-1-3. 休憩時間は従業員の自由に使わせる
企業は、休憩時間を自由に利用させる必要があります。もし休憩時間中も業務命令や連絡が強制される場合、その時間は休憩時間として認められず、労働時間とみなされる可能性があります。
休憩時間というと食事休憩になることが多いですが、休憩時間に病院へいったり、ちょっとした買い物をしてきたりなど、従業員が労働から離れて自由に使える時間としなくてはなりません。
2. 休憩を与える際に押さえておくべきルール


続いて休憩を与える際に担当者が押さえておくべきルールをまとめて紹介します。
2-1. 休憩を与える対象
休憩時間は、雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)を問わず、「条件を満たす、すべての労働者」に付与しなくてはいけません。たとえ本人が「休憩はいらない」と申し出た場合でも、きちんと理由を説明して必ず休憩時間を取得させましょう。
2-2. 休憩時間の計算方法
休憩時間の確保については、労働基準法第34条において「労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分」および「労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分」と定められています。
そのため、制度上は、労働時間が6時間ちょうどの場合、休憩なしでも問題はないとされます。8時間を超えて時間外労働をおこなう場合は、最低限60分の休憩時間を確保すれば、違法とはみなされません。
休憩時間については罰則規定も設けられているので、雇用主である企業は厳守が原則です。
2-3. 適切な休憩を付与していない場合の罰則・リスク
使用者が従業員に適切な休憩時間を与えなかった場合の罰則は「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑」です。
労働基準法は刑罰が存在する法律であるため、違反すると処分されるおそれもあります。多くの場合、経営者や企業そのもの、現場の管理職などが罰則の対象です。
加えて、適切な休憩を取らせず過酷な労働を強いている状態が従業員全体や社会に知られると、法的リスクだけでなく企業イメージやブランド価値の低下にもつながります。人材の定着率や採用活動にも悪影響を及ぼし、長期的には経営面での損失にも直結する可能性があります。
そのため、単に法令遵守の観点だけでなく、企業の持続的な成長や社会的信用を守る観点からも、従業員の休憩時間の確保は不可欠です。
2-4. 給与は勤務時間から休憩時間を控除して計算する
賃金支払いの義務がある労働時間に休憩時間は含まれません。
例えば、9時に出社して17時に退社する労働形態の場合、職場にいる時間は合計8時間です。しかし、この8時間のうち、12時から12時45分までを休憩と定めているならば、労働時間は7時間15分と計算されます。
企業にいる時間ではなく、実際に働いた実労働時間をもとに給与計算がおこなわれるので、パートやアルバイトなどの時給で給与が支払われるケースでは特に注意が必要です。
関連記事:勤怠管理における休憩時間の取り扱いとは?労働基準法の基礎知識を解説
3. 休憩時間を与えるときの注意点


これまでの章で、休憩時間の定義や付与すべき時間数、付与のしかたなどの基本的なルールを解説しました。そのうえで、勤怠管理の担当者や使用者が休憩を与える際に注意すべき点を紹介します。
3-1. アルバイト・パートの休憩時間は正社員と同じ
正社員の他にパート・アルバイトや派遣社員、契約社員を雇用している場合も、休憩時間を付与する際のルールは雇用形態によらず同じです。
パート・アルバイトや派遣社員にも労働基準法で定められている通り、労働時間に応じて休憩時間を与える必要があります。
例えば、同じ時間働いているにもかかわらず、「正社員には7時間労働で45分の休憩を与えるが、派遣社員には30分の休憩にしている」といった取り扱いはできません。
雇用形態の違いによらず、労働基準法に定められているルールで休憩時間を与えましょう。
3-2. 就業形態が異なっても休憩時間の取り扱いは同じ
就業先での働き方が時短勤務や裁量労働制である場合においても、休憩時間を付与する際のルールは通常通りです。
時短勤務は原則6時間の勤務時間となるため、休憩時間を取らせることは必須ではありません。ただし、1分でも残業をしてしまえば労働基準法違反になってしまうので、安全策として休憩を設けるケースも多くあります。
また、裁量労働制も休憩時間は適用されます。ただし、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間に基づいて判断します。そのため、みなし労働時間が6時間または8時間を超えているかどうかで、休憩の付与の有無や時間数を決定する必要があります。
このように、就業形態の違いによらず休憩時間は適用されるので、労働基準法に沿って正しく休憩を与えましょう。
関連記事:時短勤務者の休憩時間は?その上限や注意点を詳しく解説
関連記事:裁量労働制とは?労働時間管理における3つのポイントを徹底解説
3-3. 管理監督者や機密事務取扱者には休憩の規定が適用されない
労働基準法第41条に基づき、管理監督者や機密事務取扱者には休憩時間の規定は適用されません。
管理監督者は、企業の経営方針や業務運営に直接関与する立場にあるため、休憩の管理も企業から指示されるのではなく、自らの判断で調整することが前提とされています。
また、機密事務取扱者は、企業秘密や顧客情報などを扱う業務に従事しているため、業務の性質上、休憩を画一的に区切ることが困難な場合があります。
ただし、休憩規定が適用されないからといって、休憩を全く与えなくてよいわけではありません。企業には、すべての労働者に対して安全配慮義務があり、長時間労働や健康被害を防ぐ観点から、適切な休憩を取得させることが望ましいでしょう。
関連記事:管理職(管理監督者)の勤怠管理を徹底解説!労働時間の上限規制は対象外?
3-4. 休憩しながら簡単な仕事をすることは、休憩時間とみなされない
仕事に追われている従業員のなかには、昼食中にパンやおにぎりを食べながら、仕事を続けるという人もいるかもしれません。
しかし、企業は、労働者が休憩時間を自由に利用できるようにする義務があります。たとえ軽作業や簡単な業務内容だったとしても、その時間は休憩とは認められず、労働時間として扱われます。
そのため、休憩中におこなった業務に対しては、通常の労働時間と同様に賃金を支払わなければなりません。
4. 業務から離れていても休憩とみなされないケース


デスクから離れていたり、休憩室にいたりする場合でも、業務から完全に開放されて自由な行動を取れる状況でない限り休憩にはなりません。よくある休憩に該当しないケースを知っておきましょう。
4-1. 手待ち時間(待機時間)や仮眠時間
業務指示にすぐ対応できる状態で待機している時間(手待ち時間)は、労働から完全に解放されているとはいえないため、休憩に該当せず、労働時間として扱われます。例えば、警備員が巡回の合間に控え室で待機している時間や、工場の機械オペレーターが設備の稼働を待つ時間などが該当するでしょう。
また、仮眠時間については仮眠室での睡眠が認められますが、緊急事態やトラブル発生時には直ちに対応する必要があります。そのため、仮眠時間であっても手待ち時間とみなされる可能性があり、休憩時間として扱うと法令違反となるおそれがあるので注意が必要です。
4-2. 休憩中も電話や来客対応をする
企業における休憩の原則で特に重要なのは、労働者が「仕事から完全に解放されている」ことです。これは単に作業をしていないだけでなく、心身ともに業務の拘束から自由である必要があります。
例えば、休憩中に顧客からの訪問に対応しなければならなかったり、電話対応に備えてオフィス内で食事を取るよう指示されていたりする場合、その時間は休憩ではなく労働時間として扱われます。また、上司や管理者から明確な指示がなくても、暗黙の了解で労働を任されている場合も、休憩とはみなされないので注意しましょう。
4-3. 休憩中に簡単な作業をする
従業員が休憩時間中に、休息や食事をとりつつ簡単な作業をすることがあります。書類の確認や申請書の作成などはよくあるケースです。しかし、こうした「ながら作業」だとしても、労働から完全に解放されていないとみなされて休憩になりません。
4-4. 労働中のたばこ休憩
労働中のたばこ休憩は、休憩時間か労働時間かの判断が難しく、実際の判例でも両方の扱いが認められています。
例えば、飲食店内で喫煙している間も、何かあればすぐに業務に対応できる状態にある場合は、業務から完全に解放されていないとして、労働時間と評価された判例があります(北大阪労働基準監督署長事件 大阪高判平21・8・25)。
一方、喫煙場所が勤務店舗から離れており、喫煙に必要な時間が十分に確保されている場合は、指揮命令下に置かれていないとして、休憩時間と判断されたケースもあります(泉レストラン事件 東京地判平26・8・26)。
このように、たばこ休憩が休憩時間に該当するかを判断する際は、判例の考え方を踏まえ、「労働から完全に解放されている状態かどうか」を重要な判断基準とすることが適切です。
参考:相談室Q&A 業務時間中の喫煙休憩時間分につき、賃金控除してよいか|株式会社労務行政
4-5. 昼食ミーティングや勉強会
業務に関連する活動を伴う昼食会議や勉強会は、必ずしも休憩時間として扱えるとは限りません。例えば、従業員教育の一環としておこなわれるランチミーティングや、業務改善を目的とした勉強会などが該当します。
休憩として認める場合でも、業務の拘束がないことをきちんと確認する必要があります。具体的には、参加者が自由に休憩できているか、自分の意思で途中退出できるかなどがポイントです。また、トラブルを防止するためにも、参加は強制ではなく任意であることを事前に明示しておくとよいでしょう。
5. 労働時間と休憩時間を正確かつ効率的に管理する方法


5-1. 就業規則にルールを明記して従業員に周知を徹底する
労働基準法では、休憩に関する最低限の基準が定められています。しかし、実際の付与方法や運用ルールは企業によって異なる場合もあり、現場の状況や勤務形態によって誤解が生じることも少なくありません。
そのため、自社における休憩時間の取り扱いルールを、法令を踏まえたうえで就業規則に明確に規定しておくことが大切です。
また、就業規則は従業員への周知が義務づけられています。社内掲示やイントラネットでの公開などにより、誰でもアクセスし理解できる方法で周知することで、休憩に対する認識のズレを防げます。
さらに、従業員へ指示を出す管理職・現場リーダーへの教育も非常に重要です。特に現場作業や繁忙期には休憩が取りにくく、誤った運用として「勤務終了後にまとめて休憩を取らせる」といった問題が発生しがちです。しかし、休憩時間は必ず労働時間の途中に付与しなければなりません。
このように、休憩の与え方には時間数以外にも、さまざまな法的ルールがあります。誤った運用を未然に防ぐためには、説明会や研修を通じて管理者・従業員の双方に正しい知識を身につけてもらうことが不可欠です。
5-2. 休憩時間の取り扱いで迷ったら労働基準監督署に相談する
近年、働き方改革の進展により、テレワークやフレックスタイム制、副業・兼業など、多様な働き方が広がっています。さらに、デジタル技術や人工知能(AI)の発展によって、働く環境はこれまで以上に急速に変化しています。
こうした動きにあわせて、労働基準法をはじめとする関連法令も、時代に即した見直しや改正が進められています。しかし、労働時間と休憩時間の境界はわかりにくいケースも多く、新しい働き方の普及により判断がさらに難しくなる場面も想定されます。
労働時間や休憩時間の取り扱いに不安・疑問がある場合は、自己判断を避け、まずは労働基準監督署へ相談してみると安心です。専門機関である労基署では、最新の法令や実務運用に基づいた具体的なアドバイスを得られるため、誤った対応による法令違反のリスクを未然に防止できます。
5-3. 勤怠管理システムを活用して労働時間・休憩時間を自動で集計する
企業には、従業員の労働時間を正確に把握する義務があります。紙のタイムカードやExcelによる管理も認められていますが、従業員数が多い企業や在宅勤務など柔軟な働き方を導入している企業の場合、手作業での管理は手間がかかり、十分に対応できないこともあるでしょう。
もし労働時間や休憩時間の集計に誤りがあれば、給与計算にも影響を及ぼします。また、休憩時間が正しく付与されていなかったり、時間外労働の上限を超えて働かせていたりする場合には、従業員の健康確保や法令遵守の観点から問題となり、労働基準法違反として罰則の対象となる可能性もあります。
このようなリスクを防ぎ、業務を効率化するためには、勤怠管理システムの導入が有効です。PCやスマホ、ICカード、生体認証など、多様な手段で勤怠情報をデータとして管理できるため、人的ミスを減らし、管理業務の効率を高められます。
さらに、システムで情報をリアルタイムに一元管理できるので、休憩が十分に取れていない従業員や法定上限に近い時間外労働が発生しそうな従業員を即座に把握し、必要に応じて注意喚起や勤務調整をおこなうことも可能です。
6. 休憩についてよくある質問


休憩時間を適切に付与し、運用するためによくある質問を整理しました。実際に質問された場合に正しく回答できるようケースごとにポイントを押さえておきましょう。
6-1. 分割して付与することはできる?
休憩時間は、分割して付与することができます。
例えば、休憩時間を90分として、お昼休憩に60分、午前と午後にそれぞれ15分ずつの休憩を付与するなど、分割して付与することが可能です。
ただし、分割して付与したとしても、休憩時間は労働時間の途中に与えなくてはならないというルールに変わりはありません。「休憩せずに働いて、その分早く帰る」といった取り扱いはできないので注意しましょう。。
また、休憩を数分単位で非常に細かく分けて付与する場合、実際には労働から十分に解放されていないと判断されることがあります。この場合、形式上は休憩時間を付与していても、法的には休憩として認められない可能性があるため、休憩の分割は業務の実態に合わせて適切に設定することが重要です。
6-2. 残業が発生したら追加で休憩をとらせるべき?
休憩時間の付与は、実際の労働時間に応じて定められています。そのため、所定労働時間内で法定の休憩時間をすでに付与している場合、原則として残業が発生しても追加の休憩を付与する必要はありません。
しかし、残業によって実労働時間が6時間を超える場合は合計45分、8時間を超える場合は合計1時間の休憩が必要となるため、状況によっては追加休憩が必要になるケースがあります。
例えば、勤務時間が9時から17時までの場合、所定労働時間は7時間15分で休憩は45分必要です。しかし、この企業で1時間残業すると総労働時間が8時間15分となり、1時間分の休憩が必要になるため、追加で15分の休憩が必要になります。
また、残業によって法定の休憩を追加で付与する必要がない場合でも、過労防止や集中力維持の観点から、適宜休憩を設けることを検討するとよいでしょう。
6-3. 労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩の付与が必要?
労働基準法で定められた休憩時間は、労働時間が6時間を超えたときから発生します。そのため、労働時間が6時間ぴったりで1分も超過していない場合は、休憩を取らせる必要はありません。
反対に、1分でも超過した場合は、45分の休憩が必要になります。パートやアルバイト従業員のシフトを決める際は、この点に注意するとよいでしょう。
6-4. 休憩時間が取れなかったときはどうする?
休憩を取らずに勤務した時間については、必ず給与を支払う必要があります。さらに、休憩が確保できなかったことで実労働時間が長くなり、時間外労働が発生した場合には、割増賃金の支払いも必要です。
例えば、飲食店のパートやアルバイトで、昼食時などの繁忙時に十分な休憩を与えられない場合が考えられます。しかし、労働時間に応じた休憩を付与することは企業の義務です。勤務時間の調整や、後から休憩を付与するなどして、法律で定められた休憩時間を適切に確保しましょう。
当サイトでは、「休憩時間の計算方法総まとめ」という資料を無料配布しております。本資料では、休憩時間の計算方法や付与ルールなど休憩時間にまつわる定義・ルールはもちろん、休憩時間に関するよくある質問まで網羅的にまとめております。知識が正しいか不安な方はこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
7. 労働時間と休憩時間はまったく別!休憩時間は給与算定の対象外


労働時間と休憩時間は法律上で明確に区別されています。労働基準法では、労働者が業務から完全に解放されている時間を「休憩時間」と定めています。そのため、たとえ簡単な業務であっても休憩中に続けておこなっている場合は、休憩とは認められません。
もし、使用者が指示していないにも関わらず、労働者が自主的に休憩中に仕事をしていた場合でも、それを放置せず、必ず休憩を取らせる必要があります。休憩中の作業を容認していると判断されると、使用者責任を問われる可能性があります。
そのため、企業と労働者の双方が、休憩時間の計算方法や付与ルールを正しく理解し、適正に運用することが重要です。ルールを順守することで、双方の安全と権利を守ることにつながります。
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の計算時間や付与ルールについて、本記事の内容をわかりやすくまとめた無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」
「必要な休憩時間数をいつでも確認できるようにしたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-

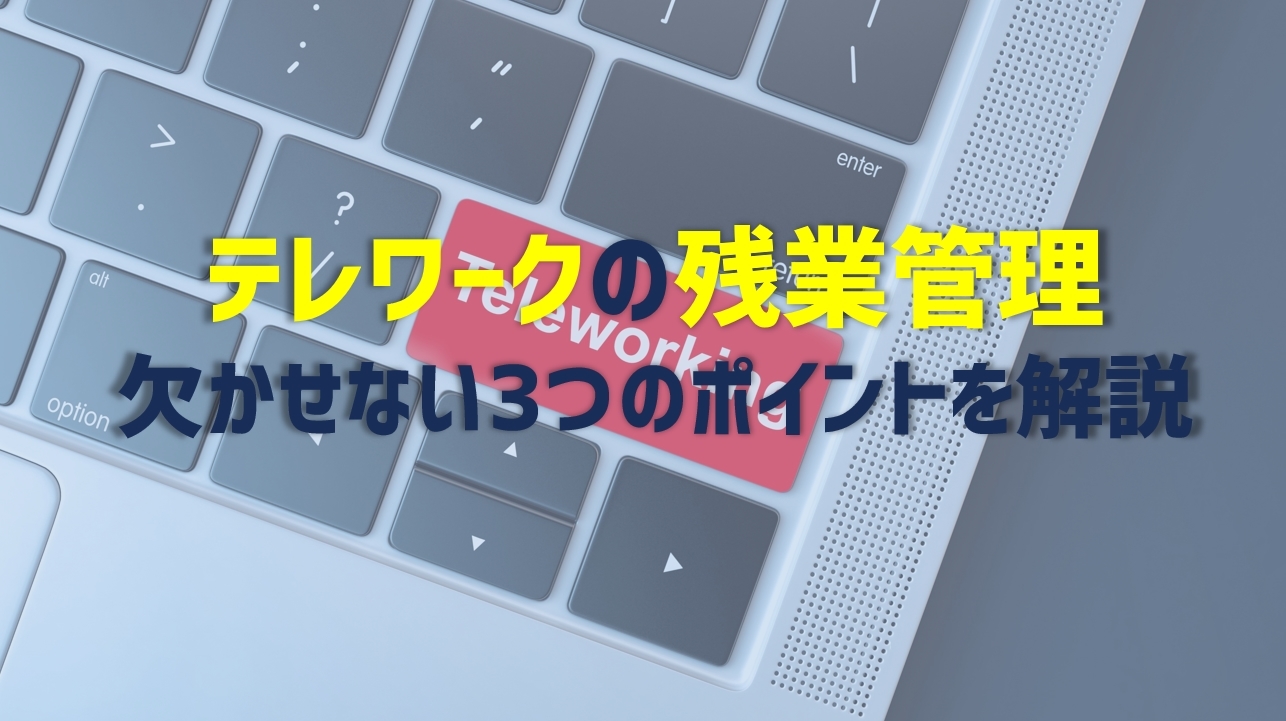
テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
労働時間の関連記事
-


副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向
勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15
-


着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06
-


過重労働に該当する基準は?長時間労働との違いや影響を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2025.08.19