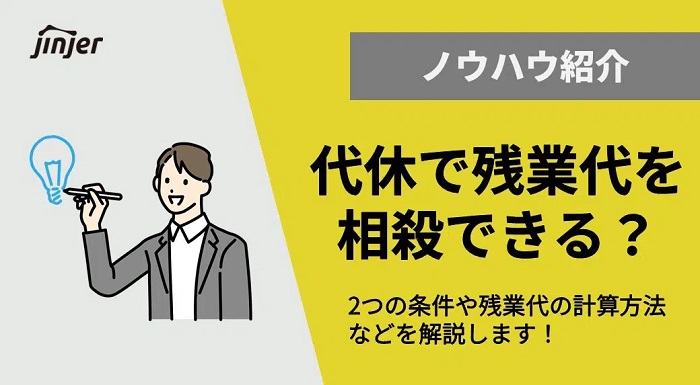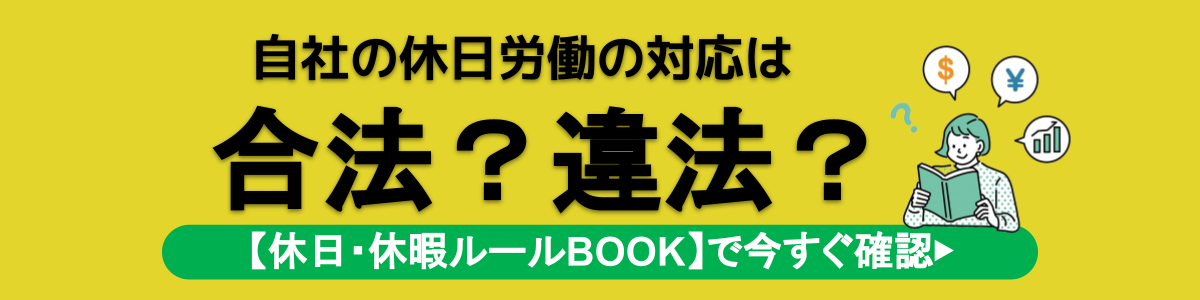従業員の残業を代休扱いにできる?法律に基づいた2つの条件
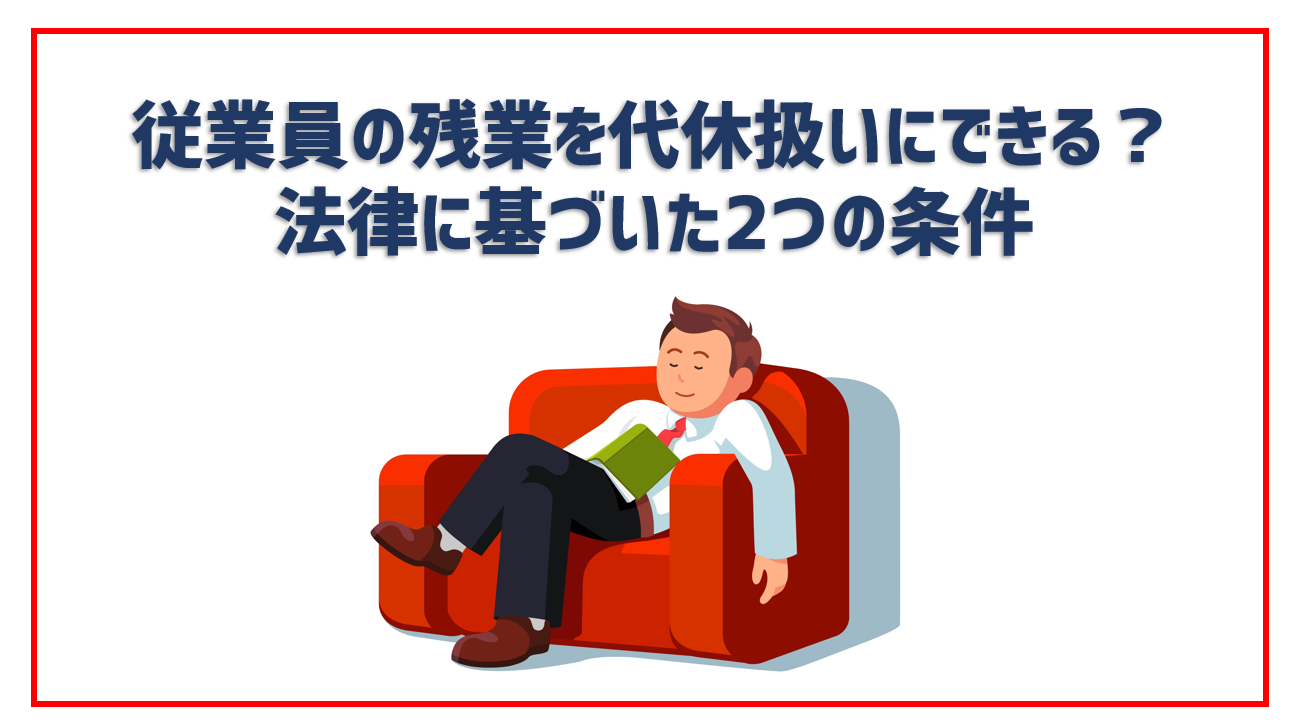
従業員の時間外労働に代休を付与して対応するためには、2つの条件が必要です。企業と従業員の間に合意があり就業規則で規定すること、代休扱いにした残業にも時間外残業として25%の割増賃金を支払うことです。
割増賃金の支払いを怠ると、労働基準法違反となるため、給料計算の際には注意が必要です。この記事では、残業を代休扱いできる条件や、代休扱いにできないケースをご紹介します。
【関連記事】残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
代休を与えた分、残業代を減らすことは違法な取扱いです。ただし、残業時間分の代休を付与することは可能です。
「なぜ代休で残業代を相殺できないのか確認したい」「どうすれば残業時間分の代休を付与できるか知りたい」という方に向け、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しておりますので、こちらからダウンロードしてご確認ください。
目次
1. 残業代休とは


代休は一般的に休日出勤した際に、別の日に休日が発生することを指します。一方、従業員の残業時間が1日の所定労働時間に達した場合、1日分の代休が付与できます。このような仕組みが残業代休と呼ばれます。
なお、企業によっては残業代休と呼ばず、残業の代休扱いと呼んでいるケースもあるでしょう。
残業代休は就業規則に記されていれば、会社が従業員に代休を強制することは可能です。しかし、就業規則にない場合は強制することはできません。
1-1. 残業代休と振替休日の違い
残業代休と似た休暇の仕組みとして振替休日が挙げられます。残業した分の代休は、残業時間が1日の所定労働時間に達した際に付与されます。
一方、振替休日はあらかじめ休日としていた日を勤務日にして、代わりに他の勤務日を休日とする仕組みです。振替休日の場合、いつの休日を勤務日に振り替えるかを前日以前までに決めて従業員に通知する必要があります。
2. 残業の代休扱いは可能だが支払う賃金に変わりはない

8時間以上の残業が発生したときに1日分の代休を付与して対応する行為自体は違法ではありません。しかし、36協定を結んでいて残業した時間分は割増賃金を支払わない場合は労働基準法違反となります。
代休扱いになったからといって、その分の労働時間が「時間外労働」でなくなるわけではないからです。残業を代休扱いにするという対応は、時間外労働に対する賃金を代休付与日にまとめて支払うことであり、給与計算上では通常の残業代を支払うことと変わりありません。
また、時間外残業のなかに22時以降の深夜労働が含まれる場合は注意が必要です。その分の残業には時間外手当25%のほか、深夜手当として25%の割増賃金を支払わなければなりません。
割増分の残業代を支払わなければ、労働基準法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)違反となり、労働基準法第119条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
当サイトでは、代休・振替休日の考え方や休日出勤させた際の対応などをまとめた資料を無料で配布しております。上記の通り、認識が違えば法律違反が簡単に起きてしまうため、少しでも不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
【関連記事】代休の定義や振休との違い・運用のポイントを詳しく解説
3. 残業を代休扱いにできる2つの条件

残業に対して代休を取得させることで対応するためには、労働基準法第37条により、次の2つの条件を満たす必要があります。
3-1. 就業規則などで規定されている
残業の代休扱いするには、企業と従業員間の合意が絶対条件です。就業規則等の代休や時間外労働の項目規定に、具体的な要件を記載しておく必要があります。
ちなみに、企業と従業員の間に「代休扱いになった分の残業代には割増手当を支払わない」といった申し合わせがあった場合、労基法第37条によりその合意は無効となります。
3-2. 時間外労働として25%の割増賃金を支払う
上述のとおり、残業を代休扱いにしたとしても、時間外労働の割増賃金まで相殺することはできません。例えば、1ヵ月の残業時間の上限を30時間とし、上限を超えた残業は8時間ごとに1日分の代休で対応する場合を考えてみましょう。
30時間の残業はもちろん、代休扱いになった労働時間も「時間外労働」として、1時間あたりの賃金に対し、25%の割増賃金を支払う必要があります。
例)月給:32万4,000円(1時間あたりの賃金2,000円)
残業時間:46時間
代休付与日数:2日
46時間分の残業代は、
2,000円×1.25×46時間=115,000円
です。この残業時間のうち、残業時間の上限30時間の残業代は、
2,000円×1.25×30時間=75,000円
になります。残り16時間は2日間の代休扱いとして、
2,000円×16時間(2日分)=32,000円
相殺されますが、実際は「時間外労働」として25%の割増率を換算しなければならないため、
2,000円×1.25×16時間(2日分)=40,000円
から差し引いた割増分の残業代、
40,000円−32,000円=8,000円
が支給されていないことになってしまいます。このことからもわかるように、代休を与える代わりに残業代を出さないことは従業員にとって不利益になるばかりか、本来支払わなければならない賃金を支払っていないことになるため、法律違反となるのです。
残業に対して代休を付与すること自体に問題はありませんが、必ず残業した時間分の割増賃金を支払ったうえで代休を付与しなければならないことを理解しておきましょう。
あれ、割増賃金支払わないといけないの?」と感じられた方は少なからずいるのではないでしょうか?そう感じたあなたは、代休と振替休日の意味が混在してしまっているので注意しましょう。
当サイトでは、代休・振替休日の考え方や休日出勤させた際の対応などをまとめた資料を無料で配布しております。上記の通り、認識が違えば法律違反が簡単に起きてしまうため、少しでも不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
【関連記事】残業代割増の仕組みと計算方法をわかりやすく解説
4. 残業を代休扱いにできない場合

労働基準法第24条により、残業代を含む賃金の全額は1ヵ月ごとに1回以上、期日を定めて支払う義務があります。したがって、代休扱いにする時間外労働と代休付与の日は同じ月(同一給与計算期間)にしなければなりません。
4月の給与計算期間の時間外労働を5月の給与計算期間の代休扱いにするといった、「月またぎ」での対応は労働基準法違反になってしまうので注意しましょう。
5. 残業の代休扱いで残業の削減にはならない

法定時間外労働を代休の付与で対応すること自体は違法ではありませんが、時間外労働の割増賃金を相殺してできるわけではありません。
時間外労働手当として25%の割増賃金を支払わない場合は、労働基準法違反となります。代休とは、時間外労働や休日労働がおこなわれた際、従業員の健康の維持や回復、自由時間の確保を図るという趣旨で取り組まれるものです。
そういった観点からも、残業の代休扱いによる残業代削減や人件費の抑制などは原則に反することを覚えておきましょう。
残業時間を削減するためには次のような取り組みがおすすめです。
- ノー残業デーを導入する
- 残業を事前申請にする
- 勤怠管理システムを導入する
【関連記事】労働時間管理を正確におこなうための7つのポイント
5-1. ノー残業デーを導入する
残業の削減にはノー残業デーの導入がおすすめです。ノー残業デーは企業が従業員に対して、定時に帰宅することを促す施策です。
ノー残業デーを成功させるには、管理者や上司などの積極的な参加がポイントになります。管理者や上司などがノー残業デーで定時に帰宅することで、その他の従業員も帰宅しやすくなるでしょう。
5-2. 残業を事前申請にする
残業を事前申請にすることで、従業員の無駄な残業を削減可能です。
残業の事前申請は、従業員が残業する旨を会社に伝えて承認を待つ仕組みです。会社の承認が得られた場合にのみ残業が可能なため、不要な残業の是正につながります。また、誰がどのくらい残業しているかも把握しやすくなります。
5-3. 勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムは残業時間を自動で集計可能です。そのため、従業員の残業時間をリアルタイムでスムーズに把握できます。例えば、事前に従業員の残業時間を把握できていれば、過度な残業が発生しないように調整ができます。
6. 残業の代休についてのルールを把握しておこう


残業時間が1日の所定労働時間に達した場合、代休を与えることが可能です。しかし、残業による代休を付与した場合であっても、残業時間分の割増賃金の支払いは必要です。
残業の代休を付与することは残業時間の削減にはつながりません。そのため、ノー残業デーの導入や勤怠管理システムの導入などを検討してみましょう。
代休を与えた分、残業代を減らすことは違法な取扱いです。ただし、残業時間分の代休を付与することは可能です。
「なぜ代休で残業代を相殺できないのか確認したい」「どうすれば残業時間分の代休を付与できるか知りたい」という方に向け、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しておりますので、こちらからダウンロードしてご確認ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
法律の関連記事
-


「二段の推定」の意味や根拠法律について詳しく解説
電子契約公開日:2023.04.13更新日:2024.05.08
-


法律上の上限はなし?福利厚生費の限度額を解説
経費管理公開日:2022.05.10更新日:2024.05.29
-


消費税なしは法律上問題なし?記載がない請求書の扱い方について
経費管理公開日:2022.05.10更新日:2024.05.08
残業の関連記事
-


残業代単価の計算方法と勤務形態ごとの考え方をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.06更新日:2024.10.17
-


ノー残業デーを導入するメリット・デメリットと継続のコツ
勤怠・給与計算公開日:2022.03.05更新日:2024.01.15
-

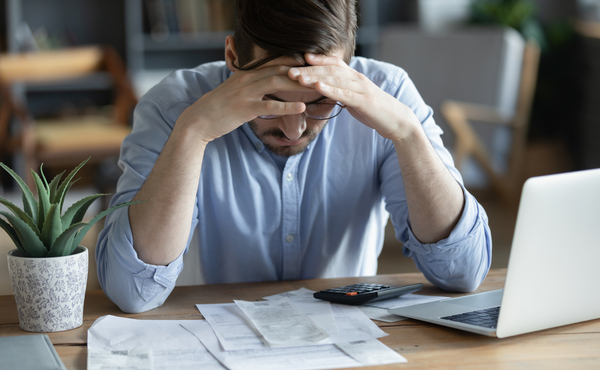
残業手当の計算方法や割増率、未払い発生時の対応を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.04更新日:2024.09.03