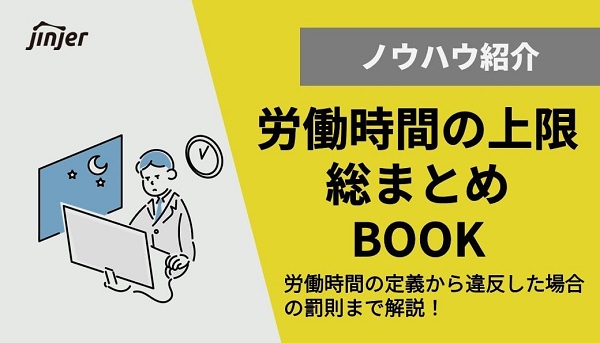労働時間を1分単位で計算する原則はいつから?労働時間の把握の義務化を解説
更新日: 2025.7.31 公開日: 2020.3.12 jinjer Blog 編集部
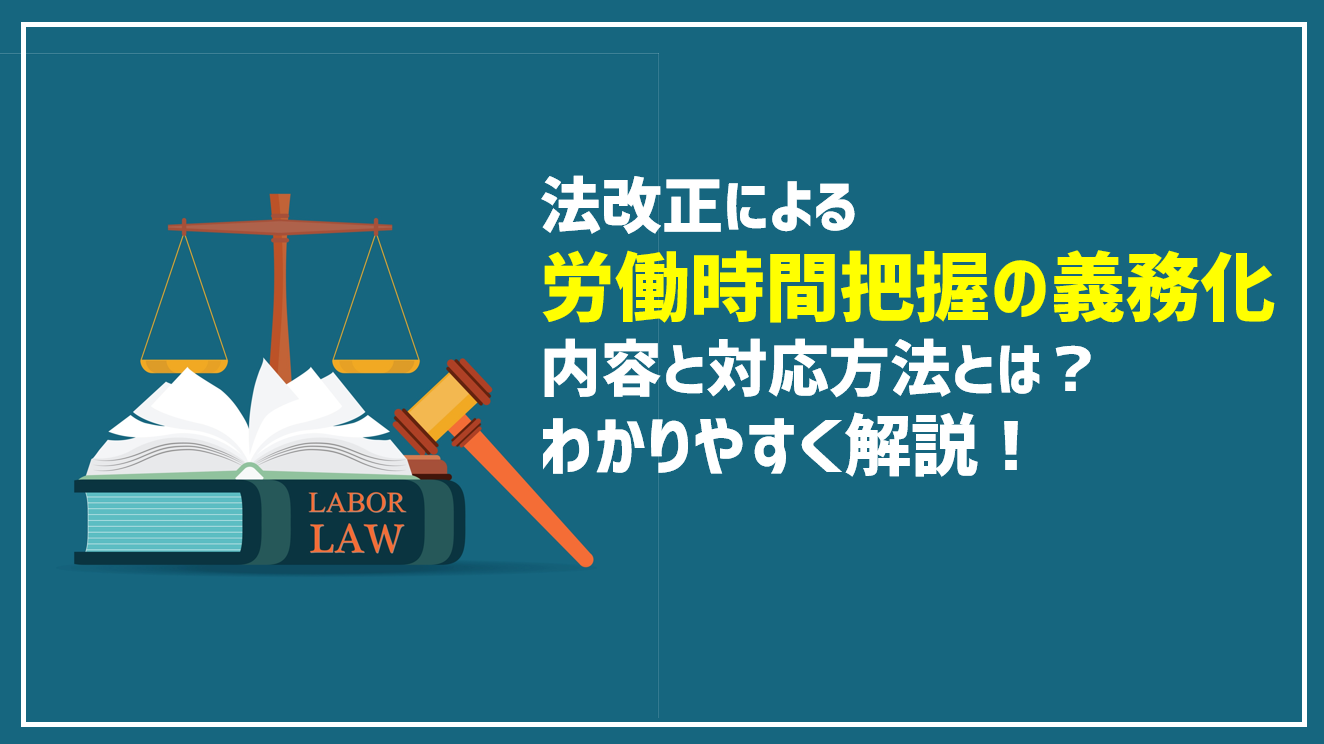
2019年の4月以降、働き方改革の一環としておこなわれた労働関連法の法改正によって「労働時間の把握」が義務化されました。従業員の総労働時間を正しく計算することは、正しく給与を支給するためにも、とても重要です。
この労働関連法の法改正によって、それまで罰則のなかった長時間労働・過度の残業に対する法的な罰則や上限が設定されました。今回は、労働時間把握の義務化に則って正しく勤怠管理をおこなうためにそもそも総労働時間の計算方法や、それに関連する労働時間把握の概要や、義務化された理由、従来の勤怠管理との相違点など、基礎的な内容を押さえていきましょう。
【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
労働時間管理は、原則だけでなく「月45時間・年360時間」という残業時間の上限や、変形労働時間制・フレックスタイム制における独自のルールなど、把握すべき点が多岐にわたります。
自社の勤怠管理が、これらの複雑な規制すべてに準拠しているか、自信を持って言えますか?
「今月の法定労働時間の上限は何時間?」「残業させられるのは、あと何時間だろう?」
このような業務上の疑問・不安をお持ちの方に向けて、労働時間の上限について解説した資料を無料配布しています。
本資料では、労働時間の定義から各種上限規制、多様な勤務形態での考え方まで網羅的に解説しています。
自社の勤怠管理を総点検したい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働時間の把握義務化とは


2019年の労働安全衛生法の改正により、雇用主に「従業員の労働時間の把握」が義務付けられました。この義務化は、従業員の勤怠時間や時間外労働など、全労働時間を客観的な方法で記録することを含んでいます。
労働時間の把握の対象者となるのは、すべての従業員です。改正前は、裁量労働制の適用者や管理監督者は対象とされていませんでしたが、今回の改正ではこれらの労働者も対象となっています。
把握した労働時間の記録は、5年間の保存(当面は3年)も義務付けられているので、退職や休職などで記録を破棄しないように注意しましょう。
参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
1-1. 労働時間の把握義務化の目的
法改正がおこなわれる前から、政府によって労働時間の把握は推奨されています。しかし、企業の勤怠管理方法に関する統一の基準や法的根拠がなかったため、実際には「どのような勤怠管理をするのかは各企業の自由」となっていました。
そのため、給与計算の根拠となる労働時間の把握状況があいまいになり、「勤怠時間を勝手に15分単位で区切る」「残業時間を勝手に減らしてサービス残業を強制する」といった問題が発生しました。
また、「企業が労働時間を正確に把握できていない」という状況で起きるのが、労働時間計算の不正です。「労働基準法を守っていたら会社が成り立たない」という意見もあるかもしれませんが、長時間労働による健康被害が出る可能性もあります。
このような問題を解決することを目的として、労働時間把握が義務化されました。
1-2. 労働基準法の「賃金全額払いの原則」により1分単位での計算が必要
厳密に言うと、労働時間の「1分単位の計算」は法律で明文化されていません。しかし、労働基準法第24条1項では以下のように定められています。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
これを「賃金全額払いの原則」と言い、これにより、1分単位での管理が求められると解釈されています。つまり、労働者が働いた時間は切り捨てることなく正確に計上される必要があり、15分単位や30分単位で労働時間を切り捨てることは原則として違法になるということです。
1-3. 労働時間の管理に関する違法な就業規則は無効になる
労働時間の管理は、就業規則よりも法律に従うことが優先されます。つまり、たとえ就業規則に「労働時間は15分単位で計算する」といった規定があっても、労働基準法に反する内容は無効です。
労働基準法に違反している就業規則は是正勧告の対象となる可能性があるため、就業規則を策定する際には、法律に基づいた内容を盛り込む必要があります。
2. 年間の総労働時間とは


労働基準法における「賃金全額払いの原則」を守るには、従業員の年間の総労働時間を漏れなく把握しなければなりません。年間の総労働時間とは、労働者が1年間に実際に働いた時間を示す指標です。労働時間把握の義務化に伴って正しく勤怠管理をおこなうためにも、この指標は、正確に把握・計算することが求められます。
2-1. 労働時間として扱われる範囲
そもそも労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。使用者の明示による指示はもちろん、黙示による指示で業務に従事している時間も労働時間に該当します。以下のような時間も、労働時間として解されるので注意しましょう。
- 着用が義務付けられた制服の着替え時間
- 就業に必要な準備または後片付けの時間
- 業務上参加が義務付けられている研修や教育訓練などの参加時間
- 使用者の指示で行った業務上必要な学習のための時間
- 昼休み中の電話番など会社から待機を義務付けられている時間(手待ち時間)
2-2. 法定労働時間と時間外労働の合計で算出する
年間の労働時間を算出する際には、「法定労働時間」と「時間外労働時間」の合計で算出されます。
ここでの法定労働時間とは、法律で規定されている一週間あたりの最大労働時間を指し、日本では基本的に週40時間とされています。この法定労働時間をもとにすると、年間の法定労働時間は以下の計算で求められます。
52.14(年間の週数)×40(週あたりの法定労働時間)=2,085時間です。
次に、法定労働時間を超えて働いた時間、すなわち「時間外労働時間」の計算方法について説明します。例えば、ある社員が1ヶ月に20時間の残業を12ヶ月行った場合、年間でその社員の時間外労働時間は240時間となります。この場合、年間の総労働時間は法定労働時間2,085時間に時間外労働240時間を加算し、合計2,325時間となります。
2-2-1. 法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限を指します。日本においては、原則として1日8時間、週40時間です。この法律は労働者の健康を保護し、過重労働から守るために設けられています。そのため、企業はこの範囲内で労働者を働かせなければなりません。
一方、所定労働時間という概念も存在します。これは、具体的な企業ごとの労働契約に基づいて決められる時間です。例えば、企業が「1日7時間、週35時間」と定めた場合、これがその企業の所定労働時間となります。企業には所定労働時間を自由に設定する権限がありますが、これは法定労働時間を超えない範囲で行わなければなりません。
このように、法定労働時間と所定労働時間は異なるものであり、また適切に管理することが求められます。労働環境を良好に保つためには、明確に違いを理解しておきましょう。
2-3. 残業時間や有休取得日は含まれる?
年間の総労働時間を算出する際、残業時間と有給休暇の取得日がどのように扱われるのかは重要なポイントです。
総労働時間は、特定の期間内に実際に就業した時間を反映しており、時間外労働、つまり残業時間は前述のとおりその計算に含まれます。具体的には、例えば、1ヶ月の所定労働時間が160時間で、さらにその月に20時間の残業を行った場合、総労働時間は180時間となります。このように、残業は実際に業務を行った時間であり、したがって総労働時間にしっかりと組み込まれます。
一方で、有給休暇に関しては取り扱いが異なります。有給休暇を取得した場合、実際に業務に従事していないため、その取得日は総労働時間には含まれません。ただし、労働基準法によれば、有給休暇は所定労働日数の一部としてカウントされます。たとえば、所定労働時間が1日8時間で、ある従業員が有給休暇を1日取得した場合、その有給休暇取得日は総労働時間からは除外されるものの、給与計算上は8時間分が支払われることとなります。
3. 年間の総労働時間の計算方法


3-1. 一般的な場合での総労働時間の計算方法
一般的な就業形態では、総労働時間の計算は非常にシンプルな計算で算出できます。
基本的な考え方は、従業員が勤務を開始する時刻から終了する時刻までの時間を計算し、そこから休憩時間を差し引くことで、1日の総労働時間を求めるというものです。
具体的には、計算式は次のようになります。
「終業時刻 - 始業時刻 - 休憩時間 = 1日の総労働時間」
例えば、始業時刻が9:00、終業時刻が17:00、休憩時間が1時間の場合、計算は次のようになります。
17:00 - 9:00 - 1時間 = 7時間
この場合、1日の総労働時間は7時間となります。一般的に、1か月の総労働時間を計算するためには、1日の総労働時間を週の勤務日数(たとえば、5日間の場合)で掛け算し、更にそれを1か月に換算します。たとえば、5日勤務の場合の計算は以下のとおりです。
7時間 × 5日 × 4週間 = 140時間
したがって、この例では1か月の総労働時間は140時間となります。このように暦に合わせて年間の総労働時間も算出しましょう。
この計算方法は、様々な業種や企業において広く採用されていますが、重要な点は、個別の企業での就業規則や労働契約に基づいて期間や休憩時間が異なる場合があるため、正確な労働時間の把握には企業のルールを考慮する必要がある点です。
3-1. 変形労働制の総労働時間の計算方法
まず、変形労働時間制を正しく理解するため制度の概要を説明します。変形労働制は、繁忙期や閑散期に応じて特定の期間における法定労働時間の総枠が設定され、その範囲内で労働時間を調整することができます。注意点として、1週あたりの平均労働時間40時間以内というルールを満たす必要があります。
それを踏まえた上で、変形労働制における総労働時間の計算式は次の通りです。法定労働時間の総枠は、「40時間×対象期間の暦日数÷7」で算出されます。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、対象期間が28日であれば、次のように計算します。
40時間×28日÷7=160時間
つまり、この28日間の間における法定労働時間の総枠は160時間となります。この時間内で労働を弾力的に調整できるのが変形労働時間制の特徴です。
変形期間を3ヶ月とした場合の例も考えてみましょう。例えば、対象期間が90日(約3ヶ月)であれば、計算式は次のようになります。
40時間×90日÷7=次のような約514時間
この場合、90日間での法定労働時間の総枠は514時間になります。このように年間の総労働時間も計算しましょう。
3-3. フレックスタイム制の総労働時間の計算方法
フレックスタイム制の総労働時間の計算方法は、労働者が自ら始業・就業の時刻を選択し、労働時間を柔軟に調整できるというフレックスタイム制のルールに基づいています。フレックスタイム制では、清算期間内での総労働時間を定める必要があり、これは変形労働時間制における法定労働時間の総枠を参考にして算出されます。
具体的には、フレックスタイム制の清算期間は最長で3ヶ月となっており、毎月の総労働時間を合算することで求めることができます。清算期間が1ヶ月の場合、例えばその月の暦日数に基づいて計算を行います。具体的には、月ごとの労働日数が異なるため、総労働時間は以下のように設定されます。
例えば、清算期間を3ヶ月とした場合は、月ごとの暦日によって次のような法定労働時間が設定されます。もし91日であれば520.0時間、90日であれば514.2時間、89日であれば508.5時間というように、日数に応じた総枠が決まります。これを元に、実際の労働者の労働時間を把握し、管理していく必要があります。
フレックスタイム制の場合、労働者本人が開始時刻や終了時刻を調整するため、忙しい時期には労働時間が増える一方で、比較的時間に余裕がある際には短縮することも可能です。この柔軟性は、仕事と生活のバランスを取りやすくする一因として高く評価されています。
3-4. 裁量労働制の総労働時間の計算方法
裁量労働制における総労働時間の計算方法は、一般的な労働時間の算出とは異なります。これは、業務の性質上、労働者に自由な時間配分を与える必要があるためです。裁量労働制では、労使間で合意した時間を基に労働が行われたものとみなされます。
具体的には、裁量労働制を適用している労働者に対しては、実際の勤務時間に関わらず、定められた時間が労働時間として計上されます。例えば、労使協定で1日8時間の労働が定められている場合、実際に7時間働こうが9時間働こうが、その日は8時間勤務したものとされます。このため、裁量労働制では、出勤時刻や退勤時刻を厳密に管理することは必要ありません。
そのため、採用時に総労働時間をどのように計算するか、裁量労働制の範囲や対象業務、賃金に関連することを取り決める方が望ましいでしょう。
このように、裁量労働制における総労働時間の計算は、労使協定に基づくものであり、実績にかかわらず定められた時間を労働したものと見なすため、労働者は自己管理が求められます。また、企業側も適切な運用のための運用ルールを策定することが不可欠です。
4. 労働時間を適切に把握し管理するためのガイドライン


「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置」にはガイドラインが発表されており、このガイドラインに沿った対応が必要になります。
下記のガイドラインに基づいて、使用者が勤怠管理する上で必要とされる対応を簡単に解説します。より詳しい内容を知りたい方は、下記のリンクからガイドラインを確認してみてください。
参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
関連記事:労働時間とは?社会人が今さら聞けない基本情報を徹底解説!
4-1. 始業・終業時間を確認し記録すること
使用者は労働時間を適正に把握するため、労働者の始業・終業時間を客観的な方法によって記録しておかなくてはなりません。客観的な記録とはタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などが挙げられます。
4-2. 始業・終業時間を確認する方法
始業・終業時間を確認する方法は、原則として次のいずれかの方法が推奨されています。
- 労働時間管理担当者が自ら現認することにより確認し記録する
- タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録する
労働時間管理担当者が現認する場合、該当労働者からも確認できるような方法が望ましいです。
4-3. 始業・終業時刻が自己申告制の場合の措置
職種や仕事内容などにより、客観的な記録ではなく自己申告によって始業時間・終業時間を記録する場合は、従業員への説明をおこないます。その際、実態との乖離があった場合は調査をおこなうなどの措置が必要です。
また、自己申告を阻害する制度を設けてはならないとされています。
4-4. 賃金台帳の適切な調整
使用者は、労働者ごとに労働日数や労働時間、時間外労働時間(残業時間)、休日出勤・深夜労働の労働時間などを賃金台帳に記入しておかなくてはなりません。
上記の内容が記入されていない場合や虚偽の内容が記入されていた場合、30万円以下の罰金に処されるため、注意しましょう。
関連記事:労働時間管理を正確におこなうためのガイドラインを徹底解説
4-5. 労働時間を記録する書類の保存
労働時間を記録する書類は、労働基準法第 109 条に基づいて5年間(当分の間は3年間)保存することとなっています。
労働基準法第109条では「その他労働関係に関する重要な書類」の保存を義務化していますが、労働時間の記録に関する書類もこれに該当するのです。
具体的には、労働時間管理担当者が始業・終業時刻を記録したもの、タイムカードなどの記録、残業命令書及びその報告書、労働者が労働時間を記録した報告書などが保存対象となります。
なお、5年間の起算点は、書類ごとに最後の記載がなされた日となるので、保存期間の間違いに注意しましょう。
4-6. 労働時間管理者の職務について
労働時間管理や労務管理をおこなう部署の責任者は、「労働時間の適正な把握など労働時間管理の適正化に関する事項を管理しなければならない」とされています。つまり、過剰な長時間労働がおこなわれていないか、労働時間が適正に把握されているかなどの確認が職務となります。
また、労働時間管理をするうえで問題点があった場合は、どのような措置を講ずるべきか、問題解消を図ることも重要な職務です。
4-7. 労働時間等設定改善委員会の設置
労働時間管理の状況によっては、必要に応じて「労働時間等設定改善委員会」などの労使協議組織を設置することとされています。委員会の設置は、労働時間管理の現状を把握した上で、労働時間管理上の問題点やその解決策などの検討をおこなうことが目的です。
5. 労働時間の把握義務化へ対応するためのポイント


労働時間把握の義務化の主な変更点は、タイムカードをはじめとした客観的な勤怠管理システムの導入による厳密な労働時間の把握があげられます。
とはいえ、単に客観的な勤怠管理をすればよいというだけではないので、どのような対応すれば良いのか、具体的に解説していきます。
5-1. 客観的に労働時間を把握するためのツールの導入
法改正によって義務化された労働時間を正確に把握するためには、「タイムカードに労働時間を刻印する」など客観的な勤怠データが必要になります。
ただし、職場の事情からタイムカードを利用できない場面もあるかもしれません。例えば、テレワークなどで在宅勤務をしていたり、直行直帰で通勤してこなかったりする場合は、労働時間を自己申告してもらうことになります。
このようなケースに対応するには、場所を選ばず出退勤が記録できるクラウド型の勤怠管理システムが最適です。新たに勤怠管理システムを導入する場合、従業員全員を集めて口頭で説明するのは大変なので、事前にマニュアルを作っておくことをおすすめします。また、就業規則や労使協定を見直して周知を徹底できるように段取りを進めていきましょう。
5-2. 労働時間は1分単位で把握する
労働時間把握の義務の内容として、重要なポイントのひとつが労働時間把握の厳密化です。
本来、企業が従業員を雇用する場合、1分単位で細かく労働時間を把握して給与を支払う必要があります。
しかし、「出社後、着替えてからタイムカードを押す」「30分以下の残業は残業として報告しない」「昼食休憩を取っても構わないが来客があれば事務員が対応すべき」など、本来給与が発生する時間を無給扱いにしてしまっている企業も少なくありません。
労働時間の把握義務化では、今までグレーゾーンになっていた労働時間を厳密に把握することが求められているので、1分単位で把握できるようにしましょう。
5-3. 管理職に対する労働時間管理の拡大
労働時間把握の対象は、管理職も含まれています。
労働時間の把握義務化は「会社で働く従業員の健康を守るため」のルールです。そして、長時間労働によって体調を崩すのは一般社員だけではありません。
管理職が一般社員より緩い残業規制の対象になるという点は法改正以前と同じです。しかし今回の法改正によって管理職に対しても労働時間把握が義務化されています。
一般社員も管理職も、アルバイトやパートであっても、長時間労働が認められた場合は医師による面接が必要なので、注意しておきましょう。
関連記事:管理職の労働時間・休憩時間についての基礎知識を徹底解説!
5-4. 労働時間の長い従業員に対する医師の面接指導
もともと、長時間労働をする従業員に対しては、医師による面接指導が義務付けられていました。
しかし、労働時間把握の義務化によって産業医の権限が強化されています。そのため、残業時間と休日出勤の時間が週40時間を越えた場合、職種に関係なく医師の面接を受けさせるかどうかを検討する必要があります。
参照:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
6. 労働時間の把握義務化に必要なツール


厳格化された労働時間を確実に把握する方法としては、『始業・終業・残業の考えのマニュアル化』『手軽にタイムカードを打刻できる勤怠管理システムの採用』がおすすめです。
パソコンの表計算ソフトを使ったり、紙製のタイムカードを使ったりして労働時間を管理するという方法もありますが、従業員の負担が多くなるとミスも発生しやすく、人事や事務社員に負担がかかってしまいます。
特に、企業の人事担当者は、労働時間を把握する以外にも法改正に併せて日々の業務を調整する必要があるため、少しでもほかの従業員に協力してもらえるような環境づくりに力を入れましょう。
6-1. 始業・終業・残業の考え方のマニュアル化
多くの従業員は、正確な労働時間の定義や残業が発生するかどうかの基準などをそもそも知りません。基準を知らない従業員に対して、一方的に「今後は正確にタイムカードを押すように」と周知をするだけでは、押し忘れなどが生じるかもしれません。正確な労働時間を把握するには、「始業・終業・残業」のルールを理解してもらう必要があるので、まずは勤怠管理のルールをマニュアル化しましょう。
- 出退勤はパソコンのログイン状態で記録する
- 出社したら着替えや朝礼をする前にタイムカードで打刻する
- 残業を申告制にする
- 個人でタイムカードを押してからおこなう業務は残業の指導の対象とする
- 直行直帰をする場合の出勤・退勤の扱い
- 月間の残業時間制限
上記のような内容を盛り込み、「始業・終業・残業」に関する正確な報告ができるように、人事主導でルールを作りましょう。ただしルールを作っただけだと、細部まで読まない人も出てくる可能性があります。そのため、必要に応じて就業時間中に従業員を集めて説明を設けたり、各部署の管理職を集めて現場の上司が適切な指導をできるようにしたりすることも考えましょう。
6-2. 手軽にタイムカードを打刻できる勤怠管理システムの採用
社内ルールの整備と並行して進めたいのが、勤怠管理システムの導入です。出社したときに出社時刻を紙に記入するなど、個々人の作業に依存した方法だと、どうしてもミスや手違いが起きてしまいます。従業員や管理職がミスした場合、人事担当者がミスを見つけて修正をお願いすることになり、二度手間になってしまいます。
勤怠管理システムには、『出社後に各自のパソコンを使って1クリックで打刻できる』『スマホのアプリを使って出退勤を記録できる』『職場の入り口に端末を置き、ICカードをタッチして勤怠をつける』など簡単に打刻できる機能が搭載されています。これらの機能により、従業員の打刻ミスを防げるため、労務管理者も手軽に出勤時刻や退勤時刻を管理できます。
このほか、「勤怠を付ける」という作業の負担を減らすこともでき、直行直帰の場合でも勤怠をつけることが可能になります。クラウド型の勤怠管理システムなら、月額課金制のため初期費用を安く抑えられるのもポイントです。
登録したデータは強固なセキュリティで保護され、バックアップも充実しています。勤怠管理以外の機能が搭載されている勤怠管理システムなら、人事としての仕事も一部削減することができるでしょう。
勤怠管理システムでどのようなことができるか気になる方は、以下のリンクから勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る
7. 便利なシステムの導入し労働時間を正しく計算し把握の義務化に対応しよう


労働関連法の改正によって、企業はこれまで以上に厳しく従業員・管理職の労働時間を把握する義務を負いました。労働時間が一定を越えた従業員に医師の面接を受けてもらったり、正確な勤怠状況を記録して長時間残業を防いだりするためには、社内ルールの整備が必要不可欠です。
人事担当者や各従業員が直接おこなう作業が多ければ多いほど、ミスや誤解が生まれやすくなるため、法改正に対応できるように使い勝手のよい勤怠管理システムの導入をおすすめします。
労働時間管理は、原則だけでなく「月45時間・年360時間」という残業時間の上限や、変形労働時間制・フレックスタイム制における独自のルールなど、把握すべき点が多岐にわたります。
自社の勤怠管理が、これらの複雑な規制すべてに準拠しているか、自信を持って言えますか?
「今月の法定労働時間の上限は何時間?」「残業させられるのは、あと何時間だろう?」
このような業務上の疑問・不安をお持ちの方に向けて、労働時間の上限について解説した資料を無料配布しています。
本資料では、労働時間の定義から各種上限規制、多様な勤務形態での考え方まで網羅的に解説しています。
自社の勤怠管理を総点検したい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
労働時間の関連記事
-


副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向
勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15
-


着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06
-


過重労働に該当する基準は?長時間労働との違いや影響を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2025.08.19