雇用契約を締結する際の必要書類や手続きの流れを詳しく紹介
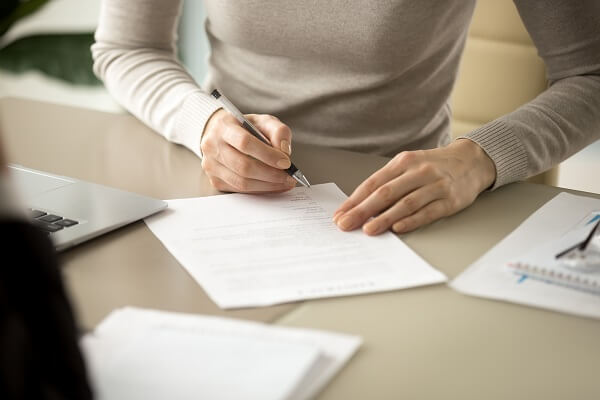
従業員を雇用する際には、労働関係の法令に則って手続きを進めなければなりません。労働基準法や労働契約法には、雇用主が踏むべき手順が定められているので、これらの法律についてよく知っておくことが求められるでしょう。
また雇用契約を締結する際には、雇用者側で用意すべき必要書類と、労働者側に用意してもらうべき必要書類があります。この記事では、法律に則って正しく雇用規約を締結するために必要な書類と手続きについてわかりやすく解説します。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用契約締結時の必要書類

雇用契約を締結する際に必要な書類を、雇用者側と労働者側のそれぞれの視点から説明します。
1-1. 雇用者が用意する書類
まず雇用契約を締結する際に雇用者側が必要とする書類について見ていきましょう。
1-1-1. 雇用契約書
雇用契約書は雇用主・労働者の双方にとって非常に重要な書類です。
法的には雇用契約書を交付しなくても問題はありませんが、トラブルになるのを防ぐために交付しておくことをおすすめします。
雇用契約書は労使双方が雇用契約の内容に同意したことを示す書類で、双方の署名捺印がされています。強制されているわけではありませんが、リスク回避の意味合いで2部作成し、同じ原本を1通ずつ各自で保管しておくことが一般的です。
後述の労働条件通知書は雇用主が一方的に労働者に提示するものですが、雇用契約書は双方の合意を示すものです。なので、万が一訴訟問題が起きた際に有効な証拠となります。
また雇用契約書の内容は、就業規則の内容を下回ってはなりません。新たなトラブルが起こる要因になりうるので、雇用契約書を作成するタイミングで下回っていないか確認するようにしましょう。
あわせて、雇用契約の原則に基づいた契約内容になっているかも確認する必要があります。契約の禁止事項に該当する場合、後々トラブルに発展しかねません。当サイトで無料配布している「<完全版>雇用契約マニュアル」では、雇用契約の基本から締結、解雇まで進め方や注意点をくわしく解説しています。雇用契約の基本を再確認したい方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。採用や人員整理に関する社内規程に不安や疑問がある方にもおすすめです。
1-1-2. 労働条件通知書
雇用契約書は法的に義務付けられた書類ではありませんが、労働条件通知書は交付が義務付けられているものです。
労働条件通知書には必ず記載しなければならない絶対的明示事項と、会社が制度として定めている場合に記載しなければならない相対的明示事項があります。
たとえば労働契約の期間、就業場所、始業・終業時間、休憩・休暇・休日、賃金の決定・計算・支払い方法、退職、就業場所・業務の変更の範囲に関する事柄などが絶対的明示事項として挙げられます。これらの項目は書面での提示が必要となるので、労働条件通知書に必ず記載しなければならないものです。
なお、労働者が希望する場合のみ、電子データでの交付が可能です。
さらに労働条件通知書とは別に、口頭で説明することができる項目もあります。現在では事務手続きを簡略化するために、労働条件通知書兼雇用契約書を電子データで作成して雇用契約を結ぶ会社が少なくありません。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
1-2. 労働者に用意してもらう書類
労働者には雇用契約時に、以下の書類を用意してもらいます。
厳密には、新卒採用時や中途採用時など入社する社員の形態によって必要な書類が変わってきますが、おおむね以下のとおりです。
- 雇用契約書
- 入社誓約書
- 身元保証書
- 従業員調書
- 住民票記載事項証明書
- 免許や資格に関係する書類
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 健康診断書
- 退職証明書
雇用契約書に関しては、捺印済みのものを当日持ってきてもらえるように手配しておくと、手続きがスムーズです。
法的な観点では当日捺印をもらい契約締結でも問題ありませんが、雇用契約書には労働条件などが記載されています。労働者は内定をもらった後にどのような労働条件なのか確認してから入社を検討したいため、労働条件通知書と共に事前に送付するのが望ましいです。
関連記事:入社手続きで必要な書類は何がある?種類と作成方法を詳しく解説
2. 労働者と雇用契約を締結する際の手続きの流れ

では雇用契約を締結する際にどのような手続きが必要となるのか見ていきましょう。
2-1. 必要書類を回収する
雇用契約書や労働条件通知書を交付した後には、雇用契約に必要な書類を従業員から提出してもらわなければなりません。入社手続きには非常に多くの書類が必要となるので、漏れがないよう注意する必要があります。
基本的に必要となるのは雇用保険被保険者証、年金手帳、従業員の住民票記載事項証明書、給与所得者の扶養控除等申告書、マイナンバーなどです。
中途採用の従業員の場合には源泉徴収票が必要ですし、従業員に署名捺印してもらった雇用契約書、健康診断書の提出を求める必要があるでしょう。
会社によっては、特定の資格の合格証明書や免許のコピーなども必要です。
2-2. 保険・税金関係の手続き
続いて行うべきなのが保険や税金関係の手続きです。基本的には社会保険、雇用保険、住民税と所得税の手続きがあります。
2-2-1. 社会保険は年金事務所もしくは健康保険組合へ
もし採用した従業員が正社員で70歳未満である場合、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を年金事務所もしくは健康保険組合に提出しなければなりません。
雇用開始日から5日以内に行うべき手続きなので、雇用契約を締結したら速やかに手続きを踏むようにすべきです。
もし採用したのが契約社員やパート・アルバイトなのであれば、契約期間が2ヵ月以上かつ所定労働時間が一般従業員の75%以上であることを条件に同じ手続きが必要です。
ただし社会保険の適用拡大に該当する場合には週の所定労働時間が20時間以上30時間未満でも他の要件を満たせば加入することになります。
2-2-2. 雇用保険はハローワークへ
雇用保険の手続きはハローワークで行います。31日以上の雇用が見込まれる労働者で、所定労働時間が週20時間以上というのが加入の条件です。
雇用契約が締結された翌月の10日までに、雇用を証明できる書類を揃えて雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。
2-2-3. 住民税は従業員の居住する市区町村へ
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあります。普通徴収は従業員自身が納付する方法で、特別徴収は企業が代理で従業員の給与から住民税を差し引きし納付する方法です。
中途採用者を受け入れ、特別徴収を希望された場合は従業員の居住する市区町村に給与所得者異動届出書もしくは特別徴収への切替申請書を提出する必要があります。
関連記事:住民税の納付方法|企業側がすべき手続きの流れをわかりやすく解説
2-2-4. 所得税は源泉徴収票の受け取りを忘れない
所得税については、給与からの天引きができるので手続きが必要ないケースもあります。
ただし、転職した同じ年に再就職した従業員に対しては、以前の職場の給与所得の源泉徴収票の提出を求めなければなりません。所得税の扱いが分かりにくい場合には税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
また、源泉徴収簿を作成している場合は入社者の情報を記入しましょう。
関連記事:源泉徴収簿を作成する必要性やその手順・注意点を解説
2-3. 法定三帳簿を準備する
税金や保険関係の手続きと共に行っておくべきなのが法定三帳簿を準備することです。法定三帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことで、企業が作成し保管しておくことが義務付けられているものです。
労働者名簿には労働者の住所氏名や生年月日、雇入れ年月日、従事する業務の内容などが記載されます。労働者名簿の変更などは遅延なく行われなければならないので、随時更新が必要です。
雇用形態、従業員の人数にかかわらず作成が義務付けられているのも特徴です。
続いて賃金台帳についてです。各労働者の住所氏名、賃金計算期間、労働時間数、時間外労働時間数、基本賃金など賃金に関する詳細が記載されています。
賃金台帳が正確に記入されていない、何らかの不備がある場合には労働基準監督署からの是正勧告や罰金が科せられる恐れがあります。
出勤簿は労働者の氏名や出勤日、始業・終業時間、休憩時間などが記載されます。
それぞれの帳簿は法律によって保存期間が定められています。労働者名簿は労働者の退職日や解雇日から3年、賃金台帳は最後に記入した日から3年、出勤簿は最後に出勤した日から3年です。
2-4. 備品の供給
従業員がスムーズに業務に取りかかれるよう、備品の供給もしっかり行う必要があります。制服や社員証、机、イス、パソコン、事務用品などを用意しましょう。
ICカードや入室に必要な指紋登録などもできるだけ早く済ませます。加えて給与システムや人事システムに情報を入力して給与や税金の支払いに必要な個人情報を管理します。
3. 雇用契約の締結をスムーズに行うポイント

雇用契約をスムーズに締結するためのポイントを2つ紹介します。
3-1. 業務手順をマニュアル化する
人事採用は不定期に発生する業務なので、必要な手続きをマニュアル化しておくとスムーズに雇用契約が締結できます。雇用契約では必要な書類が決まっているので、フォーマットを作っておけば事務処理の負担を最小限に抑えることも可能です。
3-2. 電子申請を活用する
現在では雇用契約の手続きのうち、いくつかの部分を電子申請できるようになっています。雇用保険、社会保険、労働保険の手続きは電子申請できるので、試してみるとよいかもしれません。
クラウドサービスを利用すれば、必要な情報を入力するだけで簡単に届け出を行うことができます。窓口に書類を持って行く手間も省けるので、雇用契約の締結にかかる時間の大幅な短縮が可能です。
クラウドサービスのなかには、法令の改正などに自動で対応してくれるものもあります。給与の計算などにも活用できるでしょう。
関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
4. 雇用契約の手続きをよく理解してスムーズな契約締結を

雇用契約の締結では、雇用者側にもさまざまな手続きが求められます。事務処理に手間がかかるものも多いですが、手続きをマニュアル化したりクラウドサービスを使ったりすることによって簡単に処理できるでしょう。
手続きに漏れがないよう、雇用契約についてよく理解したうえで契約を結ぶことが大切です。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
雇用契約の関連記事
-

トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説
人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2024.10.11
-

労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2024.10.18
-

試用期間に解雇できる?必要な手続きや注意点を詳しく解説
人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2024.06.13





























