モチベーション管理とは?失敗例から学ぶ部下のやる気アップに成功するコツと管理方法
更新日: 2024.10.11
公開日: 2020.1.28
jinjer Blog編集部

モチベーションを管理するということは、良い部下を育てる上では非常に重要なポイント。また、何かのプロジェクトを成功させるときにも欠かせないものでもあります。
しかし、なかには具体的な方法を知らなかったことが原因で失敗してしまうケースも。
この記事では、改めてモチベーション管理をうまく成功させるための方法について解説していきます。
目次
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. そもそもモチベーション管理とは


1-1.モチベーション管理の目的
モチベーション管理の目的は、従業員のモチベーションを高めたり維持することにあります。従業員のモチベーションが高い状態にあると、自発的に業務に取り組むため成果が上がったり、品質や精度が高まり企業の成長へと繋がります。
逆に従業員のモチベーションが下がってしまうと、意欲が低下しミスが増えたりと生産性が低下してしまう可能性があります。
従業員ひとりひとりのモチベーションの向上が積み重なり、最終的には事業の発展や成長という企業にとってのメリットへと繋がるのです。
1-2. やる気との違い
やる気の意味は「進んで物事をなしとげようとする気持ち」です。
モチベーションの意味は「動機づけ」なので、やる気との関係性を踏まえると「やる気を出すきっかけを与える」ことと捉えられます。
モチベーション管理とは、上司が部下へやる気を出すきっかけを与えるために働きかけること、と捉え程よい距離感で接することをおすすめします。詳しい理由は、後述の「5. モチベーション管理の失敗例」に記載しています。
引用:「やるき」の意味| goo国語辞書
引用:「モチベーション」の意味| goo国語辞書
1-3. モチベーションリソースとは
モチベーションリソースとは、やる気を出すきっかけとなる要素のことを指します。
モチベーションリソースは大きく「組織型」「仕事型」「職場型」「生活型」の4分類に分けられると言われています。
どれかひとつにしか当てはまらないというわけではなく、複数のものが当てはまることもあります。
部下がどの分類に興味があるか把握できると、モチベーション管理の際の参考になります。また、自分自身がどこに興味があるか把握すれば、目標を立てたりキャリアを検討する際にも役立ちます。
関連記事:モチベーションリソースとは?従業員の「働く理由」を人事に活かす方法
2. 必ず覚えておきたい「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」


モチベーション管理では、2つのポイントが欠かせません。そのポイントとは「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」です。
それぞれ内容が異なっており、どちらか欠けてしまうと失敗する恐れがあります。
2-1. 外発的動機づけとは
外発的動機づけには、報酬や教育といったものが含まれます。ここでよく勘違いされやすいのが、アメとムチです。確かにアメとムチは、外発的動機づけに位置付けられる重要なものです。
例えばしっかりと褒めた上で、意識向上を目指したハードルの高い仕事を与えてみましょう。
必要以上に評価をしてしまうと、部下はどんな小さなことでもお給料アップにつながらなければ、努力しようとしなくなります。本来、失敗をしたときに大切なのは、次に同じ失敗を繰り返さないために原因と対策を理解することです。
必要以上のマイナスの評価をされてしまうと、部下は失敗が怖くて挑戦をしなくなります。
このようなことを防ぐためにも、アメとムチの内容が適切かどうか、日頃からチェックしなければなりません。チェックすることで、アメとムチの与え方の間違えをできる限り減らすことができます。
このアメとムチをかすことで、部下が持つ仕事への集中力を保つことができ、モチベーションの管理に繋がります。
2-2. 内発的動機づけとは
内発的動機づけとは、社員のやる気や信頼性などです。外発的動機づけよりも優位性が高く、ここをうまく活用することがモチベーション向上につながります。モチベーションマネジメントと言って、内発的動機づけに軸をおいて従業員のモチベーションをマネジメントする手法も出てきています。
内発的動機づけと外発的動機づけがそれぞれどのような効果を出すか試した実験もあり、外発的動機づけのみの被験者よりも内発的動機づけのみの被験者のほうが優れた結果を出したという実験結果が出ています。
そのようなことから、外発的動機づけよりも内発的動機づけが優先されやすい傾向があります。内発的動機づけをうまく与えることにより、最終的には外発的動機づけをせずに仕事へ取り組んでくれるようになるでしょう。
しかし、社員によっては自分の興味がない仕事に対して、積極的に取り組めないケースもあります。そのような問題を解決するためには、内発的動機づけと外発的動機づけを合わせて活用する必要があるのです。
関連記事:モチベーションマネジメントとは?人材育成に役立つフレームワークも紹介
2-3. モチベーション3.0とは
モチベーション3.0とはダニエル・ピンク氏が提唱したモチベーション理論の概念です。
モチベーション3.0というのは内発的動機づけを指しており、変化の激しい現代で生き抜けるような柔軟で強い組織を作るために、従業員の内側からやる気を起こそうという考え方です。
3.0の前段階である1.0、2.0というものも存在します。モチベーション1.0は生理的動機づけ、モチベーション2.0は外発的動機づけのことを指しています。
関連記事:モチベーション3.0とは?注目される背景やメリットなどをわかりやすく解説
3. 従業員のモチベーションが下がる原因
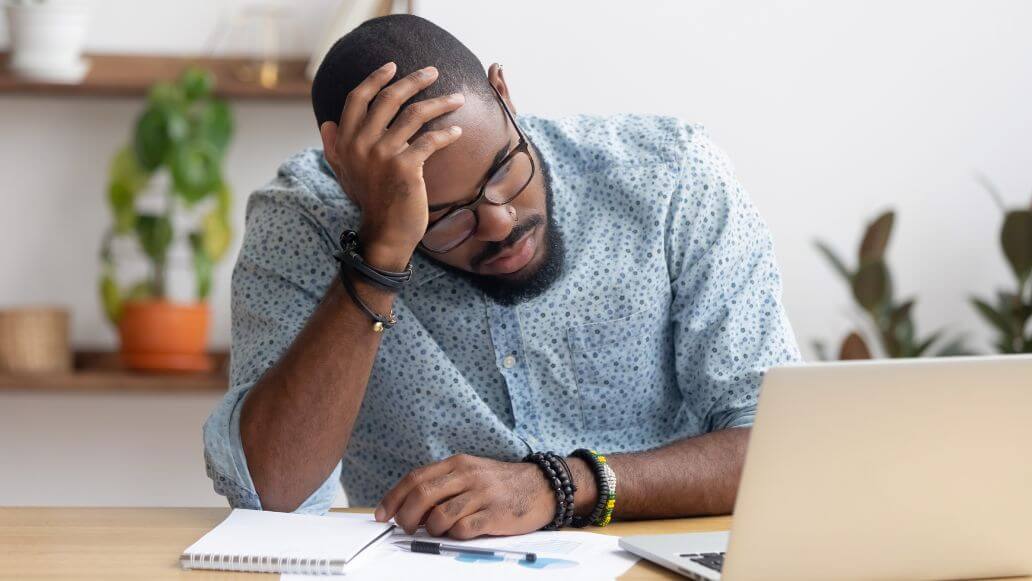
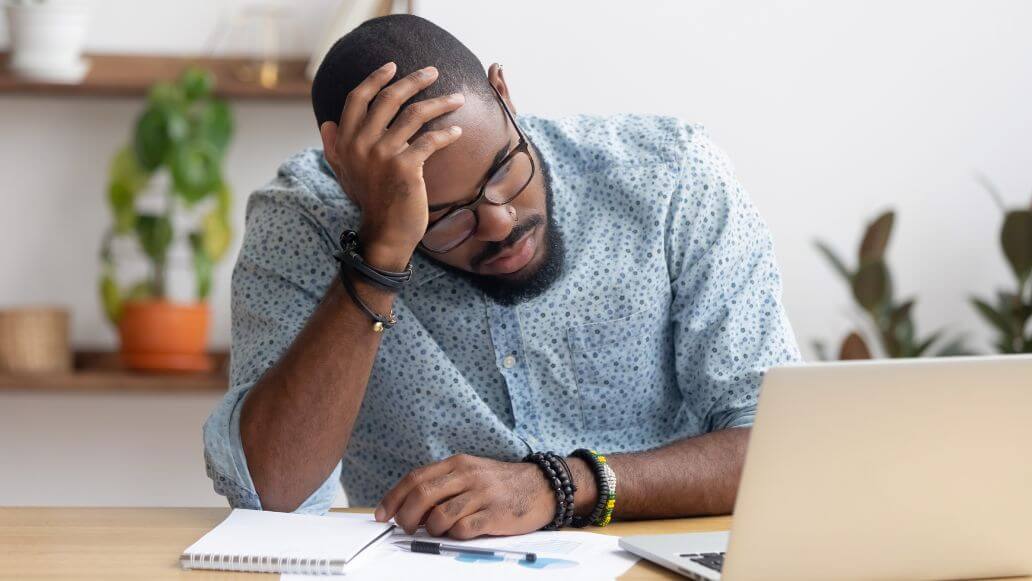
実際に従業員のモチベーションが下がってしまう原因とはどんなものがあるのか理解して対処することが重要です。ここではよくあるケースを解説します。
3-1. 取り組む業務内容に魅力を感じない
業務内容に魅力を感じない場合、従業員はモチベーションを維持するのが難しくなります。具体的には、業務内容が面白くない、やりがいを感じないといった状況に陥ると、仕事に対して興味を失い、自分自身に嫌気が差してしまうことがあります。結果として、従業員の取り組み姿勢が消極的になり、生産性の低下を招くことが多いです。また、こういった悪循環は業務結果にも影響を及ぼし、組織全体のパフォーマンスを下げる可能性があります。
3-2. 上司から部下へ誤った指導をしている
上司から部下への誤った指導は、従業員のモチベーションを大きく損なう要因となります。不適切な指導により、部下の成長スピードが低下し、業務効率も期待通りに向上しません。このような状態が続くと、部下は仕事に対する自信を失い、自己評価が下がります。最終的には、自分がその仕事に向いていないと感じ、仕事に対する誇りも薄れます。結果として、モチベーションが著しく低下し、組織全体の生産性に悪影響を及ぼします。例えば、誤った指示や過度なプレッシャーをかけることが該当します。部下が安心して仕事に取り組める環境を整えることは、管理職やリーダーにとって重要な役割です。
3-3. 給与が少ない・昇給しない
給与や昇給制度が不十分だと、不公平感や不満が生じ、モチベーションが低下します。仕事内容に対して給与が少ないと、部下のモチベーションに大きく影響します。どれだけ楽しく仕事をしていても、給与が業務内容に見合っていないと感じると、不満や期待の裏切りが生じ、モチベーションが持続しにくくなります。従業員が正当に評価され、昇給の機会が提供されることで、彼らのやる気は保たれ、組織全体の生産性が向上します。したがって、仕事内容や業務量に相応しい給与形態と評価制度を整えることが重要です。
3-4. ハラスメントにあたる行為がある
ハラスメントが職場で発生すると、従業員は緊張状態に陥り、メンタルヘルスが悪化してモチベーションが著しく低下します。具体的には、パワハラが行われる場合、従業員は怒られる恐怖心から仕事に対し不安を抱き、パフォーマンスが低下します。これが続くと、最終的には休職や離職という深刻な事態に発展するリスクがあります。組織のリーダーや管理職としては、ハラスメント対策を徹底することが重要です。具体的な対策としては、ハラスメント研修の実施や相談窓口の設置などが考えられます。
3-5. 残業が多く休めない・慢性的に疲れている
モチベーションを下げる原因として残業も大きく関係します。残業の扱い方も確認しておきましょう。残業というのは、日中でエネルギーを使い果たしていることもあり、集中力やモチベーションが下がりやすいもの。
また、残業するということは睡眠が十分にとれなくなってしまう原因にもなります。睡眠不足に陥ると、毎日の仕事における生産性が下がります。
仕事がきちんと進行しないというのは、モチベーション以前の問題。そのため、モチベーションを高めたいのであれば、残業させないようにするのが一番です。
4. モチベーション管理をするメリット


それではモチベーション管理を行うことで企業にとってどんなメリットがあるのでしょうか。具体的に解説していきます。
4-1. 会社の生産性が向上する
モチベーションが高い従業員は、仕事の質にこだわりながら効率的に業務を進めるため、結果として高い成果を出します。部下が積極的に仕事に取り組むことで、生産性が向上し、全体の業務効率もアップします。このようにモチベーション管理を徹底することで、従業員一人ひとりがより良いパフォーマンスを発揮し、会社全体の生産性が飛躍的に向上します。生産性が向上すれば、安定した収益を得ることができ、企業の盤石な経営につながることは間違いありません。モチベーション管理は、組織の成功に直結する重要な要素です。
4-2. 適材適所の正しい人材配置ができる
モチベーション管理を徹底することで、適切な人材配置が実現し、生産性の向上が期待できます。具体的には、各従業員の強みや興味、モチベーションを把握できます。たとえば、モチベーションが低下する原因が人間関係の問題であれば、部下を人間関係に悩まない部署へ配置できます。また、個々の能力を最大限に引き出せる業務内容を与えることもできます。これにより、部下の働きがいが向上し、結果として組織全体の生産性が向上します。適材適所の人材配置が実現することで、企業の活気も一層高まるでしょう。
4-3. 離職率が低下する
モチベーション管理を適切に行うことは、部下の離職率を低下させる効果があります。具体的には、モチベーション管理を通じて、従業員が仕事に対する満足度を高め、その結果として経験豊富なスタッフを長期間にわたって維持することができます。例えば、各個人のモチベーションが下がる原因を分析し、その要因を改善することは、従業員が働きやすい環境を整える一助となります。モチベーションが維持されることで、仕事に対する意欲が高まり、結果的に離職率の低下だけでなく、従業員満足度の向上も期待できるでしょう。
5. モチベーション管理の方法


5-1. システムを導入してモチベーションを管理する
モチベーションを管理するとひとことで言っても、抱えている部下の人数が多く、面談をするころにはモチベーションが下がってしまっていた、ということもあるのではないでしょうか?
日々のコミュニケーションも大切ですが、従業員のモチベーションを把握するためのシステムを導入することで、モチベーションを把握するまでの時間や手間を省略させ、浮いた時間を集めた情報の分析や従業員の理解に使うことができます。
システムによって、従業員へのアンケート機能や性格診断機能など、搭載している機能が異なります。実際にシステムで出来る管理は以下のようなものがあります。
関連記事:モチベーション管理システムとは?従業員の本音を可視化するツールを解説
目標設定をしてもらった状態で管理をする
モチベーション管理システムを活用し、従業員に目標を設定してもらうことで、その進捗状況を具体的に管理することが可能です。
システムで目標設定を行うことで、達成を目指した具体的な行動を促せるため、社員は自発的に動くことが期待されます。結果として、上司からの指示が減り、上司の負担も軽減されます。一方で、目標が間違って設定されると、逆にモチベーション管理が困難になるリスクもあります。したがって、目標設定には内容を明確にし、適切な期限を設けることが重要です。
サーベイなどで集まったデータを可視化する
モチベーション管理システムを活用し、従業員のモチベーション状態を把握するための定期アンケートを実施することで、データを可視化が可能です。
具体的には、「今の仕事に満足していますか?」「人間関係で困り事はありますか?」「待遇に不満はありますか?」といった設問を設定し、従業員に答えてもらいます。回答形式は数字で表現できるようにすることで、定量的な計測が可能になり、その後の分析が容易になります。
重要なのはアンケート回答率を高めることです。回答が集まらないと正確なデータが取れませんので、回答期限を設け、リマインドメールや社内アナウンスでフォローアップを行うことが肝要です。また、自動配信システムを導入することでアンケートの配信とリマインドを効率的に行うことができ、時間と労力を節約できます。モチベーション管理システムを駆使してデータを可視化し、組織としての生産性向上に寄与しましょう。
不満や要望に対する施策を検討する
サーベイの結果を基に集められたデータを分析し、従業員の不満や要望を汲み取ることは非常に重要です。不満に基づき、人員配置や目標設定の見直しを行うことで、ワークライフバランスの改善が図れます。例えば、特定の従業員が過重労働を訴えている場合、作業の再分配やチームの再編成が有効です。また、仕事や人間関係に対する不信感を解消するための施策として、オープンなコミュニケーションを促進する仕組みを導入することが考えられます。
これにより、従業員の信頼感が高まり、組織全体の生産性向上に寄与します。具体的な施策として、定期的な1対1のフィードバックセッションや、透明性のある評価制度の導入が効果的です。
研修や施策の振り返り
実施した研修や施策の効果を定期的に振り返り、部下のモチベーションにどのような変化があったかを確認することが重要です。まず、モチベーション管理システムを利用して意見を集めることが円滑なチーム運営につながります。具体的には、施策を実施後にアンケートや個別面談を通じて意見を収集し、その結果を分析します。これにより、どの施策が効果的で、どの部分に改善点があるのかが明確になります。
特に、モチベーションが上がった場合には、その原因となった施策を継続し、さらに強化することが推奨されます。一方で、モチベーションが下がった場合には、施策のどの部分が課題となっているのかを詳細に確認し、その課題を解消するための具体的な対策を講じます。このように、データ収集から施策の実施と振り返りまでを一つのサイクルとして、計画的にモチベーション管理を行うことで、組織全体の生産性向上につなげることが可能です。
5-2. 定期的なコミュニケーションの機会を設ける
定期的なコミュニケーションの機会を設けることは、部下のモチベーション管理において非常に重要です。定期的な対話を通じて社員の状況や心情を把握でき、問題や課題を早期に察知できます。これにより社員一人ひとりに適切なサポートを提供しやすくなり、結果として組織全体の生産性向上にもつながります。
定期的なコミュニケーションの機会を増やすことで、社員との信頼関係が強化され、モチベーション管理がスムーズになります。そして、これが組織としての長期的な成功に寄与することは間違いありません。実際の管理方法としては以下のものが考えられます。
メンター制度の導入
モチベーション管理方法の中でも、コミュニケーションの場を設ける手段としてメンター制度を導入することが有効です。メンター制度とは、経験豊富な従業員が若手社員に助言を行う制度です。特に、社員と入社年が近く、業務上で直接関わりが少ない先輩がメンターとして選ばれることが基本です。この制度により、若手社員に安心感と成長機会を提供します。
この制度の特徴として、多様な部署の同僚と接するチャンスが得られる点が挙げられます。メンターが他の部署の同僚を紹介することで、普段接点が少ない社員ともコミュニケーションが取れる環境が整います。そうすることで、社員間のネットワークが広がり、メンター制度が終了した後でも孤立感を感じることなく働けるようになります。このように、メンター制度は組織全体の生産性向上にも寄与する効果があります。
定期的な面談を行う
上司と部下で定期的に1on1の面談を行い、現状の課題や目標について話し合うことは非常に有効です。1on1の面談を通じて、部下の現状の理解やサポートが可能になり、コミュニケーションの質が向上します。特に、部下の個別のニーズや悩みを深く理解し、解決に向けた具体的な行動が取れます。また、課題の早期発見と解決を図ることでモチベーションが自然と高まります。このような1on1の面談は、上司と部下の信頼関係を強化し、組織全体の生産性向上にもつながります。状況に応じて、時には数人での面談も併用するなど、柔軟に対応することが重要です。
ランチ会を設ける
ランチ会を設けることは、部下のモチベーションやチームの生産性向上に効果的な方法の一つです。非公式な場でのコミュニケーションは、リラックスした状態での意見交換を可能にし、チームの連帯感を醸成します。特にランチ会は、飲み会と比べて費用を抑えやすいため、コスト面のメリットがあります。アルコールが苦手な社員も気軽に参加でき、多くの社員を集めやすいのが特徴です。さらに、一部の企業ではランチ会の費用を会社が負担するケースもあり、そのような取り組みは社員の満足度を高める要因となります。こうしたコミュニケーションの場を設けることで、部下のエンゲージメントを高め、組織全体の生産性向上につながります。
6. 従業員のモチベーション管理を成功させるコツとは


モチベーションの向上には、方程式があります。その方程式とは、「目標の魅力×達成可能率」というもの。この方程式は、アメリカの学者であるビクター・H・ブルームが発表しました。
目標が持つ魅力と達成できる可能性によって、モチベーションの高さが変わります。部下にとって与えられた目標が、自分の好きなことや興味があることで、なおかつ努力すれば叶えられるものの場合は向上します。しかし、自分が全く興味がない内容である上に、達成できそうにない仕事であれば、モチベーションは下がってしまうでしょう。具体的なポイントを紹介します。
関連記事:チームのモチベーションを上げる方法は?リーダーのアクションで組織は変わる!
6-1. 職務充実や職務拡大を検討する
モチベーション向上に役立つ方法として、職務充実や職務拡大があります。職務充実とは、今までよりも一段上の仕事をさせて、能力を高めることです。
一例を挙げると、10人働いている社員の中から、そのうち1人をリーダーに指名し、これまでの業務と合わせて他の社員をまとめる権限を与えます。
これにより、リーダーと指名された社員は「他の社員を管理する」機会ができ、今までより一段上の仕事をすることで能力を高まっていくのです。
もう1つの職務拡大に関しては、その人が可能な仕事の幅を広げてあげることを指します。例えば、ある会社にAという社員がいるとします。その社員が持っているスキルは1つしかなく、仕事も1つのことしかできません。
しかし、部署を変わったことによりAは新しいスキルを覚えました。このように、今までの仕事以外の業務をさせることで本人能力を引き上げるのです。
職務充実と職務拡大の2つを使うことで、一人ひとりの生産性が向上し、モチベーションもアップします。
6-2. 相手に何かしらの選択肢を与えてみる
モチベーション管理の基礎知識である内発的動機づけには、自律性というものが含まれています。自律性とは、誰かに支持されて仕事をするのではなく、自分で考えた上で仕事を進めるということ。
自分で考えて積極的に仕事をしてもらうためには、部下に選択肢を与えたほうがいいでしょう。選択肢を与えることで自主的に取り組んでもらいやすくなり、自分で考えて動ける部下となります。
6-3. 叱るときにはコツを覚えておく
部下を叱るというのは、上司としての素質が非常に求められる場面です。うまく叱ることができれば、部下との関係を壊すこと無く、良くなかった点を指摘し、よりよい方向に部下を導くことができます。まず、叱るときは、問題が発生したらすぐに叱ることが大切です。その際にいつも業務をおこなう場所以外でおこなったほうがいいでしょう。
反対に叱るタイミングが遅すぎると、「どうしてもっと早く教えてくれなかったのか、もしかしたら自分を嫌っているのでは?」というような誤解を招いてしまうことも。場所を変える理由は、部下が怒られたことを引きずらないようにするためです。
いつも業務をおこなう場所で叱ってしまうと、他の社員にも見られてしまい、部下に必要以上に嫌な思いをさせてしまいます。また、他の社員にまで嫌な思いをさせてしまい、結果的に職場全体の雰囲気が悪くなり、部下はもちろん、他の社員のやる気も下げてしまうのです。そのような問題を避けるためにも、叱る際には人がいないような部屋を使いましょう。
6-4. 成果を出したときには内容をしっかりと褒める
反対に成果を出したときには、具体的な内容をあげて褒めてあげましょう。上辺だけの言葉で褒めても、うまく部下の心には響きません。
成果を出すまでの過程や、特に良かった部分などを具体的にあげて褒めることで、自分の仕事ぶりが評価されていると感じ、ひいては「自分は会社に必要とされている」という気持ちを持てるようになるのです
そして、褒めるときもあまり人がいないところでおこなうのがベスト。人前で褒めると、あなたや部下に対して嫉妬や妬みの気持ちを抱く社員が生まれる恐れがあります。
嫉妬心や妬みを持つ人がいると、社内全体のモチベーション管理がうまくいきません。
6-5. 新入社員には「今」と「未来」を教える
まだ会社に入ったばかりの新入社員には、上司がいろいろと教える機会が多いです。このとき、「今」と「未来」を意識した教育をすると、部下のモチベーションをうまく向上させることができるでしょう。
「今」というのは、部下が今おこなっている仕事の必要性を説明するということです。必要性を伝えることで、割り振られた仕事に対して真剣に取り組んでもらえるようになります。また、部下に対して「どのような未来にしたいのか?」といったことを教えるのも大切なことです。明確な未来が見えると、部下のモチベーションは向上します。
6-6. 適切な仕事量を調整する
各従業員に合った適切な仕事量を調整することは、部下のモチベーション管理を成功させるための重要な要素です。仕事量が多すぎるとワークライフバランスが崩れ、業務に打ち込む意欲が低下し生産性が下がる原因となります。特に、残業過多や集中力の低下は部下のモチベーションを著しく損なうため、慎重な配慮が必要です。各従業員の能力や状況に合わせて適切な仕事量を割り振ることで、過労やストレスを防ぎ、持続的なモチベーションを保つことができます。このようにして、個々の従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることで、組織全体の生産性向上にも寄与します。
6-7. 仕事の裁量を与える
部下に仕事の裁量を与えることは、彼らの自己効力感を高め、自発的な動きの原動力を育てるための重要な方法です。具体的には、裁量を与えることによって、部下は自分の意思で仕事を進めることができ、責任感ややりがいを感じるようになります。結果として、彼らのモチベーションが維持され、組織全体の生産性向上に貢献します。特に管理職やリーダー層のビジネスパーソンにとって、裁量を持たせることは部下の成長を促進し、チームのパフォーマンスを最大化するための効果的な手段と言えます。
7. モチベーション管理の失敗例


部下に対して介入しすぎたり、指示があいまいだと、部下のモチベーションを向上させるのは難しくなります。具体的な内容は、以下を確認してみてください。
7-1. 部下に対して深く介入しすぎた
良い部下を育てたいという気持ちは、多くの方が持っていることでしょう。しかし、部下に対して深く介入しすぎると悪影響を及ぼします。
例えば、仕事が失敗したことを叱る際に「生活がだらしないからだ」といったプライベートな内容まで含めてしまうと、部下は「人格も否定された」と思ってしまい、モチベーションが著しく下がってしまいます。
仕事の失敗は部下の責任かもしれませんが、プライベートな生活は一切関係ありません。
そこまで介入してしまうと、あなたのことを部下は嫌うようになり、モチベーションを向上させようとしても、積極的に聞き入れてもらえなくなります。
7-2. あいまいな指示で混乱させた
モチベーション管理において、ゴールを設定しておくことは非常に大切です。ゴールを設定することで、達成しようという気持ちが生まれ、ゴールに向けて具体的な方法を自ら考えるようになり、モチベーションも向上します。
ゴールを設定した際には、部下が達成しやすいように指示を出しましょう。ただし、指示の内容は明確にする必要があります。
分かりやすく、明確な指示であれば、しっかりとゴールに向かって努力できますが、あいまいな指示だと、どのように仕事を進めれば良いのか分からず、部下を混乱させてしまうことも。
混乱してしまうとモチベーションを向上させることは難しくなるので、指示の出し方には注意が必要です。
8. 高めたモチベーションを保つためには?


モチベーションが向上した際には、部下と上司がお互いに支え合いましょう。支え合うことで片方のモチベーションが下がってしまうことを防ぐのです。
例えば、部下の1人が仕事で失敗して取引先に怒られてしまったとしましょう。その部下は「自分はこの仕事に向いていない」と考えてこんでしまい、モチベーションが下がってしまうかもしれません。そんなとき、上司が落ち込んでいる部下の悩みを聞くことで、モチベーションの低下を防げます。
「失敗というのは誰でもあることであり、その失敗によって成長できる」といったことを伝えましょう。部下は上司のアドバイス通り、モチベーションを下げることなく、次につなげるための努力をすることに注力します。
関連記事:従業員のモチベーションをアップさせるには?上がった後のフォローも解説
8-1. モチベーション管理に最適な関係性は?
部下と必要以上に親しくなるのは避けたほうがいいでしょう。その理由は、部下への同情的な意識がモチベーション管理をおこなう上では、障害となるからです。
例えば、部下への同情的意識が高いと、ムチを与えることが可哀想だと思って甘い処分しかしなかったり、他の部下よりも過度にいい評価をつけるといった偏りのあるアメを与えてしまいます。
このようなことから、お互いに支え合いながらも仕事を進めていける関係が、モチベーション管理に最適な関係性といえます。
そもそも現状のモチベーションがどうなのかがわからなくて困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」という資料を無料配布しています。本資料では、従業員の現在のコンディションを把握する方法はもちろん、調査結果をもとにどう改善していけば良いかまで具体的に解説しています。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
8-2. 「やりがい」だけではモチベーションは向上できない
モチベーションを向上するためにはやりがいだけで十分と思う方がいるかもしれませんが、その考えは誤っています。そもそもやりがいというのは、仕事をする中で生まれる充実感や達成感のこと。
その上やりがいは誰かに支持されて生まれるものではなく、本人の意識によって生まれます。例えば、ある部下に対して何かしらの仕事を渡すとしましょう。しかし、渡された部下にとって、その仕事は自分のスキルに見合っていないと思えるほど簡単な仕事でした。
そもそも仕事を依頼される時点でやりがいは生まれにくいですが、その上簡単すぎる仕事であるならば、達成感も感じないでしょう。これでは、モチベーションを高めることはできません。
もしモチベーションを高めるのであれば、重要性を説明した上で仕事を依頼しましょう。
「この仕事は簡単かもしれないが、会社にとって非常に重要なものであり、ミスが許されないものでもある」と説明をしてから仕事を部下に渡せば、部下は「ミスしないように達成しなければいけない」という緊張感を持ちます。緊張感を持つことで仕事への意識が高くなり、同時にモチベーションも上がります。
9. モチベーション管理を成功させて従業員の生産性を向上させよう


モチベーション管理は、基礎知識をしっかりと持った上で、具体的な方法を理解しておこなわないと、うまくいきません。もし部下やチームメンバーのモチベーションを高く維持したいのであれば、この記事を参考にしてもらえると幸いです。
関連記事:従業員のモチベーションはコントロールできる?人事担当が行うべきサポートを解説
関連記事:モチベーションサーベイの導入手順や実施方法を解説
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。



人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
タレントマネジメントの関連記事
-


中途入社・中途採用者にはオンボーディングが必要!メリットや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2024.07.27更新日:2024.10.01
-


オンボーディングと従来型研修の違いとは?メリットや研修の流れを解説
人事・労務管理公開日:2024.07.27更新日:2024.10.01
-


新入社員(新卒)のオンボーディングとは?メリットや重要ポイント・成功事例を解説
人事・労務管理公開日:2024.07.27更新日:2024.10.01




















