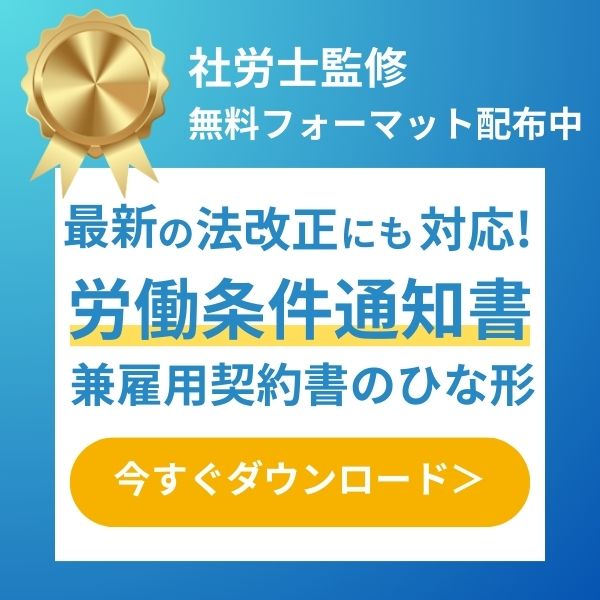試用期間は雇用契約書に記載すべき?書き方のポイントを紹介
更新日: 2025.8.7 公開日: 2022.9.22 jinjer Blog 編集部

会社によっては、本採用の前に「試用期間」を設けることがあります。
試用期間であっても本採用と同じように給料は発生し、残業代も支払わなくてはいけません。本採用後の待遇など多少の違いはありますが、業務も労働条件もほとんど変わらないというのが一般的な試用期間です。
そのため、試用期間は雇用契約書に記載しなくてもよいと思っている担当者の方もいるのではないでしょうか。
ここでは、試用期間を雇用契約書に記載すべきか、また雇用契約書に記載をするときのポイントや注意点などについて解説します。
関連記事:雇用契約書とは?法的要件や雇用形態別に作成時の注意点を解説!
目次
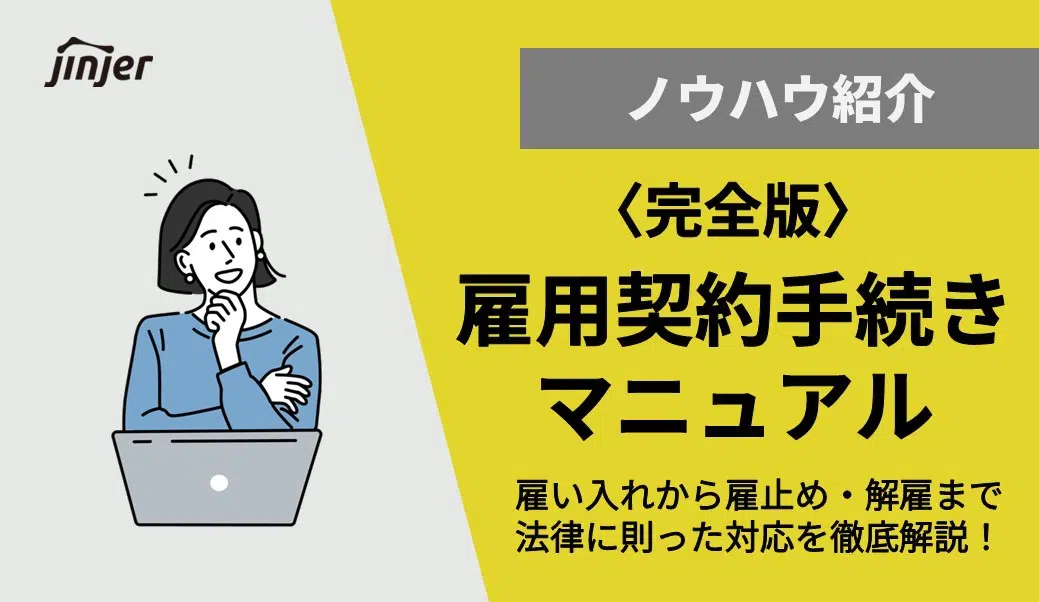
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 試用期間は雇用契約書に記載すべき?

試用期間を雇用契約書に記載するかどうかは、企業側が決めることができます。法律においても、記載を義務付けてはいません。
しかし、結論からいうと、義務でなくても雇用契約書には使用期間を記載するべきです。試用期間として勤務させた場合、従業員から「契約に書いていない」と言われる可能性があります。従業員が「試用期間がない」という認識であれば、トラブルになる可能性もあるのです。
雇用する際に、口頭で試用期間について説明をしているケースや、他の書類に試用期間について記載しているかもしれません。しかし、労働に関する内容は法的拘束力がある書類に記載しておくことが求められます。そのため、試用期間を設けて従業員を雇用するのであれば、雇用契約書に試用期間について記載をしておくのが望ましいのです。
なお、求人票については、職業安定法により試用期間の有無と内容の記載が義務付けられています。混同しないように注意しましょう。
1-1. 雇用契約書に記載をしなくてもいいケース
雇用契約書に記載をしなくてもいいケースというのは、「就業規則」に試用期間に関する項目がある場合です。
基本的に、試用期間は就業したタイミングから始まります。会社によっては、試用期間が始まるまでの間に就業規則を従業員に配布しているかもしれません。その就業規則に、試用期間について具体的な期間やルールなどが記載されていれば、雇用契約書に記載していなくても大丈夫です
しかし、ここで注意しなければいけないのは、従業員に周知しておく必要があるという点です。従業員に周知していないにも関わらず、就業規則に記載があるという理由で試用期間を設けることはできません。
就業規則には会社の重要な情報が記載されている場合もあるため、就業前の従業員に公開するのは抵抗があるという方もいるでしょう。
就業規則を配布したくないという場合は、雇用契約書に試用期間について記載しておきましょう。試用期間中のルールを記載すればいいだけなので、それほど手間がかかることではありません。
試用期間がいつまで続くのか、給料や手当の扱いはどうなるかなどを記載しましょう。
2.雇用契約書の記載項目

雇用契約書に試用期間の規定について記載する際、記載項目は企業が決めることができます。しかし、ここで項目に漏れがあると、従業員に正確な労働条件を周知することができないので、記載するべき項目をチェックしておきましょう。
| 記載項目 | 内容 |
| 試用期間の長さ |
使用期間に関しては、明確な規定がないので企業が設定できます。ただし、あまりにも長すぎると従業員を不安にさせてしまうので注意しましょう。 |
| 雇用形態 | 雇用形態は、原則として本採用でも試用期間でも変わりません。どのような雇用形態であっても試用期間を設けられるので、正社員なのかパート・アルバイトなのか雇用形態をしっかり明記しましょう。 |
| 本採用の条件 | 「試用期間」は本採用をすることが前提ですが、中には本採用に適さない人材がいるのも事実です。このような場合、トラブルにならないように本採用の条件を明記しておくことが重要になります。 |
| 給与・待遇 | 本採用と試用期間で、給与や待遇に差をつける場合は、必ず「試用期間中の給与・待遇」を明記しておきましょう。ただし、給与の減額率は20%まで、対象期間は6ヵ月という規定があるので、これに違反しないように設定してください。 |
| 社会保険 | 試用期間中であっても、社会保険加入要件を満たしている場合は、本人の意向に関係なく加入が必要です。しかし、このことを従業員が理解していないこともあるので、社会保険についても明記しておきましょう。 |
| 延長の有無 |
試用期間を延長する可能性がある場合は、雇用契約書に記載しておかなければなりません。記載していない場合は延長できないので注意してください。 また、延長の正当な理由も必要になるため、あらかじめ記載しておきましょう。 |
3. 試用期間を雇用契約書に記載するときのポイント

試用期間を雇用契約書に記載する際は、従業員とトラブルにならないようにするのがポイントです。雇用契約書とは契約の内容を書面で残すことで、お互いの認識の食い違いを防ぐために存在しています。つまり、試用期間が設けられているのならば、その内容について雇用契約書を見ればわかるようにしておかなくてはいけません。
雇用契約書に試用期間についての内容が記載されている場合でも、具体的な期間や給料については口頭で説明をしているという会社も存在します。しかし、それでは従業員との意見の食い違いが起こった際に、内容の根拠を説明することができません。
ここでは、記載するときのポイントを紹介します。
3-1. 本採用との給与や待遇の違いを明記する
試用期間中、本採用との給与や待遇に違いがある場合は、必ず明記しましょう。
基本的に、試用期間であっても雇用契約が結ばれるので大きな違いはないかもしれませんが、給与の減給や賞与がないという場合は明記しなければなりません。
他にも、本採用後に配置転換や日勤から夜勤など勤務時間の変更がある場合も、雇用契約書に明記しておくことで「聞いてない」などのトラブルを防ぐことができます。
3-2. 試用期間は適切に設定する
試用期間に関して、法的な決まりはないので、企業側が自由に決められます。しかし、あまりにも長いと従業員のモチベーションを削いでしまう可能性があるため、適切に設定しましょう。
業種によって異なるものの、3~6ヵ月を試用期間として設定する企業が多いようです。
ただし、業務が複雑だったりスキルが必要だったりする場合は、試用期間が長くなってしまうこともあるかもしれません。このような場合は、長期間になる理由を明記することで、従業員の納得が得やすくなるでしょう。
3-3. 延長の有無や本採用になる条件を明記する
試用期間を延長する可能性がある場合は、延長の有無を記載するだけでなく、延長する理由も提示しましょう。いつまでも「試用期間」では従業員の生活が安定しない上、不満の引き金になりかねません。誰がみても納得のいく延長理由を明記することが大切です。
また、本採用の条件も明記しておきましょう。試用期間中は、基本的に「解約権留保付労働契約」を締結します。
そのため、本採用に適さないと判断した場合は、企業は解約権を行使できます。しかし、この契約について理解していない従業員も多いので、スキルや勤務態度など本採用になる条件を記載しておくことも重要です。
4. 試用期間を雇用契約書に記載するときの注意点

試用期間を雇用契約書に記載する際は、試用期間中のルールについてわかるようにしておかなくてはいけません。しかし、試用期間が終わった後に、大きく業務形態が変わるような場合はそれについても明記しておくのが望ましいです。
記載していないと、従業員が納得していない状態で勤務形態や配属先が変わることになります。
ここでは、試用期間を雇用契約書に記載する際の項目の注意点を解説していきます。
4-1. 試用期間後に勤務形態に変更がある場合
例えば試用期間中は日勤として勤務をおこなうが、試用期間が終わったら三交代制度が始まるといった会社があります。その場合は、試用期間についてだけ記載するのではなく、終わったらどんな流れで業務が進んでいくのかについても記載しておいてください。
4-2. 試用期間後に配属先を決定する場合
また、使用期間中に適正を見て、配属先を決定するという会社もあるでしょう。その場合は配置変更が試用期間後に起こる可能性があることを明記しておくことをおすすめします。これらは絶対に記載しないといけないという訳ではありません。しかし、記載をしておいた方が従業員に対しては親切です。
試用期間の項目に関わらず、雇用契約書はそれを見ただけ従業員がどのような雇用内容なのか、どのようにして配属されるのかなどがわかるようにしておきましょう。
さらには、2024年4月より雇用契約の際に、明示すべき労働条件の内容が改正されています。正しい雇入れをおこなうためにも、改正内容は正しく理解しておく必要があるでしょう。 当サイトでは、従業員の雇入れ手続きのポイントから、関連する最新の法改正の内容までを解説したガイドブックを無料配布しています。
法律に則って雇用契約を結びたい人事労務担当の方は、ぜひこちらからダウンロードの上参考にしてください。
4-3. 試用期間中に給与を減額できる上限は20%
特に給料の減額が発生する場合は、しっかりと記載をしておきましょう。ただし、試用期間中に給与を減額できる上限は20%というのが、法律によって決められているので、それ以上の減額がないようにしてください。
減額についての記載がないと、従業員から「雇用契約書の通りに給料が支払われていない」とトラブルに発展してしまいます。万が一、裁判にまで発展した場合は、雇用契約書に減額について記載がないため会社側に責任があるとされる可能性が高くなるので注意しましょう。
減額だけでなく、試用期間と本採用後で何か違いがある場合は、全て記載しておくというのが雇用契約書においては重要になります。「細かすぎる」と感じる場合があるかもしれませんが、記載することでトラブルのリスクを避けられるので、可能な限り詳細に記載してください。
5. 試用期間を雇用契約書に記載しないリスク

試用期間を雇用契約書に記載しないリスクとして挙げられるのが、会社に対して従業員から不信感をもたれる点です。特に、試用期間の前後で給与や配置など労働条件が異なる場合は、従業員との間にトラブルが生じやすくなるでしょう。
説明して納得が得られなければ、従業員が辞めてしまうケースや、訴訟に発展するケースも否めません。こういったトラブルを回避する上でも、雇用契約書へ具体的に試用期間について明記し、従業員に内容について理解を促すことが重要です。
6. 試用期間は雇用契約書に明記してトラブルを回避しよう

試用期間を、雇用契約書に記載しなくてはいけないという義務はありません。しかし、就業規則を周知していない限りは、雇用契約書への記載なしで試用期間を実施することはできません。
そのため、試用期間を設けたいと考えているのならば、雇用契約書にその内容を記載しておく必要があります。雇用契約書は、あくまでも労働者とのトラブルを防ぐためのものです。
労働者から「想像しているよりも試用期間が長かった」「試用期間でも手当の支給があると思っていた」「使用期間中に給料の減額があるとは知らなかった」などと言われることがないようにしましょう。
また、雇用契約書には、試用期間以外にもトラブルを防ぐために詳細に記載をしなくてはならない箇所はたくさんあります。雇用契約の内容に間違いがあると、それだけで雇用後の紛争に発展しかねません
ミスなく作成をするためには、人事の労働環境を整える必要があります。そのためにおすすめなのは管理システムの導入です。管理システムを導入すれば、労務管理を効率よくおこなえるので、業務負担が軽減され書類作成のミスも回避できます。
人事の労働環境についてお悩みの方は、ぜひ管理システムの導入を検討してみてください。
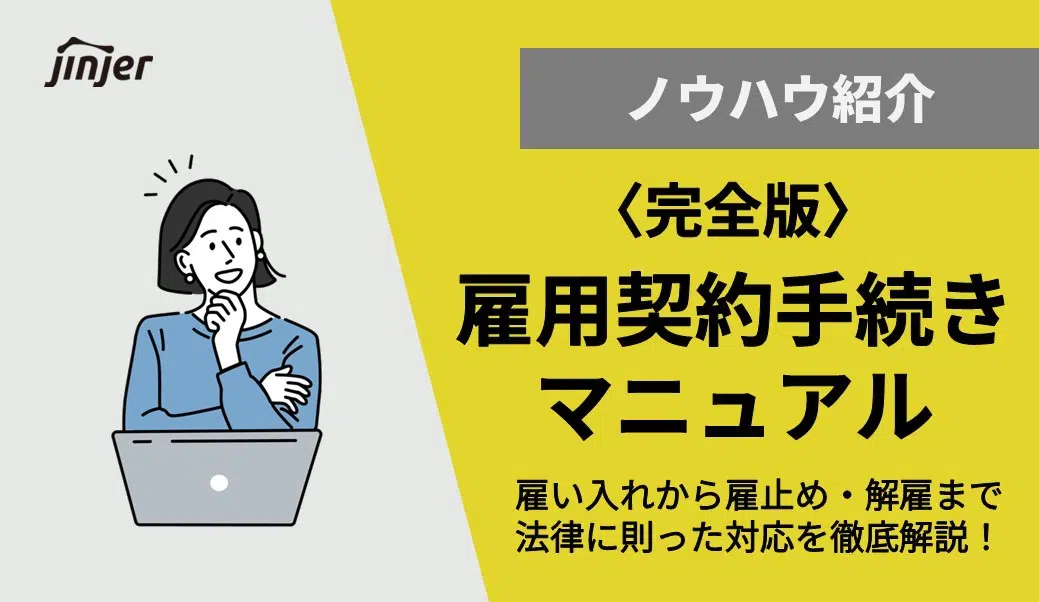
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
書き方の関連記事
-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説
人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24
-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介
人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24
-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26
雇用契約の関連記事
-

トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説
人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2025.06.11
-

労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.10.27
-

試用期間中の解雇は可能?解雇できる条件や必要な手続きを解説
人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2025.07.16