【企業担当者向け】所得税計算の仕組みとは?源泉徴収・年末調整のポイントを徹底解説
更新日: 2025.12.23 公開日: 2022.3.14 jinjer Blog 編集部

所得税計算は、経理を担当する方にとって必ず知っておくべき知識といえるでしょう。知識不足によって、万が一計算ミスが起きた場合は、加算税や延滞税などペナルティが課せられる場合もあるため注意が必要です。
所得税計算には給与や控除などが関係しているので、従業員ごとに異なります。また、従業員数が多い企業ほど担当者の方には負担がかかるため、計算間違いのリスクが高くなるのも事実です。
そこで、本記事では所得税計算の手順や効率良くおこなう方法などを解説するので、ミスなく計算するための参考にしてみてください。
関連記事:所得税とは?源泉所得税や定額減税など複雑な処理を詳しく解説
目次

「自社の給与計算の方法に不安がある」「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか心配」など、給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
資料では、労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れをわかりやすく解説しています。
間違えやすい給与の計算方法をおさらいしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 所得税とは?基礎知識をわかりやすく解説


所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課される国税のひとつです。ここでいう所得とは、単に収入の総額を指すのではなく、収入から必要経費や各種控除を差し引いた、実際に自由に使える金額に近い部分を意味します。
会社員の場合は給与所得、個人事業主の場合は事業所得、不動産の賃貸収入による不動産所得、さらに株式や投資信託の配当・譲渡益なども課税対象です。私たちの社会保障や教育、道路・公共施設の整備など、国のさまざまなサービスを支える財源となっています。
1-1. 所得税の仕組み(累進課税制度を採用)
所得税は「累進課税制度」を採用しています。これは、所得が高くなるにつれて税率も高くなる仕組みです。例えば、課税所得が195万円未満なら税率は「5%」、900万円以上になると「33%」、4,000万円以上になると「45%」といったように、所得の段階に応じて税率が上がっていきます。
この制度の目的は、所得の再分配によって社会の公平性を保つことにあります。高所得者にはより高い税率を適用し、多くの税負担を担ってもらう一方で、低所得者の負担を軽減することで、所得格差を緩和し、福祉や公共サービスの財源を確保する役割を果たしているのです。
関連記事:所得税における累進課税制度とは?基礎知識や税率、計算方法を解説
1-2. 所得税は自分で確定申告して納めるのが原則
所得税は、原則として納税者が自ら1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算し、税額を確定して納める「申告納税制度」に基づいて課されます。つまり、自分の収入や経費、各種控除を考慮して税額を算出し、申告・納付する仕組みです。
ただし、会社員の場合は少し異なります。給与所得者には、給与の支払い時に税金が自動的に差し引かれる「源泉徴収」がおこなわれ、年末には勤務先がその年の税額を再計算して過不足を調整する「年末調整」が実施されます。
そのため、一般的な会社員は自分で確定申告をおこなう必要がありません。一方、個人事業主や副業で収入を得ている人、不動産・株式の売却益がある人などは、自ら所得や経費を計算し、確定申告をおこなう必要があります。
関連記事:給与計算における所得税の計算方法とは?源泉徴収の仕組みも解説
1-3. 2037年まで適用される「復興特別所得税」と徴収額
復興特別所得税は、2011年に発生した東日本大震災への復興施策をおこなうための財源を確保する目的として、2011年に公布された特別措置法(平成23年法律第117号)に基づき創設されました。
これにより、所得税の納税者は2013年1月1日から2037年12月31日までに生じた所得について、復興特別所得税も合わせて納めなくてはいけません。
復興特別所得税額は、基準所得税額(基本的に税額控除適用後の所得税額)に2.1%を乗じた金額となります。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
会社員の場合は、企業の源泉徴収時に所得税と合わせて復興特別所得税も徴収しますが、個人事業主などは確定申告のときに所得税と一緒に納税する形となります。
1-4. 令和7年度税制改正のポイント
令和7年度税制改正により、2025年分の所得税計算から次の改正が適用されます。
- 基礎控除の引き上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除や給与所得控除の引き上げによって、所得が一定額以下の人は、これまでよりも課税されない範囲が広がります。特に給与所得者にとっては、所得控除額の引き上げにより、税負担の軽減が期待されます。
また、新たに設けられた特定親族特別控除により、従来の特定扶養控除の要件を満たさなくても、特定親族(居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の一定の親族)を扶養している場合、最大で63万円の控除を受けることが可能です。
さらに、扶養親族等の所得要件が緩和されたことで、配偶者控除や扶養控除など、これまで控除の対象外だった人も新たに適用される可能性が高まります。この見直しにより、中低所得層や子育て世帯を中心に、所得税の軽減効果が広がることが見込まれるでしょう。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
2. 所得税計算の全体の流れ


ここでは、所得税計算の大まかな流れを、実務的な観点も加えてわかりやすく整理します。なお、総合課税・分離課税の区分や損益通算、繰越控除など、一部複雑な制度は簡略化しています。
参考:所得税のしくみ|国税庁
2-1. 年間の収入を把握する
所得税の計算は、まず1年間(1月1日~12月31日)に得たすべての収入を確認することから始まります。収入の種類によって次の10種類に分類されており、それぞれ収入や必要経費の範囲、所得の計算方法が法律で定められています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
具体例として、企業から支払われる給与や賞与は「給与所得」、退職金は「退職所得」、生命保険の満期払戻金は「一時所得」、副業で得た原稿料は「雑所得(事業規模の場合は事業所得)」に分類されます。
また、所得税法では一定の収入が非課税とされています。例えば、給与所得者への通勤手当のうち法定限度額までの支給や、生活に通常必要な動産の譲渡による収入などは課税対象になりません。
2-2. 必要経費・給与所得控除を差し引いて「所得金額」を求める
収入が算出できたら、次に必要経費を差し引いて所得を計算します。所得の種類によって、どのように経費を計算し差し引くかが異なるので注意が必要です。
例えば、利子所得の場合、収入を得るために直接必要となった経費がないとみなされるので、必要経費の控除は認められません。そのため、課税対象となる所得額は、得た利子の金額そのものとなります。
給与所得の場合、給与を得るためにかかった実際の経費を一人ひとり正確に把握することは現実的に困難です。そこで税法上は、給与所得者の必要経費を概算した「給与所得控除」という制度が設けられており、収入からこの控除額を差し引くことで給与所得を算出します。
このように、所得の種類によって必要経費の取り扱い方は大きく異なり、利子所得のように控除が認められない場合もあれば、給与所得のように概算控除を用いる場合もあるという点を理解しておくことが重要です。
関連記事:給与所得控除とは?間違いやすい他の控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
2-3. 所得控除(基礎控除・扶養控除など)を差し引く
計算によって求められた所得金額からは、所得控除を差し引きます。所得控除が設けられている主な目的は、納税者それぞれの生活状況を考慮し、税負担の公平性を確保することです。所得控除には次の16種類があります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除
- 基礎控除
例えば、基礎控除は合計所得金額(一定の計算に基づき10種類の所得を合計した金額)が2,500万円以下のすべての人が適用できます。また、社会保険料控除は、給与から天引きされる健康保険料や年金保険料も対象となるため、多くの人が控除を受けられます。
このように、所得控除は個人の収入だけでなく、家族構成や支出状況などに応じて大きく異なります。適切に控除を活用すれば、税負担を軽減できるので、各控除の内容を理解しておくことが重要です。
関連記事:所得控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説
2-4. 課税所得金額を算出する
課税所得金額を算出する際には、基本的に、まず総所得金額(事業所得や給与所得など総合課税の対象となる所得を一定のもと合計した金額)、次に山林所得金額、さらに退職所得金額の順に所得控除を差し引いていきます。
例えば、総所得金額が100万円、退職所得金額が50万円、所得控除の合計額が120万円の場合を考えてみましょう。まず総所得金額から所得控除を差し引くと、所得控除後の総所得金額は0円となり、残りの所得控除額は20万円です。この残額20万円を退職所得金額から差し引くと、課税対象となる退職所得金額は30万円となります。
2-5. 税率をかけて所得税額を計算する
所得税は「累進課税制度」が採用されていますが、これは課税対象となる総合課税の所得の金額、退職所得の金額に対して適用されます。それぞれの課税所得金額に「所得税の速算表」(下記参照)にある所得税率を乗じてから、控除額を差し引いて所得税額を算出します。
【所得税速算表】
|
課税所得金額 |
所得税率 |
控除額 |
|
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
|
1,949,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
なお、山林所得は「5分5乗方式」が採用され、一時的な高額所得による税負担を軽減します。また、利子所得や配当所得、株式・土地等の譲渡所得の一部は分離課税とされ、原則として一定の税率(比例税率)で課税されます。
関連記事:所得税率は所得金額で変わる!税率改定の影響や注意すべきポイント
2-6. 税額控除を差し引く(住宅ローン控除など)
最後に、算出された所得税額から税額控除を差し引きます。税額控除には、次のような種類があります。
- 配当控除
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 外国税額控除 など
税額控除の上限は、基本的にその年分の所得税額までとなります。つまり、控除額が所得税額を上回った場合でも、超過分がそのまま還付されるわけではありません。ただし、控除しきれなかった分を住民税から控除できるケースもあります。
関連記事:【2025年分】年末調整の計算方法を5ステップで解説!計算例も紹介
3. 【具体例】所得税計算シミュレーション


ここでは、実際に所得税(令和7年分)を計算してみましょう。なお、配偶者控除(一般)の対象となる配偶者が1人、扶養控除(一般)の対象となる子が1人いるとします。また、1年間の社会保険料は100万円で、住宅ローン控除の控除額は10万円とします。
【ステップ1:年間の収入を把握する】
まずは年間の収入を把握することから始めます。今回の年収は次の条件とします。
- 給与所得の対象となる収入:700万円
- 雑所得の対象となる収入(公的年金等に該当しない):100万円
なお、山林所得や退職所得、その他分離課税となる所得(株式の配当など)は生じていないものとします。
【ステップ2:各種所得金額を求める】
次に各種所得金額(給与所得と雑所得)を求めます。なお、雑所得を得るための必要経費は40万円だったとします。
- 給与所得:520万円 = 700万円(収入金額) – 180万円(給与所得控除)
- 雑所得:60万円 = 100万円(収入金額) – 40万円(必要経費)
以上より、合計所得金額は580万円(= 給与所得:520万円 + 雑所得:60万円)と計算できます。なお、今回は繰越控除の適用がないものとし、総所得金額も580万円とします。
【ステップ3:所得控除の金額を求める】
今回適用できる所得控除は次の通りです。
- 基礎控除:63万円
- 配偶者控除(一般):38万円
- 扶養控除(一般):38万円
- 社会保険料控除:100万円(※その年支払った金額がすべて控除対象)
なお、基礎控除は、合計所得金額が580万円(489万円超655万円以下)なので、国税庁の「基礎控除額の計算表」に当てはめると、令和7年分の控除額は63万円となります。
また、配偶者控除は、納税者の合計所得金額が580万円(900万円以下)のため、一般の控除対象配偶者として最大である38万円の控除額を適用できます。
以上より、所得控除の合計額は239万円と計算できます。
【ステップ4:課税所得金額を算出する】
課税所得金額は、次のように総所得金額から所得控除の合計額を差し引くことで求められます。
- 課税所得金額:341万円 = 総所得金額:580万円 – 所得控除の合計額:239万円
【ステップ5:税率をかけて所得税額を計算する】
所得税額は、次のように対象となる税率をかけて求められます。今回は2-5章で紹介した速算表を使って求めるものとします。
- 所得税額:25万4,500円 = 課税所得金額:341万円 × 税率:20% – 控除額:42万7,500円
【ステップ6:税額控除を差し引く】
最後に、所得税額から税額控除の合計額(今回は住宅ローン控除のみ)を差し引き、実際に納付すべき所得税額を計算します。
実際に納付すべき所得税額:15万4,500円 = 所得税額:25万4,500円 – 税額控除の合計額:10万円
なお、この所得税額15万4,500円(基準所得税額)に2.1%を乗じた復興特別所得税も納付することになります。
3-1. 所得税が課税される年収・所得とは?
まず結論から述べると、2025年分以降は、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は年収160万円を超えると、また、個人事業主などの事業所得者は所得が95万円を超えると、所得税が発生する可能性があります。
所得税は「収入」そのものではなく「所得(所得控除を差し引いた後)」に対して課税されます。つまり、年収が高くても、必要経費や各種所得控除の適用によって、課税所得がなくなり、所得税がかからないこともあるのです。
具体的には、給与所得者の場合、「基礎控除:95万円」と「給与所得控除の最低保障額:65万円」の適用により、年収160万円以下であれば所得税は課税されません。
一方、個人事業主やフリーランスなどの事業所得者の場合、収入金額から必要経費を差し引いた「事業所得」が95万円以下であれば、基礎控除95万円の適用により、所得税は発生しません。
また、扶養親族等(一定の配偶者や子など)がいる場合や、社会保険料・生命保険料などの支払いがある場合には、追加の所得控除が受けられるので、これらの年収や所得の基準を超えていても、所得税がかからないこともある点に留意が必要です。
関連記事:所得税は年収いくらから?年収160万円を超える場合や年末調整・確定申告の義務も解説!
4. 企業担当者が押さえておきたい所得税計算のポイント


ここでは、企業担当者が知っておくべき所得税の計算や手続きのポイントを紹介します。給与計算や税務対応における基本知識として、必ず押さえておきましょう。
4-1. 給与や賞与からは源泉徴収が必要
企業は、従業員に給与や賞与を支払う際、所得税をあらかじめ差し引いて国に納める「源泉徴収」の義務があります。この制度により、従業員は給与支給時点で所得税が天引きされるため、年末にまとめて大きな税額を支払わなくて済むのです。
源泉徴収税額は、従業員の給与額だけでなく、社会保険料の金額や扶養親族の人数なども考慮して計算されます。源泉徴収税額表が計算には用いられ、従業員の個々の条件に応じて税額は異なります。
源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与や賞与の支払いがあった翌月の10日までです。ただし、従業員が常時10人未満の小規模事業者であれば、「納期の特例」を利用することで、半年ごとにまとめて年2回納付できます。
関連記事:給与計算における所得税の計算方法とは?源泉徴収の仕組みも解説
4-2. 企業は年末調整をおこなう義務がある
年末調整とは、1年間(1月1日~12月31日)に従業員から源泉徴収した所得税と、本来納めるべき所得税を精算する手続きです。源泉徴収税額は税額表を基に概算で算出されますが、給与の増減や扶養親族の変動などにより、本来徴収すべき税額は変わることがあります。
企業は、従業員の所得税を正確に精算するため、年末調整を必ずおこなう必要があるのです。過不足がある場合には、還付や追加徴収が実施されます。年末調整の終了後、1月31日までに源泉徴収票を従業員に交付するほか、税務署へ法定調書、市区町村へ給与支払報告書を提出する義務もあります。
関連記事:年末調整とは?【令和7年最新】確定申告との違いや必要書類、計算の流れをわかりやすく解説
4-3. 年末調整だけで対応できない場合は従業員自身による確定申告が必要
会社員やパート・アルバイトなど給与所得者は、原則として年末調整を受ければ確定申告は不要です。ただし、年間の給与収入が2,000万円を超えるなど、年末調整の対象外となる場合があります。
このような従業員は、源泉徴収で過不足が生じた分を精算するため、確定申告が必要です。
さらに、年末調整を受けていても、次のようなケースでは従業員自身で確定申告をおこなう必要があります。
- 医療費控除、寄附金控除、雑損控除を適用する場合
- 初年度の住宅ローン控除を適用する場合(2年目以降は年末調整で対応可能)
- 副業所得が20万円を超える場合
- 公的年金等の収入が400万円を超える場合 など
このように、給与所得者でも確定申告が必要となるケースは複数あります。必要な従業員には、申告期間や手続き方法について案内してあげましょう。
関連記事:年末調整の対象者とは?必要書類や確定申告との関係も解説
当サイトでは、ここまで解説してきた所得税の計算方法や注意すべき点をまとめた資料を無料で配布しております。住民税も併せて解説しているため、税金の計算に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
5. 企業担当者が所得税計算をする際によくあるミス


所得税の計算や処理に誤りがあると、企業・従業員ともにペナルティを受ける可能性があります。ここでは、企業担当者が所得税計算をおこなう際によく見られるミスと、その防止策について解説します。
5-1. 交通費や通勤手当を課税扱いとして処理する
所得税法では、すべての収入が課税対象になるわけではなく、一定の収入については非課税と定められています。非課税の収入を誤って課税対象として計算してしまうと、本来より多くの所得税を支払うことになり、従業員や企業にとって不利益となるおそれがあります。
例えば、交通費は業務遂行に必要な費用であり、従業員が立て替えた経費の返金(実費弁償)という性質を持つため、原則として非課税です。また、通勤手当も非課税の対象となりますが、1ヵ月あたり15万円までが上限であり、これを超える金額は課税対象に含まれます。
このように、非課税収入の範囲や上限を正確に理解したうえで所得税を計算することで、計算ミスや過大な税額の発生を防止できます。企業担当者は、給与計算や年末調整をおこなう際に、課税と非課税を正しく区別して確認することが不可欠です。
関連記事:年末調整で通勤手当や交通費は給与に含まれる?非課税限度額や処理方法を解説
5-2. 退職金(退職所得)の処理を間違える
給与や賞与だけでなく、退職金にも所得税が課されます。ただし、退職金は「給与所得」ではなく「退職所得」に分類されます。退職所得には、税負担を軽減する「分離課税」や「退職所得控除」といった制度があり、給与所得と同じ方法で課税すると、退職者に過大な税額が課される可能性があるのです。
まずは、どの収入が退職所得に該当するかを正確に理解することが重要です。そのうえで、退職所得の計算方法も正しく把握しておく必要があります。企業は退職金に対しても源泉徴収をおこなう義務があるため、退職区分や勤続年数、さらに「退職所得の受給に関する申告書」の提出状況を確認し、正しい所得税額を源泉徴収するよう注意しましょう。
関連記事:退職金にかかる税金は?計算方法や退職金控除についても解説
5-3. 申告書の記載・提出漏れにより計算誤りが起きる
扶養控除等申告書や保険料控除申告書など、源泉徴収や年末調整に必要な書類は、正確な所得税計算の基礎となります。そのため、記入や提出に不備があると、控除が正しく反映されず、従業員の所得税計算に誤差が生じるおそれがあります。
特に、扶養親族の人数や状況に変動があった場合は、最新の情報に基づいた扶養控除等申告書を再提出してもらうことが不可欠です。これを怠ると、源泉徴収の計算に誤りが生じ、税額の過不足が発生する原因となります。
さらに、税務署からの指摘により計算のやり直しが必要になったり、納付不足が発生したりした場合には不納付加算税や延滞税が課されるリスクもあります。このような事態は、企業にとっても従業員にとっても負担となるので、未然に防ぐことが重要です。
そのため、企業は従業員に書類の正しい記入方法を周知することが有効です。具体的には、記入例を配布し、提出期限のリマインドを複数回おこなうことで、提出漏れや記載ミスを防止できます。また、提出状況を確認し、不備があれば速やかに修正を依頼する体制を整えることも重要です。
関連記事:【2025年版】年末調整の書類の書き方とは?提出や保管のポイントも解説
5-4. 前職分の給与を含めず年末調整をおこなう
年の途中で転職した従業員は、前職の給与所得の源泉徴収票(※退職所得の源泉徴収票は不要)を提出してもらい、前職分も含めて年末調整をおこなうのが一般的です。
もし前職の情報を反映せずに年末調整をおこなうと、正しい所得税額が計算されません。この場合は、前職と現職の源泉徴収票をもとに、従業員自身が確定申告をおこなう必要があります。
なお、前提として給与を2ヵ所以上から受け取っており、かつその全額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入額と、給与所得・退職所得を除くその他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。
また、給与所得の合計額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除いた所得控除の合計を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合も、確定申告をおこなう必要はありません。
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
関連記事:年末調整を2箇所でしてしまったら?ダブルワークの注意点と正しい対処方法を解説
5-5. 非居住者の処理を間違える
海外赴任者や外国人従業員など、非居住者の所得税の取り扱いは、居住者とは異なります。居住者と同じ計算方法や源泉徴収方法で処理すると、課税誤りが発生する可能性があります。
例えば、海外赴任により非居住者となる場合、赴任期間に応じて課税区分は次のように変わります。
|
赴任期間の予定 |
所得税法上の区分 |
課税の対象所得 |
海外勤務(国外源泉)に対する給与等の源泉徴収 |
年末調整 |
|
1年未満 |
居住者 |
国内外の全所得 |
必要 |
必要 |
|
1年以上 |
非居住者 |
国内源泉所得のみ |
不要(※内国法人の役員報酬は必要) |
不要 |
ただし、居住者から非居住者になる年については、国内在住期間分の年末調整をおこなう必要があります。この際、扶養控除や配偶者控除は出国時点で控除対象となるかどうかを確認して反映します。
さらに、1年以上の海外赴任者であっても、日本国内で給与や賞与などの所得が発生する場合には、源泉徴収が必要となる場合もあるため注意が必要です。
参考:No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収|国税庁
関連記事:外国人社員の年末調整手続きは必要?注意すべき4つのこと
6. 所得税計算を効率良くおこなう方法
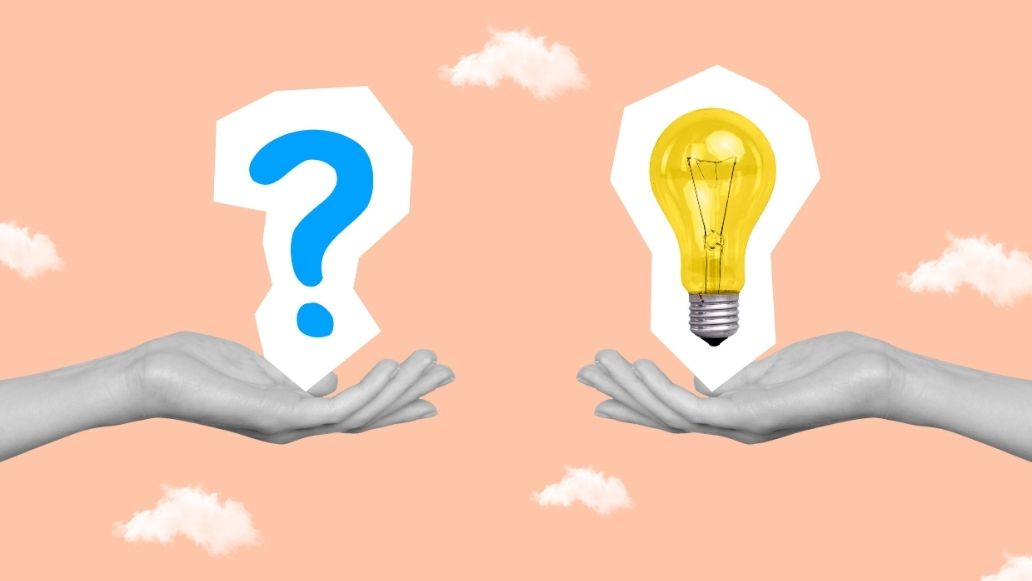
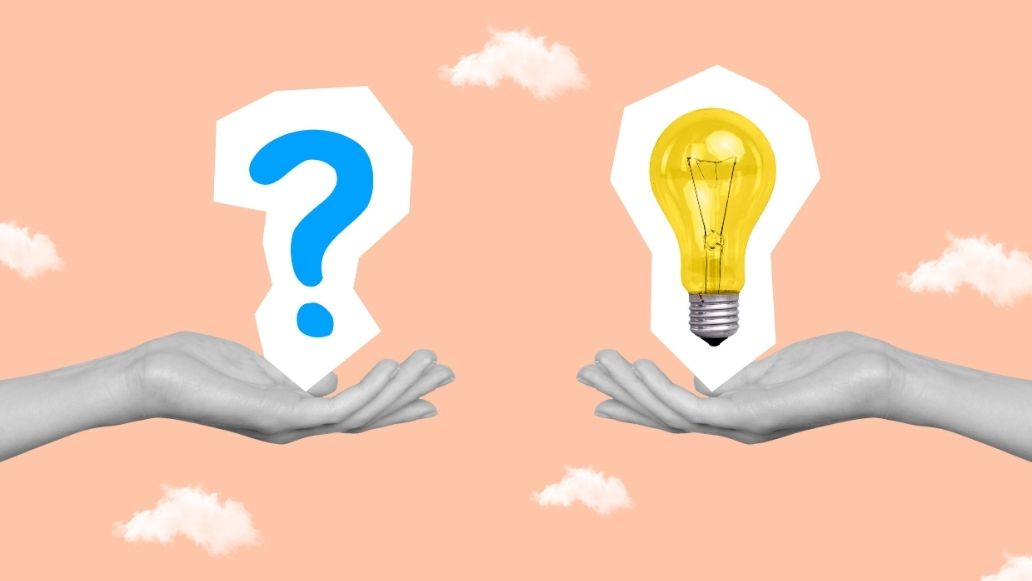
企業では、給与計算や年末調整の際に、所得税を正確かつ効率的に算出し、納付することが求められます。ここでは、所得税計算を効率的かつ正確に進めるための方法を紹介します。
6-1. 源泉徴収簿を活用する
源泉徴収簿とは、従業員ごとの給与や賞与の支給状況、社会保険料の控除額、所得税の源泉徴収額などを体系的に記録する帳簿です。法律上、作成自体は義務付けられていませんが、企業にとって有用な管理ツールとなります。
源泉徴収簿を整備すれば、従業員ごとの支給・控除情報を一元的に管理でき、月ごとの給与や賞与の確認が容易になります。また、控除額の算定ミスや重複控除を防止できるほか、税務調査や監査の際には、給与および控除内容を裏付ける重要な資料としても活用することも可能です。
参考:A2-2 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成|国税庁
関連記事:源泉徴収簿の作成方法・手順とは?必要性や注意点も解説
6-2. e-Taxを使用する
たとえ正確に所得税を計算できたとしても、システム上でのデータ入力ミスや、納付書への転記ミスが生じると、正しく納税できないおそれがあります。特に紙の納付書を利用する場合は、税務署や金融機関まで足を運んで手続きをおこなう必要があるため、時間や手間がかかるだけでなく、業務負担の増加や人的ミスのリスクも高まります。
一方で、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用すれば、インターネット経由で所得税の申告から納付までを一括でおこなうことが可能です。これにより、紙の納付書を作成・持参する手間がなくなり、手続きの迅速化や効率化が期待できます。さらに、給与計算ソフトとe-Taxを連携させれば、計算結果をそのまま電子申告用データとして出力できるため、入力や転記の手間を大幅に削減でき、人的ミスの防止にも大きく寄与します。
関連記事:所得税の納付方法は?納税方法の種類やおすすめの選び方・納付期限を解説
6-3. 給与計算システムを活用する
給与計算システムを導入すると、従業員ごとの給与や賞与の計算だけでなく、社会保険料や各種税金の計算も自動化できます。これにより、従来手作業でおこなっていた所得税の計算や控除額の確認などの煩雑な業務を大幅に効率化でき、計算ミスや人的ミスのリスクも減らせます。
さらに、年末調整機能を備えたシステムであれば、毎月の源泉所得税の計算から年末調整まで一貫して処理でき、従業員ごとの過不足税額の精算もスムーズです。クラウド型の給与計算システムなら、税制改正も自動で反映され、常に最新の制度に基づく計算が可能です。
初期費用や運用コストはかかりますが、給与計算だけでなく年末調整など関連業務全体の効率化が図れるため、長期的にはコスト削減や業務品質向上につながります。
7. 所得税の計算方法を正しく知り効率良く業務を進めよう


所得税の計算は、所得の種類が多岐にわたり、さらに扶養控除や社会保険料控除など各種控除の適用も必要となるため、どうしても複雑になりがちです。加えて、2037年までは復興特別所得税も併せて計算・納付する必要があり、少しの不注意が誤った税額での納税につながるおそれがあります。
もし計算ミスや控除の適用漏れが発生した場合は、再計算や確定申告による修正対応が必要となり、企業や従業員に余分な手間や負担が生じる可能性もあります。特に従業員数が多い企業では、手作業での計算は時間と労力がかかるうえ、ヒューマンエラーのリスクも高まります。そのため、正確かつ効率的に所得税を算出するためには、給与計算ソフトの導入が非常に有効です。



「自社の給与計算の方法に不安がある」「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか心配」など、給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
資料では、労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れをわかりやすく解説しています。
間違えやすい給与の計算方法をおさらいしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
所得税の関連記事
-


所得税の累進課税制度とは?年収別の計算事例や税負担軽減のポイントを紹介
勤怠・給与計算公開日:2022.04.18更新日:2025.12.19
-


所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.27更新日:2025.05.20
-


所得税率の種類一覧|給与や賞与の所得税の計算方法も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.24更新日:2025.12.19





















