給与計算業務に資格は必要?代行する場合の資格の必要性についても詳しく解説
更新日: 2025.2.7 公開日: 2020.12.14 jinjer Blog 編集部
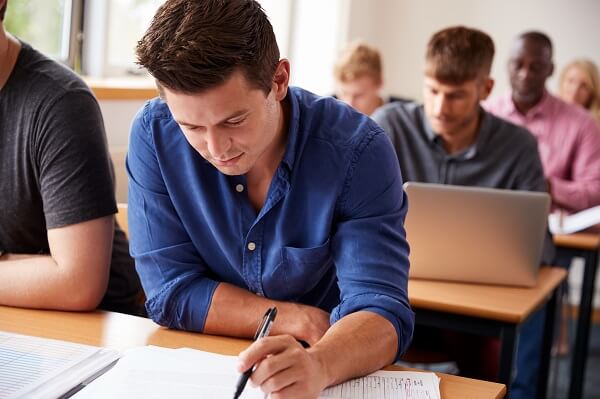
計算の複雑さや難しさ、経験や専門知識を要する給与計算は、毎月発生するもので負担も大きい業務です。そのため、「即戦力となる人材が欲しい」「代行に依頼したい」という担当者もいるかもしれません。
給与計算業務は、誰でもできる作業ではありませんが、資格があれば即戦力となってくれる可能性がありますし、代行してもらえるのであれば多いに助かるでしょう。しかし、実際のところ給与計算業務に関する資格があるのか、また代行の場合は資格が必要なのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
ここでは、給与計算業務に資格は必要なのか、給与計算の基本的な業務内容や無理なく業務負担を軽減する方法などを解説します。
【給与計算のやり方について解説はコチラ▶【図解】給与計算ガイド!例を用いて給与計算のやり方を徹底解説!】
【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】
目次

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 給与計算業務に資格は必要ない

税金や社会保険など、多くの知識が必要とされる給与計算ですが、特別な資格がなくても業務を遂行することはできます。
そのため自社で内製化し、人事担当者が給与計算業務をおこなうという企業もあるでしょう。正しい知識さえあれば、給与計算システムを利用することで、誰でもミスのない給与計算業務が可能になります。
一方で、給与計算業務を税理士事務所や社会保険労務士事務所、場合によっては給与計算の代行としてアウトソーシング事業者が請け負っている例も多く見られます。
正確な給与計算業務のためには、関係法令(労働関係・社会保険等)の様々な変更に関する情報について常にアンテナを張り、最新の知識を取り入れ続ける必要があるため、システムやアウトソーシングを用いて効率化を図る企業が多くなるのかもしれません。
2. 給与計算業務代行を依頼する場合は資格を持っている事業者が良い?


結論からいうと、給与計算業務代行を依頼するアウトソーシング事業者は、資格を持っている方が望ましいといえます。
給与計算を代行してもらう目的は会社によって異なりますが、正確な計算をおこなってもらうことを目的としているのが一般的です。つまり、正確性が重要になるため、専門的知識を持っていることや実績が選ぶ基準となります。
専門知識を持っているかを正確に判断するには、「資格を持っていること」が1つの目安になるので、代行を依頼する場合は資格の有無は大事なポイントといえるでしょう。
ただし、アウトソーシングする際には従業員の勤怠管理データや給与情報を渡すことにもなるので、情報管理の安全性も重視しなければなりません。
そのため、資格を持っているとしても、実績がなかったり個人情報の取扱についての説明がなかったりするようなアウトソーシング事業者には注意が必要です。
3. 給与計算実務能力検定とは?


給与計算業務における資格には、「給与計算実務能力検定試験」があります。
「給与計算実務能力検定試験」は、内閣府認可の一般財団法人職業技能振興会が認定する資格で、企業や組織に不可欠な給与計算業務についてその知識や遂行能力を判定し、実務能力への確かな評価を与える検定試験です。
給与計算業務には社会保険の仕組みや労働法令、所得税・住民税等の税法などに関する幅広い正確な知識が必要不可欠になるので、試験では管理部門で求められる給与計算業務に対する知識や実務遂行力を測ります。
基本的に給与計算業務の遂行に資格は不要ですが、労務リスクや税務リスクなどが身近にあるため、バックオフィス業務の中でも特に重要な役割を担っています。そのため、有資格者の方が企業としても安心して仕事を任せることができるでしょう。
4. 給与計算の基本的な業務内容


給与計算業務を任せるという企業も多いでしょう。また、現時点でアウトソーシング事業者に依頼していても、今後は自社の担当者に任せることを検討しているかもしれません。
ただし、経理担当者に任せるのであれば、給与計算にどのような業務があるのかを把握しておく必要があります。
①労働時間の集計
②時間外手当の計算
③その他手当の計算
④総支給額の計算
⑤雇用保険料の計算
⑥健康保険料の計算
⑦厚生年金保険料の計算
⑧住民税の計算
⑨源泉所得税の計算
⑩その他控除の計算
⑪差引支給額の計算
上記の通り11点もありますが、これらは給与計算の基本的な業務になるので覚えておきましょう。
各業務が具体的にどのような内容であるかについては、関連記事にまとめてありますので、自社で給与計算業務をおこなう予定の企業は確認しておくことをおすすめします。
関連記事:給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、楽にこなす方法を徹底解説
5. 給与計算をミスなく楽にこなす方法


ここまで、給与計算業務について、重要な役割である点や業務が複雑であることを解説してきました。
所得税や社会保険料の計算ミスをしたり、従業員に支払った賃金に過不足が発生してしまうなど、ただでさえ時間のかかる業務であるのに、ヒューマンエラーによってさらに業務が増えてしまい苦労した経験のある方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本章では、給与計算のミスを減らすことができたり、効率化させられる方法を2点ご紹介します。
5-1. 社労士や税理士などのアウトソーシング
給与計算の効率化において、社労士や税理士などのアウトソーシングを取り入れている企業は増加傾向にあります。
給与計算をアウトソーシングに委託すると、手間をかけずに正確な給与計算をおこなうことが可能です。その一方で、自社に給与計算のノウハウが蓄積されない、セキュリティに不安が残るなど、いくつかのデメリットもあることを認識しておく必要があります。
それでも給与計算を委託したいという場合は、実績の有無やセキュリティ体制をチェックし、安心して任せられる業者を選ぶようにしましょう。
5-2. 勤怠給与システムや給与計算システムの導入
勤怠管理システムと給与計算システムの連携をおこなうことで、普段手打ち入力が必要だった作業を大幅に減らすことが可能です。ただし、給与計算システムを使うためには勤怠データが必要なので、同時に導入することがおすすめです。
導入費用やランニングコストはかかりますが、人が手作業でやると起こりやすかった計算ミスなどのヒューマンエラーも、システムを導入れば軽減することができます。
どうしても給与計算のミスが減らない、業務が多すぎて給与計算が追いつかないなどの問題がある場合は、金耐久よや給与計算のシステム導入を積極的に検討しましょう。
6. 給与計算業務に資格は不要!システムやアウトソースの導入がおすすめ

今回は、給与計算業務に資格は不要であることや実際にどのような資格があるのか、給与計算業務はどのようなものかを解説しました。
給与計算は、時間をかけて専門的におこなえば間違いは少なくなるものの、実際にはヒューマンエラーが起こりやすい業務ともいえます。
もしも、担当者に専門知識がない場合や業務負担が大きいようであれば、給与計算業務を手作業でせずに、システムの導入やアウトソーシングを検討してみましょう。
給与計算システムやアウトソーシングに関しては、以下の関連記事をご確認の上、自社に合う方法を取り入れてみることをおすすめします。
【給与計算を自動化するメリットやデメリット、方法はコチラ▶給与計算を自動化するメリット・デメリット、方法を紹介】
【給与計算をアウトソーシングする際のポイントや費用相場はコチラ▶給与計算のアウトソーシング・代行のメリット・デメリットと相場をご紹介】



労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


人件費削減の方法とは?具体的な方法や失敗しないためのポイント
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28





















