従業員がタイムカードを押し忘れる理由で意外と多い7つのポイント
更新日: 2025.10.7 公開日: 2020.1.29 jinjer Blog 編集部

タイムカードを押し忘れる従業員が多く、注意してもなかなか改善しないことにお悩みの企業が少なくありません。タイムカードの押し忘れが頻発すると、給与計算作業が滞るため、人事担当者や総務担当者の負担が増大します。また、従業員の労働時間を正確に把握できず、労務管理にも支障が出てしまいます。
実は、タイムカードの押し忘れには多くの事業場で共通する原因があります。打刻漏れが起きる理由を知れば、会社として効果的な対策を打ち出すことが可能です。従業員のタイムカード押し忘れにお悩みの企業の方は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
目次
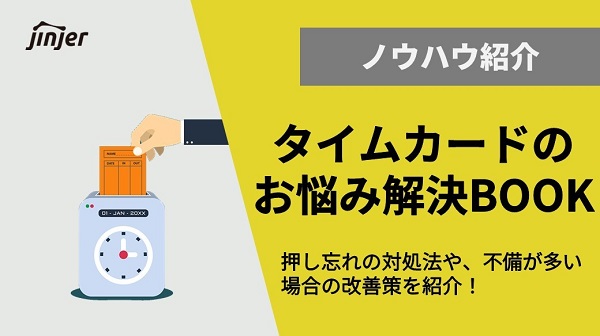
毎月の恒例となっている、タイムカードの押し忘れや不備の対応。その場しのぎの確認・修正作業で済ませていませんか?
実はその対応、コンプライアンス違反と隣り合わせかもしれません。
従業員を守り、会社の信頼を維持するためにも、日々の業務効率化と法令を遵守した管理体制の両立が求められます。
◆この資料でわかること
- 法律で定められた正しい「労働時間の管理・記録義務」とは
- ついやりがち?「減給」や「欠勤扱い」に関する法的な注意点
- 押し忘れや府不備を根本から減らすための環境・ルールの設定方法
コンプライアンスを遵守した勤怠管理を行いたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 従業員のタイムカードの押し忘れで多い理由7選

普段からタイムカードを押すよう意識付けをしていても、どうしても打刻漏れや押し忘れは発生します。ここでは、従業員がタイムカードを押し忘れてしまう理由の中で、意外と見逃しがちなものを7つピックアップしました。
1-1. 入退室時にタイムカード打刻機が視界に入らない
タイムカードの押し忘れが起きやすい理由の1つとして、入室時にタイムカードの打刻機が視界に入らないことが挙げられます。事務用品の山に埋もれていたり、目の前に遮蔽物が置かれていたり、タイムレコーダーが目立たなくなっている企業が少なくありません。
普段はタイムカードをきちんと押している従業員でも、始業前の準備に追われて、タイムレコーダーのことが頭から抜け落ちてしまうことがあります。そうしたケースでも、タイムレコーダーを一目見れば打刻のことを思い出せます。しかし、タイムレコーダーが目に入らない状態になっていると、1度抜け落ちた行動はそのままになってしまいます。
1-2. タイムカード打刻機の近くによく使う設備がある
意外と見落としがちなのが、トイレや休憩室の近くにタイムレコーダーが置かれている場合です。たしかに目につきやすく、従業員の導線と重なっていますが、思わぬ打刻漏れの原因となることがあります。
従業員がタイムカードを打刻する前にトイレや休憩室を利用し、そのまま打刻をし忘れてしまうケースが考えられるからです。タイムレコーダーを視界に入りやすい場所に置くことは大切ですが、周囲に押し忘れの原因になるものがないか確認しましょう。
1-3. 始業前から仕事脳になる熱心な従業員が多い
タイムカードの打刻し忘れが起きやすいのは、「始業前」の時間帯です。始業前はその日の仕事の準備で忙しく、タイムカードの打刻のことが頭から抜け落ちてしまいがちです。人間の脳のワーキングメモリの容量はそれほど大きくなく、新しい情報が入ってくると、すぐに古い情報を忘れてしまいます。
もちろん仕事熱心なのはよいことですが、仕事に熱中しすぎるあまり、他のことが疎かになっている従業員がいないか注意しましょう。
1-4. タイムカードを押す習慣が定着していない
新入社員または若いアルバイトやパート従業員は、タイムカードを押す習慣が身についていません。そのため、仕事の準備や周囲への挨拶に意識が奪われ、タイムカードのことは頭から抜け落ちてしまうでしょう。
「出社したら打刻する」という流れが身についていない間は、どうしてもタイムカードの打刻漏れが発生しやすいです。
毎日欠かさずに打刻をすれば自然と習慣化できるため、若い従業員には注意喚起やチェックをおこない、出社と打刻をセットで覚えられるように誘導しましょう。
1-5. 打刻機が使いにくく手間がかかる
打刻機がある場所が出入り口から離れていたり、打刻機そのものが使いにくかったりする場合も、打刻を後回しにして忘れる原因になります。
よくあるのは打刻をするために何かを取り出す必要があったり、打刻の順番待ちが発生していたりして、手間や時間がかかるケースです。エクセルで打刻管理をしている場合は、自分で打ち込む面倒を嫌う人も少なくないでしょう。
事業規模や業種に合わせて、使いやすい打刻機や勤怠管理システムを導入することでスムーズな打刻ができ、打刻漏れも減らすことができます。
1-6. 始業時間が変動しやすい・直行直帰が多い
始業時間が変動しやすかったり、直行直帰が多かったりする業務環境では、タイムカードの押し忘れが増える傾向があります。特に、現場作業や配送など、出先での業務が多い場合にはオフィスでの打刻を頻繁に忘れてしまいがちです。従業員の出勤・退勤時間が一定でない場合、周囲の従業員同士で打刻の声掛けができず、打刻忘れが頻発することもあるでしょう。フレックスタイム制や裁量労働制を取り入れている企業は、特にこの問題が多く見られます。
また働き方として外回りの営業や出張に出る従業員も、訪問先から直行直帰するため、物理的に打刻が不可能となるケースが多いです。さらに、出退勤時に周囲に従業員がいないことが多く、その結果、打刻をつい忘れてしまうことがあります。ほかにも、リモートワークを採用している場合、打刻ルールが明確に定まっていないことから打刻漏れが発生するケースもあります。
1-7. 残業に追われているため退勤打刻を忘れてしまう
忙しい時期には残業が多くなり、従業員は疲れやストレスを感じることが増えます。その結果、タイムカードの打刻を忘れてしまうことがあります。
特に帰宅が遅くなると、他のことに気を取られてしまい、退勤時の打刻を後回しにしてしまうことが多いです。業務に追われていると、打刻をすることを忘れてしまう従業員が増えます。このような場合には、打刻をリマインドする仕組みの導入が効果的です。さらに、打刻忘れを防ぐために、そもそもの業務状況を見直し、業務の効率化や改善を検討することも重要です。
2. 従業員のタイムカードの押し忘れを防ぐ5つの対策

タイムカードの押し忘れには、さまざまな理由があります。そのため、個々の理由に応じて対策を講じることが必要です。中には、複数の理由が絡み合っているケースもあるため、その場合はいくつかの対策を組み合わせて対処していきましょう。
2-1. タイムレコーダーをわかりやすいところに置く
タイムカードの押し忘れがなかなか減らない場合は、タイムレコーダーの置き場所を見直してみましょう。従業員の導線を考えて、従業員用の通路や出入り口など、通勤・退勤時に必ず通る場所にタイムレコーダーを設置すると効果的です。
タイムレコーダーが目に入りやすくなり押し忘れを防止できるだけでなく、日頃から「出退勤=打刻」という意識付けをすることができます。
2-2. 従業員の動線上にポスターを掲示する
打刻漏れ防止のポスターを目立つところに掲示して、従業員にリマインドするのも効果的な方法の1つです。「出勤・退勤時はタイムカードを必ず打刻」「始業前にタイムカードの押し忘れがないか確認」といった内容を紙に書き、更衣室や休憩室、トイレなど従業員が立ち寄りやすい場所に掲示しておきましょう。
「トイレや休憩室を利用してから打刻しよう」と考える従業員がいた場合でも、張り紙やポスターを見れば、すぐにタイムカードのことを思い出せます。また、始業前の慌ただしい時間帯でも、目につくところにリマインダーがあれば安心です。
ただし、同じポスターを掲示しつづけると従業員が見慣れてしまい、注意喚起の効果が薄れてしまうため、定期的に新しいものを貼り出すことが大切です。
2-3. 打刻を確認する担当者を決める
タイムカードを押し忘れないようリマインドを徹底しても、とくに業務量が増加する繁忙期は、どうしても打刻漏れをする従業員が出てきます。万が一に備えて、タイムカードの打刻漏れをチェックする仕組みを作るのも効果的です。
部署やグループごとに日替わりで当番を決めて、始業前にタイムカードが打刻されているか確認してもらいましょう。タイムカードをチェックする側に回ることで、押し忘れに対する本人の意識も向上します。
さらに、定期的に打刻漏れの発生状況を集計し、どの部署や時間帯に打刻漏れが多いかを分析することも有効です。このデータを基に、特に打刻漏れが発生しやすい時間帯に対策を強化するなどの改善策を講じることができます。また、リマインダーだけでなく、周囲の同僚が意識的に声をかける文化を醸成することも助けになります。こうした取り組みによって、全体的な打刻漏れの削減が期待でき、勤怠管理の精度向上にもつながるでしょう。
2-4. タイムカードの押し忘れに対してペナルティを設ける
繰り返しタイムカードの押し忘れをする従業員に対しては、ペナルティを科すことも押し忘れ防止策として挙げられます。
しかし、罰金額を設定したり、欠勤扱いにしたりすることは労働基準法に違反する行為です。減給をする場合は、就業規則で定めた上で懲戒処分として取り扱う必要があります。
減給や罰金をするよりも前の段階として、始末書の提出や教育指導を受けることなどを定めておきましょう。打刻漏れの抑止力にもなり、タイムカードの重要性を改めて周知するきっかけにもなります。
2-5. 使いやすく分かりやすいシステム・アプリを導入する
打刻をする手間がかかる環境では、なかなか打刻漏れは改善しにくいです。従業員が自然と打刻する習慣を身に着けられるように、使いやすい打刻機の導入やスマートフォン・タブレットなどからも打刻できるシステムやアプリを検討しましょう。
重要なのは業種や従業員の人数、勤務形態などに合わせたシステムを導入することです。
当サイトでは、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、タイムカードでの管理との違い(集計作業の自動化や不正打刻の対策など)を解説した資料を無料で配布しております。システムの導入で打刻漏れの対応など、勤怠管理業務が楽になりそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
ここまで対策を5点説明してきましたが、実際に打刻漏れが起きた場合の対処法も理解しておく必要があります。以下の関連記事に、打刻漏れのリスクと対処法について解説していますので、この記事と併せてご確認ください。
3. 従業員のタイムカード押し忘れは勤怠管理システムの導入で解決!

タイムカードの押し忘れが多く、この問題を解決したい場合は、勤怠管理システムの導入がおすすめです。張り紙やポスターでリマインドしたり、担当者が打刻漏れをチェックしたりする方法も効果的ですが、勤怠管理システムなら打刻漏れを根本的に防げます。勤怠管理システムの導入には、次の2つのメリットがあります。
3-1. タイムカードの押し忘れを知らせるシステムがある
勤怠管理システムには、タイムカードの打刻漏れがないか自動で監視し、すぐにアラートを鳴らしてくれる機能があります。タイムカードの押し忘れがあれば、すばやく本人に知らせてくれるため、打刻漏れの効果的な防止策になるでしょう。アラートは管理者へ飛ばすこともできるため、慢性的に打刻漏れがある従業員を見つけ、口頭で注意するといった使い方も可能です。
また、人事担当者や総務担当者が打刻漏れの有無を調べたり、担当者を決めてタイムカードを一つひとつチェックしたりする必要がなく、自動で打刻漏れを見つけてくれるため手間も時間もかかりません。
従業員数が少なく人的リソースが限られている中小企業から、従業員数が数百人を越えて勤怠チェックに時間がかかってしまう大企業まで、幅広い企業が導入メリットを実感できます。
3-2. スマホやタブレットで手軽に打刻できる
外回りにすぐに出てしまう従業員が多い職場や、始業前後が慌ただしい職場は、打刻がしづらいとすぐに打刻漏れが発生します。
スマートフォンやタブレットと連携した勤怠管理システムなら、専用アプリにログインした後に1クリックするだけで勤怠管理が完了します。忙しい時間帯でも、打刻を忘れるリスクを下げられるでしょう。
また、仕事上のコミュニケーションにSlackやChatworkなどを活用している企業は、チャットアプリに対応した勤怠管理システムもおすすめです。チャットアプリ上から簡単にタイムカードを打刻できるため、仕事の準備前に打刻したり、業務連絡のついでに打刻したりと、なにかと忙しいビジネスパーソンでも手軽に勤怠管理ができます。勤怠管理システムで従業員の打刻の負担を軽減することで、忙しい始業前の時間でも押し忘れを防止できます。
4. タイムカードの押し忘れが起きる理由をふまえて効果的に対策しよう

今回は、タイムカードの打刻漏れが起きやすい理由と対処法を解説しました。従業員のタイムカードを押し忘れには、「入室時にタイムカード打刻機が視界に入らない」「タイムカード打刻機の近くによく使う設備がある」「始業前から仕事脳になる熱心な従業員が多い」「タイムカードを押す習慣が定着していない」「打刻機が使いにくく手間がかかる」など、7つの理由が挙げられます。
タイムレコーダーを従業員の導線上に配置し、従業員が立ち寄りやすい場所にポスターや張り紙を掲示することで、効果的にリマインドできます。
タイムカードの押し忘れを根本的に解決するには、勤怠管理システムの導入も選択肢です。打刻漏れを自動で検出してくれるばかりか、スマホやタブレットで手軽に勤怠管理できるため、朝の忙しい時間でも打刻の手間がかかりません。
タイムカードの押し忘れが起きやすい理由をふまえたうえで、効果的な打刻漏れ対策を選びましょう。
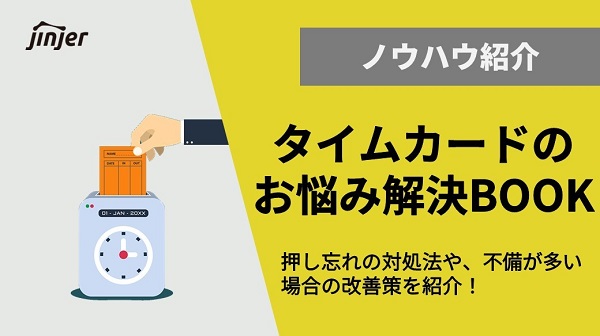
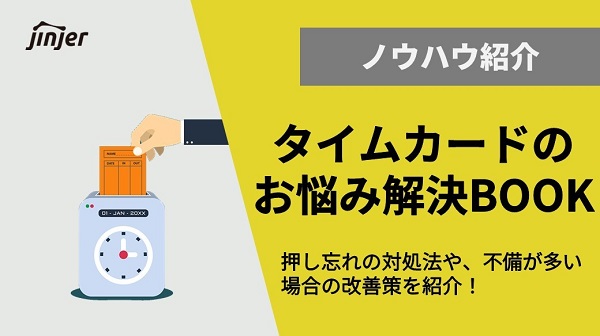
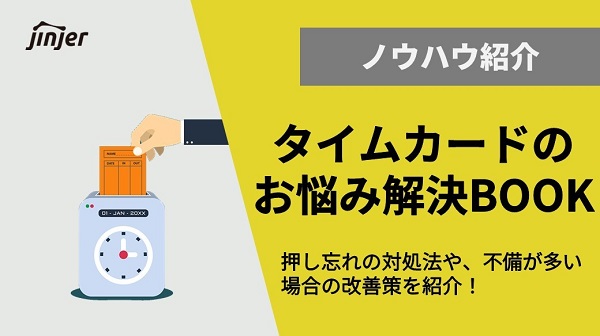
毎月の恒例となっている、タイムカードの押し忘れや不備の対応。その場しのぎの確認・修正作業で済ませていませんか?
実はその対応、コンプライアンス違反と隣り合わせかもしれません。
従業員を守り、会社の信頼を維持するためにも、日々の業務効率化と法令を遵守した管理体制の両立が求められます。
◆この資料でわかること
- 法律で定められた正しい「労働時間の管理・記録義務」とは
- ついやりがち?「減給」や「欠勤扱い」に関する法的な注意点
- 押し忘れや府不備を根本から減らすための環境・ルールの設定方法
コンプライアンスを遵守した勤怠管理を行いたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


人件費削減の方法とは?具体的な方法や失敗しないためのポイント
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
タイムカードの関連記事
-


タイムカードの電子化とは?システム導入のメリットや方法・注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2023.06.04更新日:2025.09.29
-


タイムカードを紛失した場合の対策とは?罰則や勤怠記録の残し方も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.06更新日:2025.01.31
-

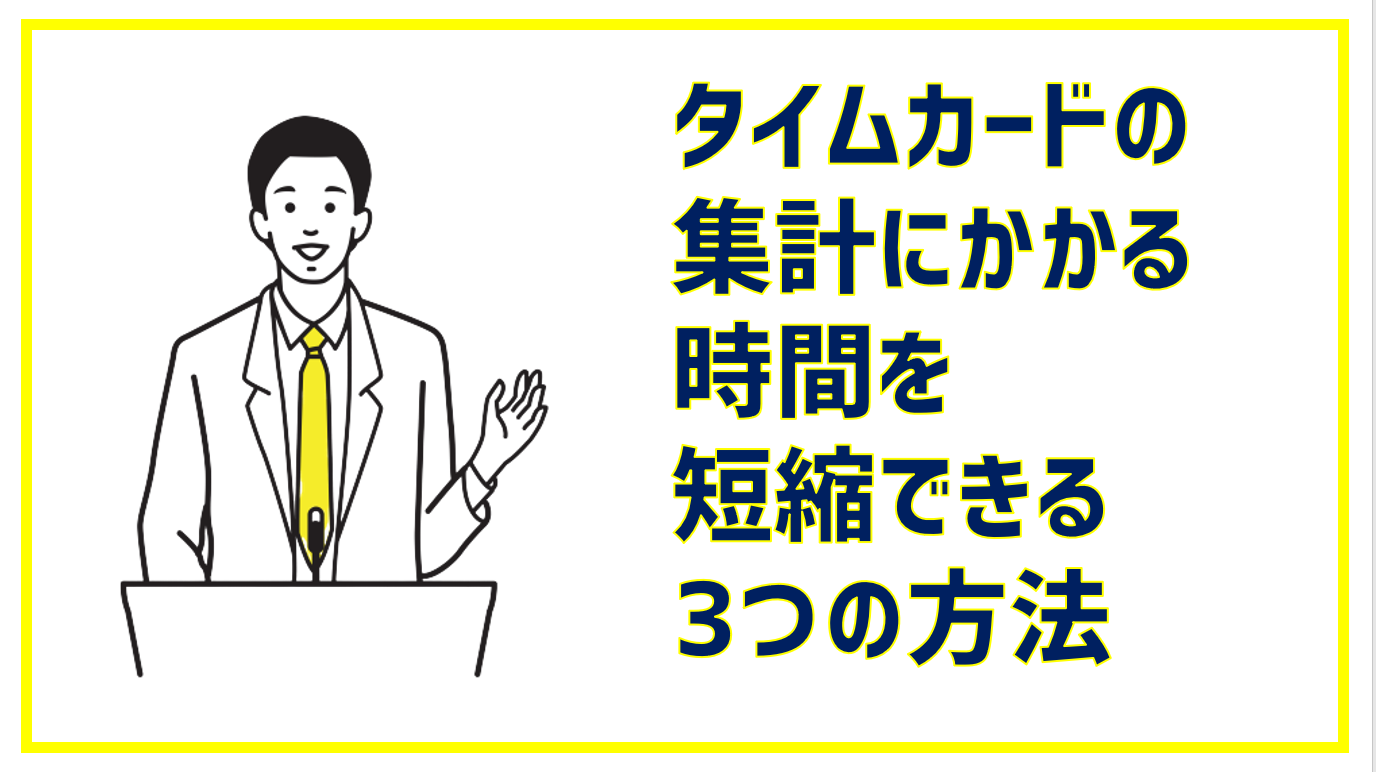
タイムカード集計にかかる時間を短縮できる3つの方法
勤怠・給与計算公開日:2020.03.04更新日:2025.02.07




















