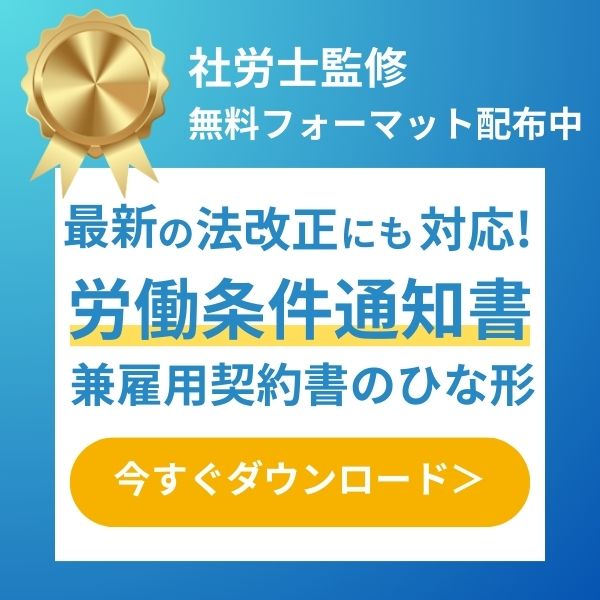雇用契約の更新とは?契約書の作り方や更新手続きの手順を解説
更新日: 2025.8.7 公開日: 2020.11.19 jinjer Blog 編集部

「雇用契約を更新したい従業員にどう対応すればいいのかわからない」「雇用契約の更新手続きをおこなう方法について詳しく知りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
有期労働契約については、契約更新をめぐる「雇止め」のトラブルが相次いで起こっているため、労働者に対して適切な対応をおこなうことが何よりも求められます。
本記事では、雇用契約の更新に関する手続きの手順をわかりやすく解説するとともに、「実は、雇用契約を更新したくない」と考えている労働者への対応や通知についてもまとめています。ぜひご活用ください。
有期雇用契約は労働基準法・労働契約法において様々なルールが設けられているため、法律に則って雇用契約を結ぶ必要がありますが、従業員とのトラブルになりやすい部分でもあります。
「法律に則って雇用契約を結ぶ方法を確認したい」「法的に正しい契約更新の対応を知りたい」という方に向け、当サイトでは「有期雇用契約の説明書」を無料で配布しております。
雇用契約の結び方から契約更新の方法、更新しない(雇止めをする)時の対応方法、無期転換ルールまで、有期雇用契約のルールを確認しておきたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
目次
1. 雇用契約の更新とは

雇用契約の更新とは、一般的には有期雇用契約をしている従業員との間に発生するものです。
有期雇用契約では、一定の期間ごとに「雇用を継続するか、終了するか」を決めることになります。その際に雇用を継続する場合に必要になるのが「雇用契約の更新」です。
雇用契約の更新をする際はこれまで通りの雇用契約内容を継続して期間のみを更新するケースと、契約内容を見直して労働条件などを変更するケースがあります。また、有期雇用契約から無期雇用契約に転換が起きることもあります。
どのような形で更新をするかによって手続きが異なるため、企業は適切に雇用契約の更新ができるように準備をしなければなりません。
なお、正社員は基本的には期間の定めがない無期雇用契約です。そのため、正社員や雇用期間を定めていないパートタイム・アルバイト従業員には雇用契約の更新は発生しません。
2. 雇用契約を更新する手順

有期雇用契約における契約期間が満了した労働者に対して雇用関係を継続する更新手続きをおこなう場合は、労使間の合意のもと、新たな雇用契約を結ぶ必要があります。
この契約更新の際は、たとえ同じ労働条件であったとしても、新たな雇用契約書や労働条件通知書を作成し、労働条件や契約期間、更新の有無、判断基準などを改めて明示しなければなりません。
労働条件が同じだからといって、新たな契約書を取り交わさずに自動更新を繰り返すと、実質期間を定めない契約だと判断されてしまうため、注意が必要です。
2-1. 雇用契約の期間のみを更新する場合
有期雇用契約は、契約期間が満了になった時点で契約が解消してしまうため、契約期間のみを延長する場合は新たに雇用契約書を書面で締結する手続きが必要です。
契約更新の面談は、雇い止めの可能性も考慮し、遅くとも契約期間満了の30日前には実施しましょう。
労働者側が契約更新を希望しない場合は、使用者が希望したとしても、雇用関係を継続することはできません。労働者に退職届、または更新を希望しない旨を書面にして提出してもらうようにしましょう。
2-2. 雇用契約の更新の際に労働条件を変更したい場合
雇用契約を更新する際に、労働者の労働条件を変更したいと考える場合もあるかと思います。このような場合は、労働者との合意を取ることで労働条件を変更することが可能です。
新たに雇用契約書や労働条件通知書を発行・交付する際に変更点を明示し、雇用契約書には署名・捺印してもらうことで、労使間のトラブルも回避できます。
企業側が一方的に労働者の不利になる条件で雇用契約を更新することはできません。必ず変更内容の確認と合意をおこない、その合意がなされたことを証明できるように書面を残しておきましょう。
関連記事:雇用契約の条件は途中変更できる?契約期間内に変更する方法をご紹介
2-3. 有期雇用契約から無期雇用契約への転換が起こる場合
有期雇用契約が反復更新されて通算5年を超えると、労働者には契約期間に定めのない無期雇用契約への転換を申込む権利が与えられます。
更新時に有期雇用契約から無期雇用契約に転換が可能な労働者には、その旨を伝えた上で雇用契約書を取り交わすようにしましょう。
労働者が無期雇用への転換を希望した場合、使用者は拒否することができません。
また、契約期間が5年以内であっても「実質的な無期雇用」や「労働者に雇用継続の期待をさせた」と判断された場合、労働契約法第19条が適用され、期間満了による雇い止めが難しくなってしまいます。
労働者には、あらかじめ契約更新の有無についても明確な基準を明示し、説明しておく必要があります。
なお、契約期間満了から次の有期雇用契約までに6ヵ月以上の空白期間がある場合は、クーリング期間として、以前の契約期間をカウントしません。
2-4. 正社員への転換が起こる場合
有期雇用契約期間中の働きぶりが認める形で、正社員への転換として契約を更新する場合もあるかと思います。
このような場合も、期間の定めのない雇用契約として、新たに雇用契約書を取り交わすようにしましょう。
正社員への転換は、場合によって助成金の支給対象となることもあるため、状況に応じて対応するようにしてください。
なお、前述した無期雇用契約と正社員への転換は、雇用期間の定めがなくなるという点においては同じです。しかし、無期雇用契約への転換は、あくまでも「雇用契約期間の制限がなくなるだけ」です。正社員になるわけではないため、有期雇用従業員の雇用形態を変更する場合は、間違いのないようにしましょう。
また、従業員も正社員への転換と無期雇用契約への転換を混同していることがあるため、給与や待遇にどのような違いがあるのか明確にしておくことが大切です。
関連記事:雇用契約書における契約社員からの正社員登用についての記載ポイント
2-5. 自動更新がおこなわれる場合
有期雇用契約に自動更新条項が定められている場合、契約更新時に特別な書面を取り交わす必要はありません。これは、契約更新拒絶の申し入れがない限り、従前の条件に基づいて自動的に契約が更新されることを意味します。
更新拒絶の通知は、契約期間の満了前におこなう必要があります。この通知がおこなわれない場合、自然に契約は更新される仕組みとなっています。
なお、自動更新がされる有期雇用契約者に対しても、期間満了をもって契約を終了することが可能です。
3. 労働更新契約書に記載する内容
 有期雇用契約者との間に取り交わした契約期間が満了し、引き続き働き続けてほしい場合には雇用契約書を更新することになります。
有期雇用契約者との間に取り交わした契約期間が満了し、引き続き働き続けてほしい場合には雇用契約書を更新することになります。
その際には、労働条件を改めて明示しなければなりません。この労働条件の明示は、原則として書面によっておこなわれるものだとされており「労働条件通知書」という形で交付します。
有期雇用契約者と雇用契約を更新する際は、以下の内容を明示する必要があります。
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 従事する業務の内容
- 始業、終業時刻
- 所定時間を超える労働の有無
- 休憩時間、休日、休暇
- 交代制勤務がある場合のルール
- 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
- 退職に関する事項
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込機会の明示
- 無期転換後の労働条件の明示
そのほか、会社に制度がある場合は退職手当や臨時の賃金や賞与などの制度についても明示が必要です。
関連記事:雇用契約の更新とは?契約書の作り方や更新手続きの手順を解説
4. 雇用契約を更新しない場合の対応・通知方法

有期雇用従業員の契約期間を更新せずに雇止めをする場合、条件を満たしている従業員に対しては、期間満了による契約終了の場合でも、労働基準法で雇止めの告知や雇止め理由の明示が必要であるとされています。雇止め告知が必要なケースについて知っておきましょう。
4-1. 雇止めの予告をする
労働者に対して、雇用契約を更新しない通知(雇止め)をしたい場合は、雇止め基準に則った手続きをしなければなりません。労働基準法14条で定められている基準であるため、これを守らない場合は労働基準監督署から指導を受ける可能性があります。
雇止め基準はすべての有期雇用従業員に適用されるものではなく、以下2つの要件をどちらも満たす場合に守る必要があります
- 有期雇用契約を3回以上更新している、または、雇い入れの日から起算して1年以上継続勤務している
- あらかじめ有期雇用契約を更新しない旨が明示されていない
この2つの条件を満たしている有期雇用従業員の雇止めをする場合は、雇止めの告知や雇止め理由の明示が必要です。
雇止めの告知は、少なくとも契約期間満了の30日前にすることが定められています。
参考:有期労働契約の雇止めについては、その基準が定められています|厚生労働省
4-2. 雇止め理由を明示する
雇止めに関する面談の結果、労働者側が雇止めを不服とした場合は、契約更新をしない理由についての証明書を請求されることがあります。
その場合は、使用者は遅延なく証明書を交付する義務がありますが、証明書に明示する雇止めの理由として、契約期間満了以外の理由を記載する必要があります。
雇止めの理由は、「客観的・合理的である」こと、「社会通念上の相当性」が求められますので、後述する「雇用契約の更新を判断する基準」を参考にあらかじめ設定しておき、いざなった際に適切な説明ができるように心掛けてください。
当サイトでは、改正労働契約法に沿って、「無期転換ルール」や「雇止め」について解説した資料を無料で配布しております。有期雇用契約社員の更新について不安な点がある方は、こちらから「有期雇用契約の説明書」という資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:雇用契約を更新しない場合の正当な理由と社員への伝え方
5. 雇用契約の更新を判断する基準

上記のように、労働者との雇用契約を更新しない場合、労働者からその理由を求められる場合があります。トラブルが起きないようにするためには、雇用契約を結ぶ前にあらかじめ「雇用契約の更新を判断する基準」を定めておくことが大事になります。
【雇用契約の更新に関する判断基準】
| ①契約期間満了時の業務量
②勤務成績や勤務態度 ③労働者の能力 ④会社の経営状況 ⑤担当業務の進捗状況 |
この判断基準は、雇用契約書または労働条件通知書、就業規則の中で労働者に明示・周知しておかなければなりません。また、契約締結後に更新の判断基準を変更した場合は、労働者に対して変更内容を速やかに周知しばければなりません。
雇用契約書の雇用期間や更新の判断基準が曖昧であり、雇用継続について労働者が期待を抱くような言動や雇用関係があった場合、契約期間満了による雇い止めが認められない場合があるため、注意してください。
6. 雇用契約を更新する際の注意点
 雇用契約を更新する際の注意点を3点ご紹介します。
雇用契約を更新する際の注意点を3点ご紹介します。
6-1. 雇用契約の期間は基本的に3年が上限
有期雇用契約の期間は、原則として3年が上限とされています。このため、3年を超える契約は無効となり、3年に修正されます。
例外として一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合や、高度な専門知識を持つ労働者との契約の場合は、契約期間の上限が緩和されることがあります。これは、特定の条件を満たす場合に適用されるため、注意が必要です。
6-2. 2024年4月以降、契約更新の際に明示すべき事項
2024年4月以降、有期雇用契約を更新する際には、使用者が労働者に対して、明示すべき事項を記載した労働条件通知書を交付する必要があります。
この通知書には、労働契約の期間や就業場所、業務内容、労働時間、休日、賃金についての詳細が含まれます。
加えて、有期雇用労働者には、契約更新の上限や無期転換の申込機会、無期転換後の条件も明示する必要があります。
2024年4月に施行された、労働条件通知書の明示事項について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項の例、2024年4月改正の明示ルールを解説
6-3. 無期転換ルールにより、自動的に無期雇用契約に転換される場合がある
無期転換ルールは、有期雇用労働者が一定期間雇用されると、無期雇用契約へ転換できる仕組みです。通算契約期間が5年を超えると、労働者は契約終了前に無期転換を申し込むことが可能で、その場合、自動的に契約が無期に移行します。
ただし、高度な専門性を持つ労働者や、定年後に雇用される場合は条件が異なることに注意が必要です。
7. 雇用契約の更新は労使間の合意のもとルールに則っておこなおう

雇用契約の更新を決定する際は、前もって客観的な判断基準を設け、労働者の理解を得ることが重要です。
雇い止めの際のトラブルを避けるためにも、判断基準については、雇用契約書や就業規則にて、できるだけ具体的に明示するべきでしょう。
また、更新手続きの際は、同じ待遇・条件での契約であっても、雇用契約書を新たに取り交わす必要があります。労働条件通知書も同様に、入社時だけでなく契約更新や変更の際も交付する必要があり、とても面倒に感じると思います。そんな手間だけど重要な業務も、電子化することで簡単に交付でき、工数の削減へとつながります。電子化が気になる方は以下の参考記事をご覧ください。
参考記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
有期雇用契約は労働基準法・労働契約法において様々なルールが設けられているため、法律に則って雇用契約を結ぶ必要がありますが、従業員とのトラブルになりやすい部分でもあります。
「法律に則って雇用契約を結ぶ方法を確認したい」「法的に正しい契約更新の対応を知りたい」という方に向け、当サイトでは「有期雇用契約の説明書」を無料で配布しております。
雇用契約の結び方から契約更新の方法、更新しない(雇止めをする)時の対応方法、無期転換ルールまで、有期雇用契約のルールを確認しておきたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
雇用契約の関連記事
-

トライアル雇用とは?導入のメリット・デメリットや助成金の申請手順を徹底解説
人事・労務管理公開日:2024.10.18更新日:2025.06.11
-

労働条件通知書はソフトを使って作成できる?選び方も解説
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.10.27
-

試用期間中の解雇は可能?解雇できる条件や必要な手続きを解説
人事・労務管理公開日:2022.09.22更新日:2025.07.16