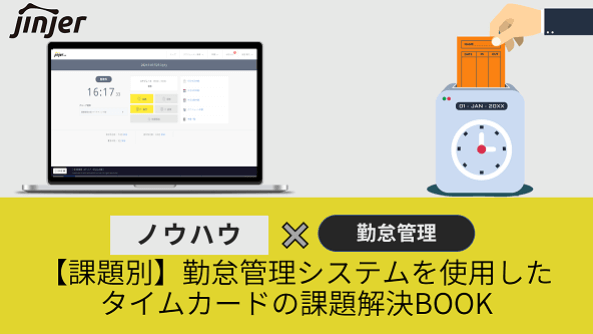タイムカード打刻のルールを就業規則で管理しよう!労働時間を正しく管理するポイントとは

企業は、社内のさまざまなルールを「就業規則」で管理しています。何かしらのトラブルにならないために、また実際にトラブルが生じた場合には、就業規則に沿って解決することになります。
最近では、タイムカードの打刻時間と労働時間のずれに関するトラブルが多いという背景もあり、そのようなトラブルにも対応できる就業規則の策定が必要になってきています。
本記事では、正しい労働時間を管理するための就業規則の作成方法についてご紹介します。
関連記事:最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 企業に合った就業規則を作成するポイント

企業と従業員のさまざまなトラブルが、今後の会社の存続に影響を与えないためにも予防対策をしておくことが必要になります。そのためには、会社を守るための「就業規則」の策定が必要です。ここからは就業規則を作る際に注意すべきポイントを解説します。
関連記事:タイムカードの打刻に関するルールを社内規定に加える理由とは?
1-1. 労働時間を明記する
労働基準法第32条によると法定労働時間は1日8時間、1週では40時間以内とされ、それを超えると割増報酬を支払う義務があります。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
例えば、就業規則に始業時間と終業時間の明記をし、従業員が遅刻した日に残業をした結果、法定労働時間を超えていなくても従業員に割増賃金を請求される可能性はあります。そのため就業規則には労働基準法の労働時間と合わせて実働時間の明記もしておき、その時間を超えた場合にだけ割増賃金が発生する、という基準を定めておきましょう。
さらに、タイムカードを使用して労働時間を管理する際には、従業員がタイムカードを適切に使用し、実際の労働時間を正確に打刻することが重要です。就業規則においては、タイムカードの打刻が勤務の開始と終了を示す参考記録であることを明確にし、実際の労働時間を管理する際の基準と位置付ける必要があります。
このようにすることで、労働者と使用者双方の認識のズレを減らし、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、タイムカードによる打刻漏れの対応策や、労働時間の自己管理がしやすくなるルールを設けることで、企業全体の労働管理の精度を向上させることが期待できます。
1-2. 時間外労働を申請制にする
時間外労働をおこなう場合は、所属長に申請をして許可を得ることを前提としておきましょう。従業員の勝手な判断に任せていると、残業代の把握もできなくなり、割増賃金が増大します。これは所定労働時間の質の低下にもつながります。
そのため、就業規則には残業の申請方法や承認プロセスを明確に記載し、労働者が遵守するべきルールを周知徹底することが重要です。また、労働時間の適切な管理を行うためには、タイムカードの正確な使用が求められます。これにより、本来の労働時間を正確に把握し、無駄な残業を減らすことができます。
労働時間を遵守することで、企業全体の生産性を向上させ、従業員のワークライフバランスの整備にもつながります。
1-3. 出勤以外は事前申請にする
遅刻や早退、欠勤は所属長に申請をおこなうことを義務付けしておきましょう。事前に申請できる早退や欠勤は申請を済ませて、承認もしくは許可が下りたものだけとします。企業が最終的に判断をするようにしておくべきです。就業規則に記載するということは、企業でのルールに定めるということにもなるので効果的といえます。
また、タイムカードに関するルールも明確にしておくことが重要です。具体的には、タイムカードが労働時間を記録する手段としての役割を持つことを明にし、適切に打刻を行うことを従業員に教育する必要があります。
加えて、もしタイムカードの打刻漏れや誤記入があった場合の処理方法も明記しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、労働時間の実態を正確に把握することができるようになります。
以下の記事では、就業規則に記載する以外の具体的なルールを紹介していますので、まずは今ある環境でできることを試したいという方はご覧ください。
▶タイムカードで打刻ミスをなくすために用意しておきたい打刻ルールの具体例
【関連記事】タイムカードの改ざんは違法!正しい対処法や対策をご紹介
2. 勤怠管理をタイムカード打刻で運用する際の問題点

企業が従業員の勤怠管理をおこなうことは義務であり、正しい労働時間を把握することが重要です。しかし、タイムカードで勤怠管理を運用している場合は、さまざまな問題が生じる可能性があります。
2-1. 打刻時間と労働時間のずれがネック
企業と従業員のトラブルで多く見られるのは、タイムカードの打刻時間と労働時間のずれが原因となるものです。企業によってはタイムカードの設置場所が、業務をおこなう場所と離れていることもあるでしょう。その場合、時間のずれをどのように処理するのかでトラブルになるケースがあります。
一般的に、タイムカードの打刻時間と労働時間がずれた場合、打刻時間が採用されます。そのため、企業としてはそのずれの時間を最小限におさめる努力をする必要があります。
【関連記事】タイムカードの打刻時間と労働時間のずれに関する対処法を解説
2-2. 始業・終業時間はどこからどこまで?
タイムカードで勤怠管理をおこなっている場合、始業時間と終業時間があいまいなことがあります。例えば、仕事を始める前に着替えたり、ミーティングや体操がある場合はどこからが始業時間になるのでしょうか。
考え方のポイントとしては、企業がその行為を義務付けしているかどうかの点が重要になります。着替えの場合、指定された更衣室での着替えを義務付けをしていれば、労働時間にあてはまります。
家で着替えたまま出勤してもいいし、更衣室で着替えてもいいという自由な裁量に任せている場合は、労働時間にカウントされないでしょう。
一方で終業時間の場合、例えば18時が本来の就業時間で、タイムカードの打刻時間がそれよりも遅く打刻されていたとしても、企業としてはタイムカードの打刻時間通りに給与計算をする必要があります。
ずれの時間に労働をしていない証拠を提出できない限りは、そのような対処をします。なぜなら、従業員の労働時間を管理する義務は、企業にあるからです。不要な残業を増やさないためにも、従業員の労働時間をしっかりと管理する必要があります。
2-3. リアルタイムで勤務時間を把握しづらい
タイムカードで勤怠管理をおこなっていると、従業員の勤務時間がリアルタイムで把握しづらくなってしまいます。例えばタイムカードで勤怠管理していると、従業員の月の時間外労働を把握できるのは集計が完了する月末のタイミングです。しかし、従業員の勤務時間はリアルタイムでの管理が求められます。リアルタイムで管理できないと、時間外労働時間が大幅に増加してしまう恐れがあります。
2-4. タイムカードの集計に時間がかかる
タイムカードの場合、集計に時間がかかってしまいます。そのため、勤怠を管理する従業員の負担が増加してしまいます。また、集計に時間がかかるだけでなく、集計方法によってはミスの発生も懸念されるでしょう。タイムカードの集計にミスが発生すると、従業員の給与に誤差が生じかねません。
こうしたトラブルを防ぐため、早出や残業を事前申請制にして承認された場合のみ可能にしたり、打刻後のタイムカードチェックをおこなったり勤怠管理システムを導入するなど、複数の解決策を講じる企業も増えています。勤怠管理システムを導入する場合は、書面での申請が不要のため申請する文化が作りやすかったり、タイムカードの手計算が不要のため人的ミスが低減されるなど、勤怠管理の担当者・従業員ともにメリットが多いです。
当サイトでは、システムの導入前後で勤怠管理業務がどのように変わるのか解説した資料を、無料で配布しております。システムの導入で打刻ずれなどのミスが低減しそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
3. 企業が抱える勤怠管理のリスクやよくあるトラブル


近年、企業と従業員の間のトラブル件数は増加傾向にあります。厚生労働省が公表している「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、平成30年の総合労働相談件数は、111万7,983件です。このような状況において、企業の経営者は勤怠管理がかかえるリスクに不安を感じているかもしれません。
3-1. 打刻と労働時間のずれが発生する
タイムカードの打刻時間と労働時間のずれの問題は、以前よりも裁判にまで発展しやすくなっている項目の1つです。
こうしたトラブルを防ぐため、早出や残業を事前申請制にして承認された場合のみ可能にしたり、打刻後のタイムカードチェックをおこなったり勤怠管理システムを導入するなど、複数の解決策を講じる企業も増えています。
勤怠管理システムを導入する場合は、書面での申請が不要のため申請する文化が作りやすかったり、タイムカードの手計算が不要のため人的ミスが低減されるなど、勤怠管理の担当者・従業員ともにメリットが多いです。
3-2. 残業代などの未払いトラブルが発生する
タイムカードの打刻時間通りに給与計算をしていない場合、未払い分として従業員から残業代の請求をされることがあります。従業員が労働基準監督署に相談すると、是正勧告書や指導票などが交付されることがあります。
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。
さらに、内容が悪質であると判断された場合は、労働基準法違反により刑事罰に課せられることもあるので注意しましょう。
また、労働基準法第114条によると、裁判で未払いの請求が認められた場合、従業員に対して未払い賃金と同等の付加金を命じられることもあります。つまり、未払い請求金額が1000万円だとすると、付加金は1000万円、合計で2000万円を支払う必要があるのです。
関連記事:残業代はタイムカードの打刻通りに支払おう!労働時間の把握が企業の義務
4. タイムカード打刻に関するトラブルを防ぐ方法
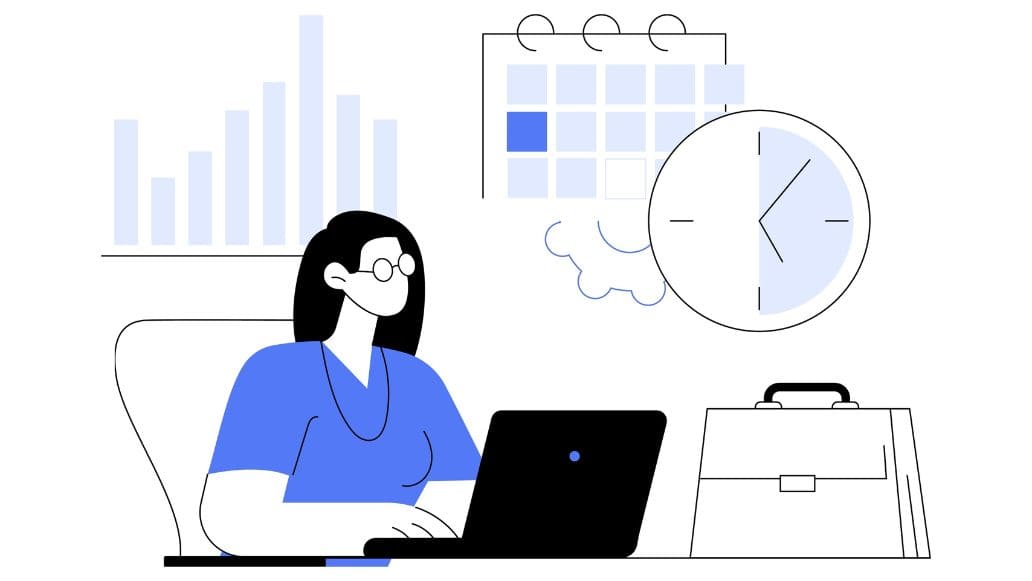
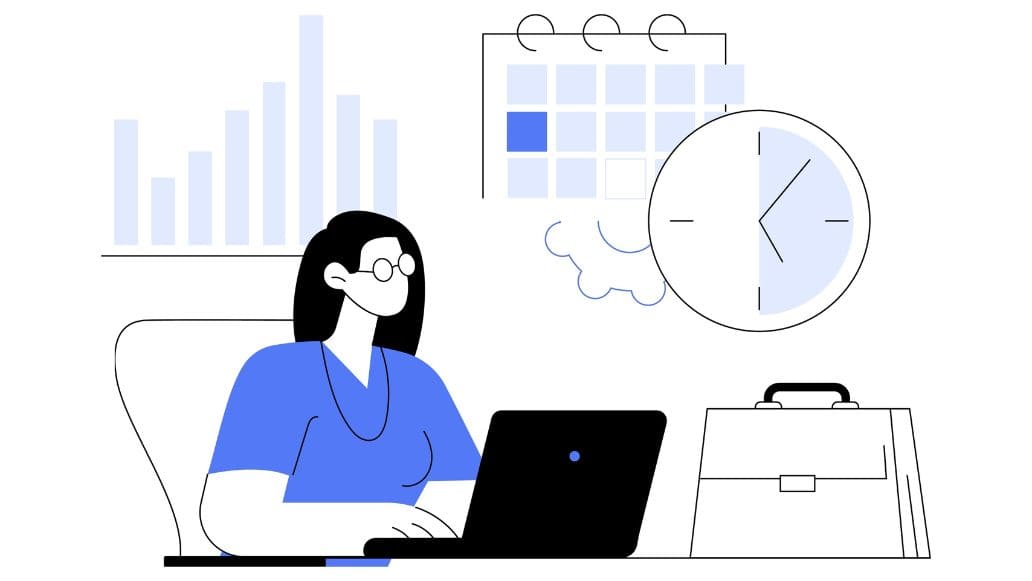
タイムカード打刻に関するトラブルを未然に防ぐためには、適切なルールを整え、勤怠管理システムの導入を検討することが重要です。
打刻ルールを明確にし、従業員がしっかりと理解することで、打刻漏れや誤記入を防ぎ、正確な労働時間の管理が可能となります。企業は、労働時間の透明性を確保し、従業員との信頼関係を築くことができます。
4-1. タイムカード打刻を勤怠管理システムに変更する
打刻をタイムカードで実施していると、さまざまな打刻のずれやそれにも伴う残業代の未払い問題、集計業務の負担、集計によるミスなどにつながりかねません。このようなリスクを回避するには打刻ルールを勤怠管理システムに変更するのがおすすめです。
勤怠管理システムであれば従業員の労働時間をリアルタイムに把握できるほか、集計にかかる業務負担の削減などが期待できます。また、タイムカードに記録されたデータは自動で集計されるため、人的ミスを減少させ、正確な給与計算が実現します。このような効率化により、企業は残業代や未払いのトラブルを未然に防ぐことができ、労働基準法に則った適正な労働時間管理を行う際にも大いに役立ちます。さらに、打刻ルールを明確にし、従業員への教育を実施することで、タイムカードの利用に対する理解を深め、運用を円滑にすることが可能です。
5. 就業規則に記載する勤怠ルールはシステムへの移行を検討しよう

タイムカードの打刻と労働時間のずれ問題、残業代の未払い問題などさまざまなトラブルを解決する1つの方法は、勤怠管理システムを導入することです。ものによってはPCやスマホだけではなくチャットツールなどからの打刻も可能で、従業員の労働時間をスムーズに管理できるでしょう。
従業員の労働時間を正確に把握するためにも、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
タイムカードの関連記事
-


タイムカードの電子化とは?システム導入のメリットや方法・注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2023.06.04更新日:2024.10.17
-


タイムカードを紛失した場合の対策とは?罰則や勤怠記録の残し方も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.06更新日:2024.05.08
-

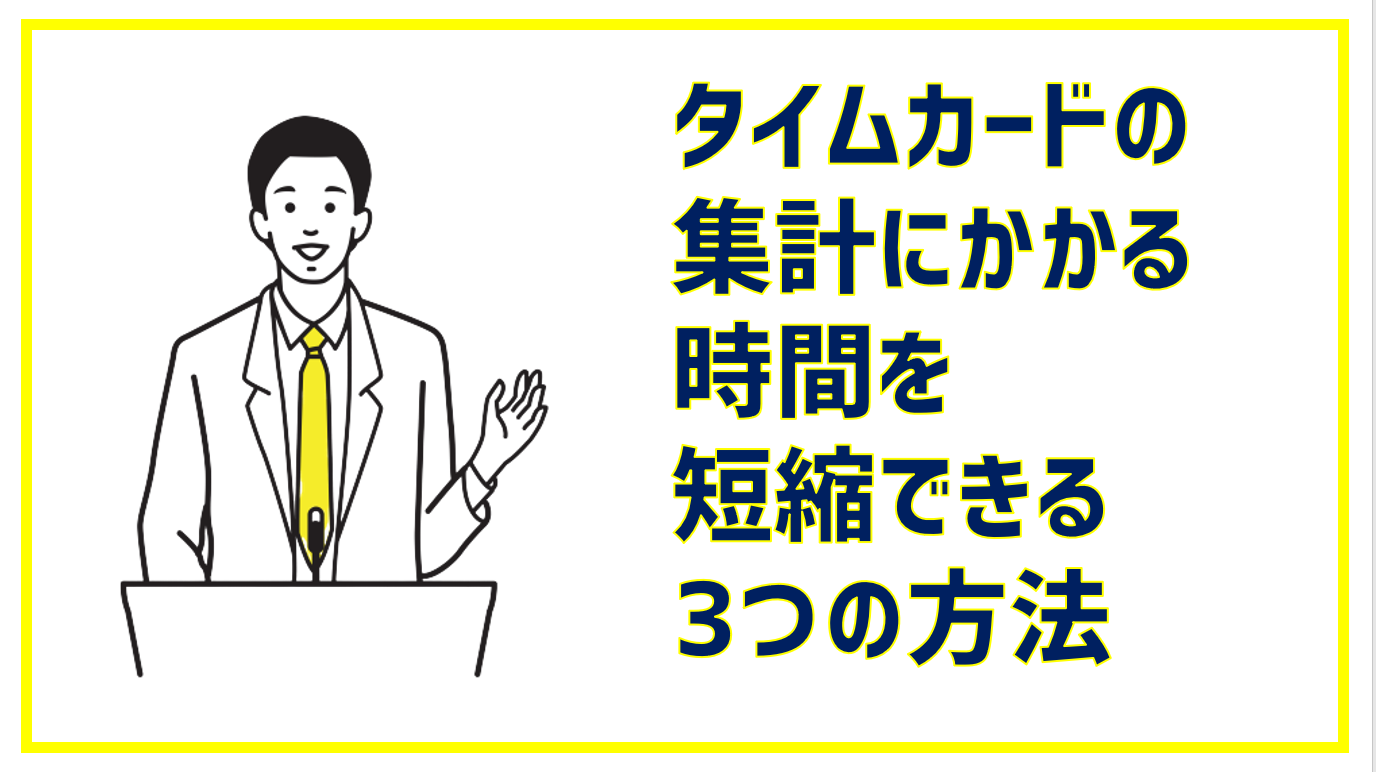
タイムカード集計にかかる時間を短縮できる3つの方法
勤怠・給与計算公開日:2020.03.04更新日:2024.06.12