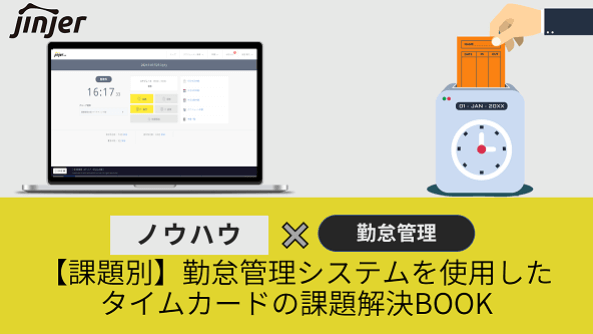残業代はタイムカード打刻どおり1分単位で支払うべき?法律の観点から解説

近年、「企業がタイムカード通りの残業代の計算をしていない」と従業員から残業代の請求をされるというトラブルが増えてきています。
そのような背景をふまえ、タイムカードの打刻通りに残業代を支払うべき理由や、タイムカードの適切な運用方法について解説していきます。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
システムを利用した課題解決BOOK!
タイムカードや出勤簿を使って手作業で労働時間を集計している場合、記入漏れや打刻ミスの確認に時間がかかったり、計算ミスやExcelへの転記ミスが発生したりと、工数がかかる上にミスが発生しやすいなどお悩みはありませんか?
そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入を検討することで、
・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる
・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに
・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 残業代はタイムカードどおり原則1分単位で支払う
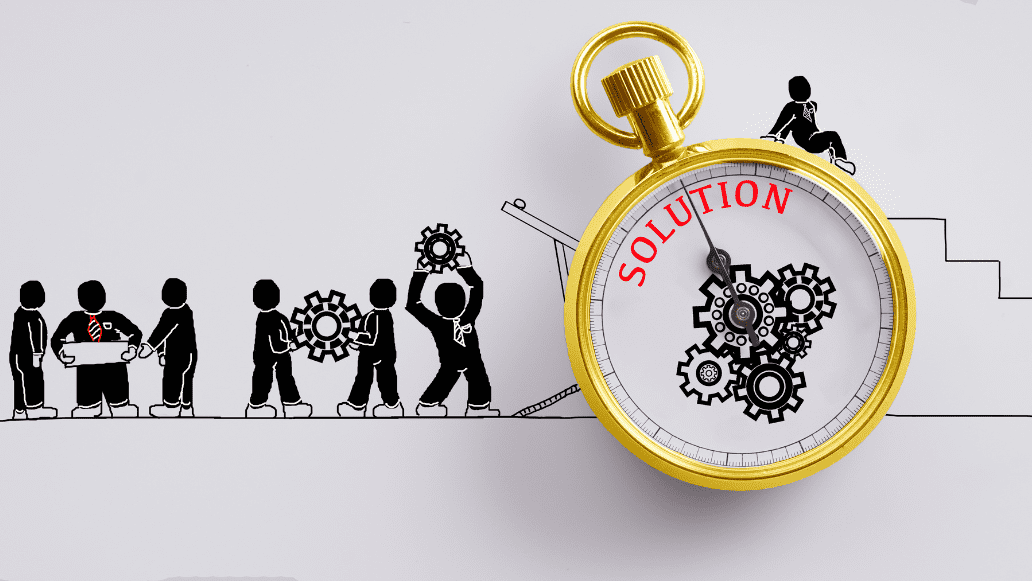
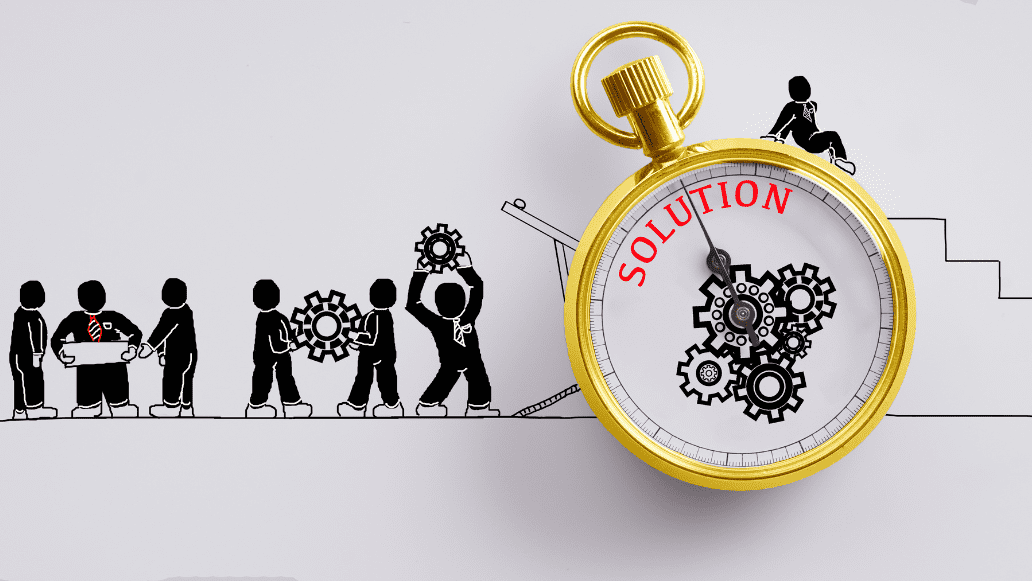
残業代はタイムカードに打刻されたとおり、原則1分単位で支払う必要があります。もし分単位で時間が計算されていなくて、残業代が1円でも少なかった場合、原則では労働基準法に違反したことになります。
しかし、従業員個々の残業時間を1分単位で計算するのには時間と労力が必要です。そのため、次のようなケースでは切り捨て切り上げが可能です。
- 1ヵ月における残業時間の割増賃金総額に1円未満の端数が生じた場合の四捨五入
- 1ヵ月における残業時間の30分未満の切り捨て、もしくは30分以上の切り上げ
【関連記事】15分単位の残業代計算は違法?残業代を正しく計算するためのポイント
1-1. タイムカードで記録をしていなくても違法ではない?
また、タイムカード自体がない場合はどういうことに注意すべきでしょうか。企業がタイムカードなどで勤怠管理をしていないのは違法ではありません。
厚生労働省から発表された「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においては、以下のように明記されています。
ア.使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ.タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
従ってタイムカードがない、タイムカードで勤怠管理をしていない場合でも、労働時間が適正に記録されていれば問題ないでしょう。
2. 企業が労働時間を把握することの重要性

平成29年1月20日、厚生労働省から「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が発表されたことや「働き方改革法」の成立により、より一層正確な労働時間の把握の義務が徹底されるようになりました。
参考:厚生労働省 | 労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
2-1. 労働時間の正確な把握が必要不可欠
ガイドラインや法が整備され、より一層企業の勤怠管理者が従業員の労働時間の正確な把握をすることが義務付けられるようになりました。
正しい勤務時間を把握するために、企業はチェックを強化しているため、より人件費が嵩んでしまうことも大きな問題となっています。
2-2. 企業が勤怠管理を怠るのは違法
企業の勤怠管理者が従業員の労働時間をタイムカードやその他の方法で記録したり把握していない場合は違法となります。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においても、使用者が始業・終業時刻を確認し記録するとあります。
また労働安全衛生法の第66条の8の3においても、事業者の労働者の労働時間の把握について触れていますので、法令を遵守することが企業として求められています。
3. 正しい残業代を支給するためのポイント

企業としては、従業員の正確な労働時間の把握を前提に、決められた労働時間を超えて業務をおこなった場合は残業代を支払わなければいけません。
3-1. 残業時間(時間外労働)の定義とは?
まず残業の定義になりますが、労働基準法第32条で定めされている1日8時間週40時間の法定労働時間を超えた時間で労働をおこなうことになります。残業をしていても残業代を支払っていない、いわゆるサービス残業は違法行為にあたりますので、勤怠管理者は注意しておきましょう。
3-2. 残業をする際は申請書が有効的
企業として従業員の労働時間を把握する際には、残業時間も同時に把握することになります。
月でどの程度残業をおこなっているかを把握するためにも、残業申請を事前にしておくことなどの社内ルールが必要でしょう。このようにルール化されていれば、残業申請が承認された労働時間のみを残業代の支払い対象とすることが可能です。つまり残業代のコントロールがしやすくなります。さらに、勤怠管理する上でも、残業申請の制度があれば給与計算の集計時だけではなく常に従業員の労働が過重労働になっていないかどうか管理することが重要になります。
【関連記事】残業申請で正しい勤怠管理|ルールの作り方と運用方法、見直し方も紹介
3-3. 残業時間を正しく把握して適切な報酬へ
残業時間が多く、過重労働になった場合は直ちに是正措置を講じて、従業員の健康管理の指導もおこなうべきでしょう。企業は使用者として常に従業員の労働時間を把握し、健康管理に努めながら、企業の生産性を維持していく必要があります。
また、労働時間を適性に把握することで、残業代などの給与計算も正しく処理され健全な勤怠管理につながります。
【関連記事】残業代はタイムカードの打刻通りに支払おう!労働時間の把握が企業の義務
4. 正しい残業計算のため勤怠管理システムが注目されている


企業は従業員の労働時間を把握して正しい給与計算をすることが重要であることを解説してきました。では、その勤怠管理を管理する手段としてタイムカードで運用する際のポイントを解説します。
4-1. 残業代の未払い問題が増加傾向
近年、タイムカードの打刻時間と労働時間のずれが生じている問題で、残業代の未払い請求が増加傾向にあります。そのようなトラブルになった場合は、タイムカードの時間通りに残業代を支払うケースが多いです。
従業員が退職した後で、企業が未払いの残業代を請求され、何千万という金額を支払ったケースもありますので、タイムカードなどで勤怠管理している場合はタイムカードの時刻通りに給与計算をしておくべきでしょう。
タイムカードの打刻と実働時間に隔たりがある場合は、タイムカードを置く場所を実働する場所の近くに設置したり、何かしらの対策を取ることをおすすめします。
もし無料で勤怠管理を楽にできないかとお考えの方で、オフィスソフトの運用ノウハウが社内にほとんどない場合は、無料で公開されている勤怠管理用のテンプレートをダウンロードして使う方法もあります。無料テンプレートが気になる方は、以下の関連記事からご確認ください。
【関連記事】「え、こんなに簡単なの?」タイムカードを簡単に集計する方法をご紹介!【無料テンプレ付き】
【関連記事】タイムカードの打刻時間と労働時間のずれに関する対処法を解説
導入し、残業時間を含めて労働時間を記録しておくことで、万一残業代を請求されたとしても、根拠となる勤怠情報があるため適切に対応ができるでしょう。
4-2. 勤怠管理システムでのタイムカード打刻が注目されている
タイムカードのみでは、残業管理や有給管理などが難しく、上述の通り残業代の未払いが発生したり、従業員から不当な請求があった場合に立場が危うくなる可能性があります。しかし勤怠管理システムを導入し、残業時間を含めて労働時間を記録しておくことで、万一残業代を請求されたとしても、根拠となる勤怠情報があるため適切に対応ができるでしょう。
さらに、勤怠管理システムは法令遵守を徹底するためにも役立ちます。労働基準法では、使用者に労働時間の適正な把握が求められており、タイムカードやICカードを利用して客観的な記録を残すことで、企業の信頼性が向上します。これにより、労使間のトラブルを未然に防ぎ、従業員との信頼関係を強化することが可能です。当サイトでは、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を参考に、システムを導入することで、どのように勤怠管理業務のミスが減り、効率化されるか解説した資料を無料で配布しております。
システムを導入することで勤怠管理業務のミスが減りそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
【関連記事】勤怠管理の方法や方法別のメリット・デメリット、勤怠管理の目的を解説
5. タイムカード打刻後のサービス残業は違法

企業のなかにはサービス残業が常態化しているケースがあります。サービス残業ではタイムカードを打刻し、退勤扱いになっているうえで残業する状態です。このようなタイムカード打刻後のサービス残業は違法にあたります。
5-1.サービス残業が違法な理由
サービス残業は、労働基準法第37条の違反とされています。具体的には同法で、時間外労働や休日労働に対して割増賃金を支払う義務が明記されています。
この法律は、使用者が労働時間を延長した場合、その延長時間について通常の賃金の計算額の25%から50%の範囲内で割増賃金を支払うと定めています。
さらに、一か月間で60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。企業が適切な残業代を支払わない場合、違法行為を行うこととなり、従業員のモチベーションが低下するだけでなく、社会的信用を失う危険性もあります。
参考:時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条) 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)|厚生労働省
また、そもそも企業には労働者の労働時間を正確に把握する義務があり、これを怠ったことで時間外労働が上限時間を超えてしまった場合も、労働基準法違反となります。
5-2.サービス残業に関する罰則
サービス残業が発覚した場合は、会社に6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられてしまいます。そのため、サービス残業を従業員に強いるのはもちろん、自主的にサービス残業している従業員に対しての指導も進めていきましょう。
5-3. タイムカード打刻後にサービス残業してしまうケース
タイムカード打刻後にサービス残業が行われることが日常化している企業も少なくありません。これは法的問題を引き起こす原因となります。特に経営理念や労務管理がしっかりしていない場合、サービス残業が慢性化しやすいです。サービス残業が横行する理由を理解し、改善していく必要がありますのでケースを紹介します。
管理職が労働基準法を理解していない
管理職が労働基準法を理解していない場合、タイムカード打刻後にサービス残業が発生する可能性があります。
サービス残業を命令する上司や経営陣が労働基準法を理解していないため、無意識に違法行為を行うことがあります。また、経営陣や管理職の中には労働基準法の違法性を知りながら、コストカットや残業時間を少なくみせるためにサービス残業を強要する悪質なケースも存在します。
こうした状況は従業員に対して非常に不利な働き方を強いるものであり、法律リスクの増大を招きます。
当たり前になってしまっている社内風土
サービス残業が当たり前になっている企業文化は、過去の慣習によって根深く根付いている場合があります。
特に、タイムカード打刻後にサービス残業が常態化しているケースでは、「残業して会社に貢献する=美徳」という考え方が強く影響します。多くの従業員が率先してサービス残業を行うため、他の従業員もそれに従わざるを得ない状況に陥りがちです。
このような風土では、サービス残業を止める声を上げることが難しく、最終的にはそれが企業全体で暗黙の了解とされる風潮となります。
結果として、労働法に基づく残業代の支払い方法や勤怠管理の徹底が難しくなり、法令遵守の観点から大きな問題となります。
従業員が会社に残業を隠している
従業員がタイムカードを打刻した後にサービス残業をするケースは、企業が注意すべき重要な問題です。要因の一つとして、従業員が自身の残業を隠すことがあります。労働法に基づく残業代の支払いや勤怠管理の観点から、この行動は非常に問題があります。
従業員が残業を報告しない理由には、評価基準が関係していることがあります。一部の上司や企業では、残業を多くの時間貢献と見なして評価する一方、他の上司や企業では残業を仕事効率の低さと見なすことがあります。
こうした評価基準の違いが従業員にプレッシャーを与え、結果としてサービス残業を選択することにつながります。
また、労働時間に対して見合わない業務量であるにもかかわらず、労働時間は上限以内におさめるように管理が厳しくなっていると、残業の上限が守られているようにみせるため、打刻をしてからも働き続けるというサービス残業が発生してしまいます。管理を厳しくするだけでなく、適切な業務量となるように調整することが重要です。
5-4. サービス残業など未払いの残業代に時効はあるの?
未払いの残業代には法定時効が設定されています。日本の労働法では、未払いの残業代の請求権は発生から3年で消滅します。
これにより、従業員は残業代を請求する権利として、3年以内に十分な証拠を集めて交渉や訴訟の手続きを始めることになります。未払いの残業代がある場合、法定時効を過ぎる前に適切に対応することで、企業のリスクを回避することができます。
5-5. 打刻時間がわかるタイムカードの情報提出を求められた場合は?
労働基準監督署や従業員からタイムカード情報の提出を求められた場合、迅速かつ適切に対応することが求められます。企業は日常的に正確な勤怠記録を保持するだけでなく、労働法に基づき残業代の支払い方法を遵守することが重要です。
未払い残業代の請求が発生した場合、勤怠履歴などの証拠書類は開示請求を通じて収集される可能性があります。開示請求に応じない企業は、裁判所に不利な証拠を隠していると受け取られ、訴訟で不利に働く場合もあります。
6. 労働時間の把握は企業の義務!正しいタイムカード打刻の管理を

タイムカードの打刻問題や労働時間、残業時間の把握を企業は正しく管理するためには、勤怠管理者の負担にもなりかねません。少しでも業務の効率化を図る上でも、勤怠管理システムを導入することをおすすめします。勤怠管理システム「ジンジャー」は、多彩な打刻システムを搭載しており、PC、スマホ、タブレット、チャットツールなど現代社会で欠かせないツールで打刻が簡単にできます。
企業の労務管理の担当者は、従業員の労働時間を適切に把握して、適正な残業代の計算をおこなわなくてはいけません。タイムカードで管理している場合は、打刻通りに残業代を計算をしておくと良いでしょう。タイムカードで残業代の計算をおこなっている場合は、打刻のミスや打刻がずれることで計算の工数がかかる場合もあります。
業務の効率化を図る方法として、勤怠管理システムの導入を検討してみる方法をおすすめします。勤怠管理者も労務状況をタイムリーに管理が可能になり、過重労働などの事態も早期に発見ができます。さまざまな機能を利用しながら、適正な勤怠管理に努めていきましょう。
関連サイト:残業代が出ない時に違法性を調べる方法と請求する手順|クロスワークマガジン
システムを利用した課題解決BOOK!
タイムカードや出勤簿を使って手作業で労働時間を集計している場合、記入漏れや打刻ミスの確認に時間がかかったり、計算ミスやExcelへの転記ミスが発生したりと、工数がかかる上にミスが発生しやすいなどお悩みはありませんか?
そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入を検討することで、
・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる
・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに
・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
タイムカードの関連記事
-


タイムカードの電子化とは?システム導入のメリットや方法・注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2023.06.04更新日:2024.10.17
-


タイムカードを紛失した場合の対策とは?罰則や勤怠記録の残し方も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.06更新日:2024.05.08
-

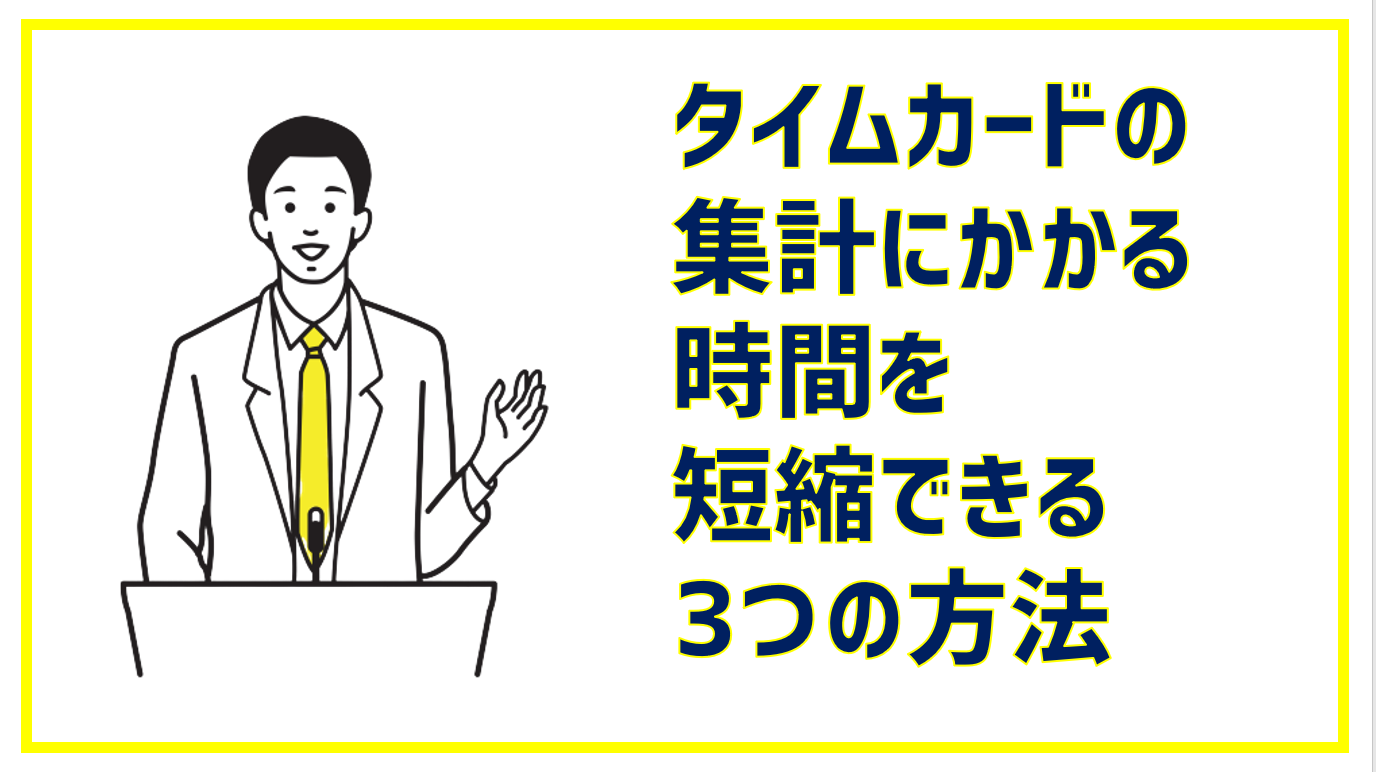
タイムカード集計にかかる時間を短縮できる3つの方法
勤怠・給与計算公開日:2020.03.04更新日:2024.06.12