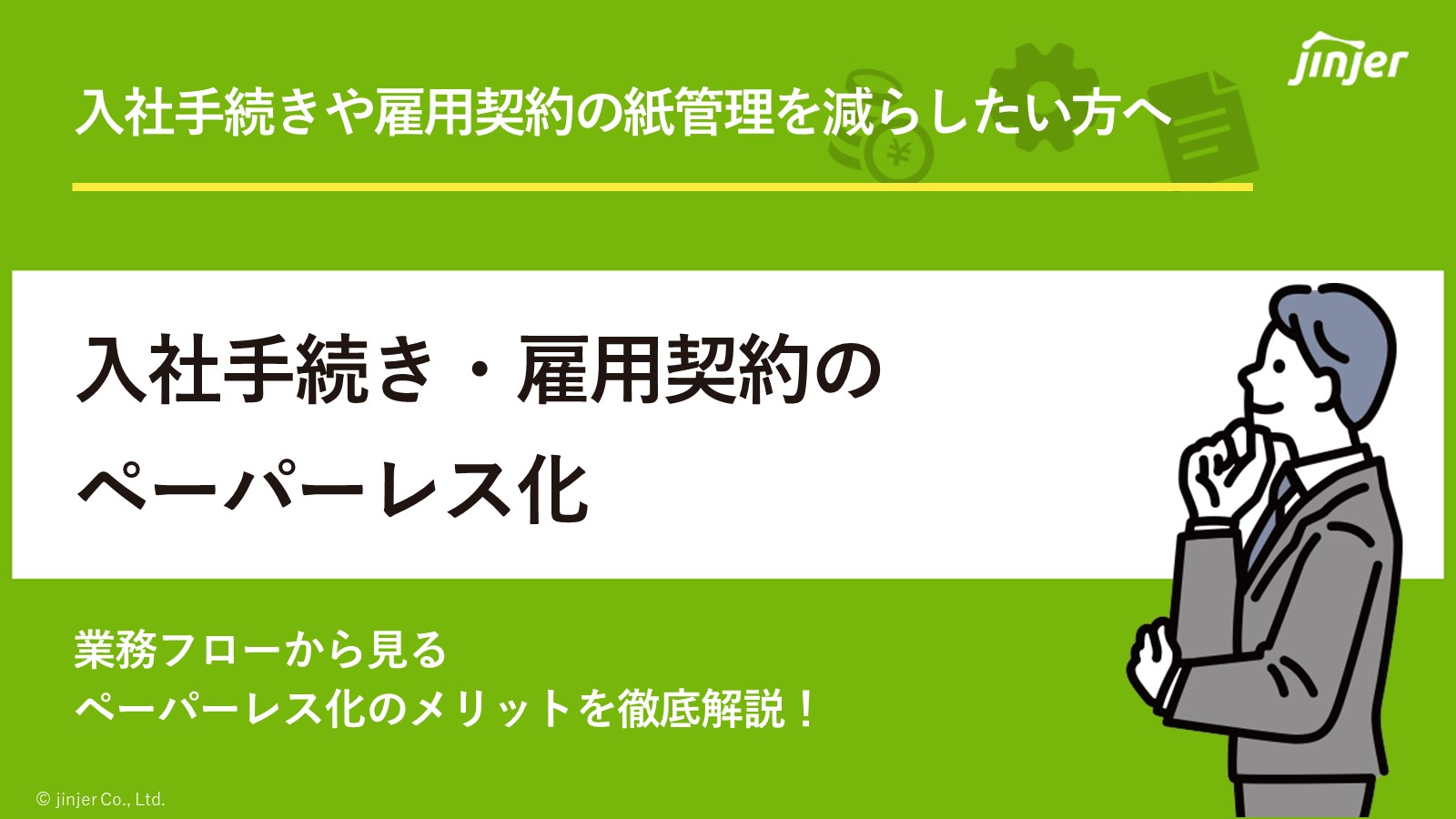雇用契約と請負契約の違いとは?それぞれの内容・注意点を解説

雇用契約と請負契約は似ている部分もあり、混同されやすい契約のひとつです。しかし、明確な違いがあるため、中小企業や一人親方はそれぞれの契約内容を十分に把握しておかなければいけません。
従業員を雇用する場合、雇用主側が雇用契約と請負契約の違いを理解しておくことは、思わぬトラブルを引き起こさないためにも非常に重要です。
本記事では、雇用契約と請負契約、それぞれの内容や注意点について解説していきます。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
1. 雇用契約と請負契約の違い

結論から記載すると、雇用契約と請負契約の違いは「労働者性の有無」です。
労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と労働基準法では定められており、雇用主は労働者に対して労働基準法などの法令に従って雇用しなければなりません。
雇用契約の場合は、雇用される側は「労働者」となるため、労働関係の法令の保護を受けることができます。しかし、請負契約の場合は、雇用主と労働者という関係ではなく、注文者と請負人という関係となります。
請負人は労働関係の法令における労働者ではないため、労働者としての保護を受けることができません。
2. 雇用契約と請負契約の具体的な意味・内容

雇用契約と請負契約の具体的な内容を見ながら、双方の特徴と違いについて深堀していきましょう。
2-1. 雇用契約とは
雇用契約の根拠になるのは民法第623条で、労働者がおこなう労務に対して雇用主が報酬を支払う関係性です。
雇用契約では、始業・就業の時刻が定められていたり、就業する場所が決められていたりするなど、雇用主に指揮命令権があります。
労働者に仕事についての指示や命令を拒否する権利がない、あるいは拒否したくてもできない状況であれば、指揮命令権があると判断されて雇用契約に該当します。
また、「時給」「日給」「月給」といったように、労働に対する報酬が支払われることに特徴があります。
関連記事:雇用契約とは?法的な位置付けと雇用契約書を作成すべき理由を解説
2-2. 請負契約とは
請負契約は注文者と受注者に分けて考えるもので、受注者は委託された業務を完遂することを約束し、注文者は成果に対して報酬を支払う関係です。
請負契約では指揮命令がないため、注文者からの依頼を拒否することができます。
雇用契約では、雇用主が材料や機材を提供することになりますが、請負契約では受注者は必要な機械や資材を自分で用意しなければなりません。
そして非常に重要なのは、民法632条では「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定められている点です。
したがって請負契約では、成果物を引き渡さないと報酬が支払われません。
請負契約の場合、仕事が完成する前であればいつでも契約を解除することが可能である点も、雇用契約と大きく異なるポイントです。
【表】「雇用契約」と「請負契約」
| – | 雇用契約 | 請負契約 |
| 指揮命令 | あり | なし |
| 労働者側に求められる要件 | 「労働」に対して 報酬が支払われる |
「成果物」に対して 報酬が支払われる |
| 労働基準法による保護 | あり | なし |
| 契約解除 | 雇用主側から一方的に 契約解除はできない |
仕事が完成しない間であれば 損害を賠償して契約解除が可能 |
3. 雇用契約や請負契約を結ぶ際の注意点

最後に、雇用契約・請負契約を締結する際の注意点を解説します。法令や契約の有効性に関係する重要な部分もあるため、契約を結ぶ際は十分に留意しましょう。
3-1. 雇用契約かどうかは労働者の実態によって決まる
雇用契約における重要な注意点は、契約上は雇用契約でなくても、働く人が労働者の実態を備えていれば雇用契約と見なされるという点です。
たとえば、雇用契約以外の形態で契約していても、従業員に業務を拒否する選択肢がなかったり、業務に必要な材料や用具を会社が用意していたりする場合などが該当します。
雇用に該当すると判断される場合や、会社側に指揮命令権があるとされる場合は、契約の名称が異なる場合でも雇用契約と見なされます。
3-2. 雇用契約の労働者は労働関係の法令で保護される
雇用契約の場合、労働者は労働関係の法令で保護されているため、雇用主としては、この点をよく覚えておく必要があります。
たとえば雇用契約を締結している労働者には、以下のような権利が与えられています。
・残業代の請求や有給休暇の申請が行える
・労働者は雇用主の指示や命令の元に業務を行うので、ある程度の範囲の損害は雇用主が負担する
・不合理な理由での解雇・契約解除を拒否できる
これらは、会社の就業規則に関係なく与えられている権利であり、たとえ就業規則に「残業代は支給されない」などと書かれていても無効になります。
3-3. 請負契約は労働者にとって不利な点が多い
請負契約は、雇用契約と比較して請負人に不利な点が多くあります。
請負契約を締結した場合、労働基準法などの保護を受けられなくなるからです。
もし不可抗力によって成果物が引渡し前に壊れてしまったり、なくなってしまったりした場合でも、報酬を請求することはできません。
雇用契約であれば会社が補填してくれる損失も、請負契約になるとすべて自分で穴埋めをしなければならないという状況も生じ得ます。
中小企業や一人親方で請負契約を結ぶ場合は、こうしたデメリットを十分に理解して検討しましょう。
4. 雇用契約と請負契約は契約内容から判断しよう

雇用契約と請負契約は似たようなものだと受け止められることが多いですが、実際には大きな違いがあります。締結する際は違いを十分に理解しておきましょう。
また、契約の名称が雇用契約や請負契約になっていても、契約内容に問題があれば別の契約であるとみなされることがあります。
契約を結ぶ際は契約の名称と内容が合致していることも確認し、後にトラブルにならないように十分に注意することが重要です。
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
▼併せてこちらの記事もチェック!
アルバイト採用でも雇用契約書は必要?作成するための4つのポイント
| <関連記事>
▶アルバイト採用でも雇用契約書は必要?作成するための4つのポイント |
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08