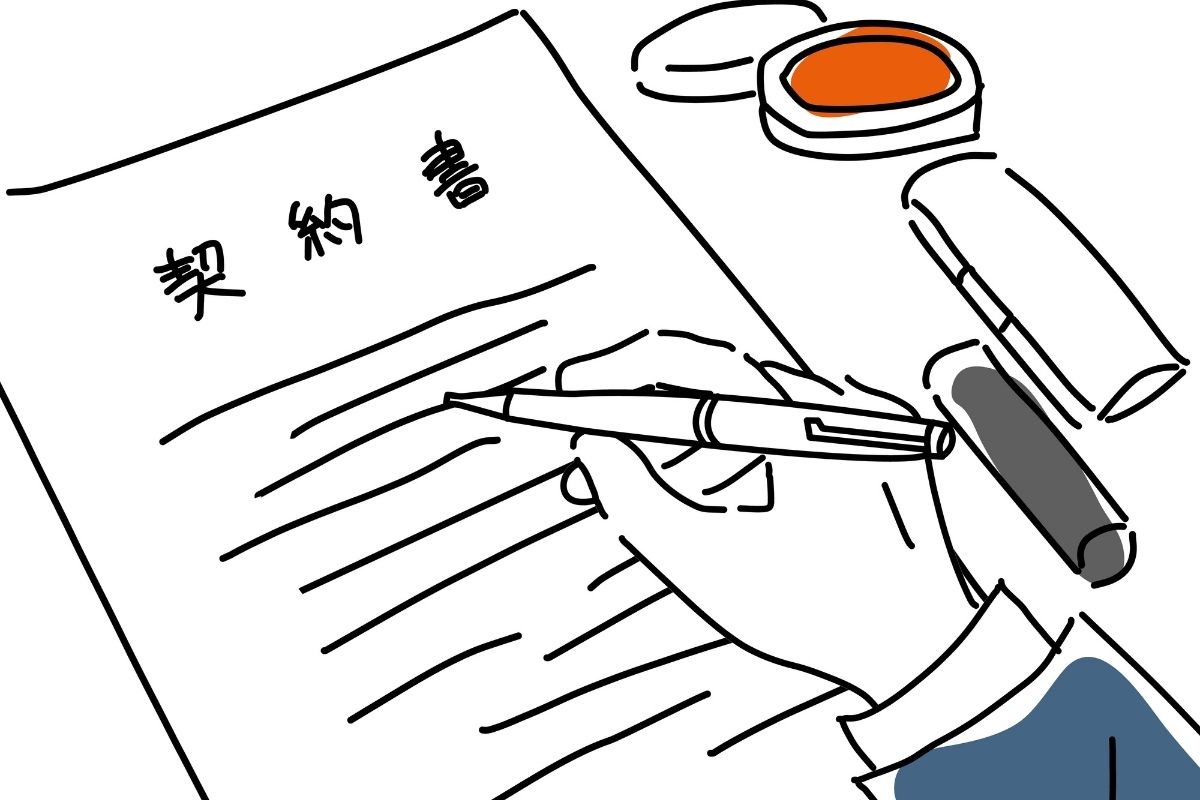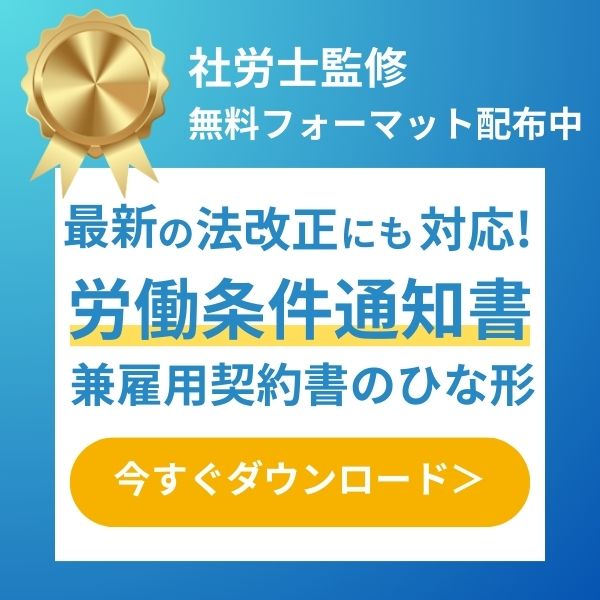パートタイム労働者の雇用契約書で勤務時間を記載するときの注意点とは
更新日: 2025.11.21 公開日: 2020.12.7 jinjer Blog 編集部

雇用契約書に記載されるべき内容の1つとして、「勤務時間」に関する内容が挙げられます。
正社員の場合は、毎日決まった時間帯で勤務することがほとんどですが、パートタイム労働者は勤務する時間帯や日数がバラバラになることが多いです。そのため、雇用契約書に記載すべき「勤務時間」の書き方で迷いやすいです。
本記事では、パートタイム労働者の雇用契約書に記載すべき内容や、勤務時間の記載方法、注意事項などについて詳しく解説していきます。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
目次
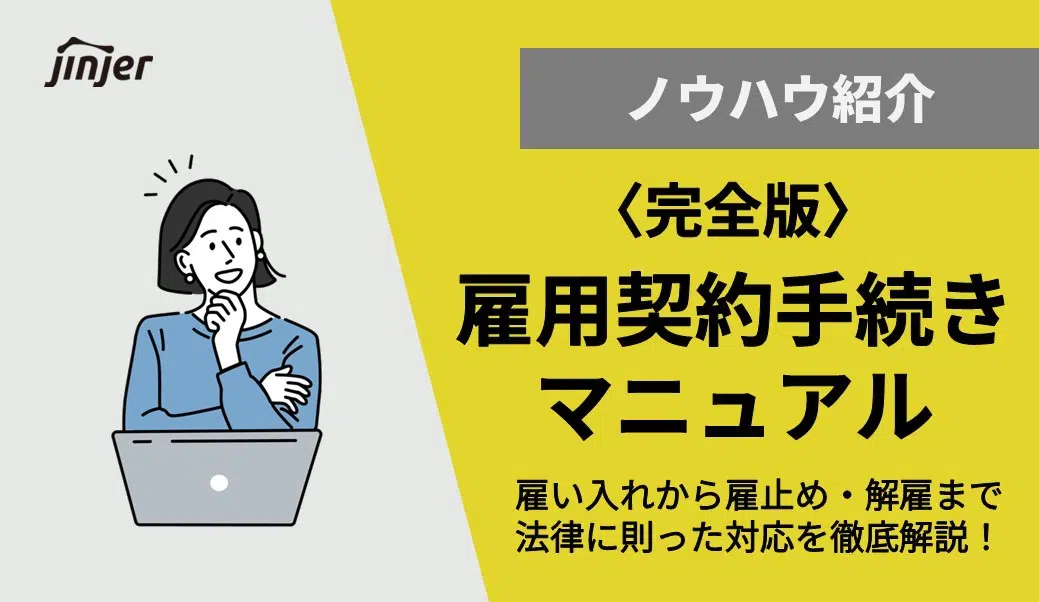
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. パートタイム労働者の定義とは?

パートタイム労働者の定義とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)第2条により、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
ここで示されている「通常の労働者」というのは、基本的に正社員や正職員のことを指します。正規型の社員がいない場合には、フルタイムで基幹的な働き方をしている労働者のことを「通常の労働者」とみなします。
企業や事業場によっては、アルバイト従業員や嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など、パートタイム労働者とは異なる名称で呼んでいることがあります。しかし、そのような場合でも条件に当てはまる場合はパートタイム労働者とみなされ、パートタイム労働法の対象になります。
2. そもそも雇用契約書とは
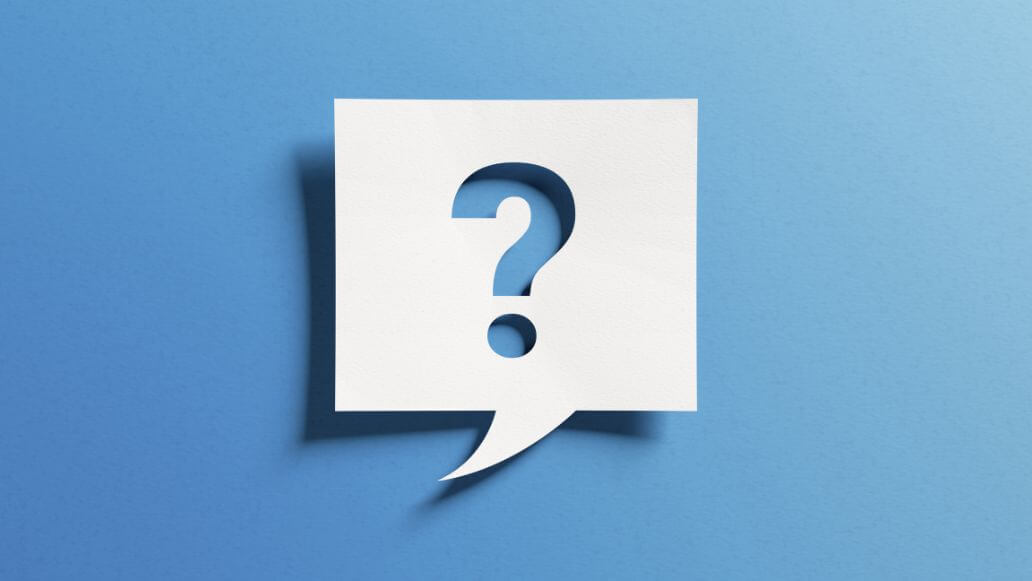
雇用契約書は労働条件通知書と異なるもので、必ずしも作成する必要はありません。しかし、作成することが望ましいとされています。
その理由と、契約締結後に辞退された場合の対処法を解説します。
2-1.雇用契約書と労働条件通知書は違うもの
雇用契約書とは、雇用主が労働者に労働条件を明示し、労働者側がその労働条件に合意したことを示すために、企業側と労働者側で取り交わす書類です。
雇用契約書は労働条件通知書と内容が似ていますが、異なるものです。労働条件通知書の交付は義務とされている一方で、雇用契約書は必ずしも交付する必要はありません。パートタイム労働者に対しては、雇用契約書を作成しないケースも多いです。
しかし、雇用契約書を交わしておかなければ、労働条件について「確認した」「確認していない」というようなトラブルが発生してしまうことがあります。それを防止するために、口頭ではなくしっかりと書類を作成しておくことが望ましいです。
なお、記載する文言の些細な点で、労使間で認識のズレが生じる可能性もあるため、新しく雇用契約書を作成する際は専門家に確認してもらうとよいでしょう。
2-2.契約締結後に辞退された場合
雇用契約を締結したとしても、人によっては締結後に辞退することがあります。
原則として、契約が締結すれば、労働者にも雇用主にも契約内容を遵守することが義務づけられます。そのため、雇用契約書の中に、雇用契約書で期間の定めがある場合は、雇用主が勝手に解雇できないのと同様に労働者もやむを得ない事由がない限り契約解除はできません。
ただし、労働基準法第137条では、期間の定めのある労働契約を締結した労働者のうち、その契約期間が1年を超える者は、雇用契約期間の初日から1年が経過すれば、いつでも契約解除ができるとされています。
3. 雇用契約書の記載事項
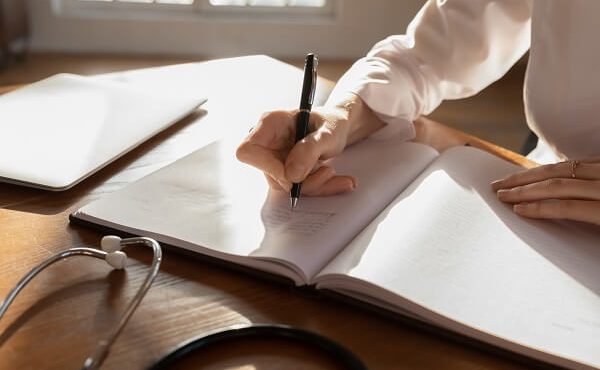
労働条件通知書を雇用契約書と兼用して使用する場合には、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、その企業において何らかの決まりやルールがある場合に記載する必要がある「相対的明示事項」があります。
必要な項目をそれぞれ確認しておきましょう。
3-1. 絶対的明示事項
必ず記載しなければならない絶対的明示事項には、以下のような内容が含まれます。
|
※昇給も絶対的明示事項ですが、書面で交付することまでは求められていません。
さらに、パートタイム労働者の場合は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)第6条によって、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の明示が義務付けられています。
そのため、正社員よりも必ず記載しなければいけない明示事項が多い点に注意が必要です。
なお、法改正により2024年4月から「就業場所・業務の変更の範囲」が絶対的明示事項に追加されているため、正確に記載されているか確認しておきましょう。改正内容に対応しないまま雇用契約を締結した場合、労働基準法第120条に基づき法律違反となり罰則が科されるリスクがあります。
当サイトでは、法改正の内容から正しく雇用契約を締結する方法をまとめたマニュアルを無料配布しております。法律に則って雇用契約を締結したい方はこちらからダウンロードしてください。
3-2. 相対的明示事項
企業にルールがある場合に記載する相対的明示事項には、以下のような内容が含まれます。
|
ここまで記載すべき事項を押さえたところで、実際に労働条件通知書(兼雇用契約書)を作成する際に参考にできるサンプルがほしいという方向けに、当サイトでは社労士が監修した労働条件通知書のフォーマットを配布しています。
令和6年に労働条件の明示ルールが変更された点も反映した最新のフォーマットで、雇用契約書として兼用することもできる雛形です。「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
関連記事:正社員雇用で必須の雇用契約書の作成方法を分かりやすく解説
4. 雇用契約書の勤務時間の記載方法
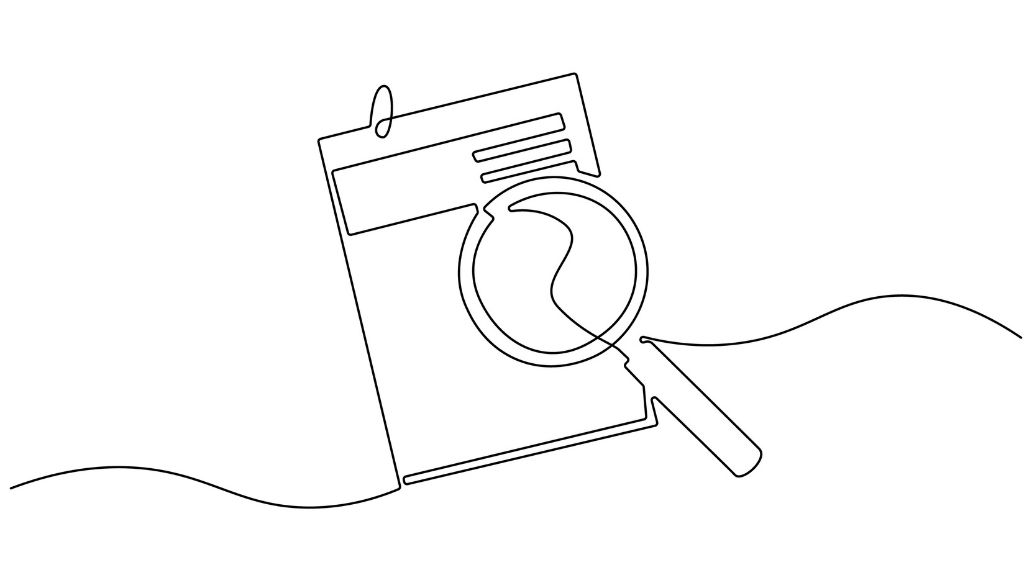
パートタイム労働者は、正社員よりも短時間での勤務であることが一般的です。
パートタイム労働者の労働時間は、固定されているケースと日によって変動するケースがあるため、どのように勤務時間を明記すればよいか迷いやすい部分です。
本記事では、それぞれのケースにおいての勤務時間の記載方法を解説します。
4-1. 勤務時間が決まっている場合
パートタイム労働者の勤務時間が定まっている場合は、始業時刻、終業時刻、休憩時間を記載すれば問題ありません。
具体的には以下のような形になります。
|
始業時刻 9時 終業時刻 17時30分 休憩 12時30分から13時30分までの1時間 |
なお、勤務時間が変動する可能性がある場合は、但し書きとして「会社の都合により始業時刻や終業時刻を変更できる」という文言を加えることも可能です。
4-2. 勤務時間が変動する場合
シフト制などで始業時間や終業時間が変わることがある場合は、厚生労働省の通達において「勤務の種類ごとの始業および終業の時刻、休日などに関する考え方を示したうえで、当該労働者に適用される就業規則上の関係項目を網羅的に示すことで足りる」とされています。
つまり、パートタイム労働者が1週間で働く日数や時間の合計を示したうえで、具体的に勤務をおこなうシフトの時間帯を示すという形で、勤務時間を記載します。
シフトについての記載は、事業場や従業員ごとにさまざまな違いがある部分ですが、イメージとしては以下のように記載します。
|
パターン1: パターン2: パターン3: |
なお、シフト制であるため、休日は決まった曜日でなくても問題ありません。
5. パートタイム労働者と雇用契約書を結ぶ際の注意点

パートタイム労働者と雇用契約書を結ぶ際には、6つの注意点があります。
- 雇用契約書で定めた勤務時間より短くしない
- 休日・休暇について明記する
- パートタイム労働者でも有給は取得可能
- 有期雇用契約の場合は更新の有無と判断基準を記載する
- 同一労働同一賃金を適用する
- 最低賃金を下回っていないか確認する
ここでは、これらの注意点を詳しく解説していきます。
5-1. 雇用契約書で定めた勤務時間より短くしない
労働基準法15条の第2項では、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定めています。
そのため、パートタイム労働者と雇用契約書で定めている勤務時間を、会社の都合で一方的に短くすることは、原則認められません。やむを得ない事情で、勤務時間が少なくなってしまった場合、労働基準法第26条に基づき、休業手当として平均賃金の6割を支払う必要があります。
こうした規則があるため、繁忙期と閑散期で勤務時間が変化する可能性がある場合などは、雇用契約書上で勤務時間の変動があることを記載するとよいでしょう。
その他にも、就業規則と雇用契約で優先順位があり、、雇用契約に関する禁止事項などもあるため、雇用契約業務には正しい知識が必須となります。そこで当サイトでは、雇用契約に関する基礎知識や禁止事項、正しい対応などをまとめた資料を無料で配布しております。雇用契約について少しでも不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
5-2. 休日・休暇について明記する
パートタイム労働者は勤務時間や勤務日が変動することが多く、定まった休みがないケースも珍しくありません。
しかし、そのような場合でも休日と休暇について、雇用契約書に明記しておきましょう。
労働基準法では、「週に1日以上、または4週間で4日以上の休日」を付与することが義務付けられています。
これを遵守した上で休日の基本的な考え方を記載することが大切です。
【休日の記載例】
- 休日は祝日・日曜日・月曜日とする
- 4週を通じて4日以上の休日を付与する
休暇(年次有給休暇・長期休暇など)についても記載が必要です。
年次有給休暇は法定通りの記載で問題ありませんが、夏季休暇や年末年始の休暇は日数も記載するようにしましょう。
5-3. パートタイム労働者でも有給は取得可能
有給休暇は雇用形態を問わず付与が労働基準法第39条で義務付けられており、以下の条件を満たすことで発生します。
- 雇用開始日から6ヵ月が経過していること
- その期間の所定労働日の8割以上出勤していること
なお、原則として上記の条件を満たすと10日の有給休暇が付与されますが、パートタイム労働者の場合、雇用契約書や労働条件通知書に記載の所定労働時間によって有給休暇の付与日数が決まります(比例付与)。
労働条件の絶対的明示事項には、休暇に関する事項も含まれているため、雇用契約書にはしっかりと有給休暇に関する記載もするようにしましょう。
関連記事:パート・アルバイトにも有給休暇はある!付与日数や発生条件について解説
5-4. 有期雇用契約の場合は更新の有無と判断基準を記載する
パートタイム労働者と有期雇用契約を結ぶ際は、「契約更新の有無」に加えて、更新ありの場合は「更新の判断基準」も明記しなくてはいけません(労働基準法施行規則第5条)。
万が一記載が漏れてしまった場合は、労働基準法第15条の明示義務違反とされ、罰則の対象になる恐れがあります。
なお、法改正により2024年4月から、有期雇用契約の場合はさらに「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」の明示も必要となるため、合わせて注意しましょう。
5-5. 同一労働同一賃金を守る
パートタイム労働者であっても、同一労働同一賃金を適用する必要があります。
「同一労働同一賃金」とは、「同一の業務をしていれば同一の賃金を支給する」という考え方で、これには雇用形態は関係ありません。「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」では、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者を含む)の待遇差を解消するため、「同一労働同一賃金」を定めています。
この法律では、非正規雇用労働者でも経験や勤続年数、能力などが正社員と同一と判断できれば、待遇差をつけてはいけないとしています。つまり、「パートだから」など雇用形態だけで賃金を低くするのは違法となる可能性があるため、不当な賃金設定になっていないかしっかり確認しましょう。
5-6. 最低賃金を下回っていないか確認する
正規社員だけでなく、パートタイム労働者にも「最低賃金」が決められています。そのため、パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際には、最低賃金法で定められている「最低賃金」を下回っていないか、必ず確認しましょう。
最低賃金は全国一律ではなく、「地域別最低賃金」もしくは「特定最低賃金」があります。
地域最低賃金は都道府県ごとに定められているもの、特定最低賃金は業種ごとに定められているものですが、どちらも不定期に改定されるため、雇用契約書を作成する場合は、その都度確認するようにしてください。
6. 「フレックスタイム制」や「裁量労働制」は記載する事項が増える

最近では働き方改革の影響などで、フレックスタイム制や裁量労働制などを取り入れている企業も増えてきています。
こういった働き方は主に正社員に対して適用されるものですが、パートタイム労働者に一切適用されないわけではありません。
フレックスタイム制や裁量労働制を採用している場合は、労使協定の締結や就業規則への規定といった法令上の要件を満たしたうえで、雇用契約書に必ずその旨を記載する必要があります。
またフレックス労働制では、必ず出社しなければならない時間である「コアタイム」と、出勤や退勤を自由におこなえる時間である「フレックスタイム」も定めている場合には記載しなければなりません。
このように、フレックスタイム制や裁量労働制で雇用契約をする場合は、記載する事項が増えるため、漏れがないよう注意しましょう。
関連記事:パートタイマーの雇用契約書を発行する際に確認すべき4つのポイント
7. パートタイム労働者との雇用契約書で定めた勤務時間は厳守しよう

雇用契約書における勤務時間記載に関しては、正社員の方とパートタイム労働者の方で大幅にルールの違いがあるわけではありません。
ただ、パートタイム労働者は正社員と異なり、シフト制などで勤務時間の形態に違いがあることが多いため、記載方法には注意する必要があります。また、働き方が「フレックスタイム」や「裁量労働」などの場合は、記載する事項が増えるため、記載漏れがないようにしっかり確認しましょう。
労働条件を明示する雇用契約書は、トラブルを避けるために重要な書類です。記載が必要な項目をきちんと把握し、漏れがないように作成することを心がけましょう。
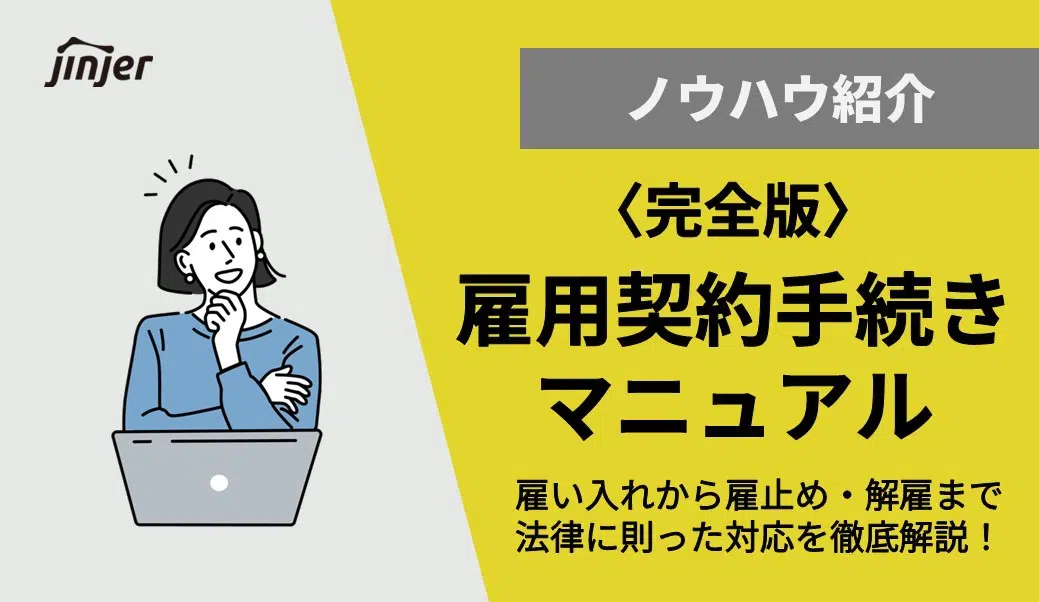
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
雇用契約書の関連記事
-

雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや作成時の注意点を解説!
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.06.09
-

雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる?兼用のメリットや作成方法、注意点をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2026.02.02
-

有期雇用契約書に正社員登用についての条件記載は必須?作成ポイントも解説!
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2025.12.24