社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説
更新日: 2025.5.30 公開日: 2022.3.28 jinjer Blog 編集部
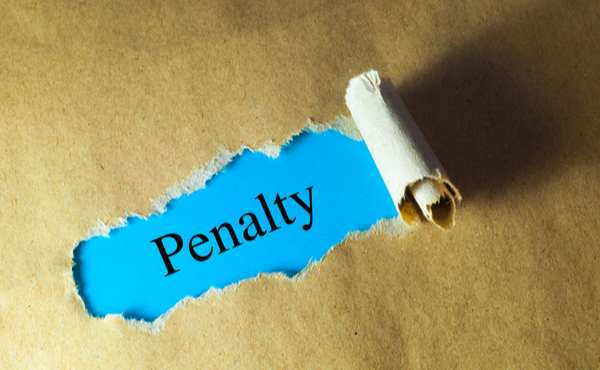
社会保険には、会社と従業員の双方に加入条件があり、当てはまるときは必ず加入しなければいけません。
万が一、加入義務を怠れば罰則を受ける可能性があります。
この記事では、社会保険未加入の罰則と、加入が義務付けられている企業や従業員の条件、加入指導が強化されている背景を解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次

従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 社会保険の未加入には複数の罰則がある


1-1. 6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
社会保険の加入対象となっている未加入事業所のうち、特に悪質なケースでは、健康保険法第208条により、6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課される恐れがあります。
悪質とは、虚偽の申告をしていたり、複数回にわたる加入指導に従わなかったりしたときを指します。
1-2. 過去2年間に遡及して保険料を徴収される
社会保険の未加入が発覚し、年金事務所などにより強制的に加入させられた場合、過去2年間に遡って未納分の社会保険料を徴取される恐れがあります。
社会保険料は給与だけでなく賞与からも徴収するため、事業を圧迫するほどの現金を一度に支払うケースもあります。
1-3. 従業員負担分の保険料も企業が支払う可能性がある
本来、社会保険料は会社と従業員が半分ずつ支払います。
これは、過去2年間に遡及したときの保険料にも当てはまります。
しかし、既に退職した従業員の分などは回収が困難でしょう。
その際は、従業員負担分の社会保険料も合わせて、企業が全額支払うこととなります。
なお、遡及支払いの場合、保険料は全額、会社が立て替えて支払わなくてはいけません。
その後、従業員分を請求することは可能です。
1-4. 延滞金が発生する
納付期日までに社会保険料を支払わないと督促状が届きます。
督促状に指定された期日までに支払いが済んでいなければ、延滞金が発生することになります。
遅延金額は割合により計算されるため、未納額が大きければ大きいほど、ペナルティも大きくなります。
1-5. ハローワークに求人を出せない
社会保険への加入が義務付けられている事業所が未加入であった場合、ハローワークで求人を出すことができません。
以上のように、社会保険への未加入は、発覚時のリスクが大きくなります。
加入条件を事前に把握し、該当する場合は速やかに加入手続きをおこないましょう。
1-6. 会社が損害賠償を請求される可能性がある
社会保険に未加入である場合、従業員やその家族から会社に対して損害賠償を請求される可能性があります。例えば、退職した従業員が年金を請求する際に、厚生年金が支給されなかったことによって、損害賠償請求に発展したというケースも報告されています。さらに、社会保険未加入となっている事業所の従業員に対しては、遺族厚生年金が支給されない可能性もあります。こうした訴訟リスクを避けるためにも、適切な時期に社会保険へ加入することは不可欠です。
2. 社会保険の加入が義務付けられている企業や従業員の条件
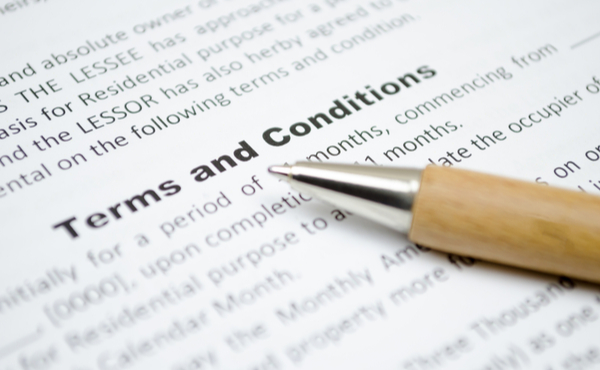
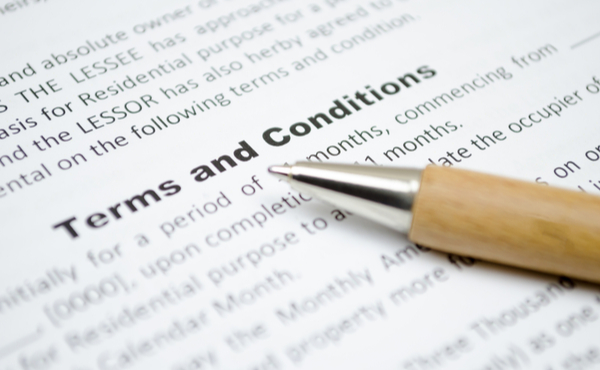
事業所の未加入だけでなく、本来加入させるべき従業員が未加入の場合も、指導や罰則の対象となります。
2-1. 社会保険への加入が義務付けられている企業の条件
事業主・従業員の意思にかかわらず、社会保険への加入が法律上義務付けられている企業を「強制適用事業所」といいます。
- 法人事業所(国・地方公共団体を含む)
株式会社、合同会社、合資会社、有限会社、〇〇法人など種類を問わず強制加入。
また、従業員はおらず、事業主(社長)のみの場合も強制加入の対象。 - 従業員が常時5人以上いる個人事業所
法定16業種に該当する場合強制加入。
それ以外の場合は任意で社会保険に加入可。強制適用とならない主な事業は一次産業、サービス業、宗教。
法人化している場合、従業員数にかかわらず社会保険への加入が必要なため注意しましょう。
参考:日本年金機構 | 被用者保険の適用事業所の範囲の見直し
関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説
2-2. 社会保険への加入が義務付けられている従業員の条件
強制適用事業所に勤務する正社員は、基本的に社会保険に加入しなければいけません。
また、「1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者の4分の3以上」の従業員は、本人の意思にかかわらず社会保険へ加入させなければいけません。
上記に該当しない者でも、下記要件をすべて満たす者は加入の対象となります。
- 現行の社会保険適用対象者が51人以上いる企業に勤めている
- 1週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 学生以外
加入要件のうち、対象となる企業は徐々に緩和されていて、2024年10月から51人以上の企業も該当しています。そのため、加入漏れには注意が必要です。
当サイトでは、上述した法改正の内容や本記事で解説している罰則、法改正に伴い増えるであろう手続きの内容などを解説した資料を無料で配布しております。社会保険手続きの内容に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!
3. 社会保険に加入したがらない従業員への対処法


しかし、社会保険制度は本人の意思によって選べるものではなく、条件に該当すれば、必ず加入させなければいけません。
3-1. 社会保険は強制加入であることを伝える
社会保険に加入したがらない従業員に対しては、まず、社会保険は任意で選べるものではなく、条件に該当すれば必ず加入しなければいけない「強制加入」の制度であることを伝えましょう。
3-2. 労働時間を短縮する
時間に融通が利く雇用方法なら、週の労働時間を20時間以下にし、月額賃金が8.8万円を超えないように調整すれば社会保険への加入は不要となります。
ただし、2ヵ月連続で残業により労働時間が週20時間を超え、さらに今後も同様の状態が続くと考えられる場合、社会保険に加入させなければいけないため注意しましょう。
3-3. 社会保険加入のメリットを伝える
社会保険に加入すれば下記のようなメリットがある点も伝えましょう。
- 受けられる社会保障が増える(傷病手当、出産手当など)
- 家族を扶養に入れられる
- 老齢厚生年金を受給できる(年金額が増える)
- 障害年金の受給条件が拡大する
- 遺族年金を受けられる遺族の範囲が拡大する
従業員の意思を尊重し社会保険に加入させなかったとしても、企業は法的責任を問われる立場にあるため注意しましょう。
4. 社会保険の未加入企業への指導が強化されている理由


- 高齢期の経済基盤の充実
- 働き方の多様化への対応
- 社会保険制度を維持する財源の確保
- 関連省庁との連携により未加入企業が把握できるようになったため
また、今までの社会保険適用推進業務は法人登記情報をベースにおこなっていたものの、幽霊会社なども含まれており、効率的な加入指導ができていませんでした。
しかし、平成27年度から国税庁の法人事業所情報の提供により、給与支払い実態から加入指導ができるようになったため、未加入事業所への指導が強化されています。
加えて、労働人口の減少や、働き方の多様化、高齢期の長期化など、社会情勢の変化も未加入事業所への指導が強化されている背景であると考えられます。
5. 社会保険の加入漏れ防止のためにも、労働の実態を正しく把握しよう
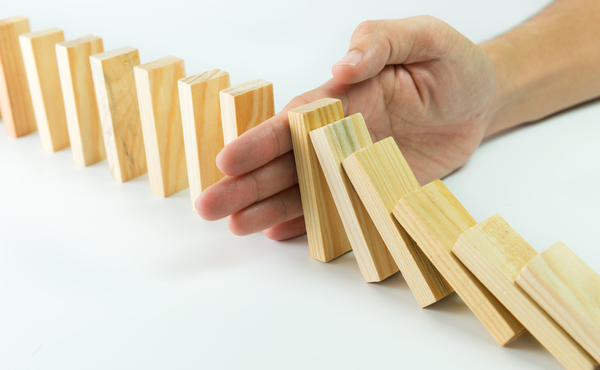
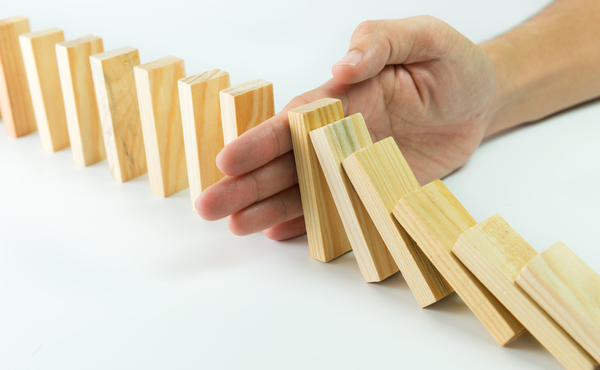
また、国税庁の情報提供も後押しし、今まで以上に社会保険への加入指導は厳しくなっています。このように加入指導が厳しくなっているのは、高齢期の経済基盤の充実や働き方の多様化への対応などが理由です。社会保険への加入要件は法改正のタイミングで変更されるため、常に最新の状態を把握しておくことが大切です。
従業員の労働時間や賃金を適切に管理し、社会保険への加入が必要な従業員がいるのであれば、速やかに届け出るようにしましょう。



従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
罰則の関連記事
-

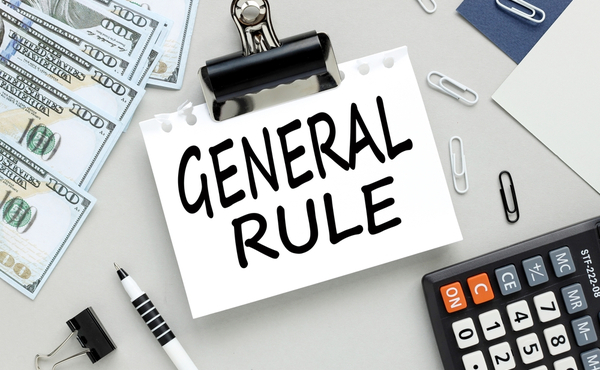
企業会計原則とは?7つの一般原則と罰則をわかりやすく解説
経費管理公開日:2022.10.25更新日:2024.05.08
-


粉飾決算とは?罰則や防止方法をわかりやすく解説
経費管理公開日:2022.10.19更新日:2024.05.08
-


試用期間でも社会保険は必要?加入対象や罰則について解説
人事・労務管理公開日:2022.09.16更新日:2025.12.24
社会保険の関連記事
-


雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説
人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27
-


養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09
-


70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは
人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28






















